文学部とは、人が人について考える場所です。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
井島 正博 教授(国語研究室)
高校の古典文法の授業で、過去の助動詞キは経験過去でケリは伝聞過去だとか、完了の助動詞ツは他動詞または意志的動詞に承接しヌは自動詞または自然的動詞に承接するとか習って、違和感はありませんでしたか。そもそも地の文は、キで結ぶものもケリで結ぶものも、どちらも使わない言い切りのものもあって、それごとに経験したこと、伝聞したことなのか、それなら言い切りは何を表わすのでしょうか。ツ・ヌに関しては、先の承接の仕方は相関関係は高いものの、「あり」「思ふ」「鳴く」「降る」などツもヌも付く動詞はどうしてくれるのか、それにこれはツ・ヌが承接する動詞の意味であって、ツ・ヌそのものの意味ではないではないか、などと悶々としたことはないでしょうか。
しかし調べてみると、キ・ケリの違いは、英語学者の細江逸記が『動詞時制の研究』(1932)において、トルコ語の過去の形に二種類のものがあって、経験した過去と伝聞した過去という使い分けがあるのですが、日本の古典語にもキ・ケリの二つがあるので、両者は同じ使い分けだと考えたところから生じ、それがいつの間にか通説になったものです。しかし今では、地の文の大方のキ・ケリがこの規定に当てはまらないことがわかっています(『源氏』冒頭「いづれの御時にか……すぐれて時めきたまふありけり」のケリは伝聞を表わしているでしょうか)。またツ・ヌは、江戸時代に本居宣長がまず『詞玉緒』(1779)でツ・ヌは「相並ぶ」(文法的振る舞いが並行する)と述べ、後に『玉霰』(1792)で承接する動詞が異なると述べたのを承けて、その弟子筋がその違いを明らかにしようと躍起になったことに起源を持つことがわかります。要するにどちらもあまり信用できる説ではなさそうです。
それではどのように考えればよいのでしょうか。簡単に言うと、キ・ケリについては、物語の現在進行中の出来事を述べる場合、物語世界のウチ側から描く場合には言い切りが、ソト側から描く場合にはケリが用いられ、物語の現在から見てそれ以前の出来事を述べる場合にキが用いられます。ことばだけでの説明だとわかりにくいかもしれませんが、そう見ていくと、たとえば『源氏物語』文章のめりはりがよく見えるようになります。実は現代語の過去の助動詞にもそのような使い分けがあるのですが、現代語ではいずれもタが用いられるので、その区別が見えにくくなっています。また、ツ・ヌに関しては、動作や状態などの始まりにヌ、継続しているところはタリ・リ、終わりにツが用いられているようです。「鶯鳴きぬ」は鳴き始めて今も鳴いているのに対して、「鶯鳴きつ」は鳴きやんだということです。こう考えることで、接続する動詞の意味ではなく、ツ・ヌそのものの意味、特に時間的意味を明らかにしたことになります。ちなみにこのようなツ・ヌの区別も、現代語ではいずれもタで表わされるので見えにくくなっています。
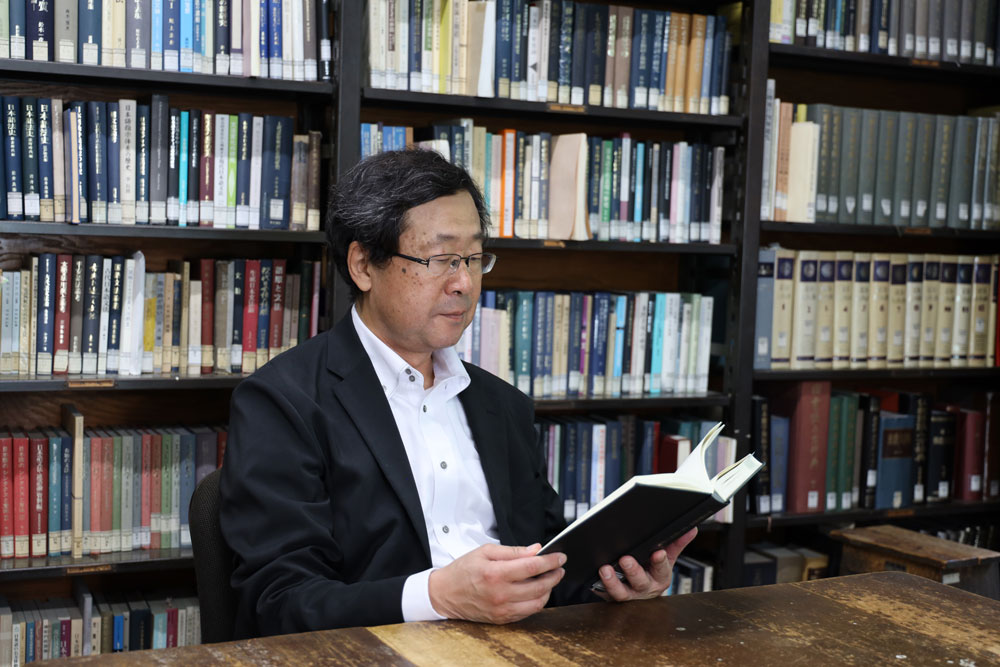
国語研究室にて
このような考えを博士論文としてまとめて、その後『中古語過去・完了表現の研究』(2011、ひつじ書房)を出版しました。さらに高校の文法の教科書として『詳説古典文法』(2012、筑摩書房)を編纂する折にはその考えを反映させましたが、高校の先生方からそれなりの評価をいただいております。
このように、日本語の文法(に限らないかもしれませんが)で、これまで無批判に正しいと信じられてきたことの中には、改めて考え直してみると、不自然なことが数多く見出されます。多くの人は、それを検討もせずに鵜呑みにして疑うことをしませんが、われわれの常識の多くは、そんなあやふやなものから構成されているのかもしれません。日本語の文法に関しては、ちょっと批判的な見方をするだけで既成の学説に多くの問題点を見出すことができますし、視点を広げればそもそもまだ解決されていない問題もいくつも探し出せます。そして先行研究をたどってその問題の核心を明らかにして、そこに見出される独自の論理を解明することには、心躍る達成感もあります。
先に挙げたことは、私の研究の一部に過ぎませんが、そのほかにも、形式名詞述語文、すなわちノダ、ワケダ、モノダ、コトダ、トコロダなどに関して考察した成果などを、『新明解国語辞典 第8版』(2020、三省堂)に反映させたりしています。
ちなみにこの二、三年は現代語の複文のテンス・アスペクトについて考えています。思いの外複雑で、うまく乗り切れるか結構スリリングで、最終的にどのような着地点を見出せるか、まだ予断のできない状態です。
| 井島 正博: | 東京大学・教員紹介ページ |
|---|---|
| 文学部・教員紹介ページ |
過去に掲載した文学部のひとについてはこちらをご覧ください
