文学部とは、人が人について考える場所です。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
今水 寛 教授(心理学研究室)
ひとのこころが読めますか? 心理学を研究していると、この質問をよく受けます。学生さんが、就職活動の面談でこの質問をされ、戸惑ったという話をよく耳にします。実際、多くの人が心理学に興味を持つきっかけにもなっているのでしょう。しかし、期待されているように「手に取るように」は、こころを読むことはできません。たとえば、fMRIという大がかりな装置を使い、数日かけてデータを集め、AIの力を借りて、その人が見ている画像を推測することはできます。しかし、「赤い色を見ている」とわかったとしても、その人にとっての「赤」と私にとっての「赤」が同じかどうかは、また別の問題です。この問いへの答えは、まだ見つかっていません。
しかし、こころは読めなくても、ひとの行動を予測することは可能と思います。もちろん、座ればピタリ当たる、とはいきませんが、「何%ぐらいの確率で、こちらを選択する」とか、「この記憶はどれくらいの間保持されるか」とか、人間の行動や意識の“ごく一部”は確率的に予測できると思います。やり方は、科学の先人たちが行ってきた方法と同じです。まずは、いろいろな条件で多くのデータを集め、データをつぶさに観察・解析して、法則を導き出します。いちど法則が解れば、予測は可能になります。そのとき、「法則」は言葉で表すこともあれば、数式で表せることもあります。そしてまた新たな実験を行い、再び予測が当たるかを調べます。こうして発見したことが、どれくらい一般性のあることなのか検討することも必要です。私自身は、そのような法則を見つけるとともに、「ひとが新しい行動の法則を身につけるとき、脳の深部の活動がどのように変化するか」脳画像で調べてきました。
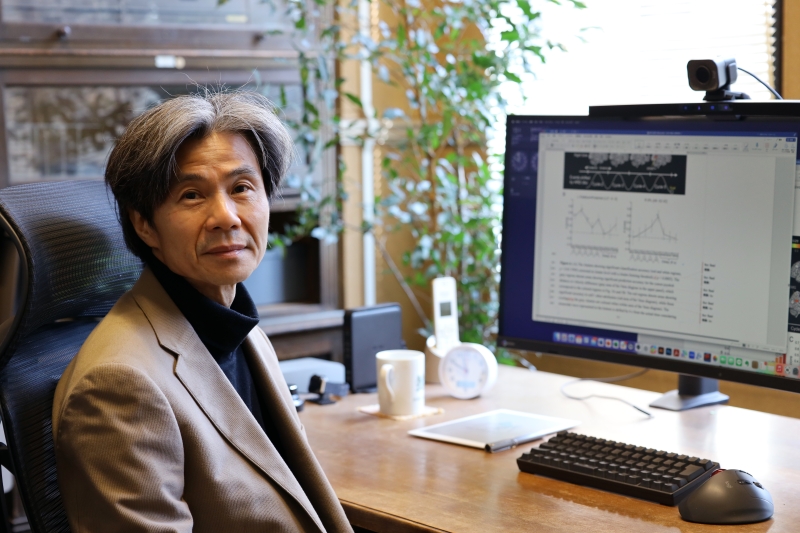
こうした研究の手順を聞くと、簡単に思えるかも知れません。ですが、ひとの行動の根源には「読めないこころ」があるため、そう簡単ではありません。そこが研究の面白さにもなります。近年は、AI・機械学習による大量データの解析、ネットワークを活用した大規模実験など、複雑な行動に隠された「法則」を見つけ出す方法が、日々増えています。また、脳の活動を測る技術や、脳を刺激する手法、画像解析による身体の動きの測定など、「こころや身体にどのように法則が刻まれているか」を調べる手段も進化しています。「意志」「主体性」「倫理」「美的感受性」といった文学部の代表的なテーマにも、少しずつデータをもとにアプローチできるようになってきました。最新の技術を活用しながら、文学部の中心的なテーマである「ひとのこころ」切り込む、「科学的な厳密さ」を守りつつ「文学部の自由さと奥深さ」を楽しむ。こころの科学の醍醐味はそんなところにあると思います。
しかし、こころは読めなくても、ひとの行動を予測することは可能と思います。もちろん、座ればピタリ当たる、とはいきませんが、「何%ぐらいの確率で、こちらを選択する」とか、「この記憶はどれくらいの間保持されるか」とか、人間の行動や意識の“ごく一部”は確率的に予測できると思います。やり方は、科学の先人たちが行ってきた方法と同じです。まずは、いろいろな条件で多くのデータを集め、データをつぶさに観察・解析して、法則を導き出します。いちど法則が解れば、予測は可能になります。そのとき、「法則」は言葉で表すこともあれば、数式で表せることもあります。そしてまた新たな実験を行い、再び予測が当たるかを調べます。こうして発見したことが、どれくらい一般性のあることなのか検討することも必要です。私自身は、そのような法則を見つけるとともに、「ひとが新しい行動の法則を身につけるとき、脳の深部の活動がどのように変化するか」脳画像で調べてきました。
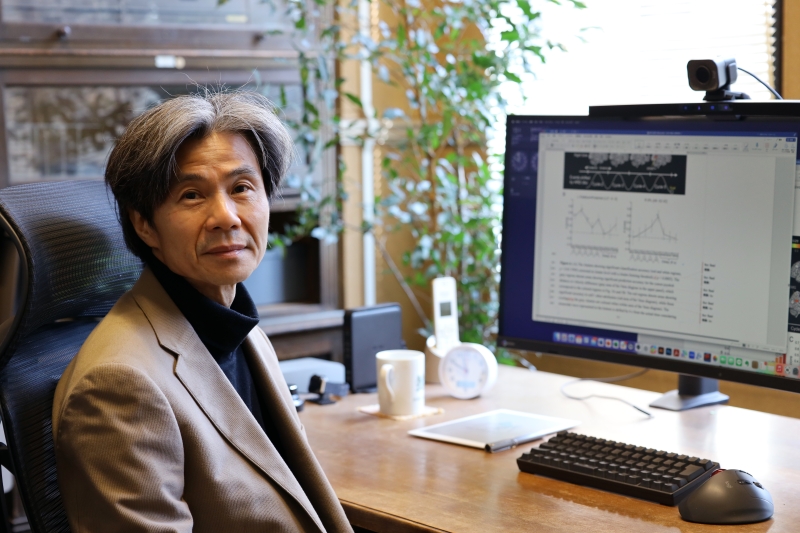
研究室にて
こうした研究の手順を聞くと、簡単に思えるかも知れません。ですが、ひとの行動の根源には「読めないこころ」があるため、そう簡単ではありません。そこが研究の面白さにもなります。近年は、AI・機械学習による大量データの解析、ネットワークを活用した大規模実験など、複雑な行動に隠された「法則」を見つけ出す方法が、日々増えています。また、脳の活動を測る技術や、脳を刺激する手法、画像解析による身体の動きの測定など、「こころや身体にどのように法則が刻まれているか」を調べる手段も進化しています。「意志」「主体性」「倫理」「美的感受性」といった文学部の代表的なテーマにも、少しずつデータをもとにアプローチできるようになってきました。最新の技術を活用しながら、文学部の中心的なテーマである「ひとのこころ」切り込む、「科学的な厳密さ」を守りつつ「文学部の自由さと奥深さ」を楽しむ。こころの科学の醍醐味はそんなところにあると思います。
