文学部とは、人が人について考える場所です。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
三浦 俊彦 教授(美学芸術学研究室)
30年近く前、「ロジカル・ハイ」という言葉を流行らせようと試みたことがあります。『虚構世界の存在論』(勁草書房, 1995)のまえがきで何気なく使った言い回しですが、ちらほら引用や言及がなされているのを見て、改めて自ら著書やエッセイで使ってみたのでした。あいにく普及には至りませんでしたが、論理的に考えることから得られる高揚感、多幸感を表わすにはよいフレーズだと今でも思っています。
学生時代に哲学書や思想書の類を読み漁った中で、論理の権化のようなバートランド・ラッセルの文体に「モノが違う!」と感銘を受けて以来、分析哲学の潮流に従った研究を続けてきました。分析哲学のパラダイムと言われたラッセルの「記述理論」は、非存在者を主語とする文の分析として一つの極端な立場を代表するものでしたが、存在論的にそれとは対極の「可能世界論」という枠組みの方に私は惹かれていきました。しかし研究方法の面では、今に至るまでラッセルの立場にどっぷり漬かっています。その立場とは、概念の理論的展開のためには日常言語は信頼できず、論理記号によるパラフレーズを要するというものです。ラッセルによると、自然科学における実験に該当する実証手続きが、哲学研究においては「パラドクスの解決」だとのこと。私はその教訓に倣って、正しい前提と正しい推論が間違った結論を導く各種パラドクスの事例を意識的に収集もしくは構成し、日常的思考と学術的思考の盲点をしばらく探り続けました。
哲学を研究することと哲学で研究することは、全く異なる仕事です。私が携わるのは後者で、主題よりも方法が肝となります。このスタンスは、主題に関心を寄せる人々からすると理解しがたいようで、市民講座を担当していた頃、心身問題、主観確率論、第二次大戦にまつわるクリティカルシンキングなど毎年異なるテーマで話をするので、常連の受講者から「いったい先生の専門は何なのですか?」と問われたこともあります。
というわけで一貫した方法で広い範囲のテーマに手を染めましたが、「美」「芸術」のような、一見捉えどころのない領域にあえて「論理」を適用したとき、論理的多幸感がピークに達するように感じています。現在の私の主たる研究対象は「芸術の定義」という分野で、芸術作品をそれ以外の事物から区別する必要十分条件を探ろうというもの。「芸術なんて千差万別だから定義できまい」「無理に定義しても検証のしようがなかろう」と思われるかもしれません。しかし、厳密に定義できそうにないから諦めるという完璧主義の態度は、哲学的分析の役割を誤解しています。「芸術の定義」とは、「芸術と非芸術を識別する道具」ではなく、「芸術という概念の明確化」さらには「概念一般の明確化」なのです。どういうことでしょうか。
我々の知的生活は、抽象概念のネットワークを基盤として成り立っています。そのネットワークは大小さまざまな境界線や包含関係が入り組んでおり、個人や社会の都合で改変することはできません。概念ネットワークは全体として知を支える一種の自然現象であって、規約の対象というより探究すべき経験的事実です。ローカルな目的に特化した派生概念は便宜上定義し直すこともできるでしょうが、「存在」「知識」「真」「善」「美」そして「芸術」のような基本概念は、文明活動の持続のためには相互の関係がほぼ一義的に決定されているはずです。構成要素のひとつを変化させると全体に影響が及ぶ有機的なシステムが「知」だからです。換言すると、特定の概念の定義とは、当該概念と他の諸概念との整合的で安定した関係を意識化することであり、概念ネットワークの姿を当該定義の波及範囲において明らかにすることなのです。
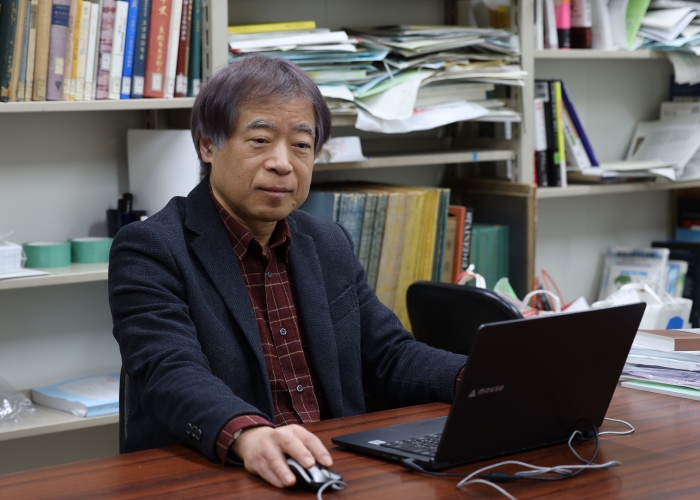
美学芸術学研究室にて
哲学の他の分野において「知識」や「真理」の定義が活発に議論されている傍らで、「芸術」の定義のみサボっていてよいわけがありません。少なくとも近似的な必要十分条件で芸術を定義することを諦めるべき理由はないでしょう。
たとえば「xは芸術作品である」を「xは美的経験をもたらす性能を意図して作られた人工物である」(Beardsley, 1983)と定義したとします。定義に使われている「美的」「経験」「性能」「意図」といった概念は「芸術」に劣らず曖昧でしょう。したがって、この定義を教えられたところで、何が芸術で何が芸術でないかを判別する眼力が高まった気はしません。だからといってその定義が無駄ということはなく、「芸術」「美的」「経験」「性能」「意図」が織り成す関係の構造を示すことで、我々の知の働きの一端を明らかにしており、芸術の捉え方を明確化しているのです。
いま挙げた定義は「機能的定義」の一種である「美的定義」の代表例であり、「美学」と「芸術学」を緊密に結びつける常識的な立場であるだけに、ロジカル・ハイといった特別な味わいを感じるほどではないもしれません。しかし、「この定義に当てはまらない芸術もありますよね?」「この定義に当てはまる非芸術もありますよね?」といった批判に晒されたとき、論理的な筋道を立てて考えることの高揚感が予感されてくるはずです。
伝統的には確かに「芸術」は「美的」で定義されてきたのですが、20世紀以降の現代アートの展開には、既製品の便器をそのまま展示したり、ギャラリーに「これは誰だれの肖像画である」と電報で文字を送ってそれを「肖像画」として登録したり、フルートを分解して再び組み立てる行為が「フルート独奏曲」として上演されたりと、どう見ても「美的経験をもたらす意図」など感じられない「芸術作品」が多く含まれています。しかも美術や音楽の教科書に載る重要な作品として。アカデミック芸術のこの状況を前にしたとき、伝統的な「美的定義」が本当に芸術の本質を捉えていると言えるのでしょうか。
そのような疑問に対し、定義論では、とりうる道を網羅的に考えることから始めます。第一の道は、定義を固守し、反例とされる逸脱事例はどれも芸術ではないのだと撥ねつける「頑固な本質主義」。最も保守的な立場ですが、教科書にも載る作品を「芸術でない」と排除するわけですから、最も過激な立場でもあります。
第二の道は、定義の対象を見直すことで定義を守ること。便器や電報は、そのままでは彫刻や肖像画として失格にみえても、異なる輪郭のもとで見直せば、別のカテゴリの芸術作品として合格するかもしれません。単なる造形物としてでなく制作展示行為全体として輪郭づければ、広義の野外演劇、すなわちパフォーマンス芸術となって、十分に美的に見えてくることがあり得るでしょう。ただ、電報をあくまで肖像画だと認定するから前衛的なパワーを持ちえたのであって、すんなりとパフォーマンスだと再解釈されてしまっては、作品が凡庸なものへ矮小化されてしまう恐れがあります。
第三の道は、定義に用いられた概念のうちいくつかを入れ替えたり拡張したりして、反例をうまく収容すること。たとえば「美的」という言葉を狭くとらずに、挑発的企画やアイロニカルな論評のような、非日常的な刺激をもたらす属性を含めるようにすれば、件の便器や電報のようなものが「広い意味で美的」となり、反例を反例で無くすことができるでしょう。純粋な「美しさ」だけが「美的」のすべてではなく、「崇高」「グロテスク」「ノスタルジー」「不条理」など多様な情感を含むように「美的」の概念が拡げられてきた美学の歴史に照らすならば、この第三の道はそれなりに説得力があると言えます。ただし、何でもかんでも美的と認めてしまう空虚な拡げ方にならないような「美的」の再解釈は難しいかもしれません。
以上のどの道もうまくいかない場合は、第四の道、最も抜本的な改訂に乗り出すことになります。美的定義は反証されたのだから、概念ネットワークの中において「芸術」という概念が占める位置・役割について、我々は誤解していたことが分かったのだ、と反省し、まったく別の定義を探すのです。
20世紀の前衛アートの隆盛に直面して、多くの美学者が第四の道を選びました。「美的」は一切用いずに、つまり「芸術」を「美的」とは独立なものとして、社会制度や歴史的継承の手続きや因果関係だけによって定義する方針へ転換したのです。「芸術作品とは、芸術共同体の中で公衆に向けて提示されるべきステイタスを付与された人工物である」(Dickie, 1969, 1984)というように。その系統の「制度的定義」は一時期圧倒的な人気を博し、伝統的な美的定義に固執する芸術哲学者の方がむしろ異端と見られるほどでした。ただし、いま挙げた定義を見て直ちに分かるように、制度や歴史による外在的定義は、定義に使われる文の中に定義されるべき語(「芸術」)が使われる「循環定義」になりがちであり、真の意味で定義の役目を果たしがたいのが実情です。
論理的には他にも採り得る道は多々あるのですが、大体この四通りが代表的でしょう。私自身が探っている道は、第三の道です。すなわち、「美的経験をもたらす性能を意図して作られた人工物」という芸術の美的定義の枠組みを守りながら、そこで用いられる概念を調整するやり方です。先ほどは「美的」の意味を拡張することで美的定義を修正する例を示しましたが、私がいま探っているのは、「意図」をもっと一般的な概念に置き換えるやり方です。「○○を意図する」「○○を信じる」「○○を望む」などの「○○」を正確に書き表わすと平叙文の形になり、真偽判定に服する「命題」を表わすので、「意図」「信念」「願望」などは「命題態度」と呼ばれます(ラッセルがRussell,1940で導入した用語)。美的定義の文言中の「意図」の箇所に任意の命題態度を代入してよいとするのが、最も見込みありそうだと私が考えている改訂版です。具体的には、「xは芸術作品である」は次のように定式化されます。
「xは美的経験をもたらす性能への任意の命題態度によって作られた人工物である」。
正確な定義に仕立てるにはさらに条件を書き込む必要がありますが、大筋のアイディアは以上です。「任意の命題態度」には、「意図する」「提案する」のようなポジティブな態度だけでなく、「否定する」「疑う」「偽装する」のようなネガティブな態度や、「試す」「問う」「想像する」のようなニュートラルな態度も含まれます。美的経験をもたらす性能を意図して作られたとは到底思えない前衛アートも、何らかの命題態度が「美的経験をもたらす性能」に向けられることによって作られたはずでしょう。彫刻として出品された既製品便器は、「これが美的経験をもたらす性能を持つ」ことを否定してみせる、装ってふざける、賭けて挑発する等々、芸術制作の美的特権性を疑問に付すために展示されたと見ることが出来るのです。
この命題態度による美的定義は、「実際には美的でない芸術作品」を包摂することができます。非芸術作品に比べて、芸術作品がより美しいとか、美的経験をもたらすとか決めつける必要はなくなります。「美的」に対しさまざまな態度を演じることで文化的コミュニケーションを促す装置、それが芸術作品だという趣旨となるのです。
これは結局、「美的という価値をめぐる文化実践が芸術である」ということの言い換えに他なりません。文化実践には分業的役割があり、それぞれ固有の「価値」に関わっています。科学は真理の探究、経済は合理性の追求、医療は健康の普及、倫理と法律は正義の実現、娯楽は快と美の提供、そして芸術は美的価値の探索というように。未知の文明(地球外文明)と遭遇したとき、意志疎通を図るために先方の各文化実践を識別しようとしたら、こうした機能的定義に頼らねばならないでしょう。とくに芸術を識別するには、美的定義による他ありません。既知の文明内で因果的にまとまった制度や歴史の外延によって文明一般の本性を理解しようとしても、不十分にとどまるのです。
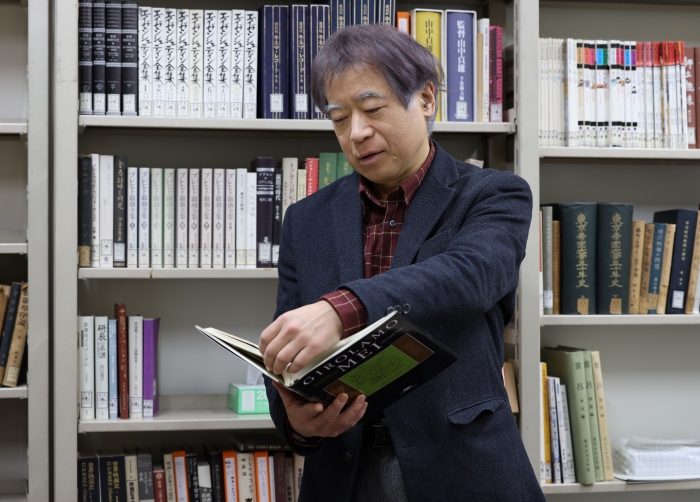
美学芸術学研究室にて
地球外文明との遭遇というシナリオは、芸術の制度的定義への批判として学界でしばしば用いられてきた思考実験ですが、さらに広い文脈では、ダーウィニズムの宇宙論的拡張である「人間原理」の対立仮説として学際的議論の的になっています。私は虚構世界論・可能世界論から並行宇宙論に分け入った関係で、『多宇宙と輪廻転生:人間原理のパラドクス』(青土社, 2007)『エンドレスエイトの驚愕:ハルヒ@人間原理を考える』(春秋社, 2018)といったSF度の高い専門書も書きましたが、そうした一連の宇宙論的思索と芸術定義論を結ぶ論理を探索する仕事は(ここではその詳細は省かざるを得ませんが)まさに概念ネットワーク内諸要素の遠隔相関を確認する機会となりました。
「意図」を「任意の命題態度」へ一般化することで美的定義を改良し、非美的な現代アートを無理なく包摂できたのは良き成果だと思っていますが、結論だけこうやって一足飛びに聞かされると、「ロジカル・ハイ」などと言うほどのことはないと感じられるかもしれません。哲学的思索の本質は結論ではなく、方法と論証プロセスです。常識に最大限合致した結論を一定以上の説得力をもって導き出す仕事は、全体構想と細部の調整とのバランスにおいて創意工夫を要し、深い自己肯定感をもたらしうるものなのです。
文化実践の中でも芸術は社会の変化にとくに敏感です。それだけに芸術研究者には、うわべのトレンドに流されない自覚がとりわけ求められます。恒常的な論証技法がシステム化されている分析哲学は、よい意味で保守的な芸術研究に最適の哲学と言えるでしょう。「芸術(的)」という概念を我々は不自由なく言語化して用いており、「科学(的)」「政治(的)」「宗教(的)」などとの連動において知と実践の土台を任せているはずですが、「芸術」の信憑性ある定義を確立することはとりわけ困難だと感じられてきました。これは「熟知しているはずの事柄をうまく説明できない」という人生あるあるというか、「言語と概念の齟齬のパラドクス」――最も基礎的な意味での「知のパラドクス」と言えるでしょう。
参照文献
• Beardsley, Monroe C. 1983 “An Aesthetic Definition of Art” Hugh Curtler(ed.) What is Art? (Haven) pp.15-29
• Dickie, George 1969 “Defining Art” American Philosophical Quarterly, Vol. 6, pp. 253-256
• Dickie, George 1984 The Art Circle: A Theory of Art (Haven)
• Russell, Bertrand 1940 An Inquiry into Meaning and Truth (Geroge Allen & Unwin)
