文学部とは、人が人について考える場所です。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
長屋 尚典 准教授(言語学研究室)
「人間とは何か」
文学部は「人間とは何か」という問いに答えようとする場所だと個人的には考えています。
俗に「哲史文」と言いますが、哲学であれ、史学であれ、語学・文学であれ、人間の社会や文化にかかわる諸側面を研究することによって、我々人間とはどういう存在なのかを解き明かそうとしています。文学部はそういう諸学問が集まっている場所です。
そんななかで私が研究している言語学は、言語という人間社会を構成する最も重要な要素のひとつに注目し、その法則性を一般化して、言語の法則性という観点から人間を理解しようとします。
なぜ言語の法則性が人間を考えるうえで重要かというと、人間であるかぎり言語の法則性から逃れられないからです。
たとえば文の組み立て方のルールである文法を考えてみると、このルールを守らないとコミュニケーションできません。それはすべての人に平等に当てはまります。権力者でも一般庶民でも、金持ちでも貧乏でも、あなたの好きな人でも嫌いな人でも、同じことです。法律や規則に従わない権力者でも言葉のルールはきっちり守ります。言葉のルールを守らないと有権者を納得させることは難しいでしょう。選挙公約だってきちんとした文法で書かれています。
このように人間なら誰しも従わざるをえない言葉の法則性を言語学では研究対象にします。
そのルールとはどういうルールなのか、なぜそのようなルールが存在するのか、どのようにそのルールは形成されるのか。言語の法則性に関する問いは尽きません。わくわくします。
たとえば、最近、私の研究チームで取り組んでいるのは示差的項標示と呼ばれる現象です。日本語でも「花奈は納豆を食べた」と「花奈は納豆食べた」のように、同じような内容の文でも目的語の表現に「納豆を」と「納豆」の2パターンがあります。このような現象はケチュア語、トルコ語、シンハラ語、ベンガル語、タガログ語、ペルシア語など世界のいろいろな言語に観察されます。
この現象で問題となるのは、どういうときにどういう目的語標示が利用されるのかということです。日本語の例ではどういうときに「納豆を」を使い、どういうときに「納豆」と言うのでしょうか?
現在、我々のチームではこの現象の背後にあるルールの解明に取り組んでいます。そして、なぜそのようなルールが存在するのかに答えようとしています。そうすることで、人間とは何かについて、何らかのヒントが得られるのではないかと期待しています。
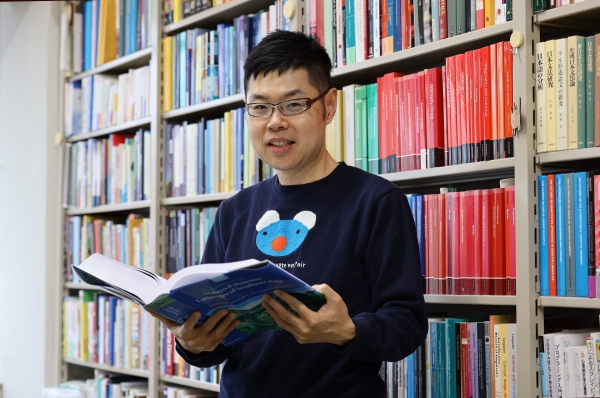
ディシプリンとしての言語学の魅力
文学部で言語学を勉強することを考えているみなさんに一番伝えたい言語学の魅力は、その自由なところです。
まず、言語学は研究対象が言語であれば何でもいいです。
現在、言語学研究室には、日本語や英語はもちろん、アイヌ語や琉球語、日本語方言などの日本のさまざまな言語や、ガレ語やイロカノ語、ラマホロット語など世界各国の言語を研究している人がいます。話される言語だけでなく手話について研究している人もいます。さらには現在実際に使われている言語だけでなく、ラテン語のように文献資料でしか研究できない言語を対象としている人もいます。
このように言語であれば何を研究してもかまいません。自由です。
私はというと、文学部の学生だったころから、フィリピンとインドネシアで話される言語の研究をしています。最近では日本語の研究もはじめましたし、世界のいくつかの言語をとりあげて比較する研究も学生と共同で行っています。
次に、研究に使う資料・データもさまざまな選択肢があります。
言語が使用される場面は人間社会にあまねく存在するので、どういうデータを使用するかにかなりの自由があります。
文学が好きであれば文学作品を対象とした研究も可能で、たとえば、聖書なり古典なりをじっくり読んで観察し、それに基づいて論文を書くこともできます。歴史が好きなら歴史書を対象に研究してもいいです。最近『御成敗式目』を使用した日本語の研究をしている研究室の先輩の話を聞きましたが、とてもおもしろかったです。コーパスと呼ばれる電子化された言語資料を使って、大量のデータを収集して分析することも可能です。さらには、医者と患者の診療のような制度化された会話を分析対象にする人もいます。
私はふつうの人がふつうに使用している場面での言語の法則性に興味があるので、日常会話やウェブ上の言語データを主な研究対象にしています。話者の許可を取った上で、話者が会話するところを撮影・録音させてもらい、その映像・音声を分析するのです。
最後に、研究方法にもかなりの自由があります。
文学部らしくコテコテの文献調査をすることも可能ですし、研究室の外に出て調査することもできます。
私自身の研究方法のメインは、調査対象言語が話される現地に赴きフィールドワークを行い、話者の方にご協力いただいてデータを収集することです。それに加えて、コロナ以降、海外にあまり出られない期間が続いたので、コーパスから収集したデータを計量的に分析し、ひとつの言語を深く分析したり、あるいは複数の言語を広く比較したりしています。特定の仮説にもとづいて実験を行い、その結果を考察するという人文学というよりは自然科学に近い方法論を採る場合もあります。
私は移り気なところがあるので、さまざまな研究方法を論文によって使い分けています。いろいろなことが楽しめるのでとても好きですね。
このような自由さが言語学の魅力です。
言語は人間の文化や社会に深く根ざすがゆえにさまざまなアプローチを可能にします。そして、言語学研究室はそのような言語を自由に研究できるところです。言語についておもしろいことさえやっていれば、それでいいというところです。
いかがでしょうか?
みなさんと一緒に言語学を勉強して、「人間とは何か」について考える日が来ることを楽しみにしています。
文学部は「人間とは何か」という問いに答えようとする場所だと個人的には考えています。
俗に「哲史文」と言いますが、哲学であれ、史学であれ、語学・文学であれ、人間の社会や文化にかかわる諸側面を研究することによって、我々人間とはどういう存在なのかを解き明かそうとしています。文学部はそういう諸学問が集まっている場所です。
そんななかで私が研究している言語学は、言語という人間社会を構成する最も重要な要素のひとつに注目し、その法則性を一般化して、言語の法則性という観点から人間を理解しようとします。
なぜ言語の法則性が人間を考えるうえで重要かというと、人間であるかぎり言語の法則性から逃れられないからです。
たとえば文の組み立て方のルールである文法を考えてみると、このルールを守らないとコミュニケーションできません。それはすべての人に平等に当てはまります。権力者でも一般庶民でも、金持ちでも貧乏でも、あなたの好きな人でも嫌いな人でも、同じことです。法律や規則に従わない権力者でも言葉のルールはきっちり守ります。言葉のルールを守らないと有権者を納得させることは難しいでしょう。選挙公約だってきちんとした文法で書かれています。
このように人間なら誰しも従わざるをえない言葉の法則性を言語学では研究対象にします。
そのルールとはどういうルールなのか、なぜそのようなルールが存在するのか、どのようにそのルールは形成されるのか。言語の法則性に関する問いは尽きません。わくわくします。
たとえば、最近、私の研究チームで取り組んでいるのは示差的項標示と呼ばれる現象です。日本語でも「花奈は納豆を食べた」と「花奈は納豆食べた」のように、同じような内容の文でも目的語の表現に「納豆を」と「納豆」の2パターンがあります。このような現象はケチュア語、トルコ語、シンハラ語、ベンガル語、タガログ語、ペルシア語など世界のいろいろな言語に観察されます。
この現象で問題となるのは、どういうときにどういう目的語標示が利用されるのかということです。日本語の例ではどういうときに「納豆を」を使い、どういうときに「納豆」と言うのでしょうか?
現在、我々のチームではこの現象の背後にあるルールの解明に取り組んでいます。そして、なぜそのようなルールが存在するのかに答えようとしています。そうすることで、人間とは何かについて、何らかのヒントが得られるのではないかと期待しています。
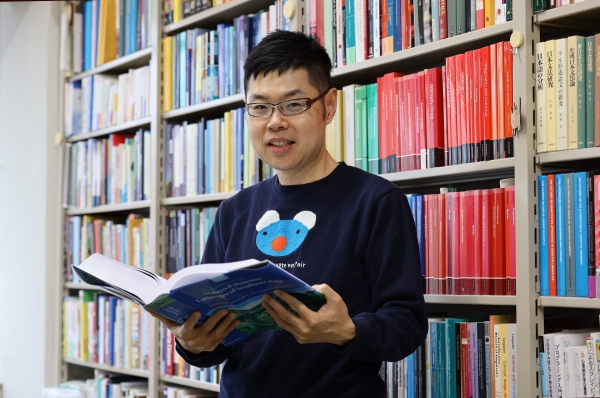
言語学研究室にて撮影
ディシプリンとしての言語学の魅力
文学部で言語学を勉強することを考えているみなさんに一番伝えたい言語学の魅力は、その自由なところです。
まず、言語学は研究対象が言語であれば何でもいいです。
現在、言語学研究室には、日本語や英語はもちろん、アイヌ語や琉球語、日本語方言などの日本のさまざまな言語や、ガレ語やイロカノ語、ラマホロット語など世界各国の言語を研究している人がいます。話される言語だけでなく手話について研究している人もいます。さらには現在実際に使われている言語だけでなく、ラテン語のように文献資料でしか研究できない言語を対象としている人もいます。
このように言語であれば何を研究してもかまいません。自由です。
私はというと、文学部の学生だったころから、フィリピンとインドネシアで話される言語の研究をしています。最近では日本語の研究もはじめましたし、世界のいくつかの言語をとりあげて比較する研究も学生と共同で行っています。
次に、研究に使う資料・データもさまざまな選択肢があります。
言語が使用される場面は人間社会にあまねく存在するので、どういうデータを使用するかにかなりの自由があります。
文学が好きであれば文学作品を対象とした研究も可能で、たとえば、聖書なり古典なりをじっくり読んで観察し、それに基づいて論文を書くこともできます。歴史が好きなら歴史書を対象に研究してもいいです。最近『御成敗式目』を使用した日本語の研究をしている研究室の先輩の話を聞きましたが、とてもおもしろかったです。コーパスと呼ばれる電子化された言語資料を使って、大量のデータを収集して分析することも可能です。さらには、医者と患者の診療のような制度化された会話を分析対象にする人もいます。
私はふつうの人がふつうに使用している場面での言語の法則性に興味があるので、日常会話やウェブ上の言語データを主な研究対象にしています。話者の許可を取った上で、話者が会話するところを撮影・録音させてもらい、その映像・音声を分析するのです。
最後に、研究方法にもかなりの自由があります。
文学部らしくコテコテの文献調査をすることも可能ですし、研究室の外に出て調査することもできます。
私自身の研究方法のメインは、調査対象言語が話される現地に赴きフィールドワークを行い、話者の方にご協力いただいてデータを収集することです。それに加えて、コロナ以降、海外にあまり出られない期間が続いたので、コーパスから収集したデータを計量的に分析し、ひとつの言語を深く分析したり、あるいは複数の言語を広く比較したりしています。特定の仮説にもとづいて実験を行い、その結果を考察するという人文学というよりは自然科学に近い方法論を採る場合もあります。
私は移り気なところがあるので、さまざまな研究方法を論文によって使い分けています。いろいろなことが楽しめるのでとても好きですね。
このような自由さが言語学の魅力です。
言語は人間の文化や社会に深く根ざすがゆえにさまざまなアプローチを可能にします。そして、言語学研究室はそのような言語を自由に研究できるところです。言語についておもしろいことさえやっていれば、それでいいというところです。
いかがでしょうか?
みなさんと一緒に言語学を勉強して、「人間とは何か」について考える日が来ることを楽しみにしています。
