文学部とは、人が人について考える場所です。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
ここでは、さまざまな人がさまざまな問題に取り組んでいます。
その多様性あふれる世界を、「文学部のひと」として、随時ご紹介します。
編集部が投げかけた質問はきわめてシンプル
「ご自身の研究の魅力を学生に伝えてくださいませんか」。
鉄野 昌弘 教授( 国文学研究室)
私は、ずっと『万葉集』の歌人論、作品論をやってきました。卒業論文は、柿本人麻呂の亡妻挽歌の構成について、修士論文は、大伴家持の歌を、漢詩文の方法の摂取という観点から考察したものです。そうした枠組は、私の学生時代にあっても、既にアナクロニズムでした。ロラン・バルトによって、とっくに「作者」は死んだことにされていたし、ミシェル・フーコーによって、「作品」という捉え方も、読者に開かれてあるテキストを、閉じたものにしてしまうと言われていました。同じく『万葉集』研究を志してはいても、年齢の近い人たちは、歌人論などする気はないと公言していましたし、一回り上の先輩からは、「古風な動機派」などと揶揄されたものです。初めての論文の抜き刷りを送った学界の老大家に、後で最初に会った時、「えっ、こんなにお若い方だったんですか」と驚かれたこともあります。
しかしそんな古い枠組を、私はなかなか捨てる気になれませんでした。それは、頭が固くて古い文学観から抜け出せなかったというのが半分でしょうが、『万葉集』とその歌が、「作者が統御する作品」という見方を求めているのではないか、ということを薄々感じていたのがもう半分のような気がします。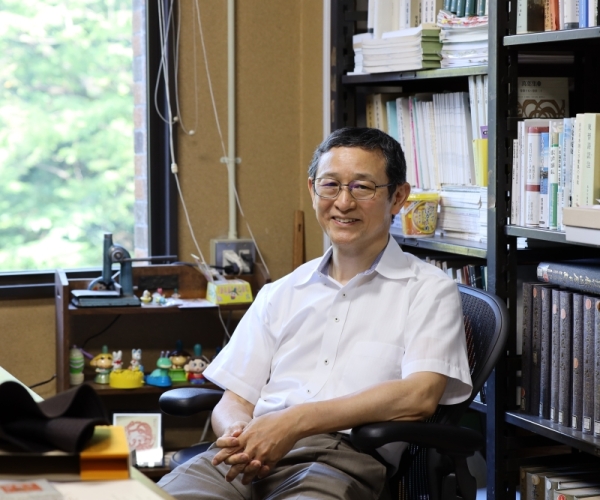
『万葉集』と『古今和歌集』以降の勅撰集との最も大きな違いは、それが歴史的な配列を持っていることです。勅撰和歌集の配列は、四季や恋の最も典型的な推移をたどっているのですが、『万葉集』は、記名の巻はことごとく制作年代順に並べられています。それは、『万葉集』の歌が、実際に詠われた場や時と切り離せない性格を持つことと連動しています。それは、一面では、和歌が言葉の次元で独立していないという、文学としての幼さでもあります。実際、『万葉集』の歌は、『日本書紀』や『続日本紀』などから得られる情報とともに読まないと、意味の伝わらない作が多いのです。テキストとして完結していない。
奈良時代になると、大伴氏の旅人(たびと)や家持、あるいは山上憶良といった、中級・上級の官人たちは、和歌に、その場その時の自分の境遇や情志をこめるようになりました。そして彼らは共通して、世の無常を和歌に詠っています。「けだし文章は経国の大業にして、不朽の盛事なり。年寿は時有りて尽き、栄楽は其の身に止まる。二者は必至の常期あり。未だ文章の無窮なるに若(し)かず」。魏の文帝「典論論文」(『文選』所収)のこの有名な言葉が、万葉歌人の受容した文学観を表しています。無常なる我が身をこの世に留めるには、いつまでも読み継がれるような文章に自己を表しておく以外に無い。だから、彼らの歌は、みな特徴的で、他人とは違うことを志向しているのです。そうした和歌の作り手は、『万葉集』の中でも「作者」とされていますし、その歌は「作品」と呼んでやりたいように思うのです。
中でも、大伴家持は、『万葉集』の最後の四巻に、「歌日誌」と言われる日付順配列の歌々を残しています。それは次々に起こる歴史的事象の中で生きる家持自身の記録です。作品論を積み重ねてゆくうちに、私は「歌日誌」の編纂者もまた「作者」なのではないかと考えるようになりました。そして今は、『万葉集』全体もまた、最終的には家持の「作品」なのではないかと感じています。
私自身も、ずっと、誰とも違う人間でいたいと思い、人の居ない方居ない方へと歩いてきて、『万葉集』の研究者になりました。周回遅れの独走を狙う結果になりましたけれども。そうした志向を持ったのは、私が生まれた時には、既に祖父母は全員亡く、父も八歳の時に喪うという育ち方をして、子供ながらに無常感を抱いていたからかもしれません。ユニークな仕事をして、後世に記憶してもらいたいという思いは、今でも強いです。はぐれ者の面白く思うことが、皆さんに魅力的かどうかは分かりませんが、文学研究者にも「作者」であることの楽しさ・喜びがある、ということはお伝えしたいと思います。
しかしそんな古い枠組を、私はなかなか捨てる気になれませんでした。それは、頭が固くて古い文学観から抜け出せなかったというのが半分でしょうが、『万葉集』とその歌が、「作者が統御する作品」という見方を求めているのではないか、ということを薄々感じていたのがもう半分のような気がします。
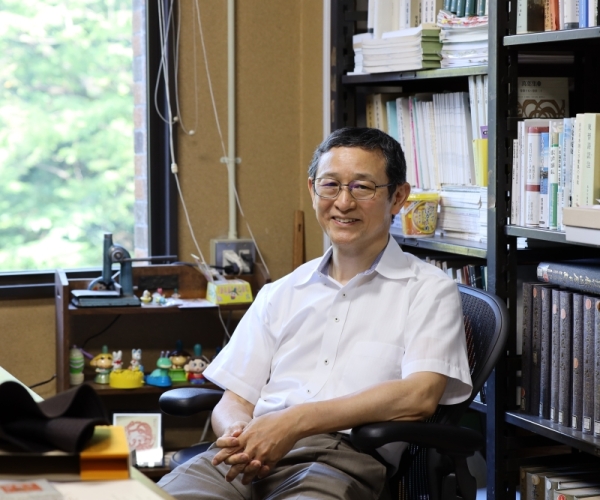
国文学研究室にて
『万葉集』と『古今和歌集』以降の勅撰集との最も大きな違いは、それが歴史的な配列を持っていることです。勅撰和歌集の配列は、四季や恋の最も典型的な推移をたどっているのですが、『万葉集』は、記名の巻はことごとく制作年代順に並べられています。それは、『万葉集』の歌が、実際に詠われた場や時と切り離せない性格を持つことと連動しています。それは、一面では、和歌が言葉の次元で独立していないという、文学としての幼さでもあります。実際、『万葉集』の歌は、『日本書紀』や『続日本紀』などから得られる情報とともに読まないと、意味の伝わらない作が多いのです。テキストとして完結していない。
奈良時代になると、大伴氏の旅人(たびと)や家持、あるいは山上憶良といった、中級・上級の官人たちは、和歌に、その場その時の自分の境遇や情志をこめるようになりました。そして彼らは共通して、世の無常を和歌に詠っています。「けだし文章は経国の大業にして、不朽の盛事なり。年寿は時有りて尽き、栄楽は其の身に止まる。二者は必至の常期あり。未だ文章の無窮なるに若(し)かず」。魏の文帝「典論論文」(『文選』所収)のこの有名な言葉が、万葉歌人の受容した文学観を表しています。無常なる我が身をこの世に留めるには、いつまでも読み継がれるような文章に自己を表しておく以外に無い。だから、彼らの歌は、みな特徴的で、他人とは違うことを志向しているのです。そうした和歌の作り手は、『万葉集』の中でも「作者」とされていますし、その歌は「作品」と呼んでやりたいように思うのです。
中でも、大伴家持は、『万葉集』の最後の四巻に、「歌日誌」と言われる日付順配列の歌々を残しています。それは次々に起こる歴史的事象の中で生きる家持自身の記録です。作品論を積み重ねてゆくうちに、私は「歌日誌」の編纂者もまた「作者」なのではないかと考えるようになりました。そして今は、『万葉集』全体もまた、最終的には家持の「作品」なのではないかと感じています。
私自身も、ずっと、誰とも違う人間でいたいと思い、人の居ない方居ない方へと歩いてきて、『万葉集』の研究者になりました。周回遅れの独走を狙う結果になりましたけれども。そうした志向を持ったのは、私が生まれた時には、既に祖父母は全員亡く、父も八歳の時に喪うという育ち方をして、子供ながらに無常感を抱いていたからかもしれません。ユニークな仕事をして、後世に記憶してもらいたいという思いは、今でも強いです。はぐれ者の面白く思うことが、皆さんに魅力的かどうかは分かりませんが、文学研究者にも「作者」であることの楽しさ・喜びがある、ということはお伝えしたいと思います。
