 #019
#019



小林 重文さん
2015年 文学部ドイツ語ドイツ文学専修課程卒業
2017年 人文社会系研究科修士課程(欧米系文化研究専攻)修了
作曲家・広告コンサルタント
「ひねくれている」ってどういうことだろう、ということを、中高生のときにずっと考えていました。
「ひねくれている」を言い換えると「斜めから物事を見る」みたいになると思うんですけど、単に斜に構えている人にはなりたくないな、と。むしろ、斜めに見ている自分をもう一回斜めから見る人は、結果的に真っ直ぐになるのかもしれない。ただ反抗するのでは相手と同レベルになってしまう。世の中に合わせることと、世の中をはみ出すことは、排反するのではなく両立できるんじゃないか……そんなことを考えていた、青臭い時期でした。
しかし青春時代に築いた価値観というのはおそろしいもので、気づけば今までずっと、その通りの生き方をしています。
文学部を選ぶまで
高校生のぼくにとって「ひねくれ」のはけ口は、作品を創ることでした。毎日欠かさず4コマ漫画を描いてネット連載し、出たばかりのボーカロイドに飛びついて作曲をし、文芸サークルを作って小説を書いた。大学受験の前日になっても、絶対にやめませんでした。勉強ばかりしている優等生という枠におさまりたくなかったんですね。
ドイツ文化への親近感もこのころ醸成されました。高校生のときにはジークムント・フロイトの精神分析に興味があったし、学校のオーケストラ部でトランペットを吹いていて、ドイツ・ロマン派のグスタフ・マーラーに夢中になった。友達と共有できない趣味を持つことが、むしろ強い自己証明になっていたんだと思います。
駒場は大学デビューという感じで、太陽が銀杏並木の合間をぬって降り注ぎ、サークルの勧誘員が呼び込みして、みんな頑張っておしゃれして……というキラキラしている雰囲気が今でも目に浮かびます。
自分も人並みに垢抜けようとしていたくせに、ここでひねくれたエネルギーが爆発しました。漫画サークルで週刊発行のビラを作り、浮き足立っている大学生たちをひたすら風刺した漫画を描いて配り歩くというのをやったのです。ツイッター黎明期だったので、主人公のアカウントを作って発信したのがうまくいって、当時はわりと学内で話題にしていただき、書籍部に置いてもらった単行本が500部完売したのは良い思い出です。のちにマーケティングの仕事に就いたのは、これが原点でした。

駒場の授業では、「社会学」というものがあるのか!という発見がとくに大きかったですね。ジェンダー論やクィア理論にかなりのめりこんでいたし、社会学科に進もうかどうか、けっこう迷いました。独文(ドイツ文学科)って、それと比べると、あまり進学選択では人気がなかったんです。でも、こういうときはたぶんひねくれているほうに行くんだろうなという予感があり、やっぱり、そうしました。
今、進学選択で悩んでいる人もいると思いますが、大事なのは「自分のことがどのくらいわかっているか」です。もし自分の外側に興味のあるテーマや具体的な仕事が見えているなら、もちろんそれに即した学部に行ったほうがいい。でもほとんどの人は、自分を見つめ直している時期のはずです。それを中途半端にしないで、自分の「ひねくれ方」のねじれ具合をとことん見てやろう、と開き直ってみるのがいいんじゃないでしょうか。そうしているうちに、身の処し方も自然とわかるものです。情報ばかり集めても、そこに答えはないですからね。

ドイツ文学科での研究
本郷は、うっそうと繁った並木道に、ひっそりとした重厚な建物が並んでいて、いよいよ研究する大学に来たぞ、みたいな純粋なワクワク感、すごくありました。
独文はとても楽しい場所でした。修士に行ったのは、学部の2年間では「自分はドイツ文学をやった」と言えないと思ったからです。ドイツ留学もしましたし、自分なりに本気でどっぷり研究に打ち込みました。そのくせ、研究者になる気は全然なかった。文系修士はかなり少数派で、就活に不利だとまことしやかに言われており、親も余計な心配をしてくれていましたが、頑として無視を決め込んでました。謎の自信があったんですね。
卒論も修論もトーマス・マンの『ヨセフとその兄弟たち』(Joseph und seine Brüder) という長編小説を扱いました。旧約聖書を元ネタにして、めちゃくちゃ膨らませた壮年期の大作です。1933年にナチスがドイツを掌握してから、マンは亡命を決めるまでの3年間すごく悩んでいて、政治的いざこざに巻き込まれたくない、一人で引きこもって小説を書きたいのに集中できない、みたいなことがそのころの日記に延々書いてあるんです。『戦争と平和』や『ドン・キホーテ』などを読みながら、おれもできるはずだ、みたいに自分を鼓舞している過程が人間臭くておもしろいというのを修論にまとめました。今思えば、社会に対する自分自身のアンビヴァレンスを、トーマス・マンの煮え切らない態度にこっそり重ねていたんですね。
指導教授は宮田眞治先生です。就職するのを「そうなんだね、君らしいね」という顔で見守ってくれました。余談ですけど、トーマス・マンを研究している人は就職しがちですよ。『魔の山』も、最後、降りますからね。
当時の自分のノートがこの間出てきて、こんなことが書いてありました。「ぼくは社会に出ることの無意味さを完璧に理解してから社会に出ようと思う」。なんともひねくれていますよね。こんなヤツでもまともに就職できるので、安心してください。

文学部の良いところ、悪いところ
文学部の良かったところは、「遅さ」の大事さを知ったことです。原文を輪読するゼミが多かったのですが、1 回の授業で1ページ進まない、場合によっては4行くらいで90分終わっちゃう。これは受験勉強をして育ってきた身としては、考えられない効率の悪さです。
それって、つまらないんじゃないの? と思われるかもしれないんですけど、すごく楽しかった。遅すぎると異化されるというか、何気なく読んでいたその言葉一つ一つに深く入り込み、ゲシュタルト崩壊みたいな感覚に陥る。「立ち止まって考える」というと普通の表現になっちゃいますけど、この「ものすごい遅さ」こそが今ますます大事になっている気がします。なぜかというと、社会がすごく速いからなんです。文学部に行かなかったら、この「遅さが大事」ということにたぶん気づけなかったと思います。ぼく自身は、どっちかというとそそっかしい人間なんですが、思いっきり自分の中の「ひねくれ」を掘っていった結果、たどり着いたのが、この「遅さ」だった。
「遅さ」は「古さ」とも関係しています。敢えて、遠い、古いところ、しかも異国の文学を異国の言語で、ものすごく遅く読む。ドイツ語にunheimlich(なじみのない、不気味な)という言葉がありますが、これは「よそよそしい」とか「距離をおく」のとは違って、親しかったものが突然異様に見えることを表します。言い換えれば、遠い昔の異国の言葉という鏡を通じて、知っていると思っていた自分が破れていき、もっとも深いところの、いわば闇の中の自分に出会うことなんです。
マルティン・ルターの研究で有名な松浦純先生が退職されるとき、教員への挨拶で「東大にいる間、毎年これだけの業績を出せ、みたいにせっつかれず見守っていただいたおかげで、すぐに成果が出ないけれども大きい仕事ができました」とおっしゃっていたと聞きました。PDCAというビジネスの常識の正反対ですよね。PDCAは基本的に生産性の原理に100%乗っかっているわけで、その生産性を問い直すのが文学部の異端らしさなんだと思いました。さすが松浦先生です。
文学部の悪いところを強いて言えば、このメリットそのものがデメリットになっているかもしれない。遅さが大事なのは、速さの概念を問い直すためであって、単に「遅れて」いていいわけではないはずです。閉じこもりすぎて、本来もっているはずの社会への批判力を錆びつかせ、結局市場原理に飲み込まれるままに弱体化している。ぼくがいた当時も文学部の予算、減らされまくっていて、独文研究室なんて黒電話を使っていました。
時代の流れに迎合しないことと、無視することとは違うと思います。ルターが長い下積み時代に沈思黙考してきた上で、活版印刷という最新メディアを戦略的に利用したからこそ、宗教改革という巨大なうねりを引き起こせたように、文学という一見どんくさい学問は、現代に対するもっとも鋭い刃になりうるのです。
ぼくに「遅さ」というスピリットを授けてくれた文学部に、いつかお返しができないか、とひそかに思っています。

スナック菓子メーカーでの6年間
東大から食品メーカーに就職する人はレアで、ましてやスナック菓子メーカーって数えるほどしかいない。本郷キャンパスの近くの「おかしのまちおか」でお菓子をいっぱい買って、裏面の会社名を見て順番にエントリーしました。スナック菓子にたどり着いたのは文学と似ている、と思ったからです。男女、年齢、階層に関係がないこと、もう一つ大事なことは、なくても生きていけること。お菓子がなくても生きていけるし、文学がなくても生きていけるけど、これがあって初めて人間らしい、みたいな感じがするじゃないですか。湖池屋を選んだのは、ガリバー企業に挑む攻める側ということと、遊び心が商品から見えてきたところです。「カラムーチョ」という普通のポテトチップスじゃないものが強いというのは、それだけマーケティングのしがいがある、ということなんです。
会社に入って配属された部署は大阪の営業です。初めての大阪、初めての一人暮らしで、ローカルスーパーを車で回って、チーフのおばちゃんに商品を売り込んだり、本部でバイヤーさんと交渉したり、まさにドブ板営業をやりました。運転も下手くそで、道ゆくナニワのおっちゃんを轢きそうになってドヤされたりしながら、1年間やっていました。ヘコみはしなかったですね。車はヘコませましたけど(笑)。若さで何とかできたというのと、あと自分の個性、つまり「ひねくれている」ことに自信があった。
特技だった店頭での試食販売で全国トップの売上になり、職場でも「おもしろい、変な東大のヤツ」みたいな感じで認められるようになって、営業本部長経由で社長の耳に入り、「マーケティング部に来い」と入れてもらいました。

マーケティング部は、次、どんな味とどんなパッケージにしたら売れるかを常に考えて、実行している部隊です。味づくりは商品開発部、パッケージデザインは社内外のデザイナー、プロモーションは広告代理店に依頼するので、自分たちはその全部を指揮する仕事です。湖池屋がコーポレートロゴから全部変えた大変革の時期に入社して、「カラムーチョ」や「スコーン」のフルリニューアルを、ブランドリーダーとして経験させてもらいました。リニューアル後の売上は今も二ケタで伸び続けています。
他には、糸井重里さんの「ほぼ日」とコラボして工場直送便のリアル販売をしたり(イベント史上一番売れたそうです)、会社初の直営店舗を作って全商品をいつでも買えるようにしたり、SDGsがテーマのオリジナルアニメを立ち上げたりもしました。
誰もやっていないことをやって世の中をびっくりさせてやろう、という単純な情熱だけで突っ走っていた20代でしたが、そんなチャレンジの機会を与えてくれた湖池屋での6年間は、ぼくにとってすばらしい経験でした。

広告代理店に異例の転職
30歳はひとつの転機でした。文学の「遅い」世界を忘れて、勢いにまかせて生きてきたのをもう一度見直すタイミングになったんです。インゲボルク・バッハマンという戦後ドイツの作家に『三十歳』という短編があるんですが、まさにあんな感じで、もはや若者ではない、という内的なクライシスが襲ってきたんですね。
転職は思い切って反対側の畑に行きました。メーカー側の発注者として広告を見てきたけど、広告をつくる側にはどんな世界が見えているんだろう。消費財のブランディングというのはわりと定性的で感覚を大事にする世界が残っているんですが、定量的にすべてを数字で語るデジタルマーケティングの世界はどうなっているんだろう。そういう興味がありつつも、結局はまたも「ひねくれ」なわけですが、敢えてアウェイな方向に行ってやれと思って入社したのがサイバーエージェントです。普通はむしろ代理店の人がメーカーに転職したがるらしく、真逆のルートでやって来たというのでずいぶん珍しがられました。
広告代理店はいろいろな事業会社さんと素早くやりとりをしないといけないので、「遅さ」の真逆です。ましてサイバーエージェントはその中でも一番スピード勝負みたいな会社なので、最初は相当大変でした。それで入社早々、半年休職したんです。
休職中に、あらためて「遅さ」に立ち戻って、好き勝手に文学や哲学書を読み漁りました。そうしたら、大学生のときには敬遠していた現代思想が、急に面白く感じるようになっていた。アーレントの『全体主義の起原』、ボードリヤールの『象徴交換と死』、マクルーハンの『グーテンベルクの銀河系』、ドゥルーズとガタリの『アンチ・オイディプス』などが、マーケティングと広告の世界を渡ってきたがゆえに、今までにない強い実感を持って迫ってきました。本って、いつでも待っててくれるんです。
上にあげた本のテーマはさまざまですが、いずれも情報化社会というものに対する根本的な批判を先取りしています。IT企業に身を置いた自分が、その中で「ひねくれ」続けるためのヒントがそこにありました。
たとえばボードリヤールは、「シミュレーションに支配された世界をぶち壊すためには、むしろシミュレーションを極端に推し進めるのがいいんだ」みたいなことを言っています。なるほど、と思い、暇を持て余していたのもあって、独学でプログラミングやAIを触るようになった。そこで、「ひょっとして今いる職場でみんながやっている業務も自動化できるんじゃないか?」と思ったんです。
復職して早々に試作品を作って提案したら、すごくいい!と言ってもらえて、気づけば「速さ」の求められるフロント業務ではなく、コンペで勝てる武器をじっくり腰を据えて創出するというミッションに抜擢され、今に至ります。
ひねくれた結果、なぜか会社の役に立ってしまっているわけですが(ボードリヤールの意図とも違うと思いますが)、そういうのが一番自分らしい生き様なんだなと改めて感じています。いつの間にかゴリゴリの理系みたいな仕事をしているのも妙な巡り合わせですけど、30代になって新たなジャンルの勉強ができるというのが面白くて、いい居場所をいただいたと思ってます。
副業で楽曲提供、趣味で漫画の個展
副業で作曲の仕事をしています。「進研ゼミ」の中学生向けタブレット教材に、VTuberならぬVティーチャーというキャラクターが教科ごとにいるんですが、勉強コンテンツの一環としてかれらが歌う「勉強ソング」を作詞作曲するというものです。今の中学生の好きな曲調を徹底的にリサーチしつつ、テストに出る項目の語呂合わせをこれでもかと詰め込む。マーケティングと学問と音楽が一緒になっているわけですから、まるでぼくのためにあるような仕事です。趣味で音楽を作っているのを公言していたら、とある先輩が「君にぴったりそうな案件があるんだけど……」と紹介してくれたのがきっかけでした。直近では、海上自衛隊やテレビ東京への楽曲提供もしています。
もうひとつの趣味だった4コマ漫画も、いまだに毎日描いていて、今年の夏には個展を開きました。なにか目指しているわけでもないのですが、ただ楽しくてやっています。職業人としての自分とズレたところにもう一人の自分を保って、思いのままに自己表現するというのは、ぼくの人生には呼吸のように欠かせないものです。
アーティストとしての活動名は「satsumaimo」といいます。

ひねくれは今も続く
30代になって、文学部スピリットである「遅さ」を再発見したことで、仕事や世の中に対する問題意識がすごく深まりました。
ぼくの現在の本業はWeb広告の黒幕みたいな仕事なんですが、Web広告がいいと思っている人、たぶんあんまりいないですよね。基本的には嫌われ者だし、AIによって商品がおすすめされ、クリック率やコンバージョン単価ですべてが回っている世界って、知れば知るほどSFチックに見える。
スナック菓子なら、少なくともつくる人と食べる人がいるけれど、実はそこにもすでに記号的な消費は含まれています。ぼくがずっとやってきたマーケティングという仕事は、まさに記号操作による需要の創出という、言ってみれば、錬金術じみた要素をもっているんです。
そして広告業界に至っては、もはや何を売って、何を買って、何が消費されているのかすら実はよくわからないにもかかわらず、巨額の資金が動いている。そういう世界を目にするようになって、この現代社会ってどうなっていくんだろう、という問いが頭の中に居座るようになりました。
だからといって、自分の仕事が無意味だと思って嫌になるとかは全然ありません。ぼくの「ひねくれ」は、ペシミズムとは違うからです。うまく言えているかわからないけど、ものごとの内部に身を置きながら、同時に外部にもいる、という感じです。両者はどこかでひとつの自分として連続しています。いわば位相的な「ひねくれ」において、この世界全体と対等に渡り合っていけるんじゃないか。そんなふうに思っています。

後輩へのメッセージ
学部選びや就活をするときは、船の威容ではなくて、乗組員を見たほうがいい。学部や会社でものを考えがちなんですが、中身は人間なので、そこにいる人間を一人でも見たほうがその組織のことがわかります。文学って、社会を描くときに登場人物で語りますよね。会社選びもそうです。だから、その船に乗ろうとしている自分を描いてみてください。
そして、「大いにひねくれてください」。検索すれば自分よりすごい人がいっぱいいるし、たいていのことはAIのほうがうまくできる時代になっている。AIにできないことは「ひねくれる」ことだけです。「たしかに合っているけれど、それってつまらなくない?」と思えるような能力、つまらないものをつまらないってすぐわかる能力です。逆に言うと、人間にできるのは、おもしろいものをおもしろいと思うことと、正論であることを敢えてひねくれて突き崩していくことです。「ひねくれ」を自分の中でとことん突き詰めると、実は近道になるよ、って伝えたいと思います。
もう一つ、これから社会人になる人へ。大学生に対して「今のうちにたくさん遊んでおけ」みたいなことを言われるのが、ぼくは昔からすごく嫌いでした。社会人になったら真面目にならないといけないというのは、抑圧的な嘘っぱちのイデオロギーです。大学だってひとつの社会ですし、会社だってひとつの遊び場です。それに、人というものはつねにひとつの肩書きである必要はないのです。全身全霊ひとつのことに打ち込むというヒロイズムは、実は脆いものです。ぼくがよく使う比喩なのですが、「頭につむじがいくつあってもいいじゃないか」と思うのです。「社会人」とかいう最近できたばかりの変な言葉に惑わされないで、のびのび生きてください。
遅い世界と速い世界のぶつかり合いの中でチャレンジしている30代、まだまだ傍目にはとっ散らかっているように見えると思います。だけど、広告も文学も、漫画も作曲も、自分の中では一つにつながっている。これらの集大成みたいなものをいつか世に問いたいなと思っていますし、ぶつかり続けていくことで、40歳のころにどうなっているか、とても楽しみです。

インタビュー日/2025.8.25 インタビュアー/髙岸 輝、加藤 隆宏、瀧川 裕貴 文責/松井 千津子 写真提供/小林 重文

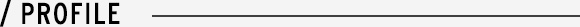

小林 重文 (こばやし しげふみ) さん
2015年 文学部ドイツ語ドイツ文学専修課程卒業
2017年 人文社会系研究科修士課程(欧米系文化研究専攻)修了
2017年〜2022年 株式会社湖池屋 商品企画
2023年〜現在 株式会社サイバーエージェント 広告コンサルタント
副業として企業案件の楽曲提供活動


-
#001

森下 佳子さん
野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -
#002

前田 恭二さん
人間のありようとして美を求める -
#003

佐治 ゆかりさん
自分がやりたいことをちゃんとやろう -
#004

内田 樹さん
乱世にこそ文学部へ! -
#005

羽喰 涼子さん
私は編集者の道を行く -
#006

大澤 真幸さん
そして同じ問いに立ち返る -
#007

佐藤 祐輔さん
ビジネスにとっていちばん大事なのは
「正義」だと思うんです -
#008

畑中 計政さん
先生ってカッコいい -
#009

越前 敏弥さん
"翻訳"という仕事にめぐり合う -
#010

濱口 竜介さん
やってみる。6割できたらいいと思う -
#011

石井 遊佳さん
根源的なものほど一見無用物 -
#012

岡村 信悟さん
文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -
#013

想田 和弘さん
観察映画という生き方 -
#014

徳田 雄人さん
「失敗しない」なんてもったいない -
#015

金 そよんさん
答えがないなんて素晴らしい -
#016

和田 ありすさん
人文学、社会科学の研究を応援する
ために進んだ道 -
#017

大島 義史
自転車で未知の世界を走る -
#018

文 聖姫
マイノリティのわたしを生きる -
#019

小林 重文
ひねくれで世を渡る
―現代における「遅さ」の力―
