 #014
#014



徳田 雄人さん
2001年 文学部社会学専修課程卒業
株式会社DFCパートナーズ代表取締役
東大生って優等生タイプが多いので、「失敗できない」みたいな状況でずっと来ている人が多いかなと思うんです。受験もうまくいって、東大に入って、名だたる企業に入って、みたいな感じだと、「失敗できない」というか、レールから外れる経験をしないので、そこから外れるための心理的なコストが上がっていってしまう。こんなに頑張って名だたる企業に入ったのに途中でやめるなんてもったいない、みたいな気持ちが強くなる。そうすると、何かにチャレンジするチャンスがあっても、心理的なコストが抑止力になってしまう気がしていて、その辺が、それこそほんとにもったいない。例えば学生時代に会社をつくってつぶすとか、大きな影響がない範囲で失敗することってすごく大事だと思います。
僕の場合は、小さな失敗を30代以降、ずっと繰り返しているので、そういう意味では失敗慣れしていますね。NHKを辞めるとき、周囲から言われたのは「東大に入って、NHKに入って、ディレクターとして一定の経験を積んで、これからじゃないの。一回、そこから外れちゃうと戻れないよ」。でも、一回辞めちゃうと楽なんです。最初のハードルが一番高い。心理的コストが低いうちに一回失敗する、というのがけっこう大事かなという気がします。
「大学時代は興味のあることだけ
やっていた」
高校生のころ、石弘之先生の『地球環境報告』(岩波新書)を読んで感銘を受け、環境問題について勉強したいと思って東大に入りました。前提をこう置くとこうなる、みたいな学問と違って、環境問題は捉えにくいし、「そもそもどういう問いなんだろうか」みたいなことをちょっと引いた視点で考えたかったんですね。なので、学部を選ぶときも特にディシプリンにとらわれない学際的なところがいいなと思っていて、ぶっちゃけで言うと進振りで点が足りなかったので文学部に来たんですけど、ちょっと引いた視点で考える学問がありそうだということで社会学を選びました。

当時、環境問題がある種のブームになっていて、エコフレンドリーな活動をすると全体が相まって地球環境問題を解決するみたい、エコとさえ言っていればいいみたいな風潮があったんですが、なんかおかしいなと。なので、環境問題の構図の変化という社会学的な視点はすごく自分にフィットしました。法政大学の舩橋晴俊先生が東大で講義をされていて、公害的なところから環境問題のパラダイムチェンジのお話をされていて、毎週、講義を受けるのが楽しみでした。ただ、興味があることだけやっていたので、授業の選び方も社会学でどうしても必要なものだけとって、あとは環境経済や環境法、環境倫理の授業を受けていました。文学部を拠点にしつつ、一人でプログラムを勝手につくっているという感じですね。文学部は、そうした学び方の拠点としてよかったと思います。ゼミは武川先生なのですが、なんだかんだ言っても「そんなのだめだよ」みたいなことはおっしゃらずに、そういう態度を応援してくださるような雰囲気はあったかなと。まあ、学際的で、そういったことを許してくれそうな先生を選んだということもあるんですけど(笑)。
大学生活で夢中になったのは、環境サークル活動です。本郷三丁目駅前の喫茶店に週1回、朝7時くらいに、いろいろな学部の同級生たちや他大学の学生も集まって、環境問題についてそれぞれ調べてきたことを発表して世の中に発信していこう、みたいなプロジェクトをやっていました。印象深かったのはサマータイムについてです。工学部や理系の人たちはサマータイムを導入して1時間ずれると環境負荷がこうなるはずだという試算を出してくる。僕は「時間がずれると人間の意識や行動変容が伴うので、そのとおりにはならないかもしれない」と言ってみたりする。たぶん入学したてのころは考え方にそれぞれの個性がけっこうあるんですけど、本郷にやってくると「何とか学的には」みたいな、学部で背負っている考え方があるので譲らない(笑)。どちらが正解ということではないと思うのですが、それぞれの色に染まりかけている人たちやいろいろなフレームでものを考える人たちと話をして、何らか一定の合意形成をしていくというプロセスを体験できたのはとてもおもしろかったし、その経験は今も迷ったときや決断する上での一つの材料になっていると思います。当時の仲間とは今も話をするのですが、官僚になったり、東大の先生になったりしています。
「NHKに就職し、“認知症”と出会い、
NPOへ」
就職を考えたとき、やっぱり環境問題をやりたくて、当時、映像の力ってすごいと思っていたので、番組制作みたいなことができたら、やりたいことと“しごと”が直結できると思ってNHKを受けました。NHKの番組ディレクターとして採用されて地方局に4年くらいいたのですが、高校野球の中継から選挙の万歳中継、台風が来れば合羽と長靴で台風中継をする、みたいになんでもかんでもやっていました。今まで興味のある環境問題に関わることだけしかやっていなかったのですが、放送っていろいろなジャンルがあるので、人の暮らし全体がわかるというか、それを体験できたのはすごく自分にとってよかったと思っています。なんですけど、当時はブラックな職場環境で、ああ、疲れてきたな、みたいな生活で、ぎりぎりのところで東京に帰ってきたという感じでしたね。
東京に戻ってきて、『生活ホットモーニング』(当時)の番組担当になって、福祉系のテーマを扱うようになりました。同僚が産休に入るので引き継いだんですけど。認知症がテーマの場合、新薬があるとか、認知症に対する画期的なケアがあるとかいう医療分野で語られることが多いんですけど、僕が取材したご夫婦は、奥さんが若年認知症になってしまって、ほんとに困っているのはスポーツクラブで水泳をするのが楽しみだったのに更衣室で着替えができないということだったんです。旦那さんは女子更衣室に入れないし、奥さんは着替えをするロッカーの場所がわからなくなってしまった。これって、誰が解決できるんだろうかっていうのがモヤモヤとして残りました。認知症は早期発見が大事です、何か異変を感じたらまず相談しましょう、相談したら病院につなぎます、病院に行ったら適切なアドバイスをします、みたいな解決法を番組で紹介しておきながらなんですけど、それでほんとに悩んでいることや暮らしづらさは解決しないだろうなと当時思いました。

ベテランのディレクターや編集マンにモヤモヤをぶつけてみると「メディアの役割って伝えることであって、個別の課題を解決することじゃないよね。そういうことをやりたいんだったらNPOをやったほうがいいよ」みたいなことを言われて、半分は納得したものの、なんかすっきりしなかったんですね。「伝える」ということに関して言えば、文字で伝えたほうがいいこと、映像で伝えたほうがいいこと、それ以外の体験で伝えたほうがいいこと、それぞれあるのでうまく活用していくことは大事だと思います。でも、目的は「伝える」ことだけではなくて、そのことによって人々が実感を持ったり、行動が変わること、価値観が変わることなのだろうと思っているんです。
振り返ってみて、認知症に関する番組をつくってはいるんだけれども、「で、どうするの?」みたいなことが出てこない。つまり、課題として認識されていないものや、あるいは課題として認識されていても、それに対してアクションを起こしている人がいない場合は、メディアは伝えられないんですね。それだったら、自分で何らか解決するアイデアを出して、そのアイデアを実現する“しごと”に挑戦しようと思ってNHKを辞めました。周囲の人に辞めようと思っていることを相談したら、「なんでもない人になってもなんにもできないよ」と止められました。でも、メディアにいたことで、お医者さんや学会の会長、家族会や当事者の方、厚労省の方も知っていて、全体を俯瞰できているかな、そのことを活かして何かできるんじゃないかと思っていました。ただ、最後の一押しになったのは、実は結婚する直前くらいでNHKを辞めたんですけど、妻になる人が「毎日、会社に通っていてもつまらなさそうだから、辞めるなら辞めれば」みたいなことを言ってくれたんですね。ただ、明日から給料が入らなくなりますという生活を体験したことがなかったので、ものすごく不安はありました。うーん、そうですね、やっぱり後押しとなったのはその言葉だったかな。
「多様な専門性を持った人が入る
仕掛けづくりとボランティアから事業へ」
北海道にNPO法人認知症フレンドシップクラブという団体があって、仲間に入れてもらいました。この団体では、地域の人と認知症の人がタスキリレーをして日本縦断をする「RUN伴」というイベントをしています。目的は、認知症って、言い方は悪いですけど、理解できない対象として見るような傾向があるんですが、「あ、こんな感じの人なんだな」ってイメージを変えることです。2019年は2万人くらい参加して、そのうち認知症の方が1割強。タスキリレーをすると隣町の人と連絡をしないといけないし、挨拶を交わすような仲になって、地域で何か課題があったときに隣町の何とかさんに相談してみようか、みたいなことにつながっていると聞いています。

今、仕事として、地域の自治体の生活課題を解決するお手伝いもしています。例えば、高齢化率40%のある地区では、「地方の高齢者や認知症の方のゴミ出し」という課題があったとき、従来の考え方では、ゴミ出しの支援が必要な人がいたら隣近所で助け合いましょうということになっているのですが、近所の人や民生委員さんも高齢化していて、手伝うことも難しい。みんな若かった時代につくられた制度やルールは、高齢化する中で、うまく機能しなくなってきているんですね。「課題がそもそも何なのか」ということを分析し、解決につながりそうな人たちを呼び込む仕掛けづくりが必要です。「地域のゴミ問題が大変だから、ボランティアで何とかしましょう」ではなく「ゴミ出しの課題のこの部分はビジネスで解決できるかもしれない」「ゴミ収集の仕組みで改善できるかもしれない」ということを示しながら、多様な専門性を持った人が解決に関われるようにしていく必要があります。
問題の現れ方は地域によって違います。これって、社会学そのものなのかもしれません。社会学に「鳥の目と虫の目」みたいな言い方がありますね。個の事例に対して入っていく部分とちょっと引いた視点で全体の流れを見るみたいな往復ですが、今、僕も、地域に出かけていって困っていることを聞く、この問題を解決するにはどうしたらいいかという提案をする、それでうまくいくかどうかわからないので、また地域に戻る、みたいなことをずっとしている感じがしていて、これって公共の課題を社会学から捉えることだし、この空気感は大学時代に得た気がします。

「自分のしたいことを“しごと”
にするために」
今は、認知症の課題解決につながることを事業としてやっていて、経済的には安定しているのですが、学生さんで社会課題を解決したいと思ってNPOの活動をしている方も多いと思います。ただ、生活の糧という面では、30年代半ばくらいになって、結婚して、子どもができてとなると、独身のときのようにはいきません。ですので、自分でこの課題を解決したいと思うことにチャレンジして、NPO活動をしたりするのはとても大事なことではあるのですが、その次の作戦が重要です。社会課題に取り組む際に、どこかから助成金をもらってやるモデルだと、それだけで生活したり、あるいは人を雇ったりということは難しくなると思うんですね。ですので、そういった活動をしている方には、次の段階としてはビジネスや事業に結びつけていく発想や経験をしてほしい。もちろん解決することを目標にすることは変わらないんですが、その中で、しっかりお金を稼いでいけることを見つけていくことがとても大事です。私自身、NPOの中で事業になりそうだと思うことにチャレンジして、できているものって、10やって1つか2つ残ればいいかなという感じです。いいアイデアだけど事業にならないこともあれば、大したアイデアじゃないけど事業になることもあるので、確率の問題です。なので、数を打たないといけない。数打った中でモノになりそうなものだけが今残っていて、それを事業として継続してやっています。

認知症の課題を10年やっているので、今やっていることを誰かに引き継いでもらえる状態にして、次のステージにいきたいと思っています。今まではテーマ型というか、社会課題みたいなことをやってきたので、もうちょっと職人的な仕事、ものづくりをしたり、農業的なことをしたいなと思って情報を収集しているところなんです。10年おきに、焼き畑農業ではないんですけれども、チャレンジしたいことに挑戦する、ということに対して心理的なコストは低いです。これも失敗慣れしているからかもしれませんね。
仕事や家庭も含めて、壁にぶつかったときに考えるときの手持ちの材料が必要です。僕の場合、大学を卒業して20年たちますが、それが大学時代に聞いた話だったり、大学時代に誰かと話したことが核になっていることが多くて、よくも悪くも、そこからそんなにアップデートしていないのかなって思うことがあります。大学時代にいろいろな人に出会うこと、その人と議論や対話することが大事だなとすごく感じますね。今でも先生のお名前や話されていた内容を覚えていて、そのとき習ったキーワードが自分の中にあるんです。すごく大事な時間だったなと振り返って思います。
インタビュー日/ 2021.9.2 インタビュアー/ 祐成 保志・井口 高志 文責/ 松井 千津子 写真/ 斉藤 真美 写真提供/ 徳田 雄人

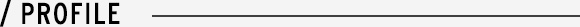

徳田 雄人(とくだ たけひと)さん
2001年東京大学文学部社会学専修課程を卒業後、NHKのディレクターとして、医療や介護に関する番組を制作。09年にNHKを退職し、認知症にかかわる活動を開始。認知症や高齢社会をテーマに、自治体や企業との協働事業やコンサルティング、国内外の認知症フレンドリーコミュニティに関する調査、認知症の人と家族のためのオンラインショップdfshopの運営などをしている。著書「認知症フレンドリー社会」(岩波新書)


-
#001

森下 佳子さん
野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -
#002

前田 恭二さん
人間のありようとして美を求める -
#003

佐治 ゆかりさん
自分がやりたいことをちゃんとやろう -
#004

内田 樹さん
乱世にこそ文学部へ! -
#005

羽喰 涼子さん
私は編集者の道を行く -
#006

大澤 真幸さん
そして同じ問いに立ち返る -
#007

佐藤 祐輔さん
ビジネスにとっていちばん大事なのは
「正義」だと思うんです -
#008

畑中 計政さん
先生ってカッコいい -
#009

越前 敏弥さん
"翻訳"という仕事にめぐり合う -
#010

濱口 竜介さん
やってみる。6割できたらいいと思う -
#011

石井 遊佳さん
根源的なものほど一見無用物 -
#012

岡村 信悟さん
文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -
#013

想田 和弘さん
観察映画という生き方 -
#014

徳田 雄人さん
「失敗しない」なんてもったいない -
#015

金 そよんさん
答えがないなんて素晴らしい -
#016

和田 ありすさん
人文学、社会科学の研究を応援する
ために進んだ道 -
#017

大島 義史
自転車で未知の世界を走る -
#018

文 聖姫
マイノリティのわたしを生きる
