 #002
#002



前田 恭二さん
1987年 美術史学卒業 読売新聞東京本社 文化部次長(インタビュー当時)
-
相対化の世界から足場を求めて
東大に入学したのは1983年のことです。それまでは山口市に住んでいて、いまから思えば奇特な高校生もいたもんだという感じですが、市内の書店に毎月2、3冊しか入らない『美術手帖』と『現代詩手帖』を買っていました。その頃の『美術手帖』はまだコンセプチュアルアートが主流でしたね。実家にあった美術全集がタイムライフ社版で、その最終巻がマルセル・デュシャンだったということもあって、「デュシャン、最高!」みたいな、イナカの現代アート小僧でした。
しかも進学した1983年は、浅田彰さんの『構造と力』が出版された年。世を挙げてニューアカデミズムという時代です。教養学部の2年間はよく分からないまま思想系の本を濫読し、友人たちと幼稚な議論で夜を明かす、といったふうでした。それがどうして美術史学科に来てしまったのかと、少しまじめな話をしますが、当時はディコンストラクション(脱構築)ということがよく言われていました。構築された命題を崩し、その先に新たな構築的な命題が生まれるなら、また逃れて相対化する。こうした議論にのめり込むと、ああも言える、こうも言える、という相対化のゲームに近づくところがある。それで生意気にも、いつまでやっても切りがないな、むしろ“かたいところ”に足場を持った形で、何かを考えてみるのはどうだろうという思いが募ってきたのです。その足場の一つはやはり歴史というものではないか、自分は美術が好きだから、歴史系の文学部第二類の美術史かなと考えて、進学先に選びました。
美術史学科でやったのは、仏教彫刻史です。来る瞬間までは当然ながら、モダンあるいはコンテンポラリーアートに興味を持っていました。ところが、そういう分野を専門とする先生はいなかったし、新入生の歓迎コンパで話を聞くうちに、ここは20世紀美術などといきがっても仕方ない場所だなということを、うすうす察知した。何より仏教美術にはとても魅力的な先輩がいらして、その人と一緒にやったほうがおもしろそうだという感じを持ったので、あっさり仏像に転んでしまいました。 

この机で根付き魚のように
仏教彫刻史では、しばしば調査に出かけます。台座から仏像を降ろして、内部を拝見したりする。じかにモノと向き合う充実感があり、何百年たった仏像がいま自分たちの前にあるんだという感慨のようなものもあるわけです。それに仏教彫刻史では、調査データや基本的な認識を共有し、一歩ずつ議論を積み重ねるフェアな学風が当時から定着していました。確かに勉強しがいのある学問だという手ごたえがありましたし、これはいまもそうだと思います。もっとも、残念ながら、東大には彫刻史の先生がいなかった。4年生になって卒論を意識しはじめた頃に、中国絵画史の戸田禎祐先生からお声をかけていただき、仏教図像に関するアイデアを生かしつつ、南宋時代の仏画で卒論を書きました。
その頃の研究室で思い出深いのは、まさにこの机です。とにかく根付き魚のように、この研究室の机の周りに居付いていました。ゼミも行われる部屋の真ん中を占拠していた机で、ゼミがないときは自由に座って、勝手に勉強していて構わない。しかも、周りには過去から蓄積された学術書や研究誌、大型の美術全集や展覧会カタログが幾らでもあるわけです。それで、この机で論文を読み、図録を引っ張り出しては、「こういう説が立てられるんじゃないか」と思いついて検証作業に入り、ああ、こんな例外もあるんじゃダメだなとか、そういうことを延々とやっていたわけです。誰もじゃまする人はいないし、本当にここにべったりいた、という感じでしたね。
ちなみに、学費は親に出してもらっていたけれど、日常的な仕送りはなかったもので、家庭教師や塾で稼いでいました。そうとう忙しかったはずなんですけど、年がら年中、研究室でこの机でべったり何かやっていた記憶しかないんですね。

就職への道
にもかかわらず社会へ出る道を選んだのは、「ある日、突然そう思った」と言うしかありません。むろん振り返ってみると、いろいろなバックグラウンドがあった。そのすべてを言うのは差し控えたいのですが、一つにはお金がなかったというのもありましたね。あとから先生方に「奨学金がとれたのに」と言われたのですが、そういう考えもなく、「よし、やめるか」と決めて、「就職しようと思っているんだ」と同級生に口走り始めたのが、7月くらいです。「え、じゃあ何をするの?」と聞かれて、「マスコミ。新聞社とか」と適当に答えたら、「読売はもう明日締め切りだよ」と言われた。「えっ?」とあわてて翌日願書をもらいに行って、喫茶店で書いて出したら、そのまま入っちゃった。幸運だったと思います。あと、カネのうらみで、どうせなら初任給の高いところがいいな、という気分もありましたね。就職したら、きれいなワンルームマンションに住むぞ、と。
ちなみに、この社会人生活の夢はたちまちついえました。新聞記者というのは普通、まず地方支局に行くんですけれど、水戸支局に配属と決まり、同期の3人が問答無用で押し込められた先は、水戸空襲でも焼け残ったという印刷所の2階。私の部屋は鍵もかからない四畳半でした。昼間は階下の印刷機の音がうるさいのなんのって。ただ、実際は日中下宿にいることはほとんどなく、ボロ布のように疲れ切って午前2時半とかに帰ってきて、翌朝6時半には水戸警察署にいるという毎日(いまはもっと快適な新人記者生活になっています、念のため)。支局には4年いたんですけど、「えーッ? それマジにやるんですか」とか、ただもう驚いているうちに過ぎてしまった。新聞社についての予備知識がなかったのが、逆によかったのかもしれません。長い目で見ると、やはり「ジャーナリズムとはなにか」といったことは考えたほうがいいのですが、最初は高邁な理念とはどう接点があるのか、少々見えにくい現場仕事でしたから、無我夢中でやっていないと、もたないところもありました。それに、自分がいま現在置かれているところで、一生懸命やらずしてどうする、ということも思いますね。これは現代アート小僧が仏教彫刻史に熱中したことにも通じますが、目の前に現れたこと、新しい環境を楽しむことで、今日とは違った明日が来るかもしれない。新しい何かに開かれていて、いつ何どきでも変わっていける自分でありたい、とは思っています。
先生がそこにいること
新聞社では結局のところ、文化部に配属され、長く美術を担当しました。人間、そう変われるものでもないということ(笑)。むろん後悔というのでもないのですが、フッと来し方を考えてしまうこともあります。たとえば、東京国立博物館の東洋館で中国絵画の特集陳列を見る、そこで李迪の「紅白芙蓉図」なんかの前に立つと、それなりには自分の人生に納得しているつもりですが、就職せずに、この絵のことだけを考えて、何ら見るべき成果を残せずに一生を棒に振ったとしても、それはそれで悪くなかったんじゃないか、というふうに。それはやっぱり絵の力というもので、その圧倒的な力に連なるものとして、美術史という学問があるんでしょうね。
同時に思い出すのは、恩師の戸田先生のことです。絵を見ること、あるいは絵を見て何かを考えるということがこれほどおもしろいんだということを、戸田先生は嬉々として全身で体現してくださった。特別講義で展覧会に行くと、誰よりも一生懸命に見る。そして「ちょっと」と満面笑顔になって学生を呼び、「ここがこうなっているところがね」と、今から考えても勉強になる、忘れがたい指摘を心から溢れ出るように話してくださるんですね。いまだに尊敬の念が失われない。文学部に入ってよかったなと思うのは、そうした先生方の人間的な感化です。何かを教えてくれるということ以上に、「その人がいる」ということで、ある種、感化を受けるような師弟関係が実際にある、という気がします。


役に立つ・役に立たない
このご時世、想像するに、文学部で勉強して「なんの役に立つんですか」ということが言われるんじゃないでしょうか。役に立つこととしては、論文を読み込む時間を過ごすことで、程度の悪い疑似アカデミズムのようなものに対して「おかしいな」と思うセンサーくらいは身につく気はします。それとは逆に、あっさり「役に立ちませんね」という答え方もあり得るとは思いますが、ただし、「役に立つ、役に立たない」というときの社会観なり、人間観なりがあまりに貧しいんじゃないかということは言ってみたい気がします。
社会的に役立つということが、ビジネスに役立つ、銭カネ稼ぐことに役立つということだとすると、人間って銭カネ稼ぐだけの存在なんですか、というふうに思うわけです。実際の問題として、どう社会と接点を持っていくかという点では、いろいろ改善したらいいこともあるでしょう。しかしながら、先年、『絵のように 明治文学と美術』という本を書いたときのリサーチでも印象に残ったことですが、近代日本の人々は「真善美」というカテゴリーで、まじめに議論を交わしています。人間のありようとして、美を求める気持ちは誰にでもある。そうした普遍的な理念について、過去の蓄積を踏まえ、具体的な作品に即して考えていく学問がなぜ役に立たないという話になるのか。人間観なり、社会観なりの貧しさをあんまりさらけださないようにしたいものです。
むろんさまざまに社会に役立つ学問領域も生まれているようですが、文学部の諸学問にはそれぞれ長い歴史があります。そこで学ぶことは、自分の前に生きた人々、先学たちと対話するということでもあるでしょう。相手にとって不足はないし、そこにわずかなりとも自分が何かを付け加えられないかと努力するのは、十分にやりがいのあることだと思います。私が年中張り付いていたこの机もそうとうな汚れっぷりですが、そうした過去との対話を幾らか経験できたことは、文学部に学んでよかったことの一つだと思います。
インタビュー日/2015.11.5 インタビュアー/髙岸 輝 文責/松井千津子 写真/斉藤真美

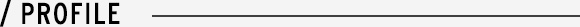

前田 恭二(まえだ きょうじ)さん
1964年、山口市生まれ。山口県立山口高校から、1983年、東京大学入学。1987年、文学部美術史学専修課程を卒業し、読売新聞社入社。
主に文化部で美術を担当。著書に『やさしく読み解く日本絵画』(2003年、新潮社・とんぼの本)、『絵のように
明治美術と文学』(2014年、白水社)(2015年芸術選奨新人賞を受賞)。


-
#001

森下 佳子さん
野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -
#002

前田 恭二さん
人間のありようとして美を求める -
#003

佐治 ゆかりさん
自分がやりたいことをちゃんとやろう -
#004

内田 樹さん
乱世にこそ文学部へ! -
#005

羽喰 涼子さん
私は編集者の道を行く -
#006

大澤 真幸さん
そして同じ問いに立ち返る -
#007

佐藤 祐輔さん
ビジネスにとっていちばん大事なのは
「正義」だと思うんです -
#008

畑中 計政さん
先生ってカッコいい -
#009

越前 敏弥さん
"翻訳"という仕事にめぐり合う -
#010

濱口 竜介さん
やってみる。6割できたらいいと思う -
#011

石井 遊佳さん
根源的なものほど一見無用物 -
#012

岡村 信悟さん
文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -
#013

想田 和弘さん
観察映画という生き方 -
#014

徳田 雄人さん
「失敗しない」なんてもったいない -
#015

金 そよんさん
答えがないなんて素晴らしい -
#016

和田 ありすさん
人文学、社会科学の研究を応援する
ために進んだ道 -
#017

大島 義史
自転車で未知の世界を走る
