 #011
#011



石井 遊佳さん
2002年 文学部インド哲学仏教学専修課程卒業 / 2013年 大学院人文社会系研究科博士課程満期退学
小説家
私が文学部卒業生インタビューの対象としてふさわしいか、ちょっと自信がないのですが、「文学部にはこんなのがいてもいいんだよ」というサンプルとしてご覧ください。私は36歳でインド哲学仏教学研究室(通称“印哲”)に学士入学しました。もともとは早稲田大学法学部の出身です。高校時代から小説家になることしか考えていなかったのですが、最初に法学部を選んだのは、政治経済が当時好きだったのと、作家になりたいから文学部というのは何となく芸がない気がしたからです。卒業後は定職に就かず小説家を目指して投稿生活を送っていました。小説を書くために様々な本を読むわけですが、その中でたびたび必要を痛感し、しかしいくら本を読んでもわからないものがひとつありました。それが「仏教」だったんです。これは小説を書くということを度外視しても、日本文化の根底を形作るもののひとつだから、きちんと知りたいと思い印哲への学士入学を決意しました。
「さまざまなアルバイトを体験」

早稲田大学を卒業したあと印哲に入るまでの遍歴についてお話ししますと、まず、菓子職人。小学生女子憧れの職業はお菓子屋さんだそうですね。私もお菓子づくりが好きで好きで、本気で菓子職人になろうとプロの洋菓子屋に入店したのですが、そんな“甘い”ものじゃなかった。想像を絶する肉体労働に2、3カ月で挫折してしまいました。
そのあとはいろいろなアルバイトをしました。ざっと挙げると、スーパーの試食販売、デパートのお歳暮・お中元承りやクレジットコーナーでの種々の業務、サラ金、カエルなど生物教材の販売会社の受付、温泉の仲居……。求人情報誌を見て、時給などの諸条件のほか、小説のネタになりそうか、つまり「おもしろそうかどうか」で決めます。特にお金に直接絡む仕事は絶好の人間観察の場と思い、意識的に選択しました。
とりわけ印象に残っているのは、デパートのクレジットコーナーや紹介屋ですね。デパートって上品なイメージですが、クレジットコーナーはデパート内サラ金とも言われる、スリルとサスペンスにあふれた職場なんです。例えば引落日に預金残金が足りないとそこへ来てお支払いいただくわけですが、後ろめたさからか、ごく普通の主婦の方が些細なことで激高して大声を張り上げるなど日常茶飯事です。即日発行カードの申込みを受け、審査発行する業務もあるのですが、通常のクレジットカードより若干審査が緩いのを狙って、借金返済目的の人も来るんです。あるときあまりに個性的な、独特のピリピリしたムードをまとった男性が即日カードの申し込みに来たさいのこと、申込書を記入したその男性に引換券を渡していったんお引き取りいただき、端末で調べるとはたして直近の同日に洗濯機10台、ビデオ数台をクレジット購入している。あきらかに、換金しやすい商品をクレジットで買って借金返済に充てています。そこで審査票に不発行と記したわけですが、30分後やってきたそのお客様に折よく出勤してきた同僚が対応、申込書を返却し不発行の旨を説明するのを離れてチラ見していたら、不意に季節外れの花吹雪。怒り狂った男性が申込書をビリビリに破いて頭上にふりまいたのでした。
紹介屋っていうのは、いわゆるブラックリスト入りの人たちを狙って、「他店で断られた方も大歓迎」などと広告を打ち、来店した人に他業者を紹介、たまたま借りられた場合に「借入できたのはうちが紹介したから」「コンピューターを操作して借入情報を書き換えたから」云々の口実で高額の手数料をぼったくる詐欺業者です。あるとき求人情報誌でサラ金だと思って行ったのですが、しばらく周りの様子を見聞きしてるうち「あ、ここ紹介屋だ」と気づいた。「やばい」と思いましたが、何であれ自分で応募して来た以上その日1日は働くべきだと思って1日だけ働きました。正直、心身ともに疲れはてましたが、それもあとあと小説のネタにできるわけです。お客さんには申し訳ないですが。
山田温泉や草津温泉の仲居もしました。草津温泉で住み込みの仲居をしていたとき、そのままにしていた埼玉の部屋にたまたま用事で戻ったんです。当時は留守電の時代で十数件入っていたんですが、そのうちの一件が『文學界』からのもの、私の作品が最終選考に残ったという通知でした。そのときは落選したものの編集者の方とお会いしていろいろお話ができましたし、「最終選考まで行ったんだからもっと本格的に小説を頑張ろう」と思った、それが33歳のときです。
「“印哲”へ学士入学」
まず仏教を学びたいと思い、そして学士入学したら自力で学費や生活費を稼がなくてはいけないからまず私立は無理、東大は他の国立大学とくらべ多種多様な入学方法があるし、しかも文学部というのは入り口がどこであれ自分のやる気さえあれば何だって勉強できる、そんなわけで東大文学部しか考えませんでした。
試験は一次が外国語と作文、作文は自分が印哲で何をやりたいかにつき真面目に決意表明すべきところ、小説を書くノリで奇天烈な文章を書きつらね、後の二次面接で他の先生方には「なんじゃこりゃ」とあきれられましたが、下田正弘先生にだけは「すごい文書くね」と言われたのをおぼえています。二次の面接のさい、私は事前に言うべきことをまったく考えておらず、要領をえないことを思いつきで話すうち木村清孝先生に「君は宗教学科のほうに向いているんじゃないか」などと言われた時点でやっとまずいと気づき、宗教学科に学士入学はないんですよ先生、と思いつつ気合いを入れ直してしゃべりまくりました。その甲斐あって何とか先生方をノセることに成功したらしく、じょじょにみなさんの顔に笑顔というか苦笑が浮かびはじめ、最後、「よろしくお願いします」と言いながらドアを閉めた瞬間、閉めたドアの向こうから末木文美士先生のワッハッハッと大笑いする声が聞こえてきて、よっしゃ、勝ったと思いました。大阪出身の私ですから、笑わせてなんぼの世界。なんとか受かりました。

ものごとを根源に遡って考えるにはインド仏教がいいなと思っていました。印度哲学研究は文献学の世界です。長い歴史の中で継承された思想や知を学ぶ行儀作法、つまり原典を読みこむための語学的修練が求められますから、サンスクリット語やパーリ語などを徹底的に勉強しなければいけません。ところが晩学の悲しさでサンスクリット語がなかなか覚えられない。当時は、毎朝3時に起きて2時間ほどサンスクリット語の文法を勉強、それから6時から9時まで駅前のコンビニで働き、電車に乗って10時20分からの2時限目の授業を受けていました。朝の授業は緊張しているからまだいいのですが、お昼を食べるとどっと睡魔におそわれ、午後一番の授業はたいてい意識を失っておりました。
率直に申し上げて、印哲研究室ってお坊さんが多いこともあり、ちょっと変わった方が多いんですね。印哲に学士入学して学部の3年生となり、周りの“同学年”の人たちと仲良くしようと思って精いっぱい努力したんですが、年齢差もあってか会話も成立しない状態が1年続き、次の年に1人、早稲田大学から隣の印度文学研究室に入ってきた人がいました。その人とはごく普通に会話が成立したため、うれしくてすぐに親しくなり、3年後に結婚までしてしまったという。実は、付き合いはじめた当初はサンスクリット語を教えてもらおうという旺盛な下心もあり、というのも彼は恐らく7世紀の玄奨三蔵以来、最も自在にサンスクリット語を繰ることのできる東アジア人なのです。ところが彼は「サンスクリット語ほど易しい言語はない」という度はずれた信念の持ち主で学習者への要求水準が半端なく、楽して教えてもらおうなどという目論見は淡雪のごとく消えました。サンスクリット語って、とにかく語形変化が複雑なんです。たとえば単数、複数だけでなく両数形なんてものがあって、動詞の活用形は最も単純なものでも90通り、名詞の曲用形なら24通り……、ほどなく諦め中国仏教に流れました。
当初から大学院まで行くつもりでした。学部では見えない世界があるだろうと。もっとも印哲は卒論のかわりに特別演習という文献購読を課すことからも分かるように、大学院進学が前提ですが。そのときどきに目標があり、それに向けとりあえず頑張って頑張って、一時の想像で「だめだ」と思うのではなくある程度まで進んだ上で、そこで見える風景で何であれ決めようと思っていましたね。大学院に入ると論文を書くという大目標があるので、それに向けて3年間頑張りました。私の修士論文は「仁王般若経」というお経をテーマにしたものです。この「仁王般若経」は「法華経」「金光明経」とともに護国三部経と呼ばれ、日本でも古代から中世にかけ鎮護国家の祈祷に重用された経典で、昔から「真経」、つまり仏陀自身が説いたと信じられる経典の漢訳として大蔵経に収められています。この経典に綿密な文献学的検討を加えた結果、同経が歴史的事実として「真・仏説」でないのはもちろん、インドに起源をもつ翻訳経典でもなく原典なしに中国で創作された経典、いわゆる「偽経」であるという結論にいたりました。この論証をもって、僭越ながら中国仏教研究に些かの貢献はできたのではないかと思いますし、自分で言うのもなんですが、文章が巧いこともあり修士論文は結構良い評価をいただきました。
博士課程に進んで、初めての学会発表も済み、これからいよいよ本格的な研究生活が始まる、というときに夫のインド留学が決まりました。初めは「はい、行ってらっしゃい」という感じだったのですが、高橋孝信先生が「インドに行ってみてもいい勉強になるんじゃないの」とおっしゃっていたという話を聞き、「それもそうだな」と思ってすぐさまそれまで一所懸命勉強していた中国語をぶんなげてヒンディー語に切り換えました。私、人生に関する決定的なことほど瞬間的に決めるんです。でも、それはたぶん、本当はすでに決まっていることなんですよ。表面上「自分が決めた」という形をとっているけれども、おそらくは選ばされている。業の力というべきでしょうか。そして、2人で向かった先がヴァーラーナシー、2006年の夏のことです。
「『百年泥』の誕生」
インドは地域によって別の国みたいに違うんですね。北より南のほうが気候も人も優しいかな、個人的意見ですが。ヴァーラーナシーはヒンドゥー教の聖都ですが、北インドの内陸部で一年の寒暖の差がはげしく、夏の暑さも半端なければ冬には10度以下になる。人もかなりシビアです。このヴァーラーナシーに行って1カ月くらいたったとき、不意に1行目が浮かんできて書いたのが、芥川賞受賞後第一作「象牛」の原型となった作品です。
芥川賞をいただいた「百年泥」は2015年に夫と行った南インドのチェンナイで書きました。某IT企業で日本語教師として働きはじめ、当初は小説どころの騒ぎではなくその日その日の状況に揉まれつづけて2年目、たまたま仕事が空いた時期があり、それまでのチェンナイ生活でため込んだネタと構想をすべてぶちこみ一気呵成に書きあげました。その作品で新潮新人賞をいただき、2017年10月小説家としてデビュー、同じ作品で2018年1月、第158回芥川賞を受賞することができました。
文章は昔から書いていますが、仏教を学ぶ前の文章と後の文章とははっきり違います。たとえば『百年泥』の中の「どうやら私たちの人生は、どこをどう掘り返そうがもはや不特定多数の人生の貼り合わせ継ぎ合わせ、万障繰り合わせのうえかろうじてなりたつものとしか考えられず」といった表現は、仏教を学んでいなければ出てこなかったと思います。作品の根底にあるのは「私」とか「個」に執着することの無意味さ、ということです。とくに仏教をテーマとして書いているのではなくても、文学部の印哲で学んだこと考えたことが私の作品のバックボーンとなっていて、それを小説で表現しようとつねに志向している。読者の方も、そこがツボだなということがわかってくださると思う。だから、正直、細かい仏教知識はみごとに頭から脱落し、今やほとんど残っていない状態ですが、本当、印哲に行って良かった。「偶然がすべてを生む」といいますか、すべての始まりがあそこにはあった。
そういえば、学士入学の面接のときに大笑いをされた末木先生に『百年泥』が新潮の新人賞をいただいたときすぐお知らせしました。折り返し返事が来て「近年まれにみる傑作です」と書いてあったんです。あの大笑いから16年目にして初めて褒められた、そう思って、ちょっとうるうるしちゃいました。


「日本の豊かさに感謝して」
日本の文学部が多数の学科をそなえ、人的資源も充実していること、つまりこれだけ優秀な教員、優秀な学生が文学部に集まっているというのは、「日本の豊かさ」ゆえだと思うのです。私が一定期間インドに住み、働き、インドの空気を吸った人間として痛感することは、日本人自身が日本の「豊かさ」を実感していないということです。夫の留学に同行したヴァーラーナシーから一時帰国したさい、2007年だったかな、日本にいなかった半年の間に「格差社会」という言葉が流行していたのには腰ぬかしました。無茶な言い方なのは承知で申し上げますが、ついさっきまでインドを見ていた目で見れば、日本に本当の格差なんてないに等しい、そう叫びたかった。以前の状況とくらべて、たとえば終身雇用の保証がなくなったり非正規雇用が増えたり、その結果個人の収入や預金残高が減ったり、そういったことは確かに個人的切実さとしてあるかもしれない、でも悪いけどその程度のこと、と言わせてほしいんです。その程度のことで「日本がビンボーになった」と大騒ぎする必要があるんだろうか。「格差」なんて言葉でまとめてしまわず、もっとゆったりした視野で日本社会の過去・現在・未来を見てほしい。さらに「格差」に関連して言うと、「スクールカースト」とか「ママカースト」とかいう言葉も聞きますが、インド独自の民族的・歴史的過程も考慮せず「カースト」なんて言葉を使ってはいけない。
日本には、人的資源をはじめとする社会に蓄積された富というものがあって、そのことを誇りに思ってほしいんです。たとえば各都道府県にそれぞれ立派な図書館があり、誰でも無料で好きなだけ本が読める。それはとりもなおさず識字率(ほぼ)100%という日本の教育水準の高さあってのことです。これは決して当たり前のことではありません。

インドのIT企業で日本語を教えていると、ほぼ全員が口を揃えて言うのは「もっと成績が良かったら医学部に行きたかった」。つまり適性やモチベーション、自分が何を本当に学びたいかなどという話は一切なく、ともかく稼げる職業に就きたい、それだけです。誰もがみな同じことを考え、同じ方向を向かざるを得ないのが現実なんです。
日本みたいに欲得ぬきにばらんばらんにやりたいことができる、私のように延々と20年も小説家を目指していられたというのは、(毎日の実生活がとくに裕福でなくとも)「豊かさ」ゆえに他なりません。ばらんばらんはすばらしい。だから、粉骨砕身して日本を豊かにしてくださった先輩たちに私は心から感謝していますし、そのことを決して忘れまいと念じております。
文学部を目指すみなさん、またすでに文学部で研究されているみなさんに申し上げたいこと、それは、ご自分の研究対象がすぐ世の中の役に立つわけでない、いかにマイナーなジャンルであっても、学ぶこと、考えることの面白さだけを見つめて邁進してもらいたいということです。何かに疑問や不思議を感じ、考え学ぶことは、それ自体がたとえようもなくすばらしく貴いことです。何であれ根源的な部分というのは一見して無用の物と判断されがちなのです。文学部というのは、学問世界をもっとも底の底で支えている、求める者にはすべてを提供できる場です。どうか豊かな国に生まれたことを感謝しつつ、有用/無用からはるかに離れた場所でそれぞれが学問のけったいなすき間を見つけ、自分のやりたいことにどんどん挑戦してほしいと願ってやみません。
インタビュー日/ 2018.9.28 インタビュアー/ 下田 正弘 文責/ 松井 千津子 写真/ 藤山 佳那

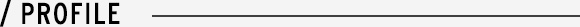

石井 遊佳(いしい ゆうか)さん
1963年、大阪府生まれ。東京大学文学部インド哲学仏教学専修課程に学士入学、さらに大学院人文社会系研究科に進学し、中国仏教学を専攻。2015年からはインド・チェンナイに在住し、日本語教師として働くかたわら小説家として活動。2017年、『百年泥』で第49回新潮新人賞を受賞。2018年には同作で第158回芥川賞を受賞。


-
#001

森下 佳子さん
野放し状態で「ものの見方を学ぶ」 -
#002

前田 恭二さん
人間のありようとして美を求める -
#003

佐治 ゆかりさん
自分がやりたいことをちゃんとやろう -
#004

内田 樹さん
乱世にこそ文学部へ! -
#005

羽喰 涼子さん
私は編集者の道を行く -
#006

大澤 真幸さん
そして同じ問いに立ち返る -
#007

佐藤 祐輔さん
ビジネスにとっていちばん大事なのは
「正義」だと思うんです -
#008

畑中 計政さん
先生ってカッコいい -
#009

越前 敏弥さん
"翻訳"という仕事にめぐり合う -
#010

濱口 竜介さん
やってみる。6割できたらいいと思う -
#011

石井 遊佳さん
根源的なものほど一見無用物 -
#012

岡村 信悟さん
文学部で学んだ比較不可能な価値の共存 -
#013

想田 和弘さん
観察映画という生き方 -
#014

徳田 雄人さん
「失敗しない」なんてもったいない -
#015

金 そよんさん
答えがないなんて素晴らしい -
#016

和田 ありすさん
人文学、社会科学の研究を応援する
ために進んだ道 -
#017

大島 義史
自転車で未知の世界を走る
