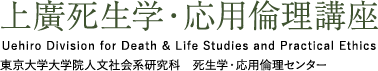概要
各種活動
臨床倫理プロジェクトの研究成果を社会に還元する活動に力を入れています。社会還元は同時に、研究成果が臨床現場において実際に有効かどうかを確認し、さらに改善しようとする実践的研究でもあります。
東京大学文学部・大学院人文社会系研究科における教育活動
死生学・応用倫理センターは部局横断型《死生学・応用倫理教育プログラム》を提供しています。これは全学に開かれたものであり、一定の単位を取得すると卒業時に修了証が交付されます。本講座教員は「死生学概論」、「応用倫理概論」を含め、数多くの科目を担当しています。
《医療・介護従事者のための死生学》基礎コース
臨床現場で働く方たちが死生についてどのように理解し、どのように医療とケアに活かしていくかを研鑽していただくための活動です。毎年、死生学セミナーとレポート書き方セミナー、およびエンドオブライフ・ケアをテーマとする春季シンポジウムなどを行っています。2024年度末の春季シンポジウムは「高齢者救急とエンドオブライフ・ケア ― 人として尊重する意思決定支援」をテーマとしてオンライン開催し、1500名以上の方々に参加申し込みをいただきました。さらに、本コースの単位として認定する下記の研究会を行っています。受講者は所定の単位を取得し、修了レポートを提出すると、審査を経て修了が認定されます。
臨床死生学・倫理学研究会
水曜日夜間に年10 回程度開催しています。死生の問題に関わる分野の方に発表をしていただき、参加者がディスカッションする研究会です。第一線の臨床家や研究者の講演の他、死生に関わる市民の活動、若手研究者の意欲的な研究など、さまざまな場面からテーマを選んでいます。2024年度はオンラインで10回開催し、3,865名の方々にご参加いただきました。2025年度もオンライン開催を継続します。
| 4月 17日 | 「ACP の光と影 ― なぜ実行されにくいのか?」 冲永 隆子(帝京大学 共通教育センター 教授) |
|---|---|
| 5月 8日 | 「エンドオブライフを支える京のまちづくり」 荒金 英樹 (愛生会山科病院 消化器外科部長、外科医) |
| 5 月 29日 | 「医療的ケア児を地域で支える」
紅谷 浩之(医療法人社団オレンジ 理事長) |
| 6月 19日 | 「“トリアージ”をめぐる共有すべき視点」 櫻井 淳(日本大学医学部 救急医学系救急集中治療医学分野 診療教授) |
| 7月 3日 | 「不確実さとともに、進行するがんと生きる ― 若年乳がん患者との関わりから」 渡邊 知映(昭和大学 保健医療学部看護学科 成人看護学 教授) |
| 10月 9日 | 「Medical HumanitiesからHealth Humanitiesへ ― 歴史的背景と現代的展開を中心にして」 足立 智孝(亀田医療大学看護学部看護学科 教授) |
| 10月 23日 | 「医療安全と医療倫理 ― 院内周知と教育」 南須原 康行(北海道大学病院 医療安全管理部 教授・部長、副病院長) |
| 11月 6日 | 「医学教育モデル・コア・カリキュラムにおける人文社会科学」 錦織 宏(名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学教育センター 教授、センター長) |
| 12月 4日 | 「チームで取り組む、末期腎不全をもつ高齢者へのアプローチ」 木下 千春(京都民医連中央病院 副院長、腎臓内科科長) |
| 12月 18日 | 「認知症の人の最期のときを支える口腔と食 ― Comfort Feeding Onlyまで」 枝広 あや子(東京都健康長寿医療センター研究所 専門副部長) |
詳細は こちら