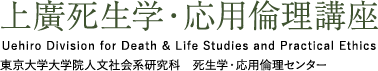行事予定
臨床死生学・倫理学研究会 (死生学特殊講義 「臨床死生学・倫理学の諸問題」)
概要
- 開催日
- 水曜 (不定期)
- 時間
- 午後6時50分~8時30分
- 定員
- 約1000名(先着順)
- 実施方法
- Zoom ウェビナーを利用したリアルタイムのオンライン研究会
- *オンライン研究会への参加には、インターネット接続環境(WiFiもしくは有線LAN)が必須になりますので、予めご了承ください。
- *参加登録いただいたメールアドレス宛に、後日オンライン研究会に使用するZoom URLおよびZoomマニュアルをお送りします。(開催のためのURLは各回で異なります。)
参加について
臨床死生学および臨床倫理学の諸課題に関して、医療と介護の現場の実践家や、医学・看護学・保健学・哲学・倫理学・社会学・教育学などのさまざまな分野で取り組んでいる研究者らからご講演いただき、質疑応答で理解を深めて参りたいと思っています。
どうぞお気軽にご参加ください。
2026年4月22日(水)鎮静の倫理
有馬 斉(ありま ひとし)先生
(横浜市立大学国際教養学部 大学院都市社会文化研究科 教授)
参加方法(4月22日分):
募集開始までしばらくお待ちください。メルマガ登録はこちら前期の開催日程
- 4月22日(水)
- 鎮静の倫理
有馬 斉 先生
(横浜市立大学国際教養学部 大学院都市社会文化研究科 教授) - 5月20日(水)
- 看取りの現場から—多職種オンラインカンファレンス『心理から考える症例検討会』
片山 和久 先生
(小松島天満クリニック 院長)
※症例検討会をしていただくので、その他数名の先生方がご登壇いたします。 - 6月3日(水)
- 『有明月の月下美人』を通じて伝えたかったこと~高齢者救急医療とACPの実態~
石井 隆之 先生
(高知医療センター 総合診療科 部長(兼)科長) - 6月24日(水)
- ケアする人のケアする—自分を大事にして元気になる—
岡山 ミサ子 先生
(オフィスJOC—Japan Okan Consultant—代表 心といのちのケア専門家(オカン)) - 7月8日(水)
- 医療における子どもの権利擁護—患者が‘子ども’であるということ—
高橋 衣 先生
(東京慈恵会医科大学地域連携看護学実践研究センター センター長 大学院医学研究科看護学専攻母子健康看護学分野 特任教授)
≪医療・介護従事者のための死生学≫基礎コース
- 参加
認定 - 受講生の方は、2回参加で1コマ分の「死生学トピック」ないし「臨床死生学トピック」として認めています。
オンライン開催のため、単位シールをご要望の方はご自身の住所・氏名を書いた封筒(110円切手を貼付してください)を上廣講座にご郵送ください。取得された単位を申告していただきますと、その分の単位シールをご返送いたします。
郵送先:
113-0033
東京都文京区本郷7-3-1法文2号館3階25号室
東京大学大学院 人文社会系研究科
上廣死生学・応用倫理講座
特任研究員 野瀬彰子 宛
大変恐れ入りますが、ご協力いただければ幸いです。
これまでの活動は こちら