
死生学・応用倫理センター
センター主任 堀江宗正
死生学・応用倫理センターにようこそ!
当センターは人文社会系研究科の付属機関で、人文知の視点から「いのち」についての学際的な研究と教育の場を提供しています。
急激に変化する現代社会で、私たちは〈いのち〉を巡って、これまでにない問題に直面しており、生き方や社会の在り方そのものを問われています。当センターではこうした問題に、死生学および応用倫理の観点から取り組んでいます。死生学分野では、死と生についての哲学、倫理、宗教観、歴史、文学、社会調査、人生の最終段階におけるケア、自殺/自死、葬送などを扱っています。応用倫理分野では、生命倫理・環境倫理・技術倫理に関わる先端的な問題、環境・経済・文化のサステイナビリティなどを扱っています。これらは、そのどれもが複数の学問分野に関連しており、学際的な対話を深めることが望まれるテーマです。
実際、当センターは、これまでも国内外の研究者や専門家集団と、シンポジウムやセミナーなどのイベントを開催してきました。また、研究成果の発表の場として『死生学・応用倫理研究』を刊行してきました。教育面では、大学全体の部局横断型教育プログラムや、社会人向けのリカレント教育を提供してきました。これらの活動は、21世紀COE「死生学の構築」やグローバルCOE「死生学の展開と組織化」、総長裁量経費プロジェクト「Sustainabilityと人文知」などを通して始められたものです。当センターは、それらのプロジェクトを引き継ぎ、恒久的な研究基盤として発展させてきました。
今後必要となるのは、第一に、国内外の死生学に関わる研究機関、応用倫理に関わる研究機関とのネットワークの構築です。また第二に、医療関係者や環境の専門家だけでなく、災害や人口減少などの問題を抱える地域社会との連携を通じ、一般市民とのあいだにも有意義な議論を喚起することです。これらのことを私がセンター主任を務める時期には力を傾けて取り組みたいと思います。
日本と世界とこの惑星の〈未来〉のために当センターが最終的に目指すのは、もちろん特定の死に方や生き方を押し付けることではありません。むしろ、そうした価値観を疑い、歴史的な経緯から相対化する必要があります。その上で土台として残るのは、「いのち」をいかなる局面においても尊重し、支えるような姿勢でしょう。そのような姿勢を持つ学問の在り方を考究する必要もあります。
この基本姿勢を大事にし、高齢化、医療と生命に関わる先端的な技術をめぐる倫理、少子化、人口減少、地球環境問題、気候変動、巨大災害といった喫緊の課題に、人文社会系の学問からアプローチし、市民社会の意識を喚起し、未来への責任を問いたいと考えています。そして〈未来〉に残る思想を紡いでいきたいと思います。今後もローカル(地域連携)とグローバル(国際交流)をつなぎ、専門家と一般市民とを架橋し、「いのち」と倫理に関する対話を広げてまいります。
堀江宗正(2024.11.6)
「死生学・応用倫理センター」の理念と事業

死生学・応用倫理センター
初代センター長 池澤優
科学と技術が我々の生活を飛躍的に便利にし、膨大な情報をもたらし、寿命を延ばすに従い、これまでは考えられもしなかった様々な問題が生まれてきた。果たして人間にとって科学技術とは何なのか、何であるべきなのか。いま現在生きている人間たちだけの経済や効率を技術的に優先させた合理性は、はたしてまだ存在しない次の世代に、理不尽な負担を押しつけることにならないのか。そうした哲学的・思想的であると同時に実践的・現実的な諸問題を根本から問い直すべく、生命倫理、環境倫理、技術倫理、情報倫理、さらには世代間倫理といった、いわゆる「応用倫理」といわれる新しい学問領域が、いま強く求められてきている。こうした要望に応えるために、文学部では2002年に東京大学全体に対して開かれた教育プログラムとして「応用倫理教育プログラム」を開設した。「応用倫理」という分野の性質上、人文学の学知に基づきつつも、学部、大学の垣根を越えて、実践的で臨床的な多くの講義・演習が設定され、それを通してわれわれも人文知への関心の高さを再認識したのである。
一方、人文社会系研究科は21世紀COEおよびグローバルCOEプロジェクト「死生学」を通して、人間の「死」に焦点をあてることで人間の「生」の営みをとらえ直す、研究教育プロジェクトを推進してきた。現代社会は生きることに一方的な価値を賦与し、生物としての人間に不可避の死のあり方にともすれば背を向け、そうすることで逆に生の内実を貧弱なものにしてきた。人間の生を、死という避けがたい根源から照射しとらえ直すには、歴史・社会上の事象に対する実証研究、哲学上の思弁的・規範的研究、それに医療や看護の現場における臨床的実践の間の学際的交流とフィードバックが不可欠である。そのような体系的な「死生学」の構築によって我々が目指したのは、生と死を分断して捉える欧米流の「死学」とは異なる、日本あるいはアジアの文化に根ざした生と死に関する叡智を世界に向け発信することであった。
COEプロジェクトの終了を前に、その成果に基づきつつ、更に継続的に発展させていくため、「死生学・応用倫理センター」は設立された。「死生学」と「応用倫理」を連結させたのは、単に両者が医療・臨床の分野で重複するからだけではない。「死生学」の目的、あるいは広い意味での任務は、すでに世を去った、すなわち死者である先行する世代の経験や遺産を受け継ぎ、未来の世代にとってより良い人間社会をどう作りあげていくかをさぐるところにあるのであって、それは現在のわれわれがいかなる存在であるべきかを考える「応用倫理」と、完全に問題関心を共有しているのである。東日本大震災を例に挙げるまでもなく、死者のいかなる記憶をどのように構築し、伝えていくかという問題は、われわれが過去をどう捉えるかを反映するだけではない。それは、われわれが現在の社会の何が問題であると感じるのか、将来、どのような社会を実現するべきと考えるのかを反映するのである。
同時に、「死生学・応用倫理センター」の設立は、人文社会系研究科がこれまで展開してきた、ディシプリンを横断して現代的状況に対応する領域を設定する試みを、更に発展するものとなるであろう。急速に変貌する現代社会に対応するには、諸問題に複合的かつ柔軟に対処する学知を構築する必要があるが、それが付け焼き刃的な対応に終わるなら、本当の意味で現代の諸問題を乗り越えることはできまい。現代に対応する真の学知は、人間存在の本質に対する深い洞察に裏付けられねばならず、そのためには過去の人類の叡智に学ぶ必要が出てくる。人文社会系研究科がこれまで行ってきた新しい領域の設定は、長い歴史を有する思想、歴史、言語、社会の研究の基礎の上に、現代を扱う学知の創設を行おうとする試みに他ならない。「死生学・応用倫理センター」もまた、人文社会学のディシプリンを現代的諸問題と結びつけることで、新たな学知を創出することを目的とするものである。
具体的な方法論としては、「死生学・応用倫理センター」の活動は、死生学分野と応用倫理分野のいずれについても、三つの核を持つものになろう。第一は、現代的な状況に積極的に関わっていく“臨床”的分野である。この分野から、われわれは現状において何が起きつつあり、いかなる知が求められているのかを知ることになる。そこで得られた知見は、人類のあり方と歴史に照らして検討されねばならない。即ち、第二の分野は、死生や倫理に関して人類が積み重ねてきた知の探求になる。第一の分野は第二の分野に刺激を与え、第二の分野は第一の分野に現状を理解し、問題点を探るための視点を与えるであろう。しかし、それだけでは充分ではない。第一の分野(現在)と第二の分野(過去)を踏まえた上で、では将来においてどうあるべきであるのか(未来)に昇華させる必要がある。つまり、現在と過去を踏まえた上で、人類の未来を哲学的に究明すること、それこそが「死生学・応用倫理センター」が構築しようとする学知になるだろう。
以上のような理念を基盤として、「死生学・応用倫理センター」は以下の4つの業務を遂行する。第一が死生学と応用倫理を部局横断的に全学の学部生・大学院生を対象に教育する「死生学・応用倫理教育プログラム」、第二が医療、看護、介護等の現場に携わる人々に東西文明の知を提供する「臨床死生学リカレント教育」、第三が公開の国際シンポジウムの開催や臨床現場への情報の提供を行う「国際的・社会的な発信」、第四がそのような活動を通じて、多様な分野の若手研究者を育成する「次世代研究者の支援育成」である。
①死生学・応用倫理教育プログラム
「応用倫理教育プログラム」は2002年の開設以来、学部・大学の垣根を越える授業を提供してきたが、更に上廣倫理財団の支援によって設けられた「上廣死生学講座」(現在の名称は「上廣死生学・応用倫理講座」)の開設科目と統合し、かつ協力部局を大幅に拡大し、部局横断型「死生学・応用倫理教育プログラム」を2012年度に開設した。このプログラムは、必修科目(「死生学概論」「応用倫理概論」)、選択必修科目(「死生学演習」「応用倫理演習」)、選択科目(「死生学特殊講義」「応用倫理特殊講義」、その他の認定科目)から成り、所定の単位を修得した場合、希望者には認定証が授与される。今後も開講科目を充実させ、同プログラムの運営をセンターの中心事業にしていく予定である。
②臨床死生学リカレント教育
「社会人リカレント敎育」は、2007年にCOEプログラムの中に「上廣死生学講座」が開設されると同時に始まった。その主なる対象は、現場の医療従事者(医師、看護師、介護士など)、福祉行政に携わる人々である。始まって5年ではあるが、医療現場で得にくい人文学の臨床的知を得ることができる場として、毎回極めて人気が高い。また、地方でのセミナーなども継続的に開催されているため、このプログラムを通して、職種や地域を越えての交流が生まれており、東京大学の社会に対する貢献として、極めて重要なものであると認識している。死生学・応用倫理センターは、この事業を継承し、「臨床死生学リカレント教育」として更に充実させていく。
③国際的・社会的な発信
COEの活動を通じ、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国、中国、台湾などとの間には恒常的なパイプができており、更にエジプトなどのイスラーム圏に及びつつある。いずれの地域でも関心や期待は大変高い。死生学・応用倫理センターは、COEプログラムで数多く開かれたような国際シンポジウムや研究集会・ワークショップを継続していく。同時に、重要なことは、これらの様々な分野の交流を広く社会に発信することであり、死生学・応用倫理センターは、臨床現場と大学を結ぶインターフェース、あるいは国際的な発信の拠点としての役割を果たしていく。
④次世代研究者の支援育成
死生学・応用倫理という新たに生まれつつある領域は、それを継承する若手研究者の育成なくしては、継続的発展を期待することができない。今後も特任研究員の採用を通して次世代の研究者の育成を続けていきたい。
死生学にせよ、応用倫理にせよ、他の人文社会系の諸学に較べれば、新しい学問領域であり、死生学・応用倫理センターが取り組むべき課題は多い。多くの方の関心と協力を願う所以である。
沿革
| 2002 ~ 2006年度 |
東京大学大学院人文社会系研究科 21世紀COE「死生学の構築」(拠点リーダー 島薗進教授) |
|---|---|
| 2007 ~ 2011年度 | 同 グローバルCOE「死生学の展開と組織化」(拠点リーダー 島薗進教授、一ノ瀬正樹教授) |
| 2007年 | 上廣死生学講座発足 |
| 2011年 | 死生学・応用倫理センター発足 (センター長 池澤優教授) |
| 2012年 | 上廣死生学・応用倫理講座 (上廣死生学講座の改組、拡充) 特任教授 清水哲郎 特任准教授 会田薫子 (総括監督者 榊原哲也教授) |
| 2013年 | 死生学・応用倫理センターに堀江宗正准教授着任 |
| 2018年5月 | 死生学・応用倫理センターに小松美彦教授着任 |
| 2021年 | 死生学・応用倫理センターに鈴木晃仁教授着任 |
21世紀COE
「死生学の構築」
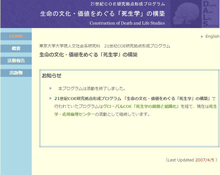
「死生学」を構想し、構築する
島薗進(拠点リーダー)
21世紀COEプログラム「生命の文化・価値をめぐる「死生学」の構築」は、現代の知の布置の中でますます重い位置を占めるようになってきている「いのち」や「死」をめぐる諸問題について、ある広がりと深みをもった総合的な学知を構想し構築しようとするものである。・・・続きを読む
グローバルCOE
「死生学の展開と組織化
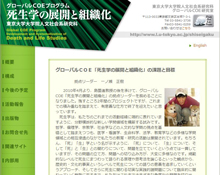
「死生学の展開と組織化」の課題と目標
一ノ瀬 正樹(拠点リーダー)
2010年4月より、島薗進教授の後を承けて、グローバルCOE「死生学の展開と組織化」の拠点リーダーを務めることになりました。残すところ2年間のプロジェクトですが、これまでの積み重ねを踏まえて、有意義な仕方で終了を迎えたいと思っています。・・・続きを読む