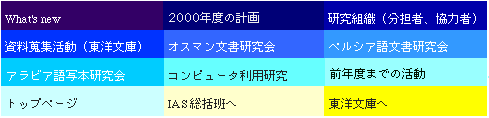 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
10:00-10:20 |
Opening Session |
|
|
10:20-11:00 |
ISOGAI Ken'ichi (Kyoto University) |
"Hanafite waqf theory reflected in waqf deeds from 16th and 17th century Bukhara". |
|
11:00-11:40 |
Christoph WERNER (University of Bamberg) |
"The Winners of Qajar Social Transformation: a Case Study in Landownership" |
|
11:40-12:20 |
KONDO Nobuaki (Tokyo Metropolitan University) |
"The Vaqf of Ostad `Abbas: The Revision of Deeds in Qajar Tehran" |
|
13:20-14:00 |
Mansur SEFATGOL (University of Tehran) |
"Majmu'eha: An Important and Unknown Sources of Historiography of the Last Safavids: the Case of Majumu'-e Mirza Moina" |
|
14:20-15:00 |
Hashem RAJABZADE (Osaka University of Foreign Studies) |
"Irrigation Examined through Documents of Qajar Iran" |
|
15:20-16:00 |
YAMAGUCHI Akihiko (The University of Tokyo) |
"On the Term 'Resm-i cift' in Ottoman Tax Registers on Iran" |
|
16:00-16:40 |
Bakhtiyar BABADJANOV (Institute of Oriental Studies, Tashkent) |
"Uncatalogued Irshad-nama from funds of the Institute for Oriental Studies named after al-Biruni (Tashkent)" |
|
16:40-17:20 |
General Discussion |
|
�{���[�N�V���b�v�̖ړI�́A�܂��������x��Ă��镶���j���Ɋւ�����������s�����Ƃł��������A�Z�t�@�g�S������уo�o�W���[�m�t�͌��n�̊w�҂Ȃ�ł͂̂���܂Ŋw�E�ɂ��܂�m���Ă��Ȃ��V�����ތ^�̕����j���̏Љ�ł���A���̈Ӗ��ŗL�Ӌ`�ł������B����ɑ��Ĉ�L�́A�Õ����w�ƃC�X���[���@�w���q�����Ƃ��郆�j�[�N�Ȍ����ł���A�I�X�}�����̉ېő䒠�̃^�[�������������R���Ƃ��킹�āA�䂪���̌����������ɐi�W���Ă��邱�Ƃ������������B���F���i�[�͕����𗘗p���ăJ�[�W���[�������̓y�n���L�̖��ɖ{�i�I�Ɏ��g���̂ł���A���N�t�����̍X�V�����������ߓ��A�����������������W���u�U�[�f�ƂƂ��ɁA�����j���̗��p�ɂ���ĉ����\�����������B
���x���̍��������������A�S�̓I�ɂ͔��\���e�̂���������A�y���V�A�ꕶ������������Ƃ��Ė����n�ł��邱�Ƃ��v�炸�����炩�ƂȂ����B�������A�I�X�}���������ҁA�A���u�����ҁA�C���h�����҂��������������ȋc�_���s���A�y���V�A�ꕶ�������̐��E�̐����𖾂炩�ɂ���Ɠ����ɁA�䂪���̒��������̐����̌�������������Ƃ��ł����ƍl������B
�@
1999�N12���X��
�T�ǁE�U�Ǎ���������i���F���s��w���w���j
����
Mansur SEFATGOL (�e�w������w)
�u�T�t�@���B�[�����(1666-1736)�̏@���E�Љ�\���v�T�t�@���B�[������̏@���E�Љ��A�R�̌����Ȓ������F�߂���B���Ƀ^�T�b���H�t�ƃX�[�t�B�[�����̒e���A���ɏ@���w���ғ����̃A�t�o���[�h�ƃI�X�[���[�h�̑Η��A��O�ɖ@�w�҂ƓN�w�҂̑Ό��ł���B�����̒����́A�R���A�C�X�t�@�n�[���A�}�V���n�h�Ƃ����R�̓s�s�̎O�p�`�̒��œW�J���ꂽ�B�T�t�@���B�[�����C�����ɂ�����12�C�}�[���h�ŏ��̖{�i�I�����ł��������ƂƂ����܂��āA�����̒����́A�����̐����I�E�v�z�I���K�肵�A���G�������B
����
Bakhtiyar BABADJANOV�i�E�Y�x�L�X�^�����m�w�������j
�u����E�Y�x�L�X�^���̃X�[�t�B�Y�����Ƃ�܂������v����̃E�Y�x�L�X�^���ł́A�X�[�t�B�Y���͋ɂ߂ďd�v�Ȑ����I���ł���B�\���B�G�g�̕���ȍ~�A�e�n�ŃC�X���[���A�X�[�t�B�Y���̕����������邪�A����Ɋւ��鐳�m�ȏ��̓E�Y�x�L�X�^���ɂ����Ă����Ăɂ����Ă����ɏ��Ȃ��A����⌻���̑Ή��ɂ����č�������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�X�[�t�B�Y���̗��j�E�`�����ӂ܂��A�M��҂̔��s����r���⋳�`�����̈ꎟ�����Ɋ�Â����������������K�v�ł���A����Ȃ����ẮA�E�Y�x�L�X�^���Љ�͔��ȍ���ɒ��ʂ���ł��낤�B
�@
�A���r�A��j����������ł̂��܂��܂Ȗ��_���������邱�Ƃ�ړI�ɔ����������̂ł���B��̓I�ȍ�ƂƂ��ẮA10���I�C���N�̕��l�q���[�����T�[�r�[���������w�J���t�{��̋V��x��ǂݐi�߁A�ŏI�I�ɂ͂��̍�i�̓��{����o�ł��邱�Ƃ�ڎw���Ă���B����11�N�x���ɂ�15��̌�������J�Â����B����̌�����́A�w�J���t�{��̋V��x�Ɋւ���֓lj�`���Ői�߂�ꂽ�B���̍ہA�e�L�X�g��ǂ݉�����Ŗ��ƂȂ�d�v�ȗp���ŗL�����ȂǂɊւ��Ċ����ȋc�_�������Ȃ�ꂽ�B�e��̖S���҂́A������ł̌������ʂ܂��ē��{��̉����ł��쐬���A�����E�F�u�T�C�g��Ō��J���Ă���B�����I�Ɍ�����ɏo�Ȃł��Ȃ������҂��A���̃E�F�u�T�C�g���Q�Ƃ��邱�Ƃɂ�蓖������̊����ɎQ�����邱�Ƃ��\�ł���A�����ߒ�����ѐ��ʂ̓������J�Ƃ����Ӗ��ŁA��������̎��݂͐V�@����ł��o�����Ƃ����悤�B�Ȃ��A11�N�����_�ŁA��i�S�̖̂�S���ɂ��Ă̍�Ƃ��I�����Ƃ���ł���B
������i199�V�A1998�j
- �u��A�W�A�������W��v(1998�N1��23���j
-
�@1��23���ɓ��m���ɂɂ����āA�u��A�W�A�������W��v���J�Â��A���Z�Ȏ����ɂ�������炸�A��A�W�A�����҂𒆐S��15�����Q�����܂����B����12������1���ɂ����āA�����N�V�i�R�w�@��w�A�U�ǁj�ƘI���N��i������w��w�@�A�U�Nj��͎ҁj�̂Q�����A�p�L�X�^���Ɏ�����������ю��W�ɏo�����A���n�̌����Ǝ����̏ɂ��ĕ��܂����B���W���������́A�y���V�A��A�E���h�D�[����͂��ߑ���ɂ킽��A�܂�19���I���̌Ï����܂܂�A�Q���҂���́A�悭�����W�ł����Ɗ����ɂ��������ߑ�������܂����B���K��������́A��A�W�A�j�ɂƂ��Ă͂������A�C�����j�⒆���A�W�A�j�ɂƂ��Ă��d�v�Ȏ���ł����A����܂Ŏ������蔖�ł����������ɁA����̎������W�́A�����̌����̔��̂��������ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����̏ڍׂɂ��ẮA�ߓ����ɂU�ǂ̃z�[���y�[�W�ɏo���� ���f�ڂ���܂��̂ŁA���������������B�Ȃ��A�U�ǂŎ��W���������́A���T�� �j���ɉ{���E���J���Ă���܂��B���m���ɂR�K�̃C�X�����n�挤���������K�˂����� ���i9:30-16:30)�B
- �y���V�A��ʖ{�u�ǃZ�~�i�[�i1999�N1��21���`2��4���j��
������w���m����������
-
�C�X���[���n�挤����U�ǂ́A����1��21���A26���A28���A2��2���A4����5��ɂ킽��A���ꂼ��2���ԋ��̃y���V�A��ʖ{�u�ǃZ�~�i�[���J�Â����B�u�t�ɂ̓e�w������w�����A�C�����E�C�X�������a���Ȋw�A�J�f�~�[�I�g����̃G�t�T�[�����G�V�����[�M�[�����}�����B���̓T�t���B�[�����̐��X�̎j�����Z�����Ă����u���n�v�̒����Ȑ��Ƃł���A���̂悤�ȍu�t���}���ĂƂ��Ɏʖ{�u�ǂ��s���������Ƃ͑����̎Q���҂ɂƂ��ċM�d�ȑ̌��ƂȂ����B���ɂ͉����k�C������̎Q���҂�����A�y���V�A��ʖ{�ɂ��Ă͏��̎��݂ł��邱�̂悤�ȍu�ǃZ�~�i�[�ւ̊S�Ɗ��҂̍������������킹���B
�Z�~�i�[����́A�Q���҂̎��ȏЉ�Ȃǂ̌�A�܂��y��G�a���i�k�C����w�E�@�j�ɂ���āA�u�ǎj���ł���wSafwa al-Safa�x�i14���I�C�����̐��ғ`�j�̗l�X�ȃ��@�[�W�����ɑ�����ʖ{�̓`�������炩�ɂ��ꂽ�B���̌�A�u�t�G�V�����[�M�[���ɂ�肱�̍�i�̐����j�A�����ȂǂɊւ���u�`���s��ꂽ�B
��2��ȍ~�͎��ۂ̍u�ǂɔ�₳�ꂽ�B�������c��wSafwa al-Safa�x�̎ʖ{�̂����ŌẪ��C�f���ʖ{����ɗp���A�Q���҂��ǂݏグ�锭�����A���̂Ȃǂ̕M�L�@�A���@����_���`�̏��T�O�ɂ����鑽�l�ȓ��e�̉����������Ƃ�����Ƃ��A�u�t�͔E�ϋ����A�������K�^�Ȃ��ƂɁA�ǂ����y���݂Ȃ���s�����B�Q���҂̑����ɂƂ��ẮA�y���V�A�����Ƃ�����j�w�҂Ɨ��j�j����ǂݍ��킹��Ƃ������Ǝ��̏��߂Ă̑̌��������̂ŁA���̍�Ƃ͎ʖ{�u�ǂ̔\�͌���Ƃ����Ӗ��ɂ����Ă݂̂Ȃ炸�A�u�C�����l�͂����ǂނ̂��I�v�Ƃ����ӊO�Ȕ������������Ɋ܂�ł����悤�ł���B���Ǐ����������4���15�Łi8�t�j�قǂ��u�ǂ����B��̎Q���҂͑���16���A�e��̎Q���҂�10���قǂł������B
����̃Z�~�i�[�͒Z���̂��̂ł��������Ƃ�����A���ꎩ�̂ŖڂɌ����鐬�ʂ����������Ƃ����Ό֒��ɂȂ낤�B�������A���łɋL�����悤�ɁA�w�����܂Ŋ܂����̎Q���҂��A�ꗬ�Ƃ���錻�n�̐��Ƃƒ��ڌ��������A�ʖ{�u�ǂɂ��Ă̒m���ƋZ�p���܂����݂̂łȂ��A����Ό��n�̕����z�������Ƃ́A���w��̑I��Ȃǂ��܂߁A�Q���Ҋe�l�̍���̌��������̐v�̏�ŗL�v�������̂łȂ����낤���B
�u�t�̃G�V�����[�M�[���́A�Q���҂̊S�̍����ƔM�S���A�܂��A�u�����̈����̈Ӗ��܂ŁA�o��l����l��l�̑f���܂Œm�낤�Ƃ�����{�l�̔M�S���ƔE�ϋ����v�Ɋ��������Əq�ׂĂ����B�Ƃ�����ƎG�Ȏd���������Ȃ��ł��Ȃ��ߔN�̃C�����ő����̐l�X���w�����鎁���A���̂悤�Ȉ�ۂ����ƂɁu���{���v�̂�肩���𐄏�����悤�Ȃ��ƂɂȂ�A���̃Z�~�i�[�̈Ӗ����܂�����܂����ƂɂȂ邾�낤�B
�Ȃ��A�Q���҂̊F�l�ɂ́A�C�X���[���@��̋֊����C�ɂ����u�t���G�X�R�[�g���ė[�H�̂��������Ă��������ȂǁA����ȋ��͂������������B�I�[�K�i�C�U�[�Ƃ��Ă��炽�߂Ďӈӂ�\�������B���肪�Ƃ��������܂����B�@�i���F�X�{��v�@������w���m�����������E����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ - ��6�nj�����E��40��H�c�L�O�ٍu����̕i1999�N1��23���i�y�j�ߌ�Q���|�U���j
�� ���s��w�H�c�L�O��
�F�ߓ��M���i�s����w�l���w���j�w�ȁE����j
���n���}�h�E���U�[�E�i�X�B�[���[�i�p���[���E�k�[����w�j�@ �A�N�E�R������������K�[�W���[�����Ɏ���U���I�ɂ킽���āA�C�����̏����Ƃ̓I�X�}�����Ɛ푈��O���܂��܂ȊW�������A���̌��ʃC�����j�Ɋւ��鑽���̕����j�������݂̃g���R���a���̏������قɎc����邱�ƂƂȂ����B�C�����j�Ɋւ��镶���j���̎c�������Ă���A�����̎j���͔��ɋM�d�ł���A�ɂ�������炸����܂ŏ\���Ɍ�������Ă���Ƃ͌�����B�g�v�J�v�{�a�����ٕ����ق���ё����{�I�X�}�����Õ����ǂ𒆐S�ɁA���܂��܂ȕ����̃R���N�V�����̐��藧���ɂ��Đ������A�C�����j�W�̕����j���̎�ނƎc���𖾂炩�ɂ����B
�G�t�T�[���E�G�V�����[�M�[���i�e�w������w�j
�@�s�s�K�Y���B�[���Ɏc��Â����z���ł���Ë��j���X�N�ɂ̓Z���W���[�N�����ȍ~�̖������������c����Ă���B�����̓��N�t�����Ⓔ�߂̎ʂ��ł���A���j�j���Ƃ��Ă����l�̍������̂ł���B�ŏ��ɃZ���W���[�N���̃A�~�[���A�t�}���^�V����12���I�����̃��N�t�������Љ�A���̗��j�I�w�i�𖾂炩�ɂ����B�܂��A�T�t�@���B�[���̃V���[�E�A�b�o�[�X�Q���̒��߂��Љ���B�T�t�@���B�[�����ɂ̓K�Y���B�[���͈ꎞ��s�ƂȂ������߁A�d�v�Ȉ�Ղ����݂��邪�A�����̈ꕔ�ɂ��Ă��X���C�h���g���Đ������������B
�@ - Efim
Rezvan���m�iSt.�y�e���X�u���N���m�w�������������j
�u���uSt.�y�e���X�u���N���m�w�������̎ʖ{�j���ɂ��āv�i1998�N12��3���j
���@���m���Ɂ@3�K��c��
- St.�y�e���X�u���N���m�w�������́A�����V�A�鍑�ȗ��̎��W��������������B
�ʖ{�@��10���_�i65�̌���ɂ��j�B�A���r�A��5000�_�A�y���V�A��1���_�ق��B
�}���@100�����i���ɒ鐭����̒����A�W�A�ł̊��s���ɂ��Ă͔[�{���x������A���ׂĔ[�߂��Ă���B�ژ^�J�[�h�����Ȃ����߁A����A���q�̂܂��͓d�q���f�B�A�ɂ��ژ^�������]�܂�Ă���j
����сA�G���ށB - 10�̌�������ɕ�����A120���̌����҂��]���B�ڂ����́A�z�[���y�[�W�Q�Ɓihttp://www.thesa.ru�j
- 1995�N���AManuscripta Orientalia: International Journal for Oriental Manuscript Research(Helsinki)���G���Ŋ��s���B��������ʖ{�̌����E�Љ���s���Ă���B
- �ʖ{�̍Z�����s���s���Ă���A�ŋ߂̊��s���Ƃ��āA�ȉ��̂��̂𓌗m���ɂɊ��ꂽ�B
- Rasa'il al-hikma�i�h���[�Y�h�̋��T�j
- Abu Bakr Muhammad al-Suli, Kitab al-awraq
- �܂��ACD-Rom�`���ł̎ʖ{�̊��s���J�n���A���݂܂�10�_�������[�X����Ă���B
- �}�G�̑����ʖ{�̗�Ƃ��āA�}�����[�N������̕��|��Ibn Abi Khazzam, Kitab al-makhzun���r�f�I��p���ďЉ���B
- �������̗��j�́A�鐭���A���V�A�v���ƃ\�A�M����A�y���X�g���C�J�E�\�A�����ƁA���V�A�ƃ��X���������Ƃ̐��������j�f���Ă���B����ɂ��ẮA�������̏Љ���܂߁AAsian Research Trends�i���l�X�R���A�W�A���������Z���^�[���j�Ɋ�e��\�肵�Ă���B
-
�Ȃ��A���m���ɂł́A���������̏����j���̃}�C�N���E�t�B�����ɂ����W���Ƃ�i�߂Ă���A����ɂ��ẮA6�ǂ̃V���|�W�E���i1998�N12/13�J�ÁA��B��j�ɂ����āA�~���R���ɂ����s��ꂽ�B�i���Ӂ@�O�Y�@�O�j
- St.�y�e���X�u���N���m�w�������́A�����V�A�鍑�ȗ��̎��W��������������B
- �V���|�W�E���u�C�X���[���n�挤���ɂ�����ʖ{�E�����j���̉\���v�i��B��w�C�X���������w�ȂƋ��ÁA��B�j�w��V���|�W�E���j
-
�����F1998�N12��13��
�ꏊ�F��B��w���蕶�n�L�����o�X�i�@���u�`���j-
�m��|�n
- �@
- �i��F�O�Y�@�O�i�����̐����q��w�j
- �F
�����@�����i������w�j
�@�u�C�N�^�[���̎ʖ{�j�������߂āv- �═�@���j�i���w�@��w�j
�@�u�C�����j�ɂ����镶���j���Ǝʖ{�j���F���N�t���������𒆐S�Ƃ����T�ρv- �����@�m���i������w��w�@�j
�@�u�I�X�}�����j�����ɂ����镶���E�L�^�j���ƓT�Ёv- �~���@�R�i������w�j
�@�u�y�e���X�u���N���m�w���������������̌����Ɨ��p�F�Ƃ��ɃE�C�O�������𒆐S�ɂ��āv- �x��@�O�i���s�O�����w�j
�@�u�q���@�E�n�����̃J�[�f�B�[�����j���ɂ��āv - �i��F�O�Y�@�O�i�����̐����q��w�j
- �@
- �m�V���|�W�E���T�v�n
- �����ł́A�Z���{�͂������ʖ{���̂ɂ������̌�L�����邱�ƁA�ʖ{���̂����Ȃ���Ίm�F�ł��Ȃ������A���������ꂪ����I�Ȏ����Ɋւ��ꍇ�����邱�Ƃ����g�̃C�N�^�[���̌������Ɏ������B�═�ł́A�y���V�A��ʖ{��17���I�ȗ��A�P�{�����[���b�p�����ɏ�������A�ژ^����������Ă���A�}�C�N���t�B�����Ȃǂ̓�����e�ՂŁA�ʖ{�ɂ����邱�Ƃ͕K�{�ƂȂ��Ă���Ƃ��A����̕ł́A�����j���̎�ނ�Z���o�łɂ��ĕ����B���N�t�����ɂ��ẮA�@�葱�����o���������@�����Ƃ��Ắu�ʂ��v�i���{����ѓ��{�j��A���N�t�̒��������{�Ƃ͓Ɨ������j�����l�������Ă��邱�Ƃ��w�E�����B�����́A�j���̃J�e�S���[���A�L�^�A�T�Ђ̂R��ɐ������������ŁA���ꂼ��̎j���̂����i����̒����E�Z�������邱�ƁA�菑���j���͋L�q���e�ȊO�ɏ��́A�M�ՁA�����A�������A���{�Ȃǂ̏��������A����炪�N�����ɗL���ł��邱�Ƃ����g�̌o�����ɒ�N���A�܂��j�������E�ۑ��ɂ�����u�o�������v�̏d�v�����w�E�����B�~���Ɩx��́A�����A�W�A�W�̎j�����p�Ɋւ��錻�ݐi�s���̃v���W�F�N�g�ɂ��Ă̕ł���B�~���́A�T���N�g�E�y�e���X�u���N���m�w�������̏������钆���A�W�A�����ꎑ���̊T�v�Ɠ��m���ɂɂ�铯�����̒����ƃ}�C�N���t�B�����ɂ����W���Ƃɂ��ĕ����B�x��́A���炪�E�Y�x�L�X�^���Ŏ��W���A�����m�w�������Ƌ������ƂƂ��Đi�߂Ă���q���@�E�n�[�����̃J�[�f�B�[�����R���N�V�����̖ژ^�쐬�ƍ���̌����̓W�]�ɂ��ĕ����B
���^�ł́A�J���~��i���s��w�j���A���s�O�����w�����A���r�A��ʖ{�ژ^�̐����Ɩژ^�쐬�Ɍg������o���̕��������B���u�̕����̒n�ł������ɂ�������炸�A40�����̎Q��������A���ɁA�ʖ{�╶���j���ɒ���ł����茤���҂��߂������B�܂��A�C�X�����j�̕�����z���A���{�̋ߐ��j�̓n�Ӎ_��i�����j���فj��[���b�p�����j��ˏƎq�i�啪��w�j������j���̌`�ԂɊւ��鎿�₪�o����A�u���j�j���v�Ƃ������ʐ��������S���Ă�ł����B���̈Ӗ��ł́A��B�j�w��Ƃ�����̂Ȃ��ŊJ�Â������Ƃ��A������������𗬂𑣂��Ă����Ƃ�����B�j���w�̃t�B�[���h�Ŏd��������Ă���n�ӎ��́A�u���{�j�ł������j�ł��A�Õ����w�͗��j�̕⏕�w����Ɨ��̗̈�Ƃ��ĔF�������悤�ɂȂ��Ă���A�}����������܂߂āA�����j�������̂ЂƂ̂�����Ƃ��ĂƂ炦��悤�ȏ��j�̎��_���K�v�ƂȂ��Ă���v�ƒ��ꂽ�B
�e�ɂ��ẮA�����z�z���ꂽ���W�����i�T�v�j���A�ȉ��Ɍf�ڂ���B
-
�ߔN�A���{�̃C�X���[���j�����ɂ����āA�ʖ{�╶���j���Ȃǎ菑���j���𗘗p�����������A����ɂȂ��Ă���B����́A���n�̐}���ق⎑���قȂǂł̉{���E���ʂ��I�[�v���ɂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ��傫�Ȏx���ƂȂ��Ă���B���̔��ʁA�����̎j���̗��p�́A���肩���ǂ܂Ō����Ҍl�̓w�͂ɕ����Ƃ��낪�傫���A�ʖ{�╶���̗��p�E�ۑ��ɂ��Ă̌n���I�ȏ����W�������x��Ă���Ƃ�������B
�C�X���[���n�挤���u�C�X���[���W�j���̎��W�v�ǂł́A��B��w�C�X���������w�Ȍ������Ƃ̋��Âɂ��A���L�̂悤�ȃV���|�W�E������悵�A�A���u�A�y���V�A�A�g���R�A�����A�W�A�j�̊e����̑����ł����̎j���̗��p�ɕ������Ă��錤���҂���A�ʖ{�╶���j����p����Ӌ`�Ɨ��p�@�ɂ��āA���H�I�ȏ�����Ă��������ƂƂ��ɁA�n���I�Ȏj���w�̖����ɂ��ċc�_���s���B
�m�҃��W�����Fpdf �t�@�C���ł��B�ǂނ��߂ɂ́AAcrobat Reader ���K�v�ł��B�n
�Ȃ��A�V���|�W�E���̊J�ÁE�^�c�ɂ������ẮA��B��w���w���C�X���������w�Ȃ̑喫�N�珕�������͂��߁A���w�Ȃ̉@���E�w���̕��X�̑S�ʓI�Ȃ����͂������ƂɁA�ӈӂ�\���܂��i���F�O�Y�@�O�j�B
- �@
�݊O�����҂�����
�݊O�����҂�����
- Christoph WERNER
- �@
- �����F�o���x���N��w�u�t
- ���ԁF1999�N12���Q���`�V��
- �����F
- 12���R���@������w���m�����������K��
- 12���S���@�u�y���V�A�ꕶ�����ۃ��[�N�V���b�v�v�ɂ����āA�� "The Winners of Qajar Social Transformation: a Case Study in Landownership". ���ɁA�Z�b�V�����̎i������߂�B�i���F������w�j
- 12���U���@�u�� "What is a Mujtahid? Functions and Stratification of Tabrizi Ulama in the Early Qajar Period".�i���F���m���Ɂj
- �T�v�F
- ���F���i�[���́A�u�y���V�A�ꕶ�����ۃ��[�N�V���b�v�v�Q���̂��ߗ��������B���[�N�V���b�v�ł͕̂ق��A�ߌ�̃Z�b�V�����̎i����Ƃ߂��B���̂ق��A12���R���͓�����w���m������������K��A�_�C�o�[�E�R���N�V���������w�A�U���ɂ͍��c�@�l���m���ɂ�K��A�U�ǎ��W�̃y���V�A�ꕶ�������w�̂̂��A������ "What is aMujtahid? Functions and Stratification of Tabrizi Ulama in the Early QajarPeriod".�Ƃ�����ōu�����s�����B�؍݂͂����Z���Ԃł��������A���{�̌����ҁE��w�@���Ɗ����Ȍ𗬂��s���A�o���ɂƂ��ėL�Ӌ`�ȋ@��ƂȂ����B
- �@
- �����F�E�Y�x�L�X�^�����m�w������������
- ���ԁF1999�N12���S���[10��
- �����F
- 12���S���@�u�y���V�A�ꕶ�����ۃ��[�N�V���b�v�v�ɂ����āA��"Uncatalogued Irshad-nama from funds of the Institute for Oriental Studies named after al-Biruni (Tashkent) "�i���F������w�j
- 12���U���@���m���ɂ�K��A�U�ǎ��W�̃y���V�A�ꂨ��ђ����A�W�A�W���������w
- 12���V���@�P�ǁE�����A�W�A�l�b�g���[�N��Â̌�����ŕ� ""The Great Schisim" among the Moslems of Ferghana Valley"�i���F������w���w���A�l�b�N�X�j
- 12���X���@�T�ǁE�U�Nj��Â̌�����ŕu����E�Y�x�L�X�^���̃X�[�t�B�Y�����Ƃ�܂������v�i���F���s��w���w���j
- �@
- �T�v�F
- �u�y���V�A�ꕶ�����ۃ��[�N�V���b�v�v�Q���̂��ߗ��������B�{�l�̑��Z�ƃE�Y�x�L�X�^���̏�����̂��ߗ����X�P�W���[�����Ȃ��Ȃ��m�肹���A�܂��A�킸���P�T�Ԏ�̒Z���؍݂Ō����������ƂȂ������A�Z�����Ԃ̂Ȃ��Ŋ����Ɍ������s���A�w�p�𗬂��ʂ������B�@�܂��A12���S���ɂ́A���c���璼�ډ��ɋ삯���A���[�N�V���b�v�ŕ��s�����B����́A�V�����̎j���Ɋւ���ŁA���n�����҂Ȃ�ł͂̓��e�ł������B�U���ɂ͍��c�@�l���m���ɂ�K��A�U�ǎ��W�̃y���V�A�ꂨ��ђ����A�W�A�W���������w�A�V���ɂ͂P�ǁE�����A�W�A�l�b�g���[�N��Â̌�����i���F������w���w���A�l�b�N�X�j�ŁA""The Great Schisim" among the Moslems of Ferghana Valley"�Ƃ�����ŕ��s�����B����Ɋ��ɂ���A12���X���A�T�ǁE�U�Nj��Â̌�����i���F���s��w���w������A�W�A�j�w�������j�ŁA�u����E�Y�x�L�X�^���̃X�[�t�B�Y�����Ƃ�܂������v�Ƃ�����ŕ��s�����B������̉�ɂ��A�����̌����ҁE��w�@�����Q�����A�����ɓ��_���s��ꂽ�B
���W�}���E���J���
���W�}���́A���ׂāA���m���ɂS�K�̃C�X�����n�挤���U�ǐ}�����ɂ����Č��J���B�R�s�[�T�[�r�X������܂��B�ǂ��������p���������B�܂��A���W�}���̏������f�[�^�x�[�X���쐬���B�܂��Ȃ��A�z�[���y�[�W��ɂāA���J���܂��B
�������X�����W�����@�~���R�������n�ɂāA������A�A���r�A��A�E�C�O����Ȃǎ���657�_���w���B�i�ڍׂ́A�o���Q���j
��A�W�A�����@�����N�V�A�I���N�痼�����p�L�X�^���ɔh�����A�y���V�A��A�E���h�D�[��A�p���W���[�u��ȂǁA���K��������̊�{����630�������W�����B�i�w�A�N�o����T�x(1892)�ANawar Kishore �Ńy���V�A�ꌴ�T�́w���ғ`�x�A�w�`�V���e�B�̌����i���z�[���j�j�x�ȂǁB�i�ڍׂ́A�o���Q���j�܂��A���c�����i�����O�����w�j�̋��͂ɂ��A�����ژ^�ޖ�90�_���p�L�X�^�������肵���B
�A���r�A�ꎑ���@�J�C�������{�w�p�U����J�C���A���Z���^�[���݂̒��c�l���i�R����w�j�̂����͂ɂ��A�v�z�E�@���W�𒆐S�Ɂi�Ƃ��ɃR�[�����̊e��̒��ߏ��ށ��^�o�^�o�[�C�[21���A�C�u���E�J�X�B�[��10���A�ߔN�̎v�z�������Ȃǁj�A��600�_�i1078���ȏ�j�̐}�����w���B�܂��A�ߔN�̓A���u���E�ł��R���s���[�^��p�����o�łɂ��A��^�̗��j�������X�Ɗ��s����Ă���A�C�u���E�A�T�[�L���w�_�}�X�J�X�j�x(50���j�A�o�O�_�[�f�B�[�w�o�O�_�[�h�j�x(24���j�Ȃǂ��w�������B�܂��A�����b�R��藯�w���̍��������Y�i������w��w�@�j���̂����͂ɂ��A���n�̏o�ŕ��𒆐S�ɁA��200�_�̐}�����w���B
�g���R�ꎑ���@�����m��i������w��w�@�j���̂����͂ɂ��A���j�E����𒆐S�ɖ�720�_�̐}�����w���B�g���R�ł́A�V���̏o�ł�����ł��邪�A��������������̂��ߊ��s�����̂����ƗǏ��ł���قǁA�w��������Ȃ�X��������A���N�x�͂Ƃ��ɁA�n���o�ŕ��Ȃǂ̋ߔN�̐V�����̕�[�𒆐S�ɍs�����B
�y���V�A�ꎑ���@�C�������A�����ށE�G���𒆐S��57�_211���i���G��10�_�A117���j�̐}�����w���B��ȎG���Ƃ��ẮA�w�A���}�K�[���x�A�w�C�[���[���V���t���x�A�w���@�q�[�h�x�A�w�o�n�[���x�A�w�i�V�����[�C�G�@�C�G�E���@�U�[���e�E�I���[���E�n�[���W�F�x�ȂǁB���ɃA�[���o�C�W������̎����P�_�i�R���j�ƎG���P�_�i15���j�B
�@
�����A�W�A���ꎑ���@���O�I�i�������͎ҁj���E�Y�x�L�X�^������уJ�U�t�X�^���ɔh�����A�E�Y�x�N��A�J�U�t��A���V�A��Ȃǂɂ�镶�w�E���j�E����W�̎����i�V�����E�Ï��E�����E�G���Ȃǁj266�_296�������W�����i�w�J�U�N�^���x�w�^���@�[���[�q���O�W�[�_�E�k�X���b�g���i�[���x�Ȃǂ̏��ЁA�w�A���V�F�����i���@�C�[�̒���̌���ډ����T�x�Ȃǂ̎��T�A�w�T���T�g�x�Ȃǂ̎G�����j�B
�A���r�A�ꎑ���@����h���i������w�A�݊w�p�U����J�C�������A���Z���^�[�j�̋��͂ɂ�萭���E�o�ό����̊�b�ƂȂ鎟�̎G������7�_���w�������B�w�Љ���G���x�i1940-46�A20���j�w�t�X�[���x�i1980-88�A27���j�w�J�C���x�i1985-97�A55���j�w��Ɓx�i1961-80�A63���j�w�@�����x�i1985-97�A12���j�A�w�q���[���x�i1951-98�A146���j����сw���O�����x�i1965-96�A52���j�B
�g���R�ꎑ���@�����m��i�������͎ҁj�̋��͂ɂ��A�n���j�A��c�^�A����A�o�ρA�g���R�����̏��������̗��j�����𒆐S�ɁA558�_610�������W�����B�w�I�X�}�������h���Z�ɂ����鋳��x�i�}�t���b�g�E�M�������j�A�w�I�X�}�������[���b�p���Z���{�x�i�n�C�_���E�J�Y�K�����j�A�w�C�X�^���u�[���_�Ǝj�x�i�A�t���b�g�E�^�o�b�N�I�E�����ҁj�ȂǁB
�y���V�A�ꎑ���@����A�@���A�����A�o�ρA�|�p�ȂǏ�����̎G��19�_216�������W�B�p�t�����B�[������Ɋ��s���ꂽ�w�A�[���[�[�V���E���@�E�p�����@���V���x�w�G�b�e���[�A�[�e�E�}�[�n�[�l�x�A�w�l�M�[���x�A����E��풆�i1941-45�j�Ƀ����h���ŏo�ł��ꂽ�w���[�Y�M���[���E�m�E�x�B�v����̐V���i�����j�w�P�C�n�[�l�E�t�@���n���M�[�x�i1984-97�A1-14���j�ȂǁB
����A�W�A�����@����A�W�A�̃C�X���[�����E�A���Ȃ킿�}���[���E�Ɋւ����b�������A���������i�T�o�E�}���[�V�A��w�u�t�j�̋��͂ɂ���Ď��W�����B�w�C�X���[���S�Ȏ��T�x�i�V���j�A�w�C�X���[���S�ȁx�i6���j�A�w�}���[�V�A�S�Ȏ��T�x�i17���j�Ȃǂ̎��T�ށA�w���n���}�h�`�x�i10�� �j�A�w�R�[������x�i11���j�A�w�R�[�������߁x�i�R���j�Ȃǂ̏@�����A���ғ`�A�N��L�Ȃnjv346�_�����W�����B
�@
�A���r�A�ꎑ���@���s���N���i��Q�ǁj����сA�喫�N�玁�i��B��w�j�̋��͂����āA���N�x�́A�����b�R�ƃG�W�v�g����P�s�{375�_460���A�G���U�_173�����w�������B���_��������ƁG�}�N���[�W�[�w�������̒m���̗��x�x�C���[�g�A1997�A�S�U���B�A���E���X�^�t�@�E�O�}�[�q���w���̎��@�����x�J�T�u�����J�A1998�B�A���[�E�z�X�j�w���@�Ɛ����w�x�}���P�V���A1998�B���X�^�t�@�E�A�b�X�o�[�C�w���m�w�Ɠ��m�w�ҁC���ƕ��̈�Y�x�J�C���A1998�B���n���}�h�E�N�g�D�u�w�R�[���������x�x�C���[�g�A1993�ȂǁB
�y���V�A�ꎑ���@���m���Ɍ����������t�����̋��͂����āA�P�s�{382�_467���A�G��67�_164�����w�������B���_��������ƁG�G�Y�g�b���[�E�l�M���t�o�[���w�C�����l�Êw��50�N�x�A���t�^�[�t�E�G���n�[���w�o���t�n���ƃI�N�Z�X�͒n���̗��j�n���x�A�A�u�h�b���[�E�A�����@�[���w���E�����҃i�[�f���E�V���[�x�A�G���w�t�@�X���i�[��?�C�F�E�e�A�[�g���x�i�P�[16���A1988-1992�j�A�G���w�J�[���F�x�i�P�[70���A1963-1978�j�ȂǁB
�g���R�ꎑ���@�U�nj������͎ҍ����m�ꎁ�̋��͂����ĒP�s�{410�_458���A�G���T�_51�����w�������B���_��������ƁG�x�g�D���E�I�Y�`�F���r�w���a������̕��w��]�x�i�S�Q���j�A�g�D���O�g�E�A�N�v�i���w�g���R�l�̏@���Ɩ@�̗��j�x�A�l�V�F�E�C�F�V���J���w�l���̉Ɓ[���̗����҂ƃC�f�I���W�[�x�A���t���g�E�J���w�g�D���N������x�A���t�@�[�C���E�t�Y���w�I�X�}��������̃u���T�̃}�h���T�x�ȂǁB
- �@
�@
�{�ǂ̊����ɂ��Ă̂��₢���킹�₲�ӌ��͉��L�̃A�h���X�ɂ����������B
���[���A�h���X�FIAS6@toyo-bunko.or.jp