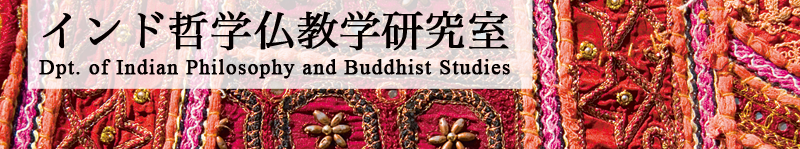『インド哲学仏教学研究』
概 要
『インド哲学仏教学研究』はインド哲学仏教学研究室で年一回発行している紀要です。
当研究室にて閲覧できるほか、東京大学学術機関リポジトリ(UT Repository)にて、全文を読むことができます。
- 【既刊号の目次】
- 第31号 (2023)
- 第30号 (2022)
- 第29号 (2021)
- 第28号 (2020)
- 第27号 (2019)
- 第26号 (2018)
- 第25号 (2017)
- 第24号 (2016)
- 第23号 (2015)
- 第21号 (2014)
- 第20号 (2013)
- 第19号 (2012)
- 第18号 (2011)
- 第17号 (2010)
- 第16号 (2009)
- 第15号 (2008)
- 第14号 (2007)
- 第13号 (2006)
- 第12号 (2005)
- 第11号 (2004)
- 第10号 (2003)
- 第9号 (2002)
- 第8号 (2001)
- 第7号 (2000)
- 第6号 (1999)
- 第5号 (1998)
- 第4号 (1996)
- 第3号 (1995)
- 第2号 (1994)
- 第1号 (1993)
『インド哲学仏教学研究』第32号
2024年3月発行
目 次
| KATO, Takahiro | “Would rather be a jackal” : Criticism of Vaiśeṣika’s concept of liberation | 李, 慈郎 | 破僧定義再考 : パーリ律における二種の破僧の関係 | 伊藤, 有佑 | パーリ注釈文献における菩提分法の「法」 | 木村, 和樹 | 〈同一判断〉ekapratyavamarśa について : Pramāṇavārttika I 109 に対する注釈者の見解 | 鈴木, 政宏 | 『文殊師利根本儀軌経』成立過程の解明の試み |
『インド哲学仏教学研究』第31号
2023年3月発行
目 次
| [著者名なし] | 下田正弘教授 略歴・業績一覧 | TAKAHASHI, Kenji | Draupadī’s Polyandry Revisited | 柳, 幹康 | 大慧宗杲の悟りの構造 |
『インド哲学仏教学研究』第30号
2022年3月発行
目 次
| KAJIHARA, Mieko | The Observances or vedavratas for Learning of the Veda | TANIGUCHI, Chikamitsu | Historically Repositioning Devaṇṇabhaṭṭa’s bhāṣādi- and dharmādivyavahāracatuṣpādatva in Medieval Sanskrit Jurisprudence | 藪内, 聡子 | 『チューラワンサ』における歯舎利: アヌラーダプラ時代からダンバデニヤ時代における王権とサンガとのかかわり | 和田, 賢宗 | ツォンカパにおける人法二無我の確定順序 |
『インド哲学仏教学研究』第29号
2021年3月発行
目 次
| 蓑輪, 顕量 | 天台智顗に見る心の負の反応への対処法 | 護山, 真也 | ヨーガ行者の直観をめぐるジュニャーナシュリーミトラの議論 -『ヨーガ行者の確定』解題にかえて- | 小谷, 昂久 | 『順正理論』に基づく『俱舎論』の改変 -kilaの解釈をめぐって- | 佐久間, 祐惟 | 虎関師錬の禅風論 -『正修論』「質惑第七」における四種禅風批判の考察- | ※冊子体第29号目次で佐久間氏の論文サブタイトルが脱落しておりました。謹んでここに訂正いたします。 |
『インド哲学仏教学研究』第28号
2020年3月発行
目 次
| 加藤, 隆宏 | 初期不二一元論派における anvayavyatireka 説再考 | 鈴木, 知子 | 『ラージャタランギニー』の第8章について -複数のバージョンが共存していた可能性- | 千房, りょう輔 | 部派仏教における入出息念の展開 -パーリ仏典と北伝の漢訳資料との比較- |
『インド哲学仏教学研究』第27号
2019年3月発行
目 次
| 下田, 正弘 | エクリチュール論から照らす仏教研究 -大乗経典研究準拠枠構築のこころみ- | 左藤, 仁宏 | Mahāvastuにおけるava-√lokの用例 -誰が何を観察するか- | 井野, 雅文 | 『中観光明論』における一乗思想と如来蔵思想 | 余, 新星 | 伝法衣の相承と仏光派の法系図について |
『インド哲学仏教学研究』第26号
2018年3月発行
目 次
| [著者名なし] | 丸井浩教授 略歴・業績一覧 | 鈴木, 隆泰 | 一切皆成の授記『法華経』 : 「常不軽菩薩品」を中心に | 楊, 潔 | 「随与」(*anupradāna)について : 五遍行における思(cetanā)の一側面 | 渡邉, 要一郎 | Saddanītiにおける文法学の位置づけ | 張, 文良 | 鳳潭の『大乗起信論議記幻虎録』について : その思想史の位置づけを中心に |
『インド哲学仏教学研究』第25号
2017年3月発行
目 次
| KAJIHARA, Mieko | Giving the Bride to the Bridegroom with Water at the Ancient Indian Marriage Ritual | 竹崎, 隆太郎 | リグヴェーダにおける表現「心臓において(L.)貫く(√vyadh)」とその意味的展開 | 内田, みどり | 仏教における自殺の意味 : Delhey論文に対する一考察 | 岡田, 繁穂 | 初期瑜伽行派3文献におけるsaṃgraha(摂, bsdus pa) : 『瑜伽師地論』『顕揚聖教論』『阿毘達磨集論』 | 曾, 柔佳 | 『楞伽経』における涅槃 : vikalpakasya manovijñānasya vyāvṛttirの解釈をめぐって | 井野, 雅文 | 『修習次第初篇』が引用する『楞伽経』X.256-258の異読とその背景 | 王, 俊淇 | 吉蔵の『中論』科段について |
『インド哲学仏教学研究』第24号
2016年3月発行
目 次
| [著者名なし] | 斎藤明教授業績一覧 | [著者名なし] | 高橋孝信教授業績一覧 | Minowa, Kenryō | Buddhist Thought in Late Tokugawa Didactic Poetry (dōka) Collections : Understandings of the Mind | 小林, 史明 | 占星術で使用される三種の時刻について : Bādarāyan. a Prásnavidyā 4–5 を手がかりに | 高橋, 晃一 | 『菩薩地』における菩薩蔵(bodhisattvapiṭaka)の位置づけ | 王, 芳 | 『嘉興蔵』と江戸仏教 : 鳳潭『扶桑蔵外現存目録』を中心に |
『インド哲学仏教学研究』第23号
2015年3月発行
目 次
| Giglio, Emanuele D. | Reconsidering the Relation Between Shunpan and Nichiren : Focusing on Nichiren’s Period of Studies at Mt.Hiei | 陳, 継東 | 釈迦への回帰 : 近代日中における釈迦原典探索の始まり | 日野, 慧運 | 義浄訳『金光明最勝王経』について : 第24章「除病品」付加部分を中心として | 井野, 雅文 | 『修習次第初篇』が引用する『楞伽経』X.256–258と菩薩の階位との対応について | 鄭, 祥教 | TattvasaṃgrahaおよびTattvasaṃgrahapañjikā第7章第6節「犢子部が構想分別するアートマン(プドガラ)の考察」テキスト考 | Licha, Stephan | 曹洞宗における切紙伝授の起源について : 五位説における「銭」の比喩を中心として |
『インド哲学仏教学研究』第21号
2014年3月発行
目 次
| 蓑輪, 顕量 | 風間真一様三回忌追悼の記念講話 | Kajihara, Mieko | Seizing the Novice’s Hand and Pouring Water into His Hands at the Vedic Initiation Ritual | Wu, Juan | Stories of King Bimbisāra and His Son Ajātaśatru in the Cīvaravastu of the Mūlasarvāstivāda-vinaya and Some Śvetāmbara Jaina Texts | 渡邉, 眞儀 | ヴァイシェーシカ哲学における過去・現在・未来 : 『キラナーヴァリー』の読解を中心に | 高橋, 晃一 | 『解深密経』の結文に関する考察 : 大乗経典編纂の痕跡という観点から | 朴, 賢珍 | 『六十華厳』の章立てに関する考察 : 『華厳経』諸本の章立ての相違を手がかりにして | 新作, 慶明 | laukikaṃ paramārtham : Prasannapadā 第24章第10偈導入箇所におけるテキストの問題 | 岡田, 文弘 | 鎮源『大日本国法華経験記』の異類功徳譚 : 第106話「伊賀国報恩善男」を中心に |
『インド哲学仏教学研究』第20号
2013年3月発行
目 次
| He, Huanhuan (何,歓歓) |
The Vedānta Simile of “Pot-space” in the Madhyamakahṛdayakārikā and the Tarkajvālā | Saitō, Akira (斎藤,明) |
A Shape in the Mist: On the Text of Two Undetermined Sūtra Citations in the Prasannapadā | 韓, 尚希 | 四聖諦と八聖道の体系からみたcetovimutti とpaññāvimutti | 荘, 崑木 (釈, 大田) |
世親作『縁起経釈』の名色支について : 五蘊の意味を中心に | 鄭, 祥教 | チャンドラキールティのプドガラ(人格主体)論批判 : 「七通りの仕方による考察」を中心として | 酒井, 真道 | ダルモーッタラの刹那滅論研究 : sattvānumāna における論証因—– 存在性(sattva)—– 成立の問題 | 張, 文良 | 連続性と非連続性 : 呂澂の中国大乗佛教批判について | Giglio, Emanuele D. | 『諸法実相抄』の来歴 : 「録内」「録外」の集成事情と最蓮房伝から | 豊嶋, 悠吾 | 『釈論愚草』における頼瑜の真言教学の特徴:「二門峙立」と理理無辺について |
『インド哲学仏教学研究』第19号
2012年3月発行
目 次
| Choi, Kyeong-jing | Did Dharmakīrti Criticize Dignāga's Assertion?: On the Purpose of Stating vyatireka in the Pramāṇaviniścaya |
| 丸井,浩 | 「正しく知られるべき対象」(prameya) としての artha 概念の変貌 ―ジャヤンタが語るニヤーヤ哲学の思想的位置をさぐる一視点― |
| 加藤,隆宏 | バースカラの無明論批判と別異非別異論 |
| 一色,大悟 | 『順正理論』における引果と取果 |
| 新作,慶明 | アヴァローキタヴラタの瑜伽行派批判についての一考察 ― Madhyāntavibhāga 第 I 章第 3 偈の解釈をめぐって― |
| 西沢,史仁 | 非認識手段の知の起源に関する一考察 |
| 王,芳 | 鳳潭の生没年及び出身地に対する一考察 |
『インド哲学仏教学研究』第18号
2011年3月発行
目 次
| Takahashi, Takanobu | Jain Authorship in Tamil Literature : A Reassessment |
| Saito, Akira | Bhavya's Critique of the Sāṃkhya Theory of pratibimba |
| He, Huanhuan | Bhavya's Critique of the Vaiśeṣika Theory of Liberation in the Tarkajvālā |
| 友成, 有紀 | Brhatī および Nyāyamañjarī に見られるパーニニ文法学批判 |
| 吉次, 通泰 | 古代インド医学における加齢と寿命について |
| 柳, 幹康 | 『楞伽経』と『二入四行論』 : 「楞伽宗」の思想とそこに占める『楞伽経』の位置 |
『インド哲学仏教学研究』第17号
2010年3月発行
目 次
| Tsuchida, Ryutaro | On the dynastic transition from the Śuṅgas to the Kāṇvāyanas |
| Saito, Akira | An Inquiry into the Relationship between the Śikṣāsamuccaya and the Bodhi(sattva)caryāvatāra |
| 近藤,隼人 | Pramāṇasamuccayaṭīkā 第 1 章に見る Ṣaṣṭitantra 注釈書の知覚論 : Yuktidīpikā との関連を中心に |
| 岩崎, 陽一 | Tattvacintāmaṇi における言葉の妥当性の根拠と確定方法 |
| 中西, 俊英 | 唐代仏教における「事」的思惟の変遷 : 華厳文献を中心として |
| 石上, 和敬 | 正倉院聖語蔵本,曇無讖訳『悲華経』に見られる朱筆の書き入れについて |
『インド哲学仏教学研究』第16号
2009年3月発行
目 次
| Tsuchida, Ryutaro | Some Reflections on the Chronological Problems of the Mahābhārata |
| Muller, A. Charles | Wonhyo on the Lotus Sūtra |
| 一色, 大悟 | 有部アビダルマ文献における無為法の実有論証について |
| 田中, 公明 | 『アームナーヤ・マンジャリー』に見るサンヴァラ曼荼羅の解釈法 |
| 西沢, 史仁 | ゲルク派の認識手段論 : タルマリンチェンの解釈について |
| 土屋, 太祐 | 玄沙師備の三句の綱宗 |
『インド哲学仏教学研究』第15号
2008年3月発行
目 次
| Ryūtarō Tsuchida | Considerations on the Narrative Structure of the Mahābhārata |
| Jonathan A. Silk | The Indian Buddhist Mahādeva in Tibetan Sources |
| 吉次 通泰 | 古代アーユルヴェーダの終末期医療 |
| 藪内 聡子 | スリランカの仏教王権 ――アヌラーダプラ時代における王権とサンガ―― |
| 柳 幹康 | 『楞伽師資記』に見える禅問答の萌芽について ――指事問義と鏡の譬喩―― |
| 張 欣 | 「念仏者是誰」 ――その思想源流について―― |
| Didier Davin | 『狂雲集』臨済四料簡試釈 |
| 王 芳 | 鳳潭と永覚元賢の曹洞偏正五位理解について |
『インド哲学仏教学研究』第14号
2007年3月発行
目 次
| Ryūtarō Tsuchida | On the Textual Division of the Original Bṛhatkathā |
| Anne MacDonald | Revisiting the Mūlamadhyamakakārikā: Text-Critical Proposals and Problems |
| 宮崎 展昌 | 『阿闍世王經』(T626) の漢訳者について |
| 吉川 太一郎 | 鮮演の用いる比喩について |
| 西村 玲 | 徳門普寂 ――その生涯 (1707-1781年)―― |
『インド哲学仏教学研究』第13号
2006年3月発行
目 次
| Ryūtarō Tsuchida | The Formation of the Akuramaṇī- and the Parvasaṃgrahaparvan of the Mahābhārata |
| Akira Saitō | Śāntideva's Critique of 'I' or Self in the Early and Later Recensions of the Bodhi(sattva)caryāvatāra |
| John R. McRae | State Formation, Indigenization, and Buddhism in East Asian History: The Theoretical Foundation |
| 高橋 孝信 | 文法以前――古典テキスト解釈の諸問題―― |
| 堀内 俊郎 | 『雑阿含』809経における「鹿林梵志子」――『釈軌論』所引の ri dgas zlog gi mdo との関連で―― |
| 爪田 一寿 | 善導浄土教のいわゆる「国家仏教」的側面について――『法事讃』と龍門石窟―― |
『インド哲学仏教学研究』第12号
2005年3月発行
目 次
| Klaus-Dieter Mathes | 'Gos Lo tsā ba gZhon nu dpal's Commentary on the Dharmatā Chapter of the Dharmadharmatāvibhāgakārikās |
| 青野 道彦 | 四大教法(cattāro mahāpadesā)の解釈の変遷 ――ブッダゴーサにおける転換―― |
| 金 天鶴 | 東アジアの華厳思想における無碍説 |
| 池 麗梅 | 『国清百録』の完成年代に関する一考察 ――随煬帝と天台山教団との交渉をめぐって―― |
| 石田 尚敬 | 〈他の排除(anyāpoha)〉の分類について――Śākyabuddhi と Śāntarakṣita による〈他の排除〉の3分類―― |
『インド哲学仏教学研究』第11号
2004年3月発行
目 次
| Jinhua CHEN | Another Look at Tang Zhongsong's (r.684,705-710) Preface to Yijing's (635-713) Translations: With a Special Reference to Its Date |
| 田村 典子 | 仏弟子アーナンダの呼称 Vedamuni について |
| 藤井 淳 | 『大乗涅槃経』とアビダルマ仏説論 ――恒河七衆生(水喩)の考察―― |
| 堀内 俊郎 | 『釈軌論』における三三昧 ――『声聞地』との比較を通じて―― |
| 大野田 晴美 | Pramāṇasamuccaya におけるディグナーガとヴァイシェーシカ学派の論争 |
| 里美 英一郎 | ソーマ祭での複合型歌詠マントラ stotra に配される数の象徴性の工夫 ――数的符号((saṃpad)を手掛かりとして―― |
『インド哲学仏教学研究』第10号
2003年3月発行
目 次
| 清水 元広 | 『カターヴァットゥ』の論理 |
| 馬場 紀寿 | 縁起支解釈の展開――上座部大寺派の三世両重因果説―― |
| 鈴木 健太 | 『般若経』における正性に確定した者の発心をめぐって――『般若経』諸註釈書の解釈方法をめぐって―― |
| 張 文良 | 澄観における如来蔵と阿頼耶識 |
| 金 京南 | 中国華厳における「入法界品「理解」――智厳と法蔵を中心として―― |
| 高柳さつき | 痴兀大慧の兼修禅――『十牛訣』を中心に―― |
『インド哲学仏教学研究』第9号
2002年9月発行
目 次
| 木村 清孝 | 「三界唯心」考 ――モノ・こころ・いのちへの仏教学的視点―― |
| 谷沢 淳三 | ダルマキールティに見る仏教論理学派の知覚論の直接実在論的傾向 |
| 志田 泰盛 | Vācaspati による認識の他律的検証過程――NVTTにおける真知論―― |
| 加藤 純一郎 | 布施の変容について |
| 加藤 弘二郎 | 「唯識」という文脈で語られる影像――『解深密経』「分別瑜伽品」と「声聞地」の比較検討を通して―― |
| 佐々木 一憲 | Śikṣāsamuccaya における菩薩の学処整理法とそのヴィクラマシーラの学僧への影響について |
| 佐藤 もな | 中世真言宗における浄土思想解釈――道範『秘密念仏抄』をめぐって―― |
『インド哲学仏教学研究』第8号
2001年3月発行
目 次
| 彌永 信美 | 如意輪観音と女性性 |
| 伊澤 敦子 | Agnicayana における動物供犠 |
| 宮本 城 | Manimekalai における turavu |
| 加藤 隆宏 | ヴィヴァラナ派における māyā, avidyā, ajñāna ― 実在の三階層との関連から ― |
| 陳 素彩 | 説一切有部における anuzaya・kleza・paryavasthāna の関係 ―『倶舎論』「随眠品」を中心として ― |
| Tomomichi NITTA | The Meaning of the Former Buddhas in the Mahāpadānasuttanta |
『インド哲学仏教学研究』第7号
2000年3月発行
目 次
| 木村 清孝 | 故江島恵教教授を想う |
| 下田 正弘 | 【随想】わすれられないおくりもの ― 江島惠教先生 ― |
| 小野 卓也 | Nyāyasūtra1.1.5 は推理を定義できるか ― Bhāsarvajña の解釈と伝統説批判 ― |
| 薮内 聡子 | 初期仏教教団における教法伝持の構造 ― 頭陀行者の系譜 ― |
| 高橋 晃一 | 『二万五千頌般若』における「空」「上可得」「上可説」 |
| 佐古 年穂 | 異熟因果について ―『倶舎論』を中心として ― |
| Stefan KOCK | The Dissemination of the Tachikawa-Ryu and the Problem of Orthodox and Heretic Teachings in Shingon Buddhism |
『インド哲学仏教学研究』第6号
1999年3月発行
目 次
| 片岡 啓 | 永遠のダルマと顕在化 ― 祭事教学ミーマーンサーにおける「ダルマ開顕説」再建に向けて ― |
| 藤井 隆道 | 文意理解の三条件と語意習得 ― anvitābhidhāna 説との関連から ― |
| 高橋 晃一 | 『大集経』に見られる anabhilāpya の用例と『菩薩地』の思想形成との関連について |
| 徐 海基 | 澄観の華厳法界観 |
『インド哲学仏教学研究』第5号
1998年3月発行
目 次
| ターナヴットー・ビック | ニカーヤにおける修行道の相互関係 ― 四念処と七覚支および八聖道との比較研究 ― |
| 李 慈郎 | 根本分裂の原因に関する一考察 |
| 鈴木 隆泰 | 『大雲経』の目指したもの |
| 護山 真也 | 来世の論証にみる Prajñākaragupta の未来原因説 |
| 藤丸 智雄 | 曇鸞の光明観に関する考察 |
| 蓑輪 顕量 | 南都における戒律復興運動初期の動向 |
| 沈 仁慈 | 凝念の戒律思想 |
『インド哲学仏教学研究』第4号
1996年12月発行
目 次
| ターナヴットー・ビック | ニカーヤにおける八聖道と三学系統の修行道 |
| 李 慈郎 | Samantapāsādikā Bāhirakanidānaとパーリ年代記の比較研究 |
| 李 栄洙 | シャンカラにおけるバクティの概念 ―『バガヴァット・ギーター註解』を中心にして ― |
| 青野 貴芳 | ブラフマンと世界の同一性 ―ヴァッラバのブラフマン観 ― |
| 曺 潤鎬 | 『円覚経』解明の視点 ―経典成立史的観点から ― |
| 王 翠玲 | 永明延寿の伝記について |
| 陳 継東 | 楊文会撰『観無量寿仏経略論』の浄土思想 ― 十六観の問題を中心として ― |
『インド哲学仏教学研究』第3号
1995年10月発行
目 次
| 金 宰晟 | 『清浄道論』における刹那定と近行定 ― Samathayāna と Vipassanāyāna の接点― |
| 西沢 史仁 | カマラシーラのディグナーガ批判 ― 唯識性の理解を巡って― |
| 杉本 恒彦 | Ānandagarbha の曼荼羅成就法論 |
| 片岡 啓 | 「ナラセル」の解釈学 ―『シャバラ註』における bhāva, kriyā, bhāvanā― |
| 西本 照真 | 三階教の教団規律について ―『制法』一巻の研究― |
| 李 恵英 | 慧苑『続華厳略疏刊定記』研究 ― 八十華厳経の翻訳と教体論をめぐって― |
| 前川 健一 | 円珍『法華論記』の引用文献 ― 未詳文献の解明を中心に― |
『インド哲学仏教学研究』第2号
1994年9月発行
目 次
| 葉 徳生 | 『大智度論』における尸羅波羅蜜 |
| 岡田 繁穂 | 『阿毘達磨集論』における仏徳の記述 ―『瑜伽師地論』『顕揚聖教論』との比較― |
| 計良 龍成 | paryudāsa と prasajya-pratiṣedha |
| 種村 隆元 | Kriyāsaṃgraha の出家作法 |
| 川尻 道哉 | 語意認識における saṃskāra の役割 ― Maṇḍanamiśra の理論― |
| 戸田 裕久 | シヴァ一元論における志向作用 ― アビナヴァグプタにおける vimarśa と pratyavamarśa の用法― |
| 沈 奉燮 | Jīvanmuktiviveka における解脱論 |
| 渡辺 浩希 | Mahānirvāṇatantra の varṇa 観 |
『インド哲学仏教学研究』第1号
1993年9月発行
目 次
| 上田 昇 | ディグナーガにおける“内包”と“外延” |
| 石上 和敬 | Karuṇāpuṇḍarīka 研究序説 |
| 岸根 敏幸 | 『入中論』における中観学説の提示 ―『十地経』の引用をめぐって― |
| 計良 龍成 | 無自性性論証における能遍の無知覚因の機能について |
| 斉藤 仙邦 | 非知覚の定義をめぐる問題 ―『因一滴論』を中心にして― |
| 高堂 晃壽 | 『南陽和上頓教禅門直了性壇語』における三学 |