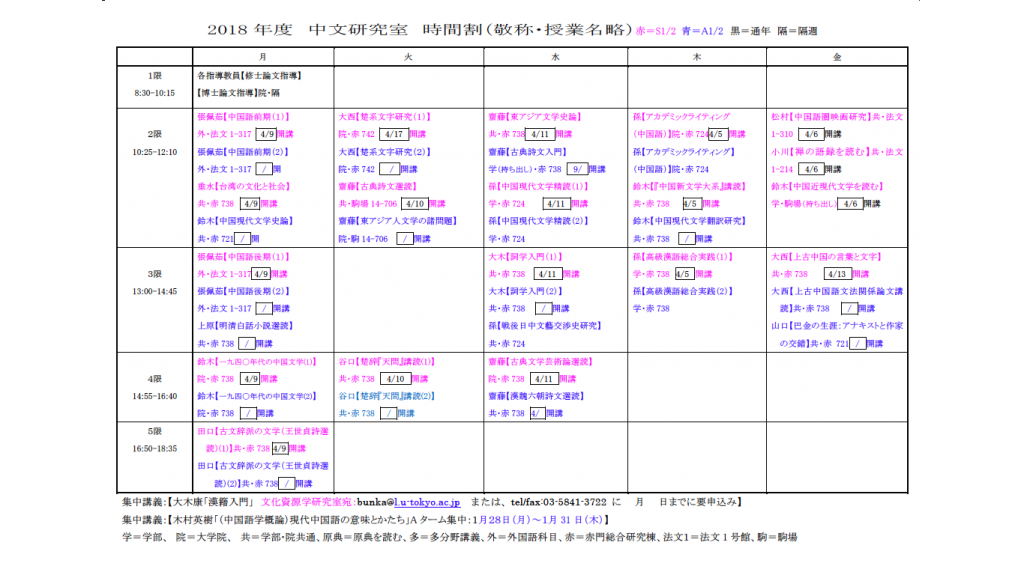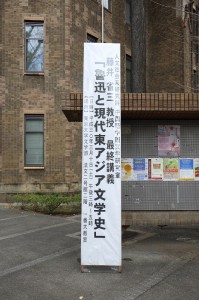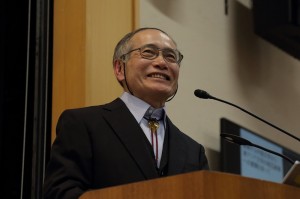2024年度修士論文(6名)
郭昕「中国古典小説における風-「異空間」への架け橋として-」
鄭徳峘「中国の歌謡を見た黄瀛」
薄鋒「漢詩制作に見る夏目漱石の「静」」
藤村明日香「『水滸傳』諸版本における詩詞の変遷をめぐって」
安原大熙「森春濤『悼亡詩』論」」
羅嘉睿「胡風における弱小民族文学翻訳『山霊』を中心に」
2023年度修士論文(5名)
顔小凡「二陸における望郷―贈答詩を起点として―」
胡睿「戦時下の徐遅における「現実」を論ずる:詩と報告文学を中心に」
裴杰「和訳『紅楼夢』の圏域と美の意識ー昭和時期を中⼼としてー」
葉曉同「上古中国語に「形容詞」という文法範疇はあったか」
楊乃馨「『玉臺新詠』における綺語の研究」
2022年度修士論文(1名)
耿沛涵「唐代における詠物詩の変化について」
2021年度修士論文(2名)
金卓「上古中国語における「疾」「病」再考――出土資料による」
森下朋美「馮夢龍と万暦三大征」
2020年度修士論文(1名)
小嶋奎吾「『漢書』における「文」の位置づけ」
2019年度修士論文(1名)
趙鈺傑「頼山陽『日本楽府』研究――創作の方法を中心に」
2018年度修士論文(3名)
三村一貴「上古漢語の副詞「蓋」のモダリティ」
片倉峻平「清華簡を中心とした楚簡の用事避複についての考察」
王 柳「莫言の文学における郷土とその想像」
2017年度修士論文(3名)
今井順子「中国“語文”教科書のなかの魯迅―「藤野先生」から考える「魯迅の希望」―」
金子賢太郎「九〇年代台湾の同志雑誌における文学――《G&L》掲載作品の分析を中心に」
武 茜「『捜神記』の編纂――「方士的儒生世界」の浮上」
2016年度修士論文(6名)
張 憶「日本における莫言文学の受容:1949年以後の中国農村社会凝視を中心に」
李 慧文「東アジアにおける村上春樹文学とウォン・カーウァイ映画について―ウォン・カーウァイと村上春樹の影響関係を巡って―」
李 筱婷「馬王堆漢墓帛書『春秋事語』用字研究」
市原靖久「上古中国語の一人称代名詞「我」と「吾」について」
彭 琳「寺山修司の作品における中国―魯迅との比較を中心に」
LI Jing「1929年-1930年における陶晶孫の左翼文芸活動について―『大衆文芸』でのプロレタリア文学作品の翻訳を中心に―」
2015年度修士論文(1名)
蔡 燕梅「清初杭州の文人ネットワークと『尺牘新語』」
2014年度修士論文(4名)
松原 功「福岡・亀井門下の女子漢詩文教育(付)少栞と雪首の贈答詩」
榑林雪子「老舎『四世同堂』日・英翻訳研究」
陳 佳「張愛玲の小説と映画化作品におけるイメージの比較研究―『傾城の恋』と『半生縁』をめぐって」
林 愷胤「台湾語の授与動詞の歴史変遷」
2013年修士論文(3名)
卓于綉「日本統治期台湾における映画文化の形成をめぐって」
宮島和也「出土文献から見た上古中国語における「于」と「於」」
張燁萌「鄧小平時代以降の中国における日本児童文学の受容―宮沢賢治、新見南吉、安房直子を中心に」
2012年修士論文(6名)
鈴木政光「温庭筠詩における情景表現の諸相―李商隠・杜牧との比較を中心に―」
杉山裕梨「『三国志演義』における女性描写について」
権慧「中国語圏・韓国における村上春樹文学の翻訳状況と受容状況の比較研究―『ノルウェイの森』を中心に―」
千賀由香「近世白話小説における民間宗教―蘇庵主人『帰蓮夢』を題材に―」
YANLU「映画『さらば、わが愛 覇王別姫』の日本における受容の研究」
張瑶「ポスト鄧小平時代における郭敬明を中心とする「八〇後」文学研究―その模作的創造と出版戦略をめぐって」
2011年度修士論文(6名)
八木はるな「映像による白先勇文学再創造―35年後の「孤恋花」、ポスト民主化の台湾で―」
徐 子怡「中国における「村上チルドレン」及び「村上春樹ファッション」~「70後」「80後」作家群・書き込みサイト読者を中心に~」
田 家綾「侯孝賢映画における空間イデオロギーの再構築」
楊 冠穹「「八〇後」と現代中国出版市場の変容~韓寒を中心に」
白石将人「渋川春海の分野説に就いて」
武井遥香「中国古典小説における女性の「侠」の変遷について―唐代から明代まで―」
2010年度修士論文(3名)
吉原小百合「中国語の名詞述語文“NP了”構文の意味と構造」
笠見弥生「「三言」「二拍」における道教」
佐髙春音「『水滸傳』における人物の形容表現について」
2009年度修士論文(4名)
明田川聡士「「虚構」の想像/創造~李喬《寒夜三部作》におけるフォークナー作品からの影響を中心に~」
加藤健太郎「「二二八文学」と台湾意識の変遷――呉濁流『無花果』と李喬『埋冤・1947・埋冤』を中心に――」
藤田 玲「饒舌なトポス――莫言が高密の大地から聞く音と声」
林 卓頴「「三言」所収白話小説とその文言原作との比較――恋愛に関する話を中心に」
2008年度修士論文(2名)
蓋 曉星「日本における中国映画『白毛女』の受容――一九五〇年代から一九七〇年代まで」
侯 蘇寒「テレビドラマから見る中国人の経済観念」
2007年度修士論文(7名)
糸原敏章「大徐本『説文解字』反切の研究」
加納留美子「蘇軾詩に見る夜の諸相」
謝恵貞「日本統治期台湾人日本語作家巫永福小説における横光利一の受容と変容――『文体模写』『空想・夢描写』による『自由間接話法』の達成」
蕭 涵珍「李漁の作品における両面性:真情の重視と伝統的礼教」
高橋直子「映像と文学に見る『女の街』上海―老上海から現代に続く系譜―」
陳 燕琪「老舎の『微神』論――ダンテおよび英文学からの影響を中心に」
長谷川賢「中国語における条件構文のカテゴリー」
2006年度修士論文(4名)
荒木達雄「容与堂本『水滸伝』における『義』~明代文学作品の『義』認識を視野に入れて」
鈴木弥生「韓世忠の妻梁氏故事の演変について」
鄧 延桓「龍瑛宗文学における女性像―『知られざる幸福』(1942)及び『ある女の記録』(1942)を通して―」
原田春子「戦国時代における各国の文字遣い分布調査―出土資料による考察―」
2004年度修士論文(6名)
上原究一「白話小説の回目に見える「義釋」について―明末清初小説相互の影響関係」
宇都健夫「接続詞“就是”の意味と機能 ―補足注釈と譲歩を中心に―」
梶村 永「妄りに語る「唐代伝奇」 ―文学を考える一つの試み―」
加納希美「動量詞のシンタクスと意味 ―QV+N型とりたて表現の成立をめぐって―」
末岡麻衣子「現代台湾作家七等生論 ―その過去への視線と語り」
福田素子「鬼討債説話の成立と展開 ―我が子が債鬼であることの発見」
2003年度修士論文(2名)
朗 潔「朱彝尊と査慎行の交友とその作品」
山崎 藍「中国厠妖怪譚 ―六朝志怪、唐代伝奇を中心に―」
2002年度修士論文(7名)
遠藤星希「唐代詩歌史上における李賀の位置 -詩的題材としての神話・伝承の扱いをめぐって-」
大野公賀「豊子愷と近代中国について」
白井澄世「瞿秋白における知識人アイデンティティの形成 -生命主義及びゴーリキー『市儈(小市民)』観の受容をめぐって-」
任秀彬「“満州”をめぐる中国、日本、韓国の三十年代文学」
陳 縦「三生石故事と『紅楼夢』」
馬場昭佳「清代知識人の『水滸伝』認識」
夫婦岩香苗「李昂研究 -都市遍歴と創作過程」
2001 年度修士論文(5名)
松浦史子「江淹新考 -郭璞との関係を中心に-」
大澤理子「淪陥期上海における日中文学者の“交流”について -太平出版公司、太平書局を中心として」
高芝麻子「韋應物詩の変遷 -同時代の言葉から自らの言葉へ-」
謝 智芬「『聊斎志異』における夢描写について -夢兆と夢幻という視点から-」
田中智行「『金瓶梅』の小説作法 -視線と批評性-」
2000 年度修士論文(5名)
古宮陽明「差異としての<文> -テクストとしての『文心雕龍』について」
馬場久佳「批評家以前 -近代都市武漢から近代国家日本-」
藤澤太郎「一九三〇年代・中国文壇のメカニズム -上海・南京・北平を中心とする作家・メディアの力学」
大村和人「六朝閨怨詩における音楽の詩的イメージ ~斉梁詩を中心に~」
谷村晃司「近代漢語における「就」と「則」について」
1999 年度修士論文(3名)
佐野誠子「五行志と志怪書 -志怪書発生に関する一考察-」
樫尾季美「趙樹理再考 -二十世紀末の視点から-」
黄 安妮「植民地作家呂赫若の東京体験 -東京留学による呂赫若のアイデンティティの流動について-」