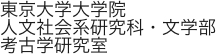考古学研究室への入・進学案内
考古学って何?
人は大昔から「自分たちはどこから来たか?」「どのようにして今のような世界ができたのか?」という疑問を抱き続けてきました。それを知るために文献に残る古い記録を探しましたが、それらは古くなればなるほど不確かになります。そこで地中に埋まっている古代人の棲みかや道具を掘り出して、そのようなモノの証拠に基づいて失われた歴史を復元する試みが始まりました。これが黎明期の考古学です。

モノによって歴史を繙くためには、まずモノの年代を知らなければなりません。モノを古いものから新しいものまで順に並べて年代の「ものさし」をつくることを「編年」といい、これが考古学研究の骨組みになります。そして、道具の種類、住居の構造、食物の残りかすなどから暮らしを復元することが、骨組みに対する肉付けになります。人間の行動の仕方や、人間同士の社会的なつながり、人間の思想などはモノとして残りません。考古学にとって最も不得手な分野であるとされていましたが、そのような事柄であっても必ず何らかの痕跡をモノの形に残しているはずです。それを見つけ出して行動・社会・思想などを復元することが考古学の新しい課題とされており、さまざまな挑戦が行われています。
大昔のことを想像することは簡単ですが、それが正しいのかどうかはなかなか分かりません。そのため考古学では仮説を立て、確実な証拠と論理によりそれを証明することが重視されてきました。また、考古学と自然科学諸分野との連携もさかんに行われてきました。モノから最大限の情報を得るために、年代測定、材質・産地分析、古環境分析、人骨・同位体分析など、さまざまな方法の自然科学分析が用いられています。
同じく歴史を扱う日本史、東洋史、西洋史、美術史などとは違い、考古学では、人類が誕生した後のあらゆる時代、あらゆる地域が研究の対象になります。日本人による海外の考古学的調査は世界各地に及んでおり、現地の研究者とともにその地域固有の課題に取り組む日本人が増えています。
日本では、文字をもたない時代の研究や文字史料の不足する蝦夷やアイヌ、琉球などの歴史研究に、考古学が大きく貢献しています。しかしそれだけでなく、文字が豊富な時代や社会もまた考古学の研究対象となります。文字記録から知り得ることの多くは、文字を残した一部の人たちが記録する価値があると考えた結果です。人々の日々の暮らしなど、当時どこにでもあったことは記録されにくく、それゆえに考古学の手法が役立つのです。近年、中世の遺跡の発掘は当然のことになっていますし、江戸時代以降の遺跡もさかんに発掘されるようになっています。考古学と文献史学の協力によって新しい歴史像が追究されているのです。
考古学研究室で学ぶには
東京大学の学部教育課程は、前期教養課程2年、後期専門課程2年に分かれます。考古学研究室は、文学部人文学科考古学専修課程という枠組みで、主として前期課程の文科三類から学生を受け入れています。
考古学に進学しようとする学生は、駒場Aセメスターのうちに必修科目となっている「考古学概論 I 」、「史学概論」の授業を必ずとるようにしてください。「考古学概論 I 」は本郷で開講されていますが、「史学概論」は駒場での開講ですので注意してください。同じく駒場Aセメスターに開講される「人類学概説」は、必修科目ではありませんが考古学研究の基礎として重要なので、進学予定者にはできるだけ受講することを勧めます。
東京大学の大学院教育課程は、修士課程2年、博士後期課程3年に分かれます。考古学研究室は、大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻考古学専門分野という枠組みで大学院生および研究生を受け入れています。大学院の入学試験は例年、修士課程が夏(8月末から9月にかけて)と冬(1月末から2月にかけて)の2回、博士課程は1月末から2月にかけて1回それぞれ実施されます。
※上記ともに文学部公式サイトに掲載
考古学研究室で学ぶこと
考古学専修課程の必修科目(括弧内は単位数)は、史学概論(2)、考古学概論(4)、考古学特殊講義(16)、考古学演習(6)、野外考古学(4)、卒業論文(12)です。
考古学独自の手法のひとつに、発掘調査があります。「野外考古学 I・II 」では、ある種の「破壊」をともなう発掘調査を適切に実施するための手順を習得します。発掘調査では、遺跡の立地や地形を正しく把握すること、遺構や遺物を正確に記録することが大切です。そのために、まず測量機器の使用法を学びます。発掘調査中は周辺の地質条件を把握し、遺構や遺物が包含される堆積物を観察しながら、図面作成や写真撮影、三次元情報などを記録します。調査後には、記録を整理し、出土した遺物の洗浄やリスト作成を済ませ、実測図や写真、三次元計測といった詳細な整理作業を行います。これらが調査研究成果を総括した発掘調査報告書に結実します。こうして公開された記録が、考古学研究の基礎データです。
野外考古学 I は、こうした基礎的技術を本郷キャンパスで開講し、野外考古学 II は人文社会系研究科附属「北海文化研究常呂実習施設」という施設でおこないます。教員と大学院生、学生が専用の宿舎に滞在し、実際に遺跡の発掘調査や整理作業を経験することで、リラックスした雰囲気でフィールド調査の楽しさや調査技術の奥深さにふれることができます。宿舎には各種設備が整えられていますので、快適な生活ができます。日本の大学のなかでは他に類を見ない恵まれた実習環境といえるでしょう。
遺構や遺物は、考古学的な方法論によって整然と分類・分析されて学術的な意味での歴史資料になります。最も基礎となる方法論は型式学です。型式学は物がもつ年代的・地方的特徴をとらえてその変化や相互関係から社会や文化を明らかにする基礎的方法論です。また、遺跡を形成した人の営み、すなわち文化的な遺跡形成だけでなく、地質学的な理論と方法から遺跡の自然的な形成過程を考慮することで、遺跡の性格をより総合的に理解できます。これらの積み重ねが、遺跡の編年や文化の地域性といった、人類史の解明につながるのです。
また、主人を失った遺構や遺物から、往時の人間行動や社会、文化を具体的に語るためには、物質文化から人間行動を読み解くために民族考古学や実験考古学がもたらすモデルを参照する必要があります。歴史時代では文献・絵画史料が同種の役割を果たします。
「考古学特殊講義」では、こうした考古学の方法論を中心にさまざまなテーマについて講義形式で、「考古学演習」ではすぐれた内外の文献にもとづいて方法論およびその具体的な実践方法を演習形式で学びます。専任教員だけではカバーできない専門的な知識についても、学内外から専門家を非常勤講師としてお招きし、幅広い分野を学習することができる機会を提供します。
学部3年生までにこれらの基礎を身につけ、4年生には卒業論文を執筆します。自らが選んだテーマを深く研究して論文にする作業です。研究史に基づいて課題と目的を明確にし、解決に必要な資料の収集と分析方法の設定を行い、分析結果に基づく考察を加え、結論を導くという作業は多くの時間を要しますが、4年間の学業の集大成といえるものです。論理的思考と努力の結晶として、その後の財産になるこの経験を大切にしてほしいと思います。
考古学は広義の歴史学の一分野ですから、考古学専修過程に入っても、歴史関係の講義は受講を勧めます。とくに歴史時代の考古学を専攻するためには、文献史学の素養を身につけておくのがよいでしょう。先史考古学では、人類学や生態学の知識が必要です。外国考古学を志す場合は、外国語がすべての基礎になりますので、その習得に努めてほしいと思います。もちろん、日本考古学研究でも、方法論を学ぶために外国語文献の講読は大切です。
なお、大学の外にも考古学を学ぶ場は数多くあります。考古学研究室の教員は夏季休暇を中心に国内外でフィールド調査を行っており、大学院生を中心に希望者が参加できます。教員の紹介で学外の発掘調査に参加する人もいます。シンポジウムなどに出かけ、実際の議論に接することも興味・関心の幅を広げてくれます。各地の博物館や資料館で実際に遺物を見学して、研究上の思索を巡らすことも良い経験でしょう。考古学はフィールドと実物の学です。一片の遺物にしか語り得ない歴史があることに気づくことが、考古学の醍醐味です。
卒業・修了後の進路
卒業後、研究を継続する場合は大学院を目指し、そうでない場合は一般就職を目指すことが多く、近年の比率は1対3ほどです。就職先は、新聞社、テレビ局などマスコミ関係をはじめとして、銀行、商社、運輸、情報、地方公務員などさまざまで、マスコミで考古学出身という経歴をうまく活かしている卒業生もいます。
修士課程進学者は、修了後一般就職する場合もありますが、多くは博士課程に進学し、研究を続けるために大学や博物館、研究機関への就職をめざすことになります。専門を活かせる場としては他にも、全国各地の地方公共団体に埋蔵文化財を保存・活用する部署が数多く存在し、こうした組織への就職の道がひらけている点は考古学の特徴です。学部卒ないしは修士課程修了の段階でも就職することができます
学部卒業者の進学先
東京大学大学院人文社会系研究科、東京大学大学院総合文化研究科、東京大学大学院新領域創成科学研究科、東京学芸大学大学院、早稲田大学大学院
学部卒業者および修士課程修了者の就職先
IHI、青森県庁、朝日新聞社、岩見沢市役所、エイチ・アイ・エス、NHK、岡山県庁、神奈川県教育委員会、川崎重工業、紀伊國屋書店、共同通信社、航空自衛隊、光和コンピューター、埼玉県教育委員会、CSKシステムズ、鈴与、住友信託銀行、住友不動産、双日、ソニー生命保険、大黒倉庫、大成建設、大日本印刷、宝島社、中国銀行、トヨタ自動車、ドワンゴ、長岡工業高等専門学校、長崎市、奈良県庁、西日本鉄道、日本ウィルテックソリューション、日本空港ビルディング、日本経済新聞社、日本工営、日本コロムビア、日本製鉄、野田市役所、八戸市博物館、早川書房、バレッグス、ビックカメラ、姫路市役所、百五銀行、福岡県庁、芳文社、みずほ銀行、三谷商事、三井住友海上火災、三菱UFJ銀行、港区教育委員会、宮城県教育委員会、明治安田生命、モルガン・スタンレー、ゆうちょ銀行、読売新聞社、陸上自衛隊、リクルートマーケティングパートナーズ
博士課程出身者(課程修了・単位取得退学・中途退学含む)の就職先
東京大学大学院人文社会系研究科、日本学術振興会(特別研究員)、愛媛大学、長崎県教育庁、沖縄県立博物館、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団、神奈川県教育委員会、福岡市教育委員会、札幌市埋蔵文化財センター、青森県教育庁、国立歴史民俗博物館、古代オリエント博物館、泉屋博古館、大田区立郷土博物館、奈良文化財研究所
※ 以上、2005~2019年度実績(ポスドクの期間後の着任含む)