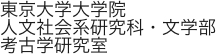東京大学考古学研究室の概要
東京大学が発足した1877(明治10)年、理学部の動物学教室に着任したアメリカ人動物学者エドワード・S・モースによって、有名な大森貝塚の発掘が行われました。これが日本最初の科学的な発掘調査といわれています。1884(明治17)年には、現在の弥生キャンパス付近で、弥生式土器の第一号が発見されました。明治年間には坪井正五郎らの理学部人類学教室が考古学的な発掘調査を行っていました。
東京大学文学部で最初に考古学の講義が開かれたのは1914(大正3)年のことで、東洋史学出身の原田淑人が講師を務めました。1938(昭和13)年には考古学講座が新設されましたが、専修学生の受け入れは第二次大戦直後となる1946(昭和21)年のことでした。これが東京大学考古学研究室が誕生した年となります。初代教授原田淑人と助教授駒井和愛は戦前東亜考古学会に属し、中国や朝鮮における調査研究で活躍した東洋考古学の専門家でしたが、第二次世界大戦後は日本考古学の比重が高まりました。こうした過程で、日本のことを広くアジア全体のなかで展望するという現在の学風の礎がつくられました。
その後、八幡一郎(縄文時代)、三上次男(東洋考古学)、斉藤忠(古墳・歴史時代)、関野雄(東洋考古学)、佐藤達夫(先土器[旧石器]・縄文時代)、渡辺仁(土俗考古学・生態人類学)、藤本強(北海道・西アジア)、上野佳也(縄文時代)、狩野千秋(中南米)、宇田川洋(北海道)、後藤直(弥生時代)、今村啓爾(縄文時代・東南アジア)、大貫静夫(東北アジア・中国)、設楽博己(縄文時代・弥生時代)、佐藤宏之(旧石器時代・民族考古学)の各先生が歴代の教鞭を執ってきました(現職教員紹介は後述)。教員の研究分野はさまざまですが、東アジアと日本の先史時代の研究は研究室開設以来継承されており、それが本研究室の特色の一つといえます。
本研究室のもう一つの特色は、北海道における調査を1947(昭和22)年以来毎年続けてきたことです。人文社会系研究科附属「北海文化研究常呂実習施設」では、前身となる「常呂研究室」(通称)が1967(昭和42)年に開設されて以来、専任教員が常駐して調査・研究を続けています。毎年、夏季休暇には発掘実習(野外考古学 II )が行われ、本研究室の新3年生はこの実習施設で合宿生活を送ります。そのため、本研究室は北海道や北アジアの考古学を専門とする人材も多く輩出してきました。
本研究室の現職教員は3名です(研究実績等は教員と学生)。
福田准教授は、シベリア・ロシア極東・日本列島における土器出現期以降の先史文化について、環境への適応という視点から復元を試みています。また、広く東北アジア史のなかで日本列島の先史を捉えています。根岸准教授は、縄文時代から弥生時代への移行を専門分野とし、その過程を人類史の中に位置付ける研究を志向しています。また、先史時代の文化・社会の解釈に役立てるため、民族考古学的研究にも取り組んでいます。森先准教授は、日本列島を含む東アジアの旧石器時代が専門であり、人類がユーラシアから日本列島に進出し適応を果たした過程を研究しています。また、考古遺跡をはじめとする文化財の保存・活用にも取り組んでいます。新井助教の専門は動物考古学で、西アジアや中央アジア、南コーカサスをフィールドに、牧畜の成立と内陸アジアへの拡散プロセスを探っています。
考古学専修の専任教員以外にも協力教員がいます(研究実績等は教員と学生)。
北海道にある常呂実習施設に勤務する熊木教授は北海道がおもなフィールドで、周辺の北方古代文化を視野に入れながら、アイヌ文化の成立過程を追究しています。北見市常呂町でおこなわれる「野外考古学 II 」という発掘実習期間中の指導を担当します。
総合研究博物館には西アジアの先史考古学を専門とする西秋教授、年代測定や同位体分析を専門とする考古科学の米田教授、人類化石の形態分析からアジアの人類史を研究する人類進化学の海部教授がいます。学内には大学施設の新設等に伴い事前の発掘調査を担当する埋蔵文化財調査室があり、本調査室の堀内准教授は近世江戸の考古学が専門で、「野外考古学 I 」も担当しています。
本研究室の出身者は現在、約50の大学・博物館・研究機関に所属し、現代日本における考古学研究の中核を担っています。
考古学研究室の所蔵図書を利用するには
学内他部局・学外の方は電子メールでの予約が必要です。(学内他部局の方は考古学研究室へメール予約、学外の方は文学部図書室へ予約)
※当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防⽌のため、考古学研究室所属者以外の方の研究室所蔵図書の利用を停止しています。(2020年7月21日)
連絡先
東京大学大学院人文社会系研究科・文学部考古学研究室
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 法文2号館3階
[ 交通案内 – 構内地図 ]
TEL/FAX: 03-5841-3793(直通)
E-Mail: kouko■l.u-tokyo.ac.jp
※ 迷惑メール防止のため、@を■にしています