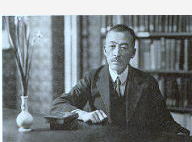在籍者students
学部生
宗教学研究室への駒場からの進学者は毎年15名前後、学士入学者は0~1名程度です。
全員が二年で卒業するとは限らないので、30~50名の学部生が在籍しています。
卒業生数は毎年15名前後で、うち3名程度が大学院へ進学、他は就職というのがここ数年の傾向です。
比較的最近の主な就職先は次のようなものですが、ごく普通の就職活動をして一般企業の会社員や公務員になっていく学生が多いということがわかります。その他、卒業後に医師や弁護士を目指すという人も珍しくありません。
卒業生の就職先例
アクサ生命、NHK、NTTドコモ、NTT西日本、NTT東日本、紀伊國屋書店、講談社、産経新聞、サントリー、資生堂、昭和電工、清水建設、住友金属工業、衆議院事務局、中央公論新社、電通、東京都庁、東レ株式会社、日本テレビ、
日本図書センター、日本郵政、野村證券、博報堂、HP研究所、富士通、日立製作所、P&G、三越、三菱電機、三菱商事、りそな銀行、早稲田アカデミー、その他、地方銀行、地方放送局、地方自治体
![]() 卒業論文題目一覧
卒業論文題目一覧
大学院生
大学院の在籍者数は修士・博士を合わせて50名ほどになります。
大学院修士課程への入学者は毎年6名前後、年によって違いますが、半数程度が他大学出身者です。
入学試験に必要なのは、修士課程は筆記試験(外国語二科目+専門科目)と 口述試験(卒業論文かこれに代わるもののを提出)
です。2年または3年で修士論文を提出し、このうち博士課程に進めるのは毎年4名程度です。
大学院博士課程への進学は
口述試験(修士論文)によって審査されます。他大学からの博士課程入学者は筆記試験も必要になります。博士課程からの入学は例外的なケースであり、多くの場合、まずは修士課程で宗教学の方法を身につけることをおすすめしています。
入学要件について詳しくは大学院人文社会系研究科による案内を参照してください。
博士課程の標準年限は3年間ですが、多くの人は休学・留学・単位取得満期退学(在籍5年で満期となります)を経て、大学院修士課程入学から数えて10年ほどかけて博士論文の提出を目指します。
| 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|
| 馬場真理子 | 中近世日本における暦注・暦占観 |
| 飯田陽子 | 19世紀アメリカにおける女性の社会参加と宗教 |
| 李 美奈 | 17世紀レオネ・モデナのユダヤ教概念 |
| 髙瀬航平 | 明治期日本における公教育と宗教の関係史 |
| 野川 祈 | E.トレルチの宗教思想 |
| 伊藤優 | 近世・近代宗教史における奇術 |
| 牛窪彩絢 | 琉球諸島の葬墓制 |
| 郭立東 | 戦後日本宗教史における「水子」の言説:新宗教・知識人・政治・大衆メディアのもつれ |
| 田宮克真 | 甲骨文資料における中国古代宗教 |
| 輝元泰文 | フランスにおける禅の受容と宗教変動 |
| 柴田峻太朗 | 西欧中世初期における聖餐論の展開 |
| 田口哲郎 | フランス・ロマン主義文学における宗教性-カトリシズムと世俗の間- |
| 坪井俊樹 | 現代日本における宗教の世代間継承 |
| 加藤基 | エチオピア正教会史における家族、宗教、国家の関係 |
| 和田知之 | 現代ドイツにおける改宗ムスリム |
| 和田理恵 | 現代日本人の宗教意識の研究(主に計量テキスト分析の手法を用いる) |
| 鵜沢祐汰 | 宗教学的生命倫理研究の方法 |
| 王子銘 | 明治末期から昭和前期における宗教・宗派連合と政府協力 |
【修士課程】
| 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|
| 三浦大樹 | 現代のスピリチュアリティと物語 |
| 山本良 | 大江健三郎と/の霊性――『燃えあがる緑の木』および『宙返り』を中心に |
| 菅原一花 | 近代ベトナムの仏教復興運動 (Phong trào chấn hưng Phật giáo) |
| 細野一斗 | 消費主義と宗教―マテリアルカルチャーの視点から― |
| 間啓希 | 現代日本文化における宗教の受容と理解 |
| 所秀親 | スピリチュアリティと先祖 |
| 小西義愛 | 神の死/ケノーシスを巡る日本哲学と神学との往還──西谷啓治とトマス・アルタイザー |
| 寺中佑多 | 近代日本における日本神話の受容と展開 |
| 坂野寛幸 | 現代日本におけるタイ上座仏教寺院の活動動機と展開 |
| 中野高宏 | 旧約聖書の歴史的背景 |
| 菊池颯竜 | 社会構築主義的観点からの宗教-法関係の研究 |
研究生
研究生は数名程度在籍しています。在籍者のほとんどは、修士課程修了後に博士課程進学を目指す学生と大学院入学を目指す海外からの留学生です。
大学院合同ゼミの発表題目
大学院生全員参加のゼミ(木曜ゼミ)の2018、2011、2009および2007年度発表題目一覧です。予定表をもとにしていますので実際とは異なっている場合が多々ありますが、参考にはなると思います。このゼミは、大学院生と研究生、教員スタッフ全員が参加し、司会、コメンテイターは大学院生がつとめます。大学院生による一時間ほどの発表のあと、コメンテイターによるコメント、全員による質疑応答、ディスカッションが行われます。
・一休の「像」からみえるもの ―「禅と日本文化」という語りを再考するために―
・D-.M.ブルヌヴィルの研究 病院のライシテ化と医学的宗教研究
・折口信夫における霊魂論の素描―「民族史観における他界観念」を中心にー
・終末期医療における「宗教」と「芸術」 ―芸術の役割の検討を中心に―
・19世紀末アメリカにおける「白人性」とプロテスタント ―万国宗教会議に着目して―
・『サムエル記』の王権表象
・現代日本におけるキリスト教用品の日本化 ―マテリアルカルチャー研究の視点から―
・近代ドイツにおけるプロテスタント神学と宗教学の関係性―エルンスト・トレルチの書評から―
・儒教の『大学』とイスラームの『大学』
・反「疑似科学」の言説と「疑似科学」における「科学」概念の諸相
・W.ケアリーと「ヒンドゥー・システム」
・ユダヤの聖書解釈と M・ブーバーの聖書研究 ―出エジプト記の中のエジプトにおけるイスラエルを例に―
・ロシアにおける「死生学」研究動向とその課題
・テイヤール・ド・シャルダンの思想
・集団的自己破壊傾向と宗教性との関係 ――連合赤軍研究を「宗教と暴力」研究に照らして
・近代神道メデイアと神道青年―神風会と『神風』を中心に―
・「その言語は完全に典礼的なものとなるために死語となった」―ゲランジェ典礼論の一理解―
・日蓮伝の 19 世紀―説話「旗曼荼羅」の形成過程を中心に
・クザーヌスにおける二重のディオニュシウス文書 ―「存在」v.s.「言葉」の15世紀?―
・宗教研究と日本文学研究の距離
・改宗者レオン・ルッツァットの家族に関する裁判における、ヴェネツィア共和国とユダヤ人共同体の司法権の関係
・スピリチュアルケアにおける思想・理念とケアの実際 ――その遊離の批判的検討――
2011年度
・19世紀前半のアメリカ合衆国における宗教批判と健康改革
・『日本霊異記』における私度僧について
・近代ロシア宗教思想史をめぐる一断面
・水子供養からみる生命観の変遷―戦後から現在まで―
・スピリチュアリティ概念の研究
・宗教法人・団体の公益活動
・倉田百三の宗教観(仮)
・解釈学の見地からのエリアーデ宗教学の検討
・ハンナ・アーレントの赦しの概念
・フランクルの人間生成論
・古代ローマ(共和政末期)の弁論における非難の際の宗教的語彙について
・D.ヒュームの宗教論
・近代におけるユダヤ人のアイデンティティーをめぐる問題
・ポスト・フロイディアンにおける幼児の宗教性について
・イスラームによる疾病観の革新 ―インドネシアにおける宗教と“スティグマ”
・近世西欧諸国の政治と宗教
・宗教と演劇
・〈日本〉をめぐる神学──北畠親房と国学
・ベイコンの自然支配
・説経節の宗教性
・「信」をめぐって―認知科学的観点からの現実/虚構―
・ロジャー・ウィリアムズの神学思想と「人間の権利」
・死者・祖先供養儀礼にみるヒンドゥー教の死生観
・ブラック・ディアスポラの宗教研究ーキューバ サンテリア
・ルドルフ・シュタイナーの「キリスト教」理解
・古代中国の宇宙観 ―神仙道教における錬丹術と竈炉
・政治と宗教:ミャンマーの上座仏教と軍事政権
・近・現代仏教の社会思想
・「かたち」と「象徴」の諸理論、その図像宗教学的考察
2009年度
・世界紅卍字会における静坐と慈善のせめぎ合い
・理性と宗教について
・古典期インド宗教におけるヨーガの諸相
・痛みの探究-その3
・古墳壁画にみる古代中国のコスモロジー
・現代ジャマイカにおけるラスタファリアニズム神学の受容と変容
・フランシス・ベーコンの思想にみる法とレリギオ
・マザーテレサの活動とキリスト教の慈善(愛)
・建国期トルコ共和国におけるイスラームの位置
・シュタイナーの人智学研究 ― エソテリシズムと教育の接点
・民俗宗教から見た説経節の宗教性
・台湾原住民族と宗教
・ハリソン『古代芸術と祭式』における「祭式」の意味
・日米における心理学的宗教心理学の動向
・日本の宗教とモダニティ
・日本霊異記について
・ヒンドゥー教の聖地と死生観
・シャブタイ派思想の反律法主義に関する研究
・「迷宮」図像群にまつわる「聖」「俗」意識の旅程、ヨーロッパを中心として
・擬ディオニュシオスの神化思想
・ビザンツ以降の東方キリスト教
・「信」と虚構~分析哲学という視座、そして日本神話へ~
・近代仏教の倫理思想
・ユダヤ教改宗制度に見る民族アイデンティティの妥当性-ラビ文献の事例から-
・『先祖』と『死者の霊』をめぐる議論-沖縄と韓国の民俗・民衆宗教研究を中心に
・イスラムと非暴力
・中世ユダヤ教における「イスラエルの土地」の概念
・心理学理論における死と宗教
・17世紀フランス「神秘主義」の宗教史的研究
2007年度
・ブレイクと十八世紀の神話論―神話叙述から文学へ―
・戦後日本のキリスト教における文化ナショナリズム
・レヴィナスにおける愛について
・現代沖縄社会とユタ的宗教者
・シャブタイ派運動におけるルーリアのカバラーの影響
・擬ディオニュシオスのキリスト
・ヘシュカスム論争
・近代中国の仏教史学における宗派概念と『八宗綱要』の役割
・日本近世儒者の鬼神論
・新宗教とナショナリズム/エスノセントリズム
・タルムードにおける異教徒の表象
・恨と新宗教~統一教会を中心に
・世俗の問題、宗教学の方法論、または虚無主義、厭世主義と宗教の関連
・ユダヤ人家庭の宗教教育
・ヨーガと十字架のヨハネ
・宗教的表象としての螺旋状文様
・痛みと癒しにおけるスピリチュアリティ
・古代中国の死生観
・ナフマニデスのヨブ記註解
・オーストラリアのイスラム教徒の開発事業
・宗教理論史における死-心理学を中心に
・信仰と他者経験-近世フランス宗教史における
・万国宗教会議とアメリカ国内の多宗教状況
・ローゼンツヴァイクとレヴィナス
・日本の倫理観における仏性的生命観の影響について
・明治期の国体論
・シオラン研究
・80-90年代の宗教と電気メディア~白南準のビデオアートから~
ナビゲーション
copyright©2007- Department of Religious Studies all rights reserved.
サブナビゲーション
- プライバシーポリシー