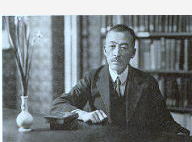修士論文題目Master Theses
2024 宗教学・生命倫理における生命 / いのち
2023 現代日本における「陰謀論」の展開
2023 アウグスティヌス『説教』における 聖遺物を通じた奇跡の語り ―生きられた宗教としての典礼と人々との交わり―
2023 「日本的」環境思想にみられる生命主義とその背景・機能
2023 国学とキリスト教―平田篤胤と松山高吉をつなぐ地下水脈―
2023 GLAにおける「選択輪廻観」の再検討 高橋信次・佳子の著作と青年会員へのインタビューから
2023 信仰を閉じるとき―転換期の隠し念仏コミュニティ―
2022 中世エチオピアにおける単婚規範の成立とその展開
2022 西洋初期中世における聖餐論の転換
2022 新宗教における感染症の語り COVID-19影響下における公式メディアを中心に
2022 日本近代文学の形成と北村透谷の《インスピレーション》
2022 歌謡曲に見る現代日本の祈りの形態 ―歌詩の計量テキスト分析を用いて―
2022 漢魏晋時代の中国における死生観の形成―病いと死に対する宗教職能者の対応に着目して―
2022 フランス・ロマン主義詩人アルフォンス・ルイ・コンスタンの「宗教的なもの」―『神の母、宗教的、人間主義的叙事詩』を読む―
2022 折口信夫の「道徳」論 発動する霊魂、国家による統一
2022 ラカン派精神分析と神秘主義―ふたつの学知の相同性について―
2022 現代ドイツにおける教会からモスクへの転用―宗教空間論と物質的宗教論の視点から―
2021 現代ロシアにおける死生学の特徴
2021 ラテンアメリカ宗教研究史 ―アルゼンチンの宗教社会科学を中心に―
2021 フランスにおける禅の受容と変容 ―弟子丸泰仙を中心として―
2020 献体思想の身体観とその死生観
2020 宗教・思想史における反出生主義の定位
2020 「宗教」と「芸能」の再編成 ―明治期日本の奇術師を題材として―
2020 宗教シオニズムにおける暴力性の源泉
2020 刑死者の弔い研究序説
2020 ウィリアム・ジェイムズの宗教思想
2020 甲骨文における「帝」観念の様相と「天」との関係性
2020 在日中国人プロテスタント教会における「新華僑」若者の信仰形成
2019 17世紀を中心とするイギリスにおけるイスラームに関する言説――他宗教・他教派批判に着目して――
2019 芸術療法における宗教性と芸術の機能
2019 イギリス人宣教師によるヒンドゥーイズム表象 ―子供向け定期刊行物を史料に―
2019 日本民俗学における「アニミズム」言説の展開 ―昭和20年代の折口信夫を中心に―
2019 戦争の語り方―フロイトからドゥルーズ=ガタリへ―
2019 ユダヤ教の聖書解釈におけるモーセ像―ギリシア・キリスト教的なモーセ研究から「モシェ、ラベヌー」への視座
2019 近代における神道青年運動と神道研究の形成―初期の神風会までを対象に―
2018 19世紀末米国キリスト教の自己認識の変容と「ホワイトネス」―比較神学と万国宗教会議を事例として―
2018 文学的サムエル記 ―文学批評と歴史―
2018 現代日本におけるキリスト教用品の日本化 ―マテリアルカルチャー研究の視点から―
2018 E.トレルチに見る世紀転換期の神学と宗教学
2017 韓国済州島女神神話研究の現状と諸問題
2017 "イスラームと中国思想との出会い―16、17世紀の原回儒である王岱與及びその『清真大学』から―"
2017 "New Religious Movement's Strategies Towards the State in the Meiji and Taisho Periods (明治大正における新宗教運動の対国家戦略)"
2016 近代日本における仏教と心理学
2016 ニコラウス・クザーヌス『知ある無知について』の研究
2016 大衆文化の中のゾロアスター教・マニ教的二元論
2016 「ニコラ・バレの修道思想と共同体論」
2016 和辻哲郎の宗教理解と宗教研究について―大正期の和辻の仏教研究を手がかりに―
2016 現代フランスのライシテ研究―セクト論争とヴェール論争の分析から―
2015 近代日本のリアリティ――井上哲次郎の「実在」の思想から見る――
2015 近代初期イタリアのヴェネツィア・ゲットーを取り巻くキリスト教社会とユダヤ社会の関係についての研究――市民に求められた2つの徳性とユダヤ社会の民――
2015 ロマン主義の展開と宗教概念の変容――浪漫主義文学が構築する価値体系の変容――
2015 アメリカ禁酒運動における女性参加と宗教性の問題――研究状況と展望――
2014 ドイツ民族主義宗教運動における神秘主義的諸要素に関する一考察
2014 若者の宗教意識調査研究の諸問題
2014 自死(自殺)問題に対する宗教の活動―自死・自殺に向き合う僧侶の会を中心に―
2014 古代日本における「天」の思想
2014 ジョヴァンニ・ピーコ・デッラ・ミランドラ研究―『ヘプタプルス』と『存在と一について』
2013 日本の地震信仰と鯰絵の研究―1855年の安政地震と世直し
2013 戦後日本宗教学におけるウェーバーの受容
2013 宗教伝統における異性装の研究
2013 自死・自殺に関する宗教学的考察
2013 近代ドイツにおけるユダヤ人のアイデンティティをめぐる問題
2013 演劇と運命―近代日本演劇を例として
2013 モシェ・コルドヴェロのカバラ思想における人間観
2012 在日コリアンのエスニック・アイデンティティと宗教の役割―キリスト教を中心にして―
2012 現代の「死者」供養としての水子供養
2012 ハンナ・アーレントの「赦し」の概念
2012 トルコのイスラーム政党
2012 エリアーデ宗教学の構造―彼の理論とそれを形成する諸前提の分析
2012 近代批判としての「イエス像」―ドストエフスキイ『悪霊』をめぐる宗教的諸問題―
2012 『日本霊異記』にみられる信仰の様相
2011 フランクルの人間生成論―その苦悩論的考察と現代宗教史的意義
2011 フランシス・ベイコンの自然探求という宗教
2011 ヒンドゥー葬送儀礼の宗教学的再考
2011 「心神」の政治神学―安斎学派における北畠親房の思想の継承
2010 中世在家における日本仏教の展開としての説経節
2010 聖者性と神秘主義
2010 終末期医療における宗教実践―マザーテレサ「死の家」と長岡西病院の事例を通して―
2010 画像石墓における"死者の中心性"について―漢代中国のコスモロジー分析を通じて―
2010 レヴィナスにおける「母性(maternité)」~その宗教的意義の探求~
2010 ルドルフ・シュタイナーにおけるドイツ哲学と神智学
2010 ジャマイカの宗教運動における記憶と抵抗―ラスタファリアニズム運動を中心に
2009 近現代ブルターニュにおける新異教主義運動と文化―図像宗教学試論、螺旋状紋様「トリスケル」の受容と使用意図・意識を手がかりとして―
2009 擬ディオニュシオス・アレオパギテースのキリスト像
2009 グレゴリオス・パラマス研究―祈りにおける身体の振る舞い万人に開かれた神秘
2008 日本のキリスト教と「日本
2008 沖縄社会と民間宗教者の現代的展開
2007 霊性と世俗の接点としての非暴力―チベット亡命政府と日本山妙法寺の非暴力運動を事例に―
2007 自分の死後を選択する人々 現代日本における墓の選択とその意味付け
2007 現と虚の狭間で―日本神話理解のための分析哲学解釈―
2007 鴨長明と吉田兼好の文学における死―死生学の立場からの一考察―
2007 ナフマニデスのトーラー註解と論争の関係性
2007 ジャン・ド・レリーにおける(1534-1613)自己/他者のイメージ―「カルヴィニズムとカ―ニヴァレスク」序説
2007 QOL概念の「曖昧さ」に関する一考察―「生活」の地位向上
2006 日本における韓国系ペンテコスタリズム―新宿の一教会における日本人への布教を中心に―
2006 宗教集団の指導者の代替わりと教団の展開課程―霊波之光の場合―
2006 社会福音・社会学・社会改革:20世紀アメリカ合衆国プロテスタンティズムの公共性の考察
2006 古代中国における日中仏教交流―民国時代の密教復興からの一考察
2006 フランツ・ローゼンツヴァイクの『贖いの星』における時間の問題
2006 シャブタイ派運動研究―ゲルショム・ショーレム批判と新たな展望―
2006 American Judaism ~Isaac Mayer Wiseとユダヤ教~
2006 18世紀における宗教的物語とそれをめぐる言説空間―上田秋成とその周辺―
2005 新聞・宗教・文明開化~明治初年の新聞に見る教導職を巡る議論の変遷~
2005 新たな倫理的基盤の確立はなしえるか
2005 古代ギリシャにおける神々との断絶意識
2005 G・マルセルとM・メルロ=ポンティにおける間主体性の構造と「超越的第三者
2004 牧者としてのユマニスト―エラスムスの教育的思想における知と宗教―
2004 東洋的キリスト教」を目指して―復興師・李龍道と韓国朝鮮巫俗および韓国朝鮮新宗教―
2004 中華民国期道院世界紅卍字会に於ける五教帰一運動の研究
2004 ブレイクの彩飾本における「預言」の詩学
2004 ニューエイジにおける倫理思想―チャネリングの事例を中心に―
2004 セバスチャン・カステリオンにおける「寛容の限界
2003 生殖医療をめぐる「いのち」の考察
2003 ユングにおける夢理解の変遷
2003 ドイツロマン派フリードリヒ・シュレーゲル研究
2003 エラガバルス帝研究序説
2002 世界観」をめぐる葛藤とネゴシエーション―ハワイ先住民運動における宗教性―
2002 宗教と美と民衆―初期柳宗悦の思想と実践―
2002 古代末期禁欲論研究
2001 ロベール・エルツの聖ベス祭祀研究―「民衆・民俗宗教」としての理解―
2001 精神の発達段階と夢の解釈
2001 慈遍の宗教思想における神仏論
2001 近世後期におけるキリシタン認識―その諸相と「大阪切支丹一件」―
2001 フアン・ルイス・セグンドの解放の神学
2001 ドグマ・系譜・主体―ピエール・ルジャンドル読解
2001 ヴィクター・ターナーと巡礼研究
2000 中国におけるマニ教の理解―唐から明清朝期における漢文史料を中心として―
2000 植村正久のキリスト教理解についての一考察―その宗教をめぐる言論を中心に―
2000 山崎闇斎における神道と儒教の契合点
2000 ラビ・ユダヤ教と法―タルムードの法の「多元性」―
2000 グノーシス 模倣の神話論理
1999 到達不可能なものへと向かうこと―ジャック・デリダにおける「ユダヤ」「神」「宗教
1999 新宗教と女性―霊友会における「下がる」という行為規範から―
1999 宗教舞踏「チャム」に関する四章
1999 ナザレのイエスの裁判に関する歴史的考察
1999 空海の宗教的言語思想―その理論と実践―
1999 近代日本における教養と宗教―明治後期から大正期を中心に―
1999 コレラにまつわる他者イメージ―日本の近代化における民俗宗教の位置をめぐる考察―
1999 アフリカ系アメリカ人に見る宗教間連帯―「100万人大行進」はなぜ可能だったのか
1998 古代メソポタミアにおける「呪術師(asipu)」の儀礼の文書化と観念体系の構築―守護精霊の像が登場する儀礼文書の場合―
1998 パウル・ティリッヒの「文化の神学」―宗教批判と宗教多元性の問題をめぐって―
1998 チベット仏教と「チベット人
1997 道元撰述の清規の特質についての一考察
1997 宗教社会学における世俗化概念とその諸問題
1997 死後世界説話の研究
1997 歌の呪性―和歌史における柿本人麻呂の位置付けから―
1997 19世紀中葉の初期スラヴ派における「宗教」的自己像の形成
1997 ジャワにおける神秘主義の伝統と近代
1996 東学とアジア主義―彼は如何にして売国奴となりし乎―
1996 近現代日本に於ける儀礼の変容―神前結婚式の成立と普及を巡る一考察―
1996 ユング心理学と宗教
1996 インド学とオリエンタリズム―二つのインド像の形成と変容
1995 気功における「自立」の思想
1995 来たるべき精神の生態学のプログラム―仏教と認知科学の対話―
1995 イスラム復興―フランス社会におけるムスリム共同体
1995 都市国家ウガリトの祖先と王権~葬送儀礼及び祖先神の分析を中心として~
1995 マンダ教の洗礼とその意味
1995 プロテスタンティズムとメキシコ革命
1995 フロイトの歴史構想―宗教史・文化史・道徳性の問題―
1995 アウグストゥスの宗教復興」の宗教学的考察―古代ローマ帝政初期の宗教事情について―
1995 内丹思想の研究―『悟真篇』を中心に―
1994? 新宗教の平和思想―一般信徒の意識と行動―
1994 ミドラッシュにおけるサウル解釈―ユダヤ教聖書解釈における思考の特色とその中で生れるサウルの意味―
1994 ガンディーの禁欲―真理・神・非暴力との関わりにおけるブラフマチャリア―
1994 ハイラーにおける「祈り」の現象学―「宗教学」と「神学」の狭間で
1994 インド大乗仏教における中期密教化について
1994 新宗教“への”救済と新宗教“からの”救出―キリスト教系新宗教を題材として―
1994 新宗教の言語形式の分析 立正佼成会における教義形成と法座
1994 大正期大本教における「復古」の性格
1993 聖なる言説空間のメタモルフォーゼ―近代における宗教言説の存立構造―
1993 William Jamesの『信じる意志』
1993 変貌する現代タイの「国教」―サンティアソーク・タンマカーイ・プッタタート比丘の思想と活動―
1993 イエスにとっての〈神の支配〉―その「終末論的」解釈の再検討―
1992 占いと災因論
1992 宗教的共同体と物語―真宗系教団におけるその展開―
1992 御霊信仰の成立と貞観5年の神泉苑御霊会―祟り・怨霊・災疫―
1992 近世・近代の社会と神葬祭の展開―日本における死の観念の社会史的考察の試み―
1992 ニュー・エイジの思想―人はどのように癒されるか―
1991 パウル・ティリッヒの宗教思想―「究極的関わり」概念の生成と展開をめぐって―
1991 日本中世における宗教的誓約と神罰観念
1991 大本教と「霊界」
1991 新宗教の社会倫理の一考察 天理教と立正佼成会の社会福祉活動を通して
1991 大正期新宗教におけける「復古」の性格
1991 ルカ福音書における女性像―マルタ・マリア物語を中心に―
1991 メリー・ベーカー・エディにおける心理学的救済論の形成
1991 プロテスタンティズムの聖書解釈―ルター派正統主義とJ. A. ベンゲルにおける―
1991 フロイト宗教論の研究―フロイト宗教論におけるイリュージョン概念の位置―
1991 コーヘレトの知恵
1990 記紀英雄神話の一考察―ヤマトタケルミコト物語の構造と成立―
1990 ナギーブ・マフフーズのイスラーム観―イスラームの近代化とスーフィズム―
1989 トーマス・ミュンツァーにおける千年王国論的変革思想の構造
1989 デュルケム供犠論の形成とその諸問題―社会的紐帯の質とは何か―
1989 キリスト教教育論における「教育」の転換―相互作用的教育のケーススタディー―
1989 エリアーデの歴史観と宗教史論
1989 預言者イザヤにおける「災いの告知」
1989 修養型新宗教における呪術的要素―修養団捧誠会の病気直しとカリスマの日常化―
1988 我が国における血盆経信仰の研究
1988 マルコ福音書における供食と晩餐
1988 シュライエルマッハー『宗教論』における宗教概念―1版・2版の比較研究
1988 R.オットーにおける「聖なるもの」とその生成過程―宗教学概念の再検討に向けて
1988 マックス・ウェーバーの『バガヴァッド・ギーター』論
1987 金教臣の思想と「朝鮮産キリスト教」論―民俗と信仰との関係を中心に―
1987 井上哲次郎の家族国家論
1987 マリア論研究―処女・母性についての一考察―
1987 キリスト教における「殉教者崇敬」―中世の「聖人崇敬」理論の為の一試論―
1986 ルーマニアにおける民間伝承の研究
1986 R.N. ベラー研究―超越と共同体―
1986 日本人の宗教的世界における秩序と価値―一つの理解の試み―
1986 都市における葬儀研究序説―東京都内における仏式葬儀の事例について―
1985 原始キリスト教における貧困の問題―イエスの語録資料における「貧しい人々への祝福」を中心に―
1985 アブド・アル・ジャッバールの倫理思想―タクリーフ論を中心として―
1985 鎮魂の諸相―鎮魂行法研究への序論―
1984 日本人の宗教的世界における秩序と価値―一つの理解の試み―
1984 ヨブ記」研究―「義人の苦難」のテーマの古代イスラエルにおける展開
1984 中国古代の祖先祭祀
1984 キリスト教の受容と変容―アメリカ黒人の場合―
1984 F・シュライエルマッハー『宗教論』における宗教概念―第一版(1799)1と第二版(1806)の比較研究―
1983 神秘経験とその解釈―前期ヤーコプ・ベーメの経験理解―
1983 インドにおける踊りの宗教的意味―南インドを中心として―
1982 中世地蔵信仰史研究序説―地蔵説話の伝承と流布―
1981 北村サヨにおける道徳思想の展開
1981 空海の密教における二系列
1981 Hoelderlinの「神」観念の発展
1980 マルスとクイリヌスー王政期ローマ宗教研究―
1980 ハタ・ヨーガ研究―『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』、『ゲーランダ・サンヒター』、『シヴァ・サンヒター』を中心として―
1979 宝暦~寛政年間かくし念仏取締り事件の研究
1979 十字架の聖ヨハネ研究―その詩と神秘に就て―
1979 ユングの宗教論―個の救済と宗教的態度―
1979 コミューン―小集団における制度と人間―
1978 表象と力―『未開』宗教の理解のために―
1978 悲劇的世界とその超克―パスカルとサドについて
1978 古代ユダヤ教の社会層とエートス
1977 声・リズム・身振り
1977 杉浦重剛の宗教思想
1977 申命記法の研究
1976 デュルケームにおける『宗教』と『社会』の構想
1976 サッラージュのtasawwuf観について
1975 タブーの構造分析―コンポーネンシャル・アナリシスによる試み
1975 J. Wachにおける『理解』の概念
1974 蓮如の思想―無常観をめぐる一考察―
1974 日本人の罪意識の一形態―謡曲「求塚」をめぐって―
1974 折口信夫における『民族論理』論の形成
1974 宗教史と象徴体系―ジョルジュ・デュメジルの学説研究―
1974 クリストフ・ブルームハルトにおける『神の国』思想の構造
1973 北海道常呂町における寺院の成立と展開
1973 平田篤胤における祖先信仰
1973 宗教現象学の現状と課題―「最高実在」の研究を中心に―
1973 古代イスラエル宗教の源流
1972 金光明教に於ける弁天の性格とその変遷について
1971 佛説天地八陽神呪経の撰述をめぐって
1971 伊勢信仰―参宮を中心として
1971 ロバート・ベラーにおける宗教社会学の展開
1970 選びと予定に関するパウロの思想
1970 宗教社会学における世俗化概念の問題
1968 天斑馬―天降る獣の伝承―
1968 ネヘミア研究
1967 日本の祖先崇拝―神奈川県川崎市生田町長沢村の調査―
1967 創価学会の教化活勤
1967 マックス・ウェーバーの宗教社会学―世界宗教の比較研究をめぐって―
1967 『第一クレメンス書』における職制の研究
1966 史的イエスの研究
1966 ヘルダーリンにおけるキリストの問題
1966 フロイドの宗教論
1965 出エジプト伝承に関する一考察
1965 会津田島教会の成立と展開
1964 日本国現報善悪霊異記の研究
1964 中世ローマ・カトリックにおける修道生活の理念の展開―ベネディクト的理念とフランチェスコ的理念
1964 パーソナリティにおける宗教情操―法然をケース・スタディとして―
1963 トインビーの宗教観
1962 明治初期宗教政策の一考察
1962 本居宣長の人と思想
1962 日本農村キリスト教の機能―宗教と宗旨―
1962 宗教学方法論―K・マルクス、F・エンゲルスの立場
1962 マックス・ウェーバーの宗教社会学における「合理化」の問題
1961 ラインホルド・ニーバーの宗教思想
1961 マルティン・ルターにおける人間形成の研究
1961 フランス・オリエンタリストの中国宗教の研究―M・グラネを中心として―
1960 宗教における苦の問題
1959 修験道組織の研究
1959 英国に於ける宗教改革
1958 ユダヤ教の成立史的研究
1958 ニューイングランドの宗教思想―R・W・エマソンを中心として―
1957 エゼキエル書の研究
1957 エーリッヒ・フロムの宗教論
1956 宗教体験の心理学的考察とその限界
1956 コーランの終末論
1956 ウィリアム・ジェイムズの宗教思想
1955 綱島梁川の研究
1955 日本神話の研究
ナビゲーション
copyright©20XX Department of Religious Studies all rights reserved.
サブナビゲーション
- プライバシーポリシー