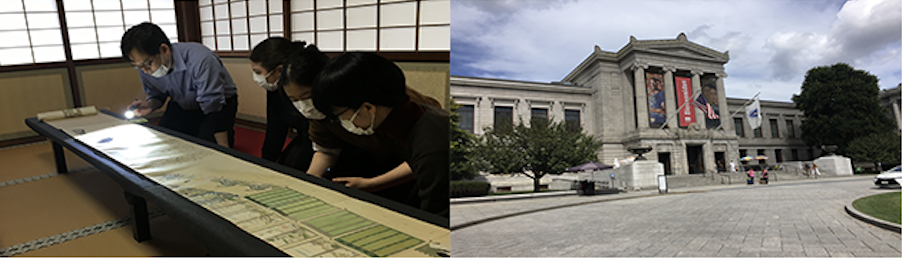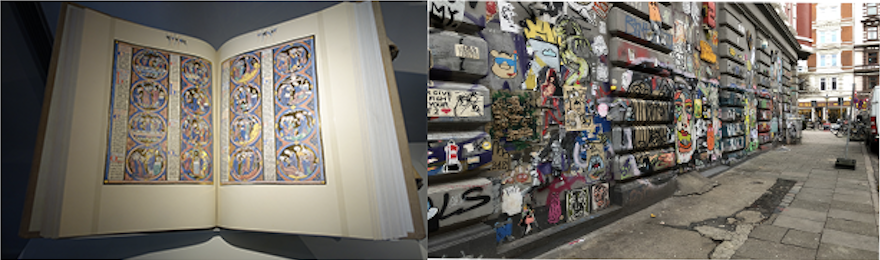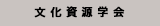学生の研究紹介
博士論文題目
| 学位授与年度 | 専門分野 | 氏名 | 題目 |
| 2025 | 文化資源学 | 関慎太朗 | 楽譜記述の機械可読化による無形文化財の保護・継承・研究 ―唐楽中小曲に含まれる三管の譜を対象としたデジタル版雅楽譜の構築を通して― | 2024 | 文化資源学 | 和田真生 | 江戸歌舞伎の「世界」に関する研究 顔見世を中心に | 文化経営学 | 大鐘亜樹 | オーケストラの財務マネジメントに関する研究 ― 文化経営学における位置づけと意義 |
| リー・カーフイ(李家慧) | Heritageisation of Everyday Urban Landscapes in Singapore (シンガポールにおける日常の都市景観の遺産化) | ||
| 2023 | 文化資源学 | 高橋舞 | バッハ鍵盤作品における演奏の継承と変遷―楽譜資料および録音資料に基づく演奏研究― |
| 2022 | 文化資源学 | 渡邊麻里 | 歌舞伎〈イヤホンガイド〉の誕生-音声メディアの展開と解説文化- |
| 文化経営学 | 武田康孝 | 洋楽放送に関する文化経営学的考察―組織体制と番組制作者の視点から― | |
| 出版物: 『教養と大衆の間でー「洋楽放送」とラジオ番組制作者たち』(春風社、2025) |
|||
| 菅野幸子 | 文化政策の形成過程における影響要因――1970年代の英国にみる文化政策の構造転換とその現代的意義―― | ||
| 李貞善 | 記憶の場としての国連記念公園:戦争墓地の文化遺産化 | ||
| 2021 | 文化資源学 | 笠原真理子 | マスネのオペラ《マノン》における「演出」-文学のオペラ化に関する考察- |
| 2020 | 文化経営学 | 安江(小出)いずみ | 日米交流史における「外国研究」とライブラリー ―福田なをみの軌跡を手掛かりに― |
| 出版物: 『日米交流史の中の福田なをみ:「外国研究」とライブラリアン』(勉誠出版, 2022, 2021年度東京大学而立賞受賞) |
|||
| 形態資料 | 桑原和美 | 楳茂都陸平の「新舞踊」の研究 ー鷲谷家所蔵舞踊譜の解読による再検討ー | |
| 鈴木親彦 | 出版を巡る流通と文化 文化資源学の視座による取次を軸とした出版流通分析 | ||
| 2019 | |||
| 文字資料学(文書) | 寺尾美保 | 大名家族としての島津家の誕生―明治前中期における華族の生成と展開― | 文化資源学 | 柴田葵 | 日本における彫刻シンポジウム:芸術家の共同体と彫刻の社会化の観点から |
| 藏田愛子 | 明治期の画工研究―植物学・動物学・人類学における図示 | ||
| 出版物: 『画工の近代—植物・動物・考古を描く』(東京大学出版会, 2024, 2023年度東京大学而立賞受賞) |
|||
| 2018 | 形態資料学 | 川瀬さゆり | 19世紀の大聖堂修復と鉄―フランスにおける材料保存思想の成立・展開とヴィオレ=ル=デュク |
| 文化経営学 | 盧ユニア | 韓国における工芸の成り立ち―朝鮮総督府の文化政策との関係を中心に― | |
| 2017 | 文化経営学 | 中村美帆 | 日本国憲法第25条「文化」概念の研究 ―文化権(cultural right)との関連性― |
| 出版物: 『文化的に生きる権利―文化政策研究からみた憲法第二十五条の可能性』 (春風社, 2021) |
|||
| 李知映 | 植民地朝鮮における近代的空間としての劇場と演劇界 | ||
| 2016 | 文化経営学 | 長嶋由紀子 | フランス都市文化政策の歴史的展開と政策理念の変遷―市民から都市へ |
| 出版物: 『フランス都市文化政策の展開:市民と地域の文化による発展』 (美学出版, 2018) |
|||
| 2015 | 文化経営学 | 土屋正臣 | 市民参加型調査・収集・展示の文化資源学的考察―野尻湖発掘を事例として― |
| 出版物: 『市民参加型調査が文化を変える』 (美学出版, 2017) |
|||
| 形態資料学 | 鄭仁善 | 日韓におけるインディペンデント映画の配給構造の形成に関する研究―政策、産業、映画運動の側面から― | |
| 出版物: 『日韓インディペンデント映画の形成と発展―映画産業に対する政府の介入』 (せりか書房, 2017) |
|||
| 2014 | 文学資料学 | 野村悠里 | 17、18世紀フランスにおける製本術研究 (1) (2) |
| 出版物: 『書物と製本術――ルリユール / 綴じの文化史』 (みすず書房, 2017) |
|||
| 形態資料学 | 鈴木聖子 | 「科学」としての日本音楽研究:田辺尚雄の雅楽研究と日本音楽史の構築 | |
| 出版物: 『〈雅楽〉の誕生: 田辺尚雄が見た大東亜の響き』 (春秋社, 2019) |
|||
| 沈池娟 | 島村抱月と「新しい女性」像-松井須磨子と近代演劇 | ||
| 2013 | 形態資料学 | 光岡寿郎 | 変貌するミュージアムコミュニケーション―ミュージアムというメディアの形態資料学に向けて― |
| 出版物: 『変貌するミュージアムコミニュケーション』 (せりか書房, 2017) |
|||
| 2010 | 形態資料学 | 矢内賢二 | 明治期歌舞伎と出版メディアの研究 |
| 出版物: 『明治の歌舞伎と出版メデイア』 (ぺりかん社, 2011) |
|||
| 形態資料学 | 小山弓弦葉 | 「辻が花」の研究―「ことば」と技法をめぐる形態資料学的研究 | |
| 出版物: 『「辻が花」の誕生―“ことば”と“染織技法”をめぐる文化資源学』 (東京大学出版会, 2012) |
|||
| 文化経営学 | 湯浅万紀子 | 科学館における教育プログラムの評価に関する研究 | |
| 2009 | 形態資料学 | 佐治ゆかり | 近世庄内における芸能興行の研究:鶴岡・酒田・黒森 |
| 出版物: 『近世庄内における芸能興行の研究―鶴岡・酒田・黒森』 (せりか書房, 2013) |
|||
| 2008 | 形態資料学 | 高野光平 | テレビCMのメディア史/文化資源学:初期テレビ放送におけるCM概念 |
| 2008 | 文化経営学 | 朴昭炫 | 「近代美術館」をめぐる「公共性」の歴史的構造 |
| 出版物: 『「戦場」としての美術館―日本の近代美術館設立運動/論争史』 (ブリュッケ, 2012) |