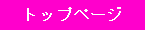

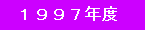

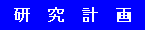
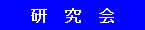
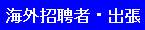
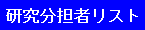
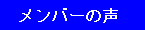
「イラン、モサデク政権に関する研究動向について」
[報告者]中西久枝
1951年イランの石油産業国有化を遂げたモサデク政権の歴史的意義は、イランの民主主義の時代として、また世俗ナショナリズムの時代として、さらには冷戦を背景にしたイランにおけるイギリスからアメリカへの覇権の転換期であった点にある。しかしながら、従来の研究は、研究者の出身国、外交史料の選定が、研究課題や解釈に大きく影響する傾向があり、いまだに全体像が掴めにくい。モサデク政権を、崩壊しつつあった大英帝国史の一コマとして描いたり、冷戦の論理が先行したアメリカ外交の一側面として位置づける研究がある一方、クーデターで打倒されたモサデクへ感情移入した、英雄像の域にとどまる研究もある。こうした動向のなかでは、MaryAnnHeissの1997年の研究書は、イラン石油抗争を国際関係史のなかでより客観的に捉え、また石油抗争における文化的な偏見の問題に留意している点が、新しい研究として評価できよう。
イラン国内では、モサデクに対しては革命前後を通じて否定的な評価で一貫しているが、革命後のモサデク研究が、石油国有化運動への貢献をモサデクよりは当時の宗教指導者に見い出すといった、ウラマーの政治的役割への再評価という方向からも出てきている点は注目に値する。今後は、石油抗争の過程で、国有化のもつ意味がイギリス、アメリカ、イランのそれぞれの国にとってどのような差異を内包していたか、また、イランのナショナリズムにおいて世俗主義と宗教勢力の関係をどう捉えるか、といった側面に照らし合わせた研究が必要ではないかと思われる。そうした研究は、革命後19年を迎えた現代のハータミ政権が、どのように西欧と対話を切り開いていくかという政治動向への重要な視点にもなるのではないかと思われる。