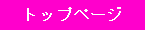

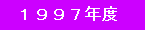

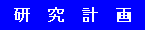
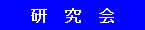
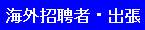
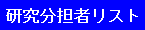
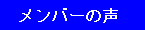
オランダのマルティン.ファン・ブライネッセン博士(ユトレヒト大学文学部教授、第2班招聘)は、10月31日(上智大学)と11月5日(京都大学)に、"The Global and the Local in Indonessian Islam"の演題で講演をなさいました。2回の講演は、力点の置き方が若干異なりましたが、同じペーパーに基づくものですので、ここにまとめてその内容を報告します。
講演では、イスラームの中心から発して広がっていく要因と、イスラームの地域的多様性を創り出すローカルな「力」との相互作用を軸に、3つの局面でイスラームの「グローバル化」と「地方化」の問題が展開された。
まず、「イスラーム化」について、「イスラーム化」とは一時の現象ではなく、現在にいたるまで継続しているプロセスであることが強調された。インドネシアではイスラーム化は13世紀末にスマトラから始まるが、外国人観察者は最近までジャワを表層的にしかイスラーム化していない社会と見てきた。19世紀のヨーロッパ人植民地官僚によると、イスラームはジャワではまだ「なじみのない alien」ものであり、1950年代のアメリカの人類学者も同じくイスラームの下にはヒンドゥー的習慣が根強く残っているとした。しかし、インドネシアで前イスラーム的なもの、ヒンドゥー的なものとされている生活実践の中には中東の習慣と同じものも多くある。特に、魔術、不死身術等がそうであるが、それらは過去にインドネシア人ハジ(メッカ巡礼者)が聖地からイスラーム学とともにもち帰ったものである。ジャワにはもともと超自然的な力を求め、それを特定の場所で獲得するという伝統があった。そのような力が権力を正統化したのであるが、それがイスラームにも適用され、聖地で獲得される精神的な力が重視された。ジャワ人はイスラームをそれ以前の宗教にかわるものとしてではなく、それに加えて受容したのである。
17世紀以前の改宗については記録がないためによくわからないが、それ以降はメッカに赴いたインドネシア人の記録があり、そこからは初期の巡礼者は宮廷に後援された人々であり、帰国後は司法官などの要職を与えられたことがわかる。その後もメッカで学んだ人々は世代ごとにインドネシアに新しいイスラームの要素を持ち帰った。ハジたちは既存の宗教実践を否定して改革するという改革者としての役割を担った
のである。このように、インドネシアのイスラーム化はインドネシア人自身によって推進された。このプロセスには、どの世代もインドネシアのイスラームをメッカで見たイスラームに似せようとする側面と、メッカでのイスラームの変化もインドネシアへ伝えられるという二つの側面があった。17世紀から19世紀にいたるまで、メッカの情勢はかなり変化したが、インドネシアのイスラームもこの波を受けたのである。
次に、イスラームが広がる中で地域的なものとグローバルなものはどのような関係にあったのかが述べられた。シャリーア(イスラーム法)と「対立するもの」としてよくアダット(慣習)が引き合いに出されるが、アダット自体はインドネシアに限らずイスラーム世界のどこにでもある現象である。しかも、土地の人々はアダットとシャリーアの間に対立を見ないが、それはアダットの中にもイスラーム的要素が多く吸収されたからである。しかし、イスラームがグローバル化する力、特に、反植民地主義を掲げたパンイスラミズムを恐れたオランダは、アダット首長を潜在的同盟者と考え、その地位を強めるために、アダットを成文化し、固定化した。もともと、アダットというのは口承で伝達された成文化されていない規則であり、状況によって非常に柔軟に解釈されててきようされてきたものであったが、オランダによって「つくりあげられ」てしまった。オランダ権力はスヌック・フルフローニェの助言ーーイスラーム法がアダットに組み入れられていない限りは、裁判の判決をイスラーム法に基づいて下すべきではないーーに従い、イスラーム法よりもアダットを優先させたのである。全インドネシア人のためのスーパーアダットと言えよう。伝統の中から掘り出された普遍的文明が地域的形態をとったものである。パンチャシラはインドネシア式のイスラーム解釈だと言われるかもしれないが、パンチャシラの中の多くの要素はイスラーム起源である。
続けて、地域的な信仰とグローバルなムスリム文明、シャリーアとの対立は19世紀の末に顕在化したことが指摘された。これは帰国したハジのアジテーションによるところも大きいが、当時の植民地の状況と切り離せない。我々が「アバンガン」「クバティナン」と呼ぶ人々は、長い間自らをムスリム、もしくはジャワ的ムスリムと考えていたが、19世紀末に反イスラーム的、もしくは反ハジ的反応を示した。例えば
、9世紀のジャワの文化ヒーロー、アジ・ソコの新しい「伝説」(実はアジ.ソコはメッカ巡礼をし、預言者から直接教えを受けてそれを伝えたので、ジャワ文化はより純粋のイスラームであるという)がつくられたのもこの頃である。このようなジャワ文化からの防御的反応は19世紀のジャワ文学にも見られる。しかし、「サントリ対アバンガン」の構図は20世紀になってもそれほど先鋭ではなく、1910年代の大衆組織イスラーム同盟もその支持者は、サントリともアバンガンとも区別できないが、多くはアバンガンであったはずである。ギアツが東ジャワで調査を行った1950年代は、政治的対立の激しい時代であったが、「サントリ対アバンガン」はその産物民はいずれかの公認宗教を信奉することを義務づけられたからである。スハルト時代の初期、多くの住民が名のみのムスリムであったが、その後この人々のイスラームが進行した。
さらに、最近のインドネシアで、インドネシア・イスラームの地域性と普遍性はどのような展開を見せているかが述べられた。1970年代から80年代にかけて、ヌルホリシュ・マジッドを代表とする「革新派」グループがメディアや外国人研究者の関心を引いた。彼等は近代化主義者で、政府に妥協的で、イスラームと政治は連動する必要性がないことを強調した。これはスカルノ時代にイスラームが政治と密接に関わっていたのとは対照的である。かつてイスラーム政党は宗教儀礼を奨励するのもその役割としていたし、国家をイスラーム化しようとする政党もあった。しかし、ヌルホリッシュ・マジッド等は"Islam, yes. Partai Islam, no"をスローガンに掲げ、個人の敬信を高めることに関心を向け、イスラーム的価値を唱導したが、政治活動は行わなかった。これはイスラームの「非政治化」をはかる新秩序体制に受け入れられるものであり、1980年代、このグループからは官僚のトップ・レベルに入る者もあった。このグループに影響を与えたのはパキスタンの思想家ファズルールラフマンであるが、彼はイスラーム伝統に知識の基礎を置きながらも、イスラームを新しいコンテキストに適応させ、クルアンを新しく解釈しようとした。「革新派」は、外国からの影響に対して開放的であるという点でコスモポリタン的であった。ヌルホリシュ・マジッドはキリスト教との対話、共生を説くと同時に、よいムスリムであることはアラブ的である必要はなく、インドネシア人のアイデンティティーを捨てないようにとローカルなあり方を積極的に肯定した。元宗教大臣のムナウィル・シャザリも、大胆にもクルアンの中にはインドネシアのコンテキストには適しない部分もあると指摘した。彼は現代のインドネシア社会の必要に対応したイスラーム法学を唱道したが、あまり成功しなかった。
一方、インドネシアには国際指向の急進的なグループも台頭してきた。これは旧マシュミの指導者が組織したデワン・ダクワーというグループである。新秩序体制下で政治活動を禁じられた彼等は、インドネシアのムスリムをイスラーム化するために布教活動に専心した。リヤドに本部を持つ国際組織と強い繋がりを持ち、これを通してサウジ資金と、出版物、思想ーーサウジ的解釈の、原理主義的イスラームーーが流入した。その中には反ユダヤ主義文献があった。いわゆる「ユダヤの陰謀」説はもともとロシアに発祥し、のちにヒトラーによって20ヵ国語に翻訳されてアラブに入り、それがさらにインドネシアに伝わったのである。この反ユダヤ主義文献で「ユダヤ」に象徴されるのは、非民族的なもの、異質性、(民族的統合を破壊するものとしての)コスモポリタニズムである。インドネシアにはユダヤ人はほとんどいないが、ムスリム急進派はすべてのコスモポリタン的な人々を「ユダヤ的」と非難した。ヌルホリシュ・マジッドやその仲間もさることながら、より明確に「コスモポリタン」とされるのは、コミュニスト、資本家、そして少数派の中国人である。これは非常に逆説的バル化を恐れているということである。残念なことに、このような文献は最近のインドネシアでの出来事に影響していると言わねばならない。
現在インドネシアでは、急進的な中東タイプのイスラームグループが台頭してきている。ICMI(全インドネシアムスリム知識人協会)はハビビの「道具」であったが、これを通してこの急進的な思想がインドネシア社会に広く受け入れられつつある。現在の権力闘争はアラブ指向のムスリムに権力構造の中に根を下ろす可能性を与えている。「インドネシアはもうひとつのアルジェリアになりうるか」というのは10年前
にはほとんどばかげた問いであったが、現在にわかに現実味を帯びてきつつある。この「グローバル化」は増大する外国の影響の結果ではなく、まさにインドネシアという「ローカル」な政治的プロセスの結果である。(文責:小林寧子)