生まれてはじめて高校教科書の執筆者となったのは、1990年代の初め。近現代史に重点をおいて内容を精選した〈世界史A〉という新しい試みで、1992年に「白表紙本」として提出するまで2年間、柴田さん、佐藤さん、岸本さんと協議し、模索し、書き、改稿し、とまどいつつもやりがいのある大仕事でした【1991年5月の「思想の言葉」にその一端を記しました】。
執筆がおわっても、検定、採用と、まる2年もかかることには当惑しましたが、文部省検定なるものが(日本史ではないから ?)とくに身構えるほどのことではないことは、一つの発見でした。初版がじっさいに授業で使用されはじめたのは、1994年度です。
やがて現場からの声が聞こえはじめます。ごくわずか、個人的な知己からのフィードバックもありましたが、大多数は出版社を介しての、未知の方々からの反応や意見でした。何々高校の先生、と判明する場合と、まったく匿名の場合とありますが、とにかく氏名までは知れないことがふつうです。たくさんのファイルから、最近のものを選んで抜粋引用してみます。ただし、これらは1998年度から使用されはじめた【改訂版】についての論評です。
我田引水、自画自賛、と読まれるむきもあるかもしれませんが、じつはふたたび学習指導要領が改訂されて*、それにもとづき改訂され、2003年から使用される教科書の編集・執筆にとりくむ者として、これらは叱咤激励と受けとめています。
お名前を存じあげない先生方、ご承諾なきまま勝手に引用させていただきます。有難うございました。
* 中学社会の教育から四大文明もイスラムもルネサンスも無くなることについて、わたしの意見は、こちらに記しました。高校世界史は、嫌でもこの事態に対応せねばなりません。
近藤 和彦
→ ページの頭 へ ![]()
世界史A
『現代の世界史【改訂版】』
「教科書研究指定校 研究報告」 岡山県立玉野光南高等学校
平成10年度
全88ページの充実した報告書ですが、これから
ごくごく一部を抜粋します。p. はこの「研究報告」のページ。
(n)は『現代の世界史』の該当ページ。・・・
は省略です。
p.6 ・・・専門用語の羅列におわる教科書ほど魅力に乏しいものはない。その点、・・・ こと「社会史」なかんずく「庶民の社会史」の部分に関しては、この教科書の記述は非常に分かりやすく生き生きとしているだけでなく、格調高く文学的でさえある。もし教科書全体を通じてこのようなタッチが持続できれば、というのは無理な願いであろうか。
p.7 ・・・第二次世界大戦前後から現代社会にいたる分野に関しては、記述内容に斬新さが見られ、教員自身が「目から鱗の落ちる」思いをさせられる箇所も多かった。これを生徒がどう理解するかということは、また別の問題ではあるが、この「新しさ」という点こそ、本教科書のもつもっとも大きな特色ではないか・・・
p.26 (55) 「イギリスの革命」に関する記述
この項目は非常に詳しく専門的な記述に満ちている。しかし、前述した細かい歴史用語を記憶させることよりも、「なにがあったかを考えさせる」態度が貫かれていて小気味よい。
p.26 (57) ・・・「生活史」は生徒の興味を大いに引くであろう。なかでも「処刑」が「催し」で「楽しむ」対象であったということは、意外な印象をもって生徒に受け取られ、歴史的興味をかき立てることだろう。このような記述は増やしてもらいたい。
p.31 (79) 生徒の感覚から言えば、「音楽室でのみお目にかかる古くさい音楽家」であるベートーヴェンを、「前衛芸術家」であるととらえる視点はおもしろい。また彼が「産業革命でうまれた鋼線をはったピアノの能力を十分ひきだした」とあるが、このようなピアノと産業革命とベートーヴェンの取り合わせは、非常にユニークで、こういった記述を読めば、生徒もベート−ヴェンの音楽を聴きたくなるであろう。
p.31 (86) イタリア統一運動と[ヴェルディなどロマン派の]音楽との関連を明記したことは秀逸。次ページのヴァーグナーとドイツも同様。
p.35 (108〜110) 「大衆社会と国家」
読み物としても優れており、教科書を読んでいることをしばし忘れさせるほどである。特に庶民生活関連の描写は秀逸であり、一般大衆の姿を通して、時代を語ろうとする態度には非常に好感がもてる。・・・
中でも「移民の増加」と「秘密の花園」(バーネット)、「クオレ」(デ=アミーチス)、などの作品を結びつけたところはすばらしく、「母をたずねて三千里」はアニメ化されたこともあり、多くの生徒が視聴していることが予想されるので、歴史理解を図るうえで非常に効果的である。
p.37 (116) 三国協商に関して、このようにアジア・アフリカの民族運動をおさえる帝国主義ブロックであったとする・・・ 多角的な理解を可能としてくれる。また、日本がその一員となる過程に関する説明は、常に日本発の視点を忘れないようにするという、現在の世界史教育のモットーとも合致しており、秀逸な記述である。
〈以下略〉
私が勤務している高校は、難関大学への希望者が多くいます。その立場で申しあげます。多くの卒業生が
「入試の論述問題の練習にもっとも役に立ったのは、山川の『現代の世界史』」
と言います。各章の始めにおかれた網かけの部分を読みつなげば、各時代の像、かかえる問題がわかり、後々理解しやすいと言います。
教育課程は簡単なほうへ流れても、入学試験のレベルはそれほど簡単にはなっていない。・・・
また、単に入試のためだけでなく、様々な階層・職業の人々の心情や情念を盛り込み、問題解決の困難さや努力について記述したこの教科書は、多くの生徒に感動を与えています。
・・・ 出版産業自体が冬の時代で、たくさん売れる本を作ることは、それはそれで重要なことだとわかっておりますが、ぜひ、このすばらしい教科書を、今に近い形で残していただきたいと願っています。
〈以下略〉
→ ページの頭 へ → 『現代の世界史』へ
→ 朝日百科〈働く女たち〉へ ![]()
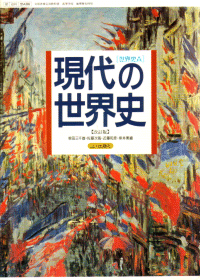 これは現行【改訂版】の表紙(三色旗の氾濫)です。
これは現行【改訂版】の表紙(三色旗の氾濫)です。