東京大学フィレンツェ教育研究センター活動記録(1999-2006年)
序文
以下に、1999年3月の開設から2006年7月の閉鎖にいたる間に、センターが主催ないし共催した、あるいは協力・参加した催しの一覧を掲げる。
1)
1999年3月5日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
「東京大学フィレンツェ教育研究センター開所式」
出席:東京大学教職員10名(青柳正規副学長、樺山紘一人文社会系研究科長ほか)、招待客として瀬木博基駐イタリア日本大使、フィレンツェ大学関係者ほか約30名
2)
1999年3月25日~27日 ヴュッスー資料館
国際シンポジウム
「フィレンツェ、日本、東アジア」(参加)
主催:ヴュッスー資料館
3)
2000年10月6日 フィレンツェ大学(「11月4日」の間)
東京大学フィレンツェ教育研究センター開設一周年記念シンポジウム
「日本の中のイタリア・イタリアの中の日本」
主催:東京大学文学部および東京大学フィレンツェ教育研究センター
共催:フィレンツェ大学
協賛:伊藤謝恩育英財団、鹿島美術財団、ロムアルド・デル・ビアンコ財団
後援:在日イタリア大使館、東京イタリア文化会館
開会の辞:田村毅(東京大学)
第1部 司会:長神悟(東京大学)
パオロ・マラッシーニ(フィレンツェ大学)「フィレンツェにおける東洋学の歴史」
鷺山郁子(フィレンツェ大学)「フィレンツェにおける日本学の歴史」
木下直之(東京大学)「1880年前後の日本におけるイタリア式美術教育」
質疑応答
第2部 司会:鷺山郁子(フィレンツェ大学)
河野元昭(東京大学)「来舶イタリア人美術家と日本美術」
アレッサンドロ・ベルナルディ(フィレンツェ大学)「日本に恋したイタリア映画:黒澤とレオーネ、パゾリーニと溝口」
高階秀爾(東京大学名誉教授)「イタリアで学んだ明治の芸術家たち:川村清雄と彼の同時代人」
質疑応答
閉会の辞:パオロ・マラッシーニ(フィレンツェ大学)


4)
2001年11月23日 ヴュッスー資料館(フェッリの間)
学術講演会
河野元昭(東京大学)
「日本美術の特質」
司会:アドリアーナ・ボスカロ(ヴェネツィア大学)
共催:ヴュッスー資料館、スティッベルト美術館、ロムアルド・デル・ビアンコ財団
後援:伊藤謝恩育英財団

5)
2001年11月24日 スティッベルト美術館(舞踏の間)
日本美術セミナー
河野元昭(東京大学)、ジャンカルロ・カルツァ(ヴェネツィア大学)
「フレデリック・スティッベルトのコレクションと16世紀から19世紀までの日本美術」
司会:アドリアーナ・ボスカロ(ヴェネツィア大学)
共催:ヴュッスー資料館、スティッベルト美術館、ロムアルド・デル・ビアンコ財団
後援:伊藤謝恩育英財団

6)
2002年1月31日〜3月28日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本文学セミナー
土肥秀行(東京大学)
「俳句をめぐって」
1月31日 「イントロダクション:俳句とはなにか」
2月14日 「伝統的俳句の韻律と主題」
2月28日 「日本とヨーロッパにおける俳句の歴史的位置付け」
3月14日 「俳句の現在:様々な国における適正化の試み」
3月28日 「文学形式としての俳句:分析的アプローチ」

7)
2002年2月27日 ヴュッスー資料館(フェッリの間)
学術講演会
石井元章(大阪芸術大学)
「東アジア美術旅行:想像による旅人、美術評論家ヴィットリオ・ピーカ」
司会:マウリツィオ・ボッシ(ヴュッスー資料館)
共催:ヴュッスー資料館、スティッベルト美術館、ロムアルド・デル・ビアンコ財団

8)
2002年4月20日 スティッベルト美術館(舞踏の間)
学術講演会
ドナテッラ・ファイッラ(キヨッソーネ美術館)
「キヨッソーネ美術館:ジェノヴァ市中心にある日本美術の秘宝」
司会:フランチェスコ・チヴィタ(スティッベルト美術館)
共催:ヴュッスー資料館、スティッベルト美術館、ロムアルド・デル・ビアンコ財団

9)
2002年5月10日 ヴュッスー資料館(フェッリの間)
学術講演会
アドリアーナ・ボスカロ(ヴェネツィア大学)
「吉原:江戸の文化、美術、社交」
司会:マウリツィオ・ボッシ(ヴュッスー資料館)
共催:ヴュッスー資料館、スティッベルト美術館、ロムアルド・デル・ビアンコ財団

10)
2002年5月2日〜6月13日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本美術セミナー
「日本美術の諸相(第1部)」
共催:ボローニャ大学附属極東美術研究所
5月2日 アレッサンドロ・グイーディ「日本の仏像」
5月16日 アレッサンドロ・グイーディ「浮世絵序論:誕生から1780年まで」
5月30日 ラッファエーレ・マンツォ「18世紀末の浮世絵師」
6月13日 マルティーナ・ベカッティーニ「西洋における日本美術の受容:ジャポニスム序論」


11)
2002年9月12日〜19日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「北野武特集:冷酷と叙情」
監修:ダニエーレ・メオーニ
9月12日 「Hana-bi」(1997)
9月17日 「ソナチネ」(1993)
9月19日 「あの夏、いちばん静かな海。」(1991)

12)
2002年9月26日〜10月9日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本美術セミナー
「日本美術の諸相(第2部)」
9月26日 土肥秀行「『茶の本』と岡倉覚三:モダニティの情熱と憂鬱」
10月1日 熊井啓監督『利休:本覺坊遺文』(1989)上映会
10月3日 土肥秀行「日本と世界のあいだの岡倉」
10月8日 山口静一(埼玉大学名誉教授)「“文明開化”期の日本におけるフェノロサ」
10月9日、ヴュッスー資料館(フェッリの間)
学術講演会
山口静一
「欧化政策に背を向けた画家、河鍋暁斎」
司会:アドリアーナ・ボスカロ(ヴェネツィア大学)


13)
2002年11月21日〜12月3日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第1部)。黒沢清特集:ホラー映画から作家主義へ」
監修:ダニエーラ・ラッディ
11月21日 「キュア」(1997)
11月26日 「回路」(2001)
11月28日 「カリスマ」(1999)
12月3日 「ニンゲン合格」(1998)
14)
2002年11月24日 ヴェッキオ宮殿(五百人広間)
「フォスコ・マライーニの90歳を祝して」
主催:フィレンツェ市、ヴュッスー資料館
共催:東京大学フィレンツェ教育研究センターほか

15)
2003年1月30日〜2月13日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第2部)。形式と逸脱:5人の最近の映画作家」
監修:ダニエーラ・ラッディ
1月30日 中田秀夫監督「カオス」(2000)
2月4日 森淳一監督「トイド」(2002)
2月6日 石井聡互監督「エレクトリック・ドラゴン80000V」(2001)
2月11日 三池崇史監督「オーディション」(1999)
2月13日 塚本晋也監督「双生児」(1999)
16)
2003年1月31日 ヴュッスー資料館(フェッリの間)
学術講演会
パオラ・ビッリ、ニコラ・ピッチョーリ
「現代美術における東アジアの書道」
司会:アドリアーナ・ボスカロ(ヴェネツィア大学)
共催:ヴュッスー資料館、スティッベルト美術館、ロムアルド・デル・ビアンコ財団
17)
2003年2月27日〜3月13日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第3部)。ジャンルの起源:60年代の映画作家たち」
監修:ダニエーラ・ラッディ
2月27日 小林正樹監督「切腹」(1962)
3月4日 鈴木清順監督「殺しの烙印」(1967)
3月6日 今村昌平監督「果てしなき欲望」(1958)
3月11日 新藤兼人監督「鬼婆」(1964)
3月13日 大島渚監督「青春残酷物語」(1960)

18)
2003年3月21日 ウフィツィ宮殿図書館(マリアベキアーノ大広間)
国際シンポジウム
「洋の東西の美術と思想にみられる死後の世界観」
主催:東京大学大学院人文社会系研究科・21世紀COEプログラム(「死生学の構築」)および東京大学フィレンツェ教育研究センター
協力:ピサ高等師範学校、フィレンツェ大学、パドヴァ大学、ロムアルド・デル・ビアンコ財団
後援:在イタリア日本国大使館、在日イタリア大使館、フィレンツェ美術館連合監督局
開会の辞:島薗進(東京大学)
第1部 司会:小佐野重利(東京大学)
エンリコ・カステルヌオーヴォ(ピサ高等師範学校)「ブッファマルコによるピサの壁画中の死と救済のイメージ」
浦一章(東京大学)「ブレイク:ダンテの読者にして挿絵画家」
長島弘明(東京大学)「日本における地獄イメージの流布:『往生要集』の影響」
質疑応答
第2部 司会:サルヴァトーレ・セッティス(ピサ高等師範学校)
マリア・グラツィア・チャルディ・デュプレ・ダル・ポッジェット(フィレンツェ大学)「14、15世紀のダンテの天国挿絵に関する基本的な観察」
木下直之(東京大学)「明治維新期の地獄イメージの変容」
カテリーナ・リメンターニ・ヴィルディス(パドヴァ大学)「ペスト、狩猟、そして死」
小佐野重利(東京大学)「イメージにみる源信とダンテの地獄:比較美術史の試み」
質疑応答
閉会の辞:サルヴァトーレ・セッティス(ピサ高等師範学校)
シンポジウム・プログラム
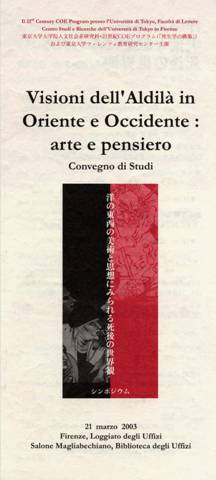



シンポジウム報告集(2003年10月刊)
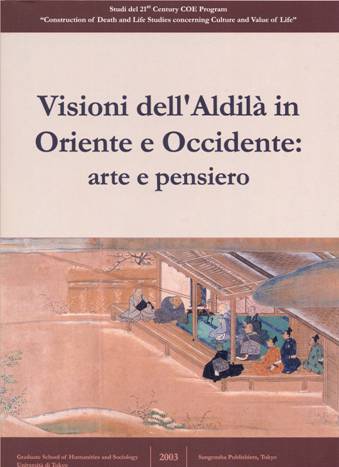
19)
2003年3月28、29日 ヴュッスー資料館(フェッリの間)
国際シンポジウム
「東洋と西洋における科学と文学の関係」
主催:ヴュッスー資料館、SISL
共催:国際交流基金、東京大学フィレンツェ教育研究センター、ロムアルド・デル・ビアンコ財団
20)
2003年4月1日〜5月20日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第4部)。今村昌平特集:日本のアイデンティティをもとめて」
監修:ダニエーラ・ラッディ
4月1日 「にっぽん昆虫記」(1963)
4月8日 「人間蒸発」(1967)
4月15日 「復讐するは我にあり」(1979)
4月29日 学術講演会 ダニエーラ・ラッディ
「直接的・間接的現実:ドキュメンタリーと物語のはざまの今村昌平」
5月6日 「ええじゃないか」(1981)
5月13日 「楢山節考」(1983)
5月20日 「黒い雨」(1989)
21)
2003年4月10日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
学術講演会
ジョヴァンニ・ペテルノッリ(ボローニャ大学、ボローニャ大学附属極東美術研究所)
「『源氏物語』の詩的空間」
共催:ボローニャ大学附属極東美術研究所


22)
2003年6月10日〜7月12日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第5部)。ドラマの再発見:6人の最近の映画作家」
監修:ダニエーラ・ラッディ
6月10日 橋口亮輔監督「渚のシンドバット」(1996)
6月17日 利重剛監督「クロエ」(2001)
6月24日 相米慎二監督「風花」(2001)
7月1日 諏訪敦彦監督「M/Other」(1999)
7月8日 是枝裕和監督「ディスタンス」(2001)
7月12日 青山真治監督「ユリイカ」(2000)
23)
2003年6月12、19日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
伝統芸能セミナー
矢内賢二(東京大学、東京国立劇場)
「文楽:ジャンルの成立と『曾根崎心中』」
作品ビデオ上映あり
6月12日 「文楽の規範」
6月19日 「近松の作劇法」


24)
2003年7月10日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
伝統芸能セミナー
矢内賢二(東京大学、東京国立劇場)
「日本の打楽器、太鼓:神代から現代へ」
作品ビデオ上映あり
25)
2003年9月9日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
特別映画上映会
「愛のコリーダ」
(フランス、1976)大島渚監督
26)
2003年9月16日〜10月21日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第6部):大島渚特集」
監修:ダニエーラ・ラッディ
9月16日 「 愛と希望の街」 (1959)
9月23日 「日本の夜と霧」 (1960)
9月30日 「白昼の通り魔」 (1966)
10月7日 「絞死刑」 (1968)
10月14日 「新宿泥棒日記」 (1969)
10月21日 「東京戦争戦後秘話 」(1970)
27)
2003年10月28日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
現代美術レクチャー
「幻想音楽:影の音楽」
演奏:片岡祐介、片岡由紀
司会:野村幸弘(岐阜大学、幻想工房)
ビデオ「場所の音楽」上映&レクチャー
パーカッショニスト2名による即興演奏あり
28)
2003年10月30日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
学術講演会
マルティーナ・ベカッティーニ(ボローニャ大学附属極東美術研究所)
「日本美術の諸相(第3部):トスカーナのジャポニスム」
共催:ボローニャ大学附属極東美術研究所
29)
2003年11月11日〜12月9日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第7部):最近の日本映画における家族の肖像」
監修:ダニエーラ・ラッディ
11月11日 岩井俊二監督「リリィ・シュシュのすべて」(2001)
11月18日 杉森秀則監督「水の女」(2002)
11月25日 竹中直人監督「東京日和」(1997)
12月2日 三池崇監督 「カタクリ家の幸福」(2002)
12月9日 黒沢清監督 「アカルイミライ」(2002)
30)
2003年11月17日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
新刊プレゼンテーション
ジョルジョ・アミトラーノ(ナポリ東洋大学)、鷺山郁子(フィレンツェ大学)、和田忠彦(東京外国語大学)
「メリディアーニ叢書における川端康成作品集出版を記念して」


31)
2003年12月13日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
特別映画上映会
「孔雀」
(日本・香港、1998)クリストファー・ドイル監督
32)
2004年1月29日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
現代美術レクチャー
坂野嘉彦(作曲家)、野村幸弘(岐阜大学、幻想工房)
「幻想音楽:回転の音楽」
演奏:鬼頭加代子、水野みどり、伊藤真美、坂野嘉彦
<第1部>(映像:野村幸弘)
1. 窓
2. Outside
<第2部>「回転の音楽」
1. 平行カノン曲
2. レコードプレーヤーのための音楽
3. 回転テーブルといくつかの楽器のための音楽


33)
2004年1月27日〜2月24日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第8部):70年代日本映画特集」
監修:ダニエーラ・ラッディ
1月27日 山田洋二監督「幸福の黄色いハンカチ」(1977)
2月3日 神代辰巳監督「赫い髪の女」(1979,)
2月10日 藤田敏八監督「修羅雪姫」(1973)
2月17日 伊藤俊也監督 「女囚さそり第41雑居房」(1972)
2月24日 長谷川和彦監督 「太陽を盗んだ男」(1979)
34)
2004年2月26日 フィレンツェ大学文学部
学術講演会
菊池真(早稲田大学)
「日本文学における猫:源氏物語と形代の猫」
司会:鷺山郁子
共催:フィレンツェ大学文学部言語学科
35)
2004年3月11日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
討論会
「アンナ・アントニーニ著『世界の魅惑:宮崎駿の映画』(Il
principe constante刊、2003)をめぐって」
参加:サラ・ファーヴァ、ダニエーラ・ラッディ、著者
引き続き宮崎駿監督「となりのトトロ」(1988)上映
36)
2004年3月19日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
学術講演会
ダニエーレ・セスティーリ(ローマ大学)
「神楽、神々の音楽と踊り」
37)
2004年3月30日〜5月4日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
日本映画セミナー
「日本映画の傾向、伝統、革新(第9部):三池崇史特集」
監修:ダニエーラ・ラッディ
3月30日 極道戦国志 不動 (1998)
4月6日 デッド・オア・アライブ 犯罪者 (1999)
4月20日 中国の鳥人 (1998)
4月27日 アンドロメディア (1998)
5月4日 極道恐怖大劇場 牛頭 GOZU (2003)
38)
2004年4月22日、5月25日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
連続講演会
「日本美術の諸相(第4部):源氏物語の美術と音楽」
共催:ボローニャ大学附属極東美術研究所
4月22日
ジョヴァンニ・ペテルノッリ(ボローニャ大学、ボローニャ大学付属極東美術研究所)
「源氏物語絵巻:絵画と文学の卓越した関係」
5月25日
小山真由美(イヴレア市立ガルダ美術館)
「漆器、源氏香、書道における源氏物語の伝統」
39)
2004年5月27日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
学術講演会
ロベルタ・ノヴィエッリ(ヴェネツィア大学)
「戦前の日本映画におけるジャンル作品」


40)
2004年6月3日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
学術講演会
土肥秀行(東京大学)
「ピエル・パオロ・パゾリーニ監督『アポロンの地獄Edipo
re』と<運命のテーマ>」
41)
2004年6月11日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
東京大学フィレンツェ教育研究センター年報
「『日伊文化Cultura Italo-Giapponese』創刊号発刊を記念して」
出席:鷺山郁子(フィレンツェ大学)、土肥秀行(東京大学)、フランチェスコ・チヴィタ(スティッベルト美術館)、フランコ・チェザーティ(チェザーティ出版社)、ダニエーラ・ラッディ、マルティーナ・ベカッティーニ(ボローニャ大学付属極東美術研究所)
42)
2004年6月29日 東京大学フィレンツェ教育研究センター
音楽セミナー
「ある晴れた日に:『蝶々夫人』初演から100年を記念して」
藤井泰子(ソプラノ)、セルジョ・ペトルツェッラ(テナー)、マッシモ・スカピン(伴奏)、ミケーレ・スオッツォ(解説)
後援:日本大使館
公演プログラム
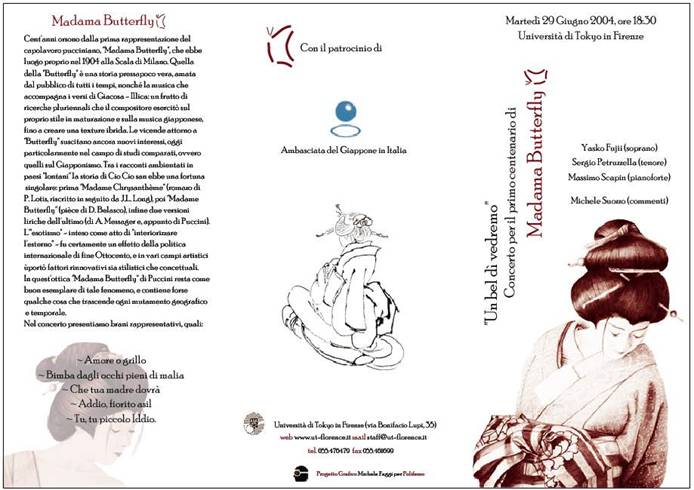


43)
2004年9月16日 BZF
「映画監督・高畑勲氏をむかえて」
司会 ダニエーラ・ラッディ
同日15時 フィレンツェ大学文学部
高畑監督作品上映会
「おもひでぽろぽろ」 (1991)
「ホーホケキョ となりの山田くん」(1999)
英語字幕付き原語上映


44)
2004年10月18日 ヴュッスー資料館(フェッリの間)
学術講演会
「初期のヴェネツィア・ビエンナーレにおける日本」
アドリアーナ・ボスカロ(ヴュッスー・アジア所長)、アレッサンドロ・トージ(ピサ大学)と
「ヴェネツィアと日本Venezia e il
Giappone: studi sugli scambi culturali nella seconda metà dell’Ottocento」
(Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte,
2004)
の著者・石井元章(大阪芸術大学)による対話
共催:ヴュッスー資料館


45)
2004年10月27日 フィレンツェ大学文学部
学術講演会
西野春雄(法政大学)
「能の魅力:伝統と現在」
司会:鷺山郁子(フィレンツェ大学)
共催:フィレンツェ大学文学部言語学科

46)
2004年11月15日 ヴュッスー資料館
「マライーニ文庫・開設記念式典」(参加)
主催:ヴュッスー資料館
出席:レオナルド・ドメニチ(フィレンツェ市長)、ミエコ・マライーニ、ダーチャ・マライーニ、ジョヴァンニ・ゴッツィーニ(ヴュッスー資料館長)、アドリアーナ・ボスカロ(ヴュッスー・アジア所長)など
47)
2005年3月5日 BZF
朗読会
吉増剛造、マリリヤ・コルボ
「The Other Voice」
司会:マルコ・マッツィ
48)
2005年3月31日(木) スティッベルト美術館(舞踏の間)
学術講演会
菅野覚明(東京大学)
「武士道とは何か」
共催:スティッベルト美術館


49)
2005年5月12, 13, 16日
映画特集上映会
「吉田喜重:われわれを見返す映画」
主催:東京大学フィレンツェ教育研究センター、国際交流基金
協力:ステンセン学院、イタリア書房フィレンツェ、BZF、フェスティバル・デイ・ポポリ
5月12日 ステンセン学院
「鏡の女たち」(2002年、伊語字幕付)
上映後講演会
吉田喜重(監督)、岡田茉莉子(女優)
「女性に見返されるヒロシマ」
5月13日 ステンセン学院
20:00「秋津温泉」(1962年)
22:00「エロス+虐殺」(1969年)
(共に伊語字幕付)
5月16日 ヴュッスー資料館(フェッリの間)
講演会
吉田喜重(監督)、岡田茉莉子(女優)
「吉田喜重:われわれを見返す映画」
フィレンツェの他、ミラノ県立シネマテーク、ボローニャ市立シネマテーク、ローマ日本文化会館、トリノ市立シネマテークにて上映会と講演会を行った。
特集プログラム表紙



50)
2005年6月28日 ヴュッスー資料館(フェッリの間)
学術講演会
「吉増剛造、詩集The Other
Voice (Scheiwiller, 2005)について」
出席:鷺山郁子(フィレンツェ大)、マッシモ・モーリ(詩人)、ヤーコポ・リッチャルディ(Playon叢書監修者)、マルコ・マッツィ(詩集監修者)
協力:思潮社



51)
2005年9月22-24日 ヴュッスー資料館
「イタリア日本学会第29回年次大会」(開催協力・参加)
主催:イタリア日本学会
52)
2005年12月9日 "Area N.O." Natura Cultura
シンポジウム
「オリエントからオリエント・エキスプレスへ
中国・日本・イギリス・イタリアの推理小説について」
後援:フィレンツェ大学日本語日本文学科
土肥秀行(東京大学、司会)「文学のジャンルとしての推理小説の機能」
ルーカ・スティルペ(フィレンツェ大学)「法の学び場 中世中国の推理小説の教育的機能」
スーザン・ペイン(フィレンツェ大学)「ホームズからヘヴルスへ イギリス推理小説の捜査官」
鷺山郁子(フィレンツェ大学)「理性の病理 日本の現代推理小説」
レンツォ・クレマンテ(パヴィア大学)「イタリア推理小説の流れ」
全体討論
シンポジウム・プログラム
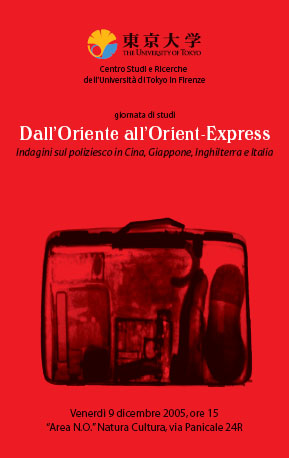


53)
2006年3月28日 “Area N.O.” Natura
Cultura
東京大学フィレンツェ教育研究センター年報
「『日伊文化Cultura Italo-Giapponese』第2号発刊を記念して」
参加:マッシモ・モーリ(詩人)、マルコ・マッツィ、トンマーゾ・リーザ(フィレンツェ大学)、土肥秀行(東京大学)
会の終わりにM・マッツィ作、M・モーリ出演、映画Niente da vedere,
niente da nascondere(部分)を上映。
54)
2006年4月11日 "Area N.O." Natura Cultura
朗読会
「吉増剛造、マリリヤをむかえて」
参加:マッシモ・モーリ(詩人)、鷺山郁子(フィレンツェ大学)、マルコ・マッツィ、土肥秀行(東京大学)




55)
2006年5月12日 フィレンツェ市立スティッベルト美術館
「能楽シンポジウム 花伝、心より心に伝ふる花」
共催:スティッベルト美術館、ボローニャ市シンバレン文化協会
後援:日本大使館、フィレンツェ大学日本語日本文学科
午前の部
挨拶:中村雄二(日本大使)、キルステン・アッシェングリーン(スティッベルト美術館館長)
演舞:モニック・アルノー(金剛流シテ、師範代) 仕舞「高砂」
司会:鷺山郁子(フィレンツェ大学準教授)
西野春雄(法政大学教授) 「現代に蘇る古典:復曲能と再創造」
引き続き「雪鬼」ビデオ上映
ボナヴェントゥーラ・ルペルティ(ヴェネツィア大学教授)「能における引用と能からの引用」
演舞:モニック・アルノー 舞囃子「山姥」
午後の部
司会:ボナヴェントゥーラ・ルペルティ
鷺山郁子「源氏に取材した能:六条御息所について」
マッテオ・カザーリ(ボローニャ大学講師)「伝統のかわらぬ活力」
モニック・アルノー「能面に仕えて」
シンポジウム・プログラム
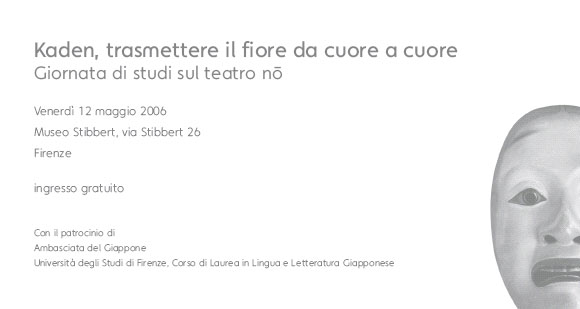




(利用状況に続く)