東京大学フィレンツェ教育研究センター活動記録(1999-2006年)
作成:長神 悟、土肥 秀行
東京大学フィレンツェ教育研究センター外観(2階部分)

会議室

図書室

センター建物入り口

東京大学フィレンツェ教育研究センターは、東京大学海外学術交流拠点の1つとして、イタリア・フィレンツェ市に1999年3月5日正式オープンした。元フィレンツェ市長宅を全面改装した施設は、中央駅からほど近いボニファーチョ・ルーピ通りに面する建物内部に設けられた。
フィレンツェは、周知の通り、西欧近代の幕開けとなったイタリア・ルネサンスの中心都市であり、その輝かしい過去を物語る文化遺産を今なお豊富に有し、世界中から多くの人びとを呼び集めている。このトスカーナ地方の都はまた、フィレンツェ大学のほか、数多くの研究所、アカデミー、図書館を擁し、市内や近郊にイタリア以外の大学・研究所の施設が集中する学術都市でもある。なかでもアメリカは、ハーヴァード大学をはじめ、多数の大学が分校や研究施設をもち、その多くが、自国の学生のために恒常的に授業を行っている。
東京大学教育研究センターも、それらフィレンツェに集まる学術教育機関と同じく、東京大学における教育・研究を充実させるべく設立されたものにほかならない。すなわち、学術の国際交流を図り、東京大学における教育・研究の一層の発展に寄与することを目的に発足した。本センターは、フィレンツェないしイタリアにある大学などの高等教育研究機関、研究所、学術団体、美術館などとの交流の調整・推進基地としての役割を果たすべく、具体的には、東京大学と学術交流協定を結んでいるフィレンツェ大学や、古くからフィレンツェにおける知識人の交流の場であったヴュッスー資料館、また日本美術品の収集で知られるスティッベルト美術館などとの交流を図った。
なお、本センターの運営全般は東京大学大学院人文社会系研究科長のもとに置かれた「東京大学フィレンツェ教育研究センター運営委員会」が担当し、2001年8月以降はフィレンツェに派遣された土肥秀行・同研究科助手(当時)が現地での活動を担った。さらに、2004年8月以降は鷺山郁子・フィレンツェ大学文学部教授をセンター顧問として迎え、センター活動への協力を得た。
東京大学代表団とフィレンツェ大学副学長の会談(1999年3月5日)

フィレンツェ大学関係者との会見(1999年3月5日、於・フィレンツェ大学文学部講堂)

センター内におけるオープニング・レセプション(1999年3月5日)

「東京大学、フィレンツェに上陸」(レプッブリカ紙、1999年3月27日)

本センターでは開設一周年を記念した国際シンポジウム「日本の中のイタリア・イタリアの中の日本」(2000年10月)をフィレンツェ大学で開催して以降、センターの内外で定期的に学術講演会・セミナー等を継続的に催した。そうした催しに際しては、東京大学所属の研究者のみならず日本・イタリアの諸機関から専門家を講師として招聘し、主に日本美術・文学・映画等をテーマとして掲げた。2003年3月には「洋の東西の美術と思想にみられる死後の世界観」と題した国際シンポジウムを、東京大学大学院人文社会系研究科・21世紀COEプログラム(「死生学の構築」)の一環として、ピサ高等師範学校、フィレンツェ大学、パドヴァ大学の協力を得て開催した。
その後、2004年8月、ボニファーチョ・ルーピ通りにあった専有スペースを離れてフィレンツェ大学文学部内に移転し、さらに強固となった外部団体との協力関係をもととした活動を展開した。2005年秋から2006年7月にかけてのセンター活動最後の期間は、2つの大きなシンポジウム(中国・日本・イギリス・イタリアの推理小説について、能楽について)の開催などにより実り多きものとなった。
2004年にはセンターについてのホームページが開設されている。
またセンターの活動を記録し、その活動内容の一端をイタリア内外に紹介すべく、紀要『日伊文化Cultura Italo-Giapponese』を2004年6月に発刊し、2006年7月のセンター廃止までに3号を発行した。
次に紀要全3号分の目次を日本語で掲げる。紀要の使用言語はイタリア語だが、各号の巻末には和文アブストラクトが付されている。
『日伊文化Cultura Italo-Giapponese』(発行元:Franco Cesati Editore, Firenze)
第1号(2004年6月)
・ 河野元昭、「狩野山雪と馬図」
・ 山口静一、「文明開化に背を向けた画家、河鍋暁斎」
・ マルティーナ・ベカッティーニ、「19世紀末トスカーナにおける日本文化の影響」
・ ジョヴァンニ・ペテルノッリ、「『源氏物語』の詩的空間の豊かさと特異性」
・ 土肥秀行、「パゾリーニと俳諧」
・ ジョルジョ・アミトラーノ、鷺山郁子、和田忠彦、「対談:曖昧さを訳す 川端康成と彼の作品翻訳について」
・ ダニエーラ・ラッディ、「日本ヌーベルバーグの内と外で:今村昌平と大島渚の映画」
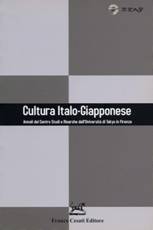
第2号(2005年12月)
・ 菅野覚明、「武士道とは何か」
・ 小山真由美、「漆器、源氏香、書道における『源氏物語』の文学的伝統」
・ マルコ・マッツィ、「“第三の河岸”エクリチュールに関する自立的仮説のためのメモ エミリオ・ヴィッラと吉増剛造について」
・ 土肥秀行、「吉田が語る映画 吉田喜重著『小津安二郎の反映画』考」

第3号(2006年7月)
・ ルーカ・スティルペ、「法の学び場:中世中国の推理小説の教育的役割」
・ レンツォ・クレマンテ、「イタリア推理小説の流れ」
・ 西野春雄、「現代に蘇る古典:復曲能と再創造」
・ マッテオ・カザーリ、「能、その伝統の“不動の”活力」
・ 長神悟、土肥秀行・編、「東京大学フィレンツェ教育研究センター活動記録:1999-2006年」

(年譜へと続く)