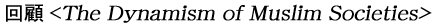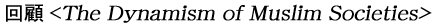本国際会議のオープニングを飾ったのは、アブドゥルカリム・ラーフィク氏(米ウィリアム・アンド・メアリー大学教授)の「アラブ近代史の解釈と時代区分―私の省察」(英語)と杉田英明氏(東京大学教授)の「中東文化と日本―その出会いの歴史」(日本語)の2つの公開講演である。
まず、ラーフィク氏は、母校であり、教鞭を振るったこともあるシリア・ダマスクス大学の歴史教育カリキュラムの史的展開を紹介した。そして、近東古代史とアラブ・イスラーム史とならび、カリキュラムの中核となっているアラブ近代史に焦点を当てる。
氏は、アラブ近代史の始まりと終わり(歴史区分)に関しては、多くの議論がなされていることを指摘する。すなわち、アラブの歴史家の多くは、オスマン朝によるアラブ地域の征服(1516年)をアラブ近代史の始まりとしているが、その終焉とアラブ現代史の開始となる日付については、アラブのみならず非アラブの歴史叙述においても意見が分かれている。ナポレオン・ボナパルトがエジプト遠征を行った1798年をアラブ現代史の開始とするものもいれば、近代史の開始だと捉える見方も存在する。
いずれにしても、実際のアラブと非アラブの大学でのアラブ近代史の授業では、19世紀と20世紀に重点が置かれているのが現状であるが、このことはそれに先立つオスマン朝支配の3世紀間をほとんど無視していることを意味する、と氏は批判する。その背景には、(特に20世紀初頭においては)青年トルコ革命以後先鋭化したアラブとトルコの対立、換言すれば、アラブ民族主義の台頭がもたらした民族主義的歴史観があったとされる。
近年ではオスマン朝時代の新たな資料の入手も可能になり、オスマン朝のアラブ属州に関する研究・教育が拡大しているが、それらの研究のほとんどが、特定の時代や都市に限定したもの、あるいは土地所有、ギルドやワクフといった特定のトピックに焦点を絞ったミクロなものであるとされる。現在では、そこから一歩進んでアラブ地域全体を視野に入れたマクロな研究が必要となっている。そして、それによってアラブ属州とバルカンやアナトリアとの比較研究への地平が拓けるのだと、氏は強調する。
次に、マクロな視点を提示するべく、アラブ近代史を4つの時代にわける試みがなされた。そして、氏はこれまでのミクロな研究成果を踏まえた上で、属州を横断するオスマン朝の全体像を描いていく。
(1) オスマン朝が強力であった時代(1516年〜1550年代半ば)
(2) 貨幣価値の下落に始まるオスマン朝弱体の時代(1560年代〜17世紀)
(3) オスマン朝の凋落とアラブ属州で広がる反抗の時代(18世紀)
(4) 王朝権力強化のための改革の時代(19世紀)
オスマン朝によるアラブ地域支配の遺産に対する評価は、既に触れたように、アラブ民族主義者にとっては暗黒の時代であった。その一方で、オスマン主義者やアラブのイスラーム主義者は、オスマン朝をイスラーム的公権力の正当な後継者と見なす。現在では、このようなイデオロギー性の強い歴史観から距離を置いたより公平な研究者たちが、新たな視座を提示している。すなわち、帝国の緩やかな統合は相応の経済的・政治的な自由を保証するものであり、そのなかでアラブ属州は繁栄を享受できたのだというものである(とは言うものの、19世紀後半以降の歴代のスルターンや青年トルコが対ヨーロッパ政策を重んじ、アラブとの距離を開いていったために、アラブとトルコの亀裂が生まれたことも事実であると、氏は付け加えた)。
アラブ近代史はオスマン帝国の崩壊とともに終焉し、ここにアラブ現代史が始まる、という認識がアラブの歴史家によって共有されているという。アラブ現代史は、西洋列強からの独立を目指す闘争の歴史に始まる。当初、非都市部でのタリーカやウラマー層を核にした宗教的な形態で起こった闘争も、都市に基盤を置く土地所有者やブルジョワジーが担う、民族主義を冠したものが中心となっていった。独立後は、旧来の支配体制への闘争の歴史となり、確固たる主義主張をもった組織が、軍部との結びつきを背景に、闘争を繰り返すという様相を呈している。
以上のような、4つのアラブ近代史の時代区分、そして闘争の変質を鍵にしたアラブ現代史の時代区分は、これまでのミクロな地方史により意味を与えるために、理解の枠組みや文脈を築くことに他ならない。また、そのような時代区分は、地方史によって生み出されるものである。ラーフィク氏は、このようなマクロとミクロの相互補完的な、そして弁証法的な関係が必要なのだと強調した。
この「ムスリム社会のダイナミズム」シンポジウムは、氏が提示する「枠組みとミクロな研究との関係」の「理想的な例」であると評価する。そして、「優れた客観的な研究であれば、どこのものだろうと、誰が書いたものであろうと賞賛されるべきである」と述べ、講演を締めくくった。
ラーフィク氏が強調する「マクロとミクロの関係の重要性」は、私たち研究者が日々認識しながらも、実践に移すことが困難であるものだと感じていることであろう。細部と全体像の両方を見よ、という氏のメッセージを、「実際には何も言っていないことに等しい」と批判するのは容易い。しかし、敢えてこのような提言がなされる背景には、現在の「イスラーム世界研究」におけるいくつかの「断絶」が認識されているのだと考えられる。すなわち、特定の地域・国に立った視点とグローバルな視点、事実発見的な研究(ファクト・ファインディング)と文化解釈的な研究との「断絶」である。特定地域や国に終始する研究は、比較の視点やより大きな枠組みや文脈を欠く傾向があることは否めない。かといって、現在の「ポスト・モダン」期において増えている文化解釈的な研究に問題が無いわけではない。それらが提示する解釈やモデルには、職人的な手法によって初めて得られる「実証性」が欠如していることも少なくない。イスラーム世界には、時代を超えた多くの資料(史料)の蓄積がある。
ラーフェク氏はアラブ近現代史を専門にする「歴史家」であるため、本講演はオスマン朝時代のアラブ地域の歴史を、各属州における社会・経済的趨勢の分析から、「全体」として捉えること(すなわち時代区分を行うこと)が議論の中心であった。しかし、氏が講演の最後で「枠組みとミクロな研究との関係の理想的な例」としてこの国際会議への期待を示しているように、言うまでもなく、氏のメッセージは「歴史家」だけに対するものではなく、イスラーム世界を対象にするすべての研究者に送られるものである。今回のような大規模な国際会議は、世代、方法論、研究対象地域の違いを超えた様々な研究者たちが一堂に会するものであり、特に私のような若い研究者にとっては、自身の研究上のスタンスを再確認し、自己点検をするための非常によい機会となる。「マクロとミクロの関係の重要性」という困難な問題を敢えて提示した氏の講演は、高い気概を感じる、まさにオープニングを飾るのにふさわしいものであったと言えよう。
次の杉田英明氏の「日本と中東―その出会いの歴史」は、まず「中東的なるもの」が何であるかの明示を避け(「中東」という地理認識はおろか言葉も19世紀以前には存在していなかった)、現代に生きる(特に中東研究者ではない)日本人の視点から今日の「中東像」が歴史的にどのように「構成」されていったかを、OHPや実物投影機やビデオなどのAV機器を駆使し、数々の事例を紹介することで描いていった。
例えば、古くは東大寺正倉所蔵の獅子や駱駝をモチーフにした工芸品(7〜8世紀)から、アラビア文字によるペルシア語の詩が記されている高山寺方便智院旧蔵「紙本墨書南蛮文字」(13世紀)、江戸時代初期の「万国人物図」などが紹介された。近代に入ると、日本人自身による中東渡航から生まれた旅行記や風景描写が目立つようになり、1862年の第2回遣欧使節に随行した高島祐啓の『欧西行記』では、カイロのムハンマド・アリー・モスクが「阨日多城寺院之図」として描かれ、20世紀初頭には滞欧経験を持つ石井柏亭や内藤秀因が、中東の風景を題材にした西洋画を残している。この頃になると日本国内でも神戸回教寺院(1935年)や東京回教礼拝堂(1938年)などのイスラーム建築が現れ、日本と中東は急速に接近していった。
戦後には「新たな中東像」が創られた。いわゆる「シルクロード熱」を背景にしたロマン主義的な中東像である。それを代表するものとして、某酒造会社や百貨店によるモロッコやエジプトをモチーフにしたPR広告などが紹介された。また、芸術の分野においても吉田左源二による墨彩画に見られるように、クルアーンの章句やアラビア文字を日本の伝統的な技法で描くという、新たな試みがなされた。
このように、日本人の中東との出会いの歴史的な推移を追った後、杉田氏はさらに1つの事例を取りあげ、それを掘り下げる試みを行う。ここでは「中東を見る窓口」として、駱駝に焦点が当てられた。1821年にオランダ船によって初めて日本へもたらされた単瘤駱駝は、絵画・引札、狂歌・小唄、随筆・記録などの主題にされた。なかでも印象的であったのは、駱駝に「楽だ」という安直なイメージが抱かれたということである。また、「形ばかり大きく役立たぬ事物」や「夫婦和合の象徴」としてのイメージも抱かれ、落語の演目の「らくだ」とよく知られた歌である「月の沙漠」(1923年発表)がそれぞれを象徴しているとされる(それぞれビデオとオーディオで紹介され、会場を沸かせた)。このようなイメージは、今日でも見られ、駱駝=楽=安楽の象徴として鉄道会社のポスターや運送会社のテレビ・コマーシャルで駱駝が扱われていることが触れられた。
最後に、今日では身近なところで中東文化に出会うことができるようになったとして、日本国内のいくつかの建築が紹介された。その多くが、中東に実在するモスクや庭園など(例えばグラナダ・ヘネラリーフェ)の様式を模したものであるのだが、杉田氏は姿形が著しく異なる両者の写真を比べることで、日本人の目にそれらの元となった建築がどのように写っているか、そしてどのように解釈されているかを示そうとした。
杉田氏の発表は、一般の聴衆も参加する公開講演とあってか、特に明確な議論は展開されず、事例の紹介に留まるものであったことは否めない。しかしながら、資料の数は膨大で、日本中世の文書から、今日のサブカルチャー的なものまで広くカバーしている。これまでも「日本人の中東発見」を研究してきた杉田氏の幅広い見識と日頃からの観察力には驚くべきものがある。氏の発表から感じられたのは、今日の日本人が抱いている「中東像」は、アラブ、ペルシア、トルコ(さらにはインド)といった地理的な認識のみならず、駱駝やイスラームをモチーフにした異なるレベルの事物もが混在する、非常に曖昧なものであるということである。この点からすれば、杉田氏が行ったのは日本人の「中東像」の「構成」過程を検証することではなく、日本人が「中東」と聞いて連想するものの個々の歴史的なルーツとそれに対する認識の変化を探る作業であったとした方が、より正確に講演の内容を言い表しているのかも知れない。氏がその著書『日本人の中東発見―逆遠近法のなかの比較文化史』(東京大学出版会、1995年)の冒頭で述べているように、こうした作業が日本人自身の中東の再発見にも繋がるものであり、さらには中東人の日本認識の再整理までもが期待されているものであることを考えれば、講演が英語で行われなかったことが少々惜しまれる。
|