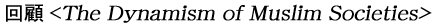
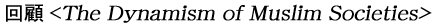
近藤亜依実(北海道大学大学院文学研究科)
| 2日目の午前・午後にまたがって行われたセッション5は発表者の数も11人と多く、相対的な関心の高さがうかがわれた。9月11日に起こった悲劇的なテロの為、予定されていた発表者Asef
Bayat氏の来訪が不可能となり、急遽ロシアからVictor A. Shnirelman氏が招待されたが、皮肉にも現在のイスラーム世界を取り巻く国際情勢の暗い面を浮き彫りにしたこの事件によって、今回の国際シンポジウムに対する社会的関心が高まった印象を受けた。全報告を通して、帝国主義時代の負の遺産をいまだ抱えるイスラーム圏の現状を、歴史を分析し認識を広めることによって、明るい方向に転化しようという傾向が見受けられた。 本セッションに一貫して見られたテーマは、グローバリゼーションへの批判と“nation”の内外におけるオリエンタリズム的隔絶を改めて指摘するものであった。各発表者はそれぞれの研究テーマの特色を出しつつ参加者との活発な論議を展開した。以下に限られた字数ながら、その内容を紹介したい。 最初の発表はStephane Dudoignon氏による、ブハラを巡る植民地時代・革命期・ソビエト政権下を通じた民族独立運動に関するものであった。ソビエト初期体制が現代に遺した思想・文化・政治・経済他広範にわたる影響を“memory”と称し、その負の面を強調したともとれる発表は、セッション後のディスカッションにて論議を呼んだ。 第2発表者の帯谷知可氏は、1917年の革命後、中央アジア各地で展開されたバスマチ運動の所産について報告した。ロシア革命後、綿花の生産地として中央アジアにロシア資本が進出した後、従来の支配階級によって起こったこの運動はやがてトルキスタニズム、パン=トルコ主義、パン=イスラム主義等に形を変えて、各国に波及した。氏が最後に述べた、部族的・地域的アイデンティティが近代ウズベクのそれに収斂される傾向があったとの言葉に、社会抵抗運動の追求する“nation state”像とはどのようなものであるのかと自問させられた。本セッションの核となるこの問題については追って述べたい。 第3発表者の栗田禎子氏は、スーダンの現状を19世紀のマフディー運動や植民地時代を通して考察する事が必要であると述べた。氏はこうした場合に使われる“nation”について、地域や人種その他の過去へと結び付く文化的存在と定義するよりもむしろ、政治的に共通した未来に向かって、各々の自由意志と選択に基づき、社会的苦境と闘争を分かち合った人々の政治的共同体として見なされる事が多いとした。更に今日の「グローバリゼーション」は帝国主義の発展段階に過ぎないと述べるスーダン共産党のメンバーの表明を紹介した後に、今回の発表において“nation state”という語を、人々の自由意志と決定によって起こる絶え間ない闘争の所産として、未来に勝ち得る事のできるものとして位置付けたと述べ、発表を終えた。 第4発表者の吉村慎太郎氏のテーマは1926〜41年のイランにおけるレザー・シャーの独裁と抵抗運動に関するものだった。イギリス・ロシア両国の対立に利用される形で興った独裁体制のパフレヴィー朝には、多くの社会抵抗運動が起こった。が、氏は運動がレザー・シャーに対抗し得るイデオロギーを持ち得ず、抵抗は不可能であったという理由から“Pahlavism”と“anti-Pahlavism”は同義であるという結論に達している。 午前の部最後の発表者である青山弘之氏のテーマは、アラブ民族主義における理念と現実の矛盾というものであった。「自由と民主主義」を求めた筈のこの運動は政治的に特徴づけられる事を余儀なくされ、やがて独裁主義の台頭を許してしまう。このような抵抗運動が理念と相反する結果を生み出す傾向については午後の部でも言及されており、ある程度の普遍性を見出す事が可能である。氏は自由と民主主義を追及したバース党の勢力は現在アラブの中で大きくはないが、その理念と活動は無意味なものではなかったとし、発表を締めくくった。 午後の部最初の発表者、Isam al-Khafaji氏は「革命の根源:中東における社会的原動力の比較分析」と題し、マシュリクにおける社会抵抗運動について扱った。大土地所有層と富裕商人層による支配体制が、運動の萌芽を促すとしている。 第7発表者の酒井啓子氏のテーマは1991年のイラクで起きたインティファーダについてであった。個人的に、社会抵抗運動の特徴を丁寧に説明する氏の発表には興味を引きつけられるものがあった。1990年代まで、イラクにおける社会運動の担い手は、1950年代に反乱を頻発させた共産党のような政治的な集団に限られると認識されていた。湾岸戦争後に勃発したインティファーダは、そういった運動とは(1)運動の領域の範囲と地理的拡大、(2)特に南部においてより顕著に見られたイデオロギー、指導者の不足、(3)運動参加者の社会階層の多様性において性質を異にしていると氏は指摘している。だが、自らの利害のためにインティファーダと1920年の暴動に近似性を見る勢力もある。一般的・思想的にも対極に位置し対立しているムスリム達と共産主義者は、体制に責任を転嫁しようと、暴動の原因を湾岸戦争の敗北と圧制に対する人々の鬱積した不満にあると一致して主張した。しかし、両者共に外国の援助を得られなかった事が不成功の主要な原因であるとは認めていない。民族統合のための象徴は、結局は体制を強化する道具であり、インティファーダの主目的は、体制によって作り出された現存の象徴を崩壊させる事だった。だが、氏は象徴に代替し得るものがあるのかどうか疑問を抱き、また、新たな象徴による支配を招く可能性を危惧する必要性があると指摘する。確かに、アゼルバイジャンにおけるイスマーイール1世や、ウズベキスタンにおけるティムールの例を取ってみても、体制が便宜的に用意する象徴を元に民族の統合を図る試みが、体制主体に終始する傾向が見られる。 第8発表者のJuan R. Cole氏は19・20世紀におけるムスリムの「非公式な植民地」パキスタンにおける抵抗運動をテーマに取り上げた。ここでも農民層のみならず都市住民による抵抗運動も、注目に値するものには育ち得ないとの指摘が為された。 第9発表者のSaodat Olimova氏は、タジキスタンにおけるイスラームと国家の相互関係を論じた。タジキスタンにおいて、イスラームは社会・文化・政治的に深く根を下ろしており、原理主義派の政党は国内外の両者のイメージに大きく影響を及ぼしている。発表後に、タジキスタン周辺においてウサマ・ビン・ラディンの活動が活発である理由についてどう思うかとの質問に対し、氏が悲しげに両者の関係はないと信じていると答えていたのが印象的であった。 今回の会議での発表が直前に決定したVictor A. Shnirelman氏は、ソ連邦崩壊後の北コーカサスの知識人によって展開された歴史観に着目し、歴史の共有こそが民族のアイデンティティにおいて重要であり、さらにそれが民族の政治的状況や領土問題とも密接に関わっていることを指摘した。また、伝統文化と言語の正統性を証明する為に遺伝学・考古学・歴史学が政治に利用された例を引き、学問と政治が不可分である実態について改めて指摘した。私は前述で“nation state”の解釈方法についての言及の必要性を述べたが、この場合は同祖観念と言語の共有という条件を追求する面から、「民族国家」と解釈し得るように思える。だが、社会抵抗運動が追求する“nation state”のイメージは、当初「民族国家」を理念としていた筈が、国家の内外の圧力によってついには政治色の強い「国民国家」に集約される傾向が概して強い。これは本セッションの各発表でも繰り返し述べられていた。氏はこうした流れの中で、固有のアイデンティティの希薄化が促されることを危惧していた。 最後の発表者である宇山智彦氏は、カザフスタンを中心に、中央アジアにおける民族独立運動の弱さの理由について述べた。移住と労働を強制されたソビエト市民も抵抗運動に参加していたが、結局は一部の知識階級に決定権があるとの概念を瓦解させるに至らなかったことが、運動の諸階級への波及を妨げる結果を導いた。“Nation-building”とグローバリゼーションは民族自決の理念に何ら協賛するものではなく、知識階級をして既存の体制を強化せしめるものに他ならないと指摘した。 ディスカッションでは、Dudoignon氏の多用したソビエト初期の“memory”という語について活発な論議が展開された。現在“memory”は、ネガティヴなイメージが強いが、良い遺産もあるのではないかという意見も見られ、この問題が抱える困難さが窺われた。 全体の発表を通して、ここ1〜2世紀の中央アジアにおけるイスラーム国家は、物理的・精神的植民地支配からの脱却を図るべく、民族自決の理念の実現を目指した事が述べられた。多かれ少なかれソビエト社会主義に影響を受ける事を余儀なくされた諸国は、冷戦崩壊後、それぞれのヴィジョンを模索している段階である。 いずれの発表においても、主体・客体(労働者階級と知識階級、個人と国家、オリエントとオクシデント)それぞれの意識改革を困難たらしめている西洋によるグローバリゼーションへの危機感が指摘されていた。その文化・社会・経済・政治的諸範囲に及ぶ弊害は、それまでの両者の地位を固定化させる結果を生んだ。結局は欧米諸国の援助を受けなければ改革もままならない現状が、今回のような過激な原理主義の活動や排外的な単一民族的思想が台頭する土壌を用意したとも言える。私は今回の会議に出席し、従来客体に位置付けられていた側から始めるグローバリゼーションの必要性を再認識した。 |