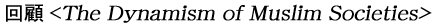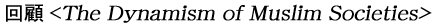|
以下は2001年10月7日に行われた第5セッション"Social Protests and Nation-Building in Muslim Societies"での発表の内容を要約したものである。なお、Ingeborg Baldauf 氏(Humboldt University of Berlin)と Assef Bayat 氏(American University in Cairo)は参加を取りやめ、かわりに Victor A. Shnirelman 氏が自身の発表をすることとなった。
Stephane A.Dudoignon(CNRS,Strasbourg) "The "Tumani" and "Kulabi" Factions(Taifas) in Bukhara during the Colonial, Revolutionary, and Early Soviet Periods(1876-1929):Diachronical Approaches"
中央アジア史におけるこれまでの歴史叙述は国家建設を主眼としたもので占められてきたが、近年、歴史的記憶と共同体意識、中央アジア内部における集団アイデンティティと分節などに対する新たな視角が見られる。ブハラの著名なウラマー、Mirza Muhammad Sarif Sadr-i Ziya の「日記」は、ペルシア語史料が軽んじられてきたこの地域の歴史研究を是正すると共に、それが一度焼失した後に再び書かれたものであることから、「記憶」の性格を有するものとして注目される。ここには1870年代後半から1920年代のブハラの政治状況、とりわけズィヤー自身も属した Tumani とその敵である Kulabi という政治派閥に関する記述が見られる。こうした派閥は地域的なものであり、カリスマ的な資質と社会的地位等を介した個人的なネットワークによって形成されている。したがってこのような研究は、権威のあり方、地域の政治システムにおける親族の果たす機能等、社会学、人類学など他の分野に対しても開かれた議論を提供しうる。
帯谷知可(国立民族学博物館地域研究企画交流センター) "The Basmachi Movement as a Mirror of Central Asian Society in the Revolutionary Period"
バスマチ運動は、ソビエト期には反革命的、ブルジョワ民族主義的運動として否定的に評価されていたが、ペレストロイカ後の歴史の再評価の中では逆に、「民族解放運動」「独立運動」として肯定的に評価されるようになった。しかし両者とも革命期の中央アジアを捉える視角としては不十分であるとし、バスマチ運動を、革命期の混乱と中央アジアの多様性を反映したものとして捉える視点を提出した。バスマチ運動は反ソビエトという点のみが共通するがそれ以外の点では雑多な人々からなっており、政治的目標である「トルキスタン」のイメージも様々であった。コルバシと総称される運動のリーダーの一人、マダミンベクは、最近の研究から地元でかなり影響力を有していたことが明らかになっている。彼は自警団をもとにバスマチ運動に加わり、伝統の擁護とソビエトとの協調路線を掲げていた。一度はソビエト側とムスリムの自治体建設を約束したものの、その後のソビエトの態度硬化により挫折した。
栗田禎子(千葉大学) "The Dynamics of Nation-Building in the Sudan"
スーダンの国家形成を考える際、マフディスト運動を再考することが必要となる。マフディスト運動は、農民や遊牧民のほかに、重税から逃れて商人となった者や奴隷兵士など、近代的、都市的要因を広範に含み、マフディーのもとで「スーダン国民」の原形に当たるものを目指した運動であった。従来、20世紀以降のスーダン・ナショナリズムは、ウンマ党とユニオニスト諸政党の二分法の枠組みで説明されてきたが、両者ともに、奴隷出身の官僚が重要な役割を果たしたという点で共通性が見られる。そして、彼らのあいだから「スーダン国民」の概念がはっきりとした形となって登場するのである。更に、彼らの子孫が後にスーダン共産党の中心的な位置を占めたことも重要である。このように様々な社会的地位の人々による「スーダン国民」を希求する運動が、人種や宗教によらない、「社会契約」に基づいた、現在あるような「スーダン国民」概念に結びついているのである。
吉村慎太郎(広島大学) "Reza Sha's Changing Dictatorship and Protest Movements in Iran, 1926-41."
抵抗運動との関連でレザー・シャーの「パフラヴィー主義」を見ると、それはシーア派ウラマーとの関わりから始まる。西洋を模範とした、法や教育などの一連の改革の中で、ウラマーたちは徴兵制度をきっかけとして抗議行動を行なった。シャーには部族民などに対する懸念もあり、これには妥協案を示して対処した。しかしカシュガイをはじめとする諸部族の反乱を強権で抑えこむことに成功すると、シャーはイスラーム以前からの文化的要素を重視するナショナリズムを打ちだした。ウラマーたちに対しても強い姿勢で望むシャーがヴェールの廃止を定めると、この政策に対する批判の声がモスクに現れ、軍隊の突入による死傷者とウラマーの逮捕という事態を見るに至った。こうしてシャーは数々の不満分子を制圧し、独裁制を完成することができた。イラン近現代史のこのような歩みから、抵抗運動がコミュニティを越えて広がることがないこと、そこに分権的なイラン社会の特徴が見られること、ウラマーたちの反応が一枚岩ではないこと、抵抗運動にイデオロギー上の求心力がないこと、といった諸特徴が見出される。
青山弘之(アジア経済研究所) "Contradiction between Thoughts and Realities in Arab Nationalism:Wahib al-Ghanim's Contribution to Development of the Arab Bath Movement"
自由と民主主義を掲げたアラブ・ナショナリズムがなぜ権威主義体制という結果に至ったのか。アラブ・バース運動の指導者であった Zaki al-Arsuzi の理論的側面を更に発達させた Wahib al-Ghanim の業績と、その後継者の「逸脱」に焦点を当てることで説明しようとした。アル=ガーニムは、アル=アルスーズィーの思想のうち、アラブ主義、自由と民主主義の主張の部分は評価しながらも、「リーダーシップ」の部分はポピュリズムにつながるものとして警戒していた。アル=ガーニムは代案として社会主義を打ち出した。それは「国家民主主義的社会主義」とでもいうべきもので、階級対立を否定し、無産者階級による政治参加とそれによる国家統合、経済関係ではなく人間性に基づく社会主義、アラブ社会主義にこだわるよりもまず国家統合と国家財産による、社会主義実現のための具体的なヴィジョンといった特徴を持つ。こうしてミッシェル・アフラク率いるアラブ社会主義バース党との合同によりアラブ・バース党が誕生した。しかし、アル=ガーニムが1950年代後半に政治活動から引退した後に党を動かす立場となった後継者たちは、アフラクやアル=ガーニムの社会主義に見られる「理想的な性格」に批判的であり、「政治活動」は搾取される人々の参加を意味するのではなく、自分たちが権力を握るための手段であるとして、アル=ガーニム本来の思想から「逸脱」してしまったがために権威主義体制の性格を帯びることとなったのである。
Isam Al-Khafaji(University of Amsterdam) "Roots of Revolution:A Comparative Analysis of the Social Dynamics for Change in the Middle East"
1930から40年代の中東では、都市部への人口流入による都市の拡大、官僚層等、国家セクターの拡大が見られ、エジプト、イラク、シリア等で起きた革命はこうした歴史的背景から生じた。革命の担い手は大部分、中下層の自営農民出身であり、大商人、地主などの富裕層を敵視した革命を起こした。革命勢力が富裕層の打倒を目標としたのに対し、都市部の民衆は都市における生活の改善を望んでいたため、革命後には都市部の民衆との乖離が目立つようになる。やがて革命のリーダーらは、イデオロギーに有効な政治的力を認めることができず、政治活動において、親族や友人関係のネットワークにしか頼れなくなった。こうしたことの結果、マシュリク社会のアトム化や経済への国家介入の度合いの増大などが引き起こされたのである。
酒井啓子(アジア経済研究所) "The 1991 Intifada in Iraq:Through Analysing the Discourses of Iraqi Intellectuals"
1991年にイラク南部で起きたインティファーダについてのディスコースを、イスラーム主義者と共産主義者を対象として検討すると、両者共に社会階層を越えた広範な大衆の参加を認識し、インティファーダという用語で運動の枠組みを規定したことがわかる。また組織力の無さが運動の失敗につながったとする見解も共通する。運動の失敗については、集団的・組織的基盤を通さない、ネットワークによる権力の浸透という、フセイン政権の特徴からこれを解釈する見方もあり、これはイラク社会の市民性の欠如を暗示する解釈である。しかし、シーア派的な宗教性を基盤としたものとして運動を見る見解と、「イスラーム革命」ではなく、「市民の抵抗」という語感のある「インティファーダ」という言葉で運動を規定した側面を考慮すると、そこに公的領域を形成する努力を読み取ることができるのではないか。
Juan R.Cole(University of Michigan) "Rebellions and Revolutions against Informal Empire in the Middle East"
2001年9月のテロ事件以後、パキスタン政府は対米協力に向けてこれまでの方針を転換することとなった。この決定には、カシミール問題、多額の債務、経済制裁等の諸問題において事を有利に運ぼうとする政権の思惑が読み取れる。一方、このような政府に対する「群集」のデモやストライキの発生を見ると、それはおおむね不首尾に終わっているといえる。イスラマバード、ラホールの生活は普段と変わらないものであった。パンジャブ地方ではストの発生は都市により大きく異なる。ストへの呼びかけが成功したのはクエッタとカラチであるが、それでも都市の規模の割には参加者はかなり少ない。ストが発生したのはいずれもデーオバンド学院の影響力が強く、イスラーム主義政党の活動しているところであり、これと対立するスーフィー教団の影響下にあり、パキスタン人民党の支持者の多い地域ではストは起きていない。このように、「群集」の問題を考える際には、地域ごとに異なる政治文化、政治伝統を考慮することが必要である。
Saodat Olimova(Center"SHARQ", Tajikistan) "Islam and Construction of a National State in Central Asia:Islamic Movement in Tajikistan"
タジキスタンにおけるイスラーム運動と国家との関係を考慮する際、二つの主要な問題が認められる。ひとつは、イスラーム政党と世俗的政治システムとの関係である。内戦と和平協定締結というプロセスの結果、世俗体制は憲法通りに温存され、イスラーム政党の活動は合法化された。しかし、民主主義、法、教育等の分野においてイスラーム主義がどのように扱われるかは依然問題として残されている。もうひとつの問題は、国家建設と超国家的なイスラーム運動との関わりである。これまでのところ、国家によるナショナリズムの影響が大きく、イスラーム政党の指導者もこの枠組みを越えようとする動きを示してはいない。しかし、トルコ系など、非タジク系民族の動きについては予測がつきかねる。また、社会、経済上の諸問題がイスラーム解放党の勢力拡大につながっている点も見逃せない。
Victor A.Shnirelman(Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences) "A Caucasian Knot:Origins of the Peoples,and Politics in the Caucasus"
ソビエトでは独自の言語と文化を有することがエスニック・グループの政治的地位を左右した。そのために、何よりも民族がアイデンティティとして重要視された。この理由から、先史学や古代史の研究が政治的に偏向する事態が生じた。カフカスにおいては、この地域に古代に存在した民族との地域的・文化的連続性を学術的に示すことがそれぞれの民族の立場から行われた。そのために、紀元前7世紀頃に存在した、イラン系とされるアラン人について、オセット人などのイラン系民族はそれをイラン系であり、自分たちはその直接の子孫であると主張し、バルカル人やカラチャイ人などのトルコ系民族はそれをトルコ系だと主張するような、正反対の主張が見られる。このように、後世の、複雑な文献史学ではなく、相互に明確に区別される考古学的文化を民族的に解釈することで、各民族の「黄金期」が学術的装いのもと、政治的に追究されているのである。
宇山智彦(北海道大学スラブ研究センター) "Why Is Social Protest Weak in Central Asia?:Relations between the State and the People in the Era of Nation-Building and Globalization"
中央アジアでは五ヶ国間の統合よりも、個々の国の発展の方が重視され、大統領の強力な権限のもと、経済の重要な分野は大統領の一族や官僚が占めることで民間セクターの発達が阻害され、イデオロギー的には民族史が鼓舞されて国家の正当性を示すものとなった。こうした状況下で、都市の知識人が主導する市民運動が若干見られたものの、それらは権力による介入を受け、その過程で多数の死者も出たために、人々は運動よりも秩序を求めるようになった。イスラーム主義者でさえ、国家自体を否定するような構想は示さなくなっている。さらに、グローバリゼーションが国家を脅かすという危機感が、軍備増強、経済取引に対する国家の介入、国境管理の強化などを通じて国家権力の強化につながっている。国家建設が急務であるという観念が国家と国民の双方に共有されるようになったために、この地域では抵抗運動が弱いのである。
さて、本セッションは近代以降を扱うものだが、それでも対象とする地域や分析の視角は多様であり、これらの報告を一括して論じることは筆者の手にあまる。しかし、最後に一点だけ指摘しておきたい。発表者の一人宇山氏は、自身の発表の冒頭に、セッションのタイトルに「社会的抵抗」とありながら、どの発表者もそれを正面から論じていないと指摘しておられたが、おおむね同じことが「国家建設」についても言えるのではないか。何人かの発表者は、国家建設、国民統合という国家の理想のもと、歴史記述が偏向するという状況があると指摘している。そのためか、「国家」よりも、「国家内部での地域的差異や多様性」に注目する発表が多く、それはそれでもっともなことであると思えるのだが、しかしそれを踏まえたうえでもう一度「国家建設」という主題に戻ろうとする発表が少なかったのが残念である(この点で栗田氏と酒井氏の発表はそうした視点を保ったものであると評価できる)。いくつかの発表において、イデオロギー的な求心性が働かないという指摘が共通して見られたという印象を筆者は持った。さらに、そうした場合、個人間のネットワークの重要性という現象が現れているようにも見受けられる。例えば、これらの二点について地域ごとに比較し、それがその後の国家建設にどれほど影響しているのか、またはいないのかといった視点から「国家建設」を論じるのであれば、微細な地域的差異に目をむける実証的研究がさらに生かされるのではないだろうか。
|