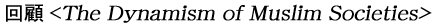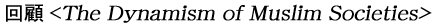|
第一セッション「現代ムスリム世界におけるイスラーム主義と世俗主義」では、イスラーム主義と世俗主義およびイスラーム主義内部の軋轢・論争・変容について、特に1980、90年代の各地でのイスラーム主義の興隆を念頭に、各発表者から報告がなされた。
まず、柳橋博之氏の「アラブ諸国における古典法と現代法制度の関係」では、近代シリア身分法の分野におけるイスラーム法体系の展開が議論された。多くの近代イスラーム諸国の法体系では、多くの分野が西洋の世俗法を基本としているが、身分法の分野においては伝統的なイスラーム法(フィクフ)が未だその命脈を保っている。柳橋氏は近代シリアの身分法においてフィクフがどのように活用されているかを、庶子の認知や法的能力を欠いた者の婚姻契約などの例を挙げながら探ることで、フィクフの基本的な性質について考察を加えた。
例えば法的能力(アフリーヤ)を欠いた者の婚姻契約について、シリアの身分法では、アフリーヤを備えた者のみ自らの意志によって婚姻契約を結ぶことができるが、それ以外の精神障害者などアフリーヤを欠いた者が婚姻を結ぶ場合は、裁判官の許可が必要であることが明記されている。しかし、判例ではアフリーヤを欠いた女性でも、彼女の保護者の許可があった場合には、その婚姻は有効であるという判断が示されている。実際、アフリーヤを欠いた未成年者でも、保護者の許可・監督を条件に、売買契約などを締結する能力をもつとされている。しかしながら、他の判例では、アフリーヤを欠いた未成年者の婚姻は無効(ファースィド)であるとの判断も示されている。このように、アフリーヤを欠いた者の婚姻契約の有効無効について、シリア身分法は定まった判断を示してはいない。ところで、このファースィドとは何かについての詳細を知るためには、伝統的なフィクフを参照しなければならない。それによれば、ファースィドとは法学派によって判断の分かれるような事例をいう。シリアの判例で示されたようなファースィドな婚姻とは、それゆえ、有効か無効かのイジュマーが成立していないような婚姻のことであり、そのような事例はそのときどきの状況に合わせて適宜判断することが求められている、ということなのである。
このような例から、柳橋氏はフィクフの性質を以下のようにまとめている。すなわち、第一に、近代に入って制定された身分法には曖昧な点が多く、語句の詳細な定義に欠けるため、フィクフの伝統を参照することで法解釈をより明確なものとしてきたという。このためシリアの近代身分法は、伝統的なイスラーム法によって補完され、またその延長線上にあるものと考えることができる。第二に、しかしながら重要なのは、イスラーム法の延長線上にあるシリア近代身分法は決して、閉じた体系、単なる過去に成立した法解釈の反復ではなく、様々な問題が完全には解決されないまま、その解決は後世の法解釈に委ねられているという点において、つねに変化する性質のものである、ということである。
柳橋氏はフィクフとシャリーアを区別しなくてはならない、と主張するが、その理由は、「フィクフとはシャリーアを解釈しようとする試みであり、それゆえイジュマーによって支持されないかぎり、批判に対して開かれている」からである。その意味でフィクフとは、「伝統的な法体系」ということばにつきまとう硬直性のイメージとは逆に、状況対応的な柔軟性に富んだものであることが示唆されている。
N. Chandiramani氏からは、「ムスリム家族法:ジェンダー・バイアス」と題し、インドにおけるムスリム身分法・家族法の成立過程とその規定について、特に女性差別的側面に関する報告がなされた。
インドにおける身分法・家族法は各宗教で異なるため、インドのムスリム女性はムスリム身分法・家族法の適用を受ける。英国統治下に制定されたムスリム身分法適用法(1937年)、ムスリム離婚法(1939年)、そして、独立後の1986年のムスリム婦人(離婚における権利の保護)法である。
前二者は、法制の近代化と女性の地位向上を目指すとしたが、実際は、例えば各地の慣習法の影響を受けることで従来容認されていたある種の女性の権利がシャリーアに矛盾するとしてそれ以降認められなくなるなど、かえって女性に不利に働いた。また、後者は、その前年のシャー・バーノー裁判(離婚されたあるムスリム女性が前夫による扶養費の支払いを求め、勝訴)の判決に激しく抗議したムスリム原理主義者を宥めるべく制定されたという経緯があり、これにより、ムスリム女性は離婚後の扶養費支払いを規定する刑事訴訟法典の適用外となった。以降、裁判所の判例による法改革の試みがなされるも、限定的である。
これらムスリム身分法・家族法により、婚姻、メフル、配偶権の回復、離婚、扶養費、子の後見・監護、養子縁組、相続の各面で、ムスリム女性はヒンドゥーなど他宗教の女性と比べ著しく権利の制限を受けており、これは宗教の平等、男女の平等を保証する憲法に明確に違反している。従って、ムスリム女性は平等を勝ち取るべく、全国民に等しく適用される世俗主義的な家族法典の制定を要求すべきである。
以上が氏の報告であるが、総じて、世俗主義的な憲法を擁護する立場から、現行のムスリム身分法・家族法を女性差別的であるがゆえに断罪するものである。そのため、彼ら「保守的」な「原理主義者」がイスラーム法をムスリム・アイデンティティの拠り所と見なしてその危機を叫ぶことの政治性、歴史的・社会的背景を分析する視座を欠いている。例えばヒンドゥー・コミュナリズムとの軋轢の歴史についての言及も欲しいところであった。
小林寧子氏の「インドネシアにおける公式ファトワーとウンマ:味の素事件をめぐって」では、インドネシアにおける「政府とウンマの相互作用、フィクフをめぐる言説、世俗主義と宗教の関係」が分析された。
小林氏によれば、インドネシアにおける再イスラーム化には、キリスト教徒との関係における宗教的不寛容という側面がある一方、他方で政府に対する不満を表現するときの媒介としてイスラームが活用される側面や、社会的コンテクストにイスラームを柔軟かつ積極的に順応、適応させようとする、「イスラームの土着化」の側面などがあり、イスラームがときに相対立する政治的立場を表明するのに用いられているという。
このようなイスラームの多義性は、インドネシアで公式のイスラーム組織である「ウラマー評議会(MUI)」の発令するファトワーとそれをめぐる賛否両論の様々な議論によく現れている。氏の議論では避妊方法に関する問題(子宮内避妊器具の使用の是非について)、異教徒との婚姻・養子縁組に関する問題、賭博をめぐる問題(サッカーくじは是か非か)、食品のハラール問題(食用ガエルの養殖とその摂取、豚の成分が最終的な製品に含有されているわけではないが触媒として使用されたときの味の素社の調味料の是非)など、様々なウラマー(中央MUI、地方MUI、民間イスラーム団体の間の、あるいは強硬派ウラマーとリベラル派ウラマーの間の)によるイスラーム法の解釈をめぐる論争、その判断のインドネシア政府の国民統合理念との一致と齟齬、それらに対する社会(「ウンマ」)の反応など、インドネシアにおける再イスラーム化の諸相が非常に興味深い形で紹介されている。
例えば、MUIはインドネシアのキリスト教化への危惧から、政府の堅持する国民統合理念とは対立する仕方で、ムスリムの異教徒との結婚、ムスリムの子供の異教徒への養子縁組、ムスリムが相続した土地の異教徒への売却などを禁じ、また中心的に論じられている味の素社の調味料のケースでは、MUIは「ハラールなものとハラームなものとが混じり合った場合は、ハラームの方が勝る」とのカーイダ(法格言)から、調味料についてハラーム認定をしたのに対し、ワヒド大統領は、別のカーイダ、すなわち「有益なものを獲得するよりも、大きな危険を拒む」とのカーイダを用いてMUIのハラーム認定を批判する、といった具合に、インドネシアではイスラームが様々な利害対立の焦点として、ますます耳目を集めるようになってきているという。
B. Babadjanov氏の「非イスラーム国家におけるイスラーム共同体:共和国独立前・後のフェルガナ渓谷における伝統派ウラマーと革新派ウラマーの見解」では、中央アジア・フェルガナ地方における再イスラーム化の潮流について、分析がなされた。
フェルガナ地方の伝統派ウラマーは、イスラーム的知識の未来への継承という大義のために、非イスラーム国家による支配に適応していかなければならないという、ハナフィー派(そしてフェルガナ地方におけるその発展型であるマートゥリーディー派)の伝統的解釈を受け入れてきた。これに対して、ハナフィー=マートゥリーディー派の考え方は政教分離を追認するものに他ならないとして拒否する革新派が1980年代以降、現れるようになる。その代表的論客Muhammad-Pajab
Quqandiは、異教徒によって押しつけられたビドアからイスラームを浄化し、ムハンマドとその教友が生きた初期イスラーム共同体の時代、サラフたちの生きた時代へと回帰しようと主張する。このような革新派=サラフィー主義者の挑戦に対して、コーランや預言者ムハンマドの言行を根拠にした、非イスラーム的国家における非ムスリムとムスリムの共存を主張するハナフィー=マートゥリーディー派からの応酬もあるなど、中央アジア・フェルガナ地方の再イスラーム化の様相は決して単純ではない。むしろ、Babadjanov氏の議論を敷衍すれば、「イスラーム」を巡る様々な議論・言説間の対立・葛藤のただ中にこそ、「再イスラーム化」の潮流が見出されるということになろう。
澤江史子氏の「トルコにおけるイスラーム主義者の新潮流:1990年代のイスラーム主義系雑誌の分析から」では、政教分離・世俗主義(ライクリッキ)を国是とするトルコにおける再イスラーム化、特に1990年代におけるその新たな潮流に焦点が合わされた。
トルコにおける「イスラーム主義者」とは、1970年以前までは「モスクに定期的に通う人々」を、70年代には、「共産主義に対してイスラームを防護しようとする人々」を、そして80年代には「イスラーム国家の樹立を主張する人々」を意味していた。しかし、1983年の民政移管後のオザル政権以後のリベラルな政治状況により、疎外された存在としてのイスラーム主義者たちの自己イメージが否定されると、90年代、彼らは「政治倫理としてのイスラームを強調する人々」との政治的自己アピールを行うようになったという。
例えば1990年代前半から中葉にかけてイスラーム主義知識人によって発行された三つの雑誌Panel、 Yeni Zemin、 Bilgi ve Hikmetは、「世俗主義者」を排撃しイスラーム主義者を擁護するためのものではなく、一方で「世俗・リベラル主義者」たちの親民主主義的・反権威主義的意見に敬意を表し、彼らと対話するリベラルな雰囲気をつくりだし、他方でトルコ内外のイスラーム主義者を批判する自己批判的性格をもった雑誌であった。これにより、このような新たな傾向をもったイスラーム主義知識人と世俗・リベラル主義者たちの間に、教条的・権威主義的なトルコの世俗主義を批判し、政教分離や信仰・思想の自由という民主主義の原理を擁護する共通の対話的土俵が生まれた、と澤江氏は指摘している。
さらに氏は、宗教的信仰へと回帰することで、西洋的近代性によって惹起された問題に対処し、近代性に対して実践的な代替モデルを提起するという、「イスラーム国家」の構想を紹介する。宗教・民族・イデオロギー的多元主義を擁護し、複数の法の存在、人々がそれぞれ独自の信仰に基づいた生を送る権利を認め、一元的な法の支配を要求する民主主義の欠点を超克できる、と主張するものであるが、しかし、差異や多元主義に対する彼らの理解は、澤江氏によれば決して深いものではない。そのため、ムスリム共同体とキリスト教徒やユダヤ教徒の共同体の平等な関係はどのように実現されるのか、そもそも誰が自らの共同体をイスラーム的であると決定する権利をもつのか、という問題は未解決のまま残されており、また、自らのムスリムの定義から世俗主義的なムスリムを排除してしまう懸念もあるのだという。
最後に、F. Burgat氏からは、20世紀以降の「ムスリム・テロリズム」「イスラム原理主義」として名指される政治的暴力を分析するにあたり、いかなるアプローチがなされるべきか、について発表がなされた。
まず示されたのは、分析者側が「イスラム原理主義」の宗教的用語法に引きずられ、彼らムスリム直接行動派の実際の活動や政治的アジェンダをイスラーム決定論式に説明づけてしまうことの、危険性である。実際のイスラーム社会においては、イスラーム文化の語彙と政治的暴力の正当化の間には深い断絶があるのが一般的であるのに対し、分析者は「イスラム原理主義」即ち暴力として見なしてしまう。20世紀におけるムスリムの政治的暴力の歴史をフランス人の立場から概観しても、アルジェリアのナショナリストたちの運動や、ナーセルによるスエズ運河国有化などの際に見受けられた言説は、実は極めて没宗教的な内容であり、むしろ昔ながらの反帝国主義・反植民地主義的言説がイスラーム的用語法で表されたものと捉えることができるのである。
結論として氏は、「ムスリム・テロリズム」分析の際の留意点として、以下の点を指摘する。まず、対象に対する憎しみ、敵意から分析を始めてはならないこと。それから、イスラームを旗印とした運動を考察するのに、社会・経済学的アプローチのみでは不十分であること。例えば、貧困、失業に全てを還元することはできず、同様にナショナリズムという観点だけでも説明は難しい。そして、直接行動派の暴力的行為は、反帝国主義運動以外の側面も考える必要があり、その際、人々の動員を可能にしているイスラーム文化の語彙の用い方のヴァリエーションにも注意を払うべきであること、である。
セッションの主題であるイスラーム主義と世俗主義の対立とは直接関係のない発表ではあったが、イスラーム主義の宗教的用語法を相対化するためのバランスのとれた視座を目指すという点で、示唆に富むものであった。
終わりに、上に紹介したイスラーム主義と世俗主義の相克をめぐる各地の事例報告を踏まえ、今後の展望を探ってみたい。
発表はどれも、国家の世俗主義に対するイスラーム主義の挑戦という営為のなかで、「イスラーム」が特殊近代的状況のなかで再現出していく過程を描き出しており、非常に興味深いものであった。ただ、専らイスラーム主義運動の実践的・制度的な側面ばかりが取り上げられ、イスラーム主義と世俗主義のイデオロギー的・思想的な側面が後景に押しやられている感が否めなかった。「〜主義」に関する研究にありがちな観念論的な議論に終始することがなかったのは歓迎すべき傾向であるが、欲を言うなら、事例紹介にとどめずさらに一歩進めて、この二つの思想的基盤の批判的分析にまで踏み込む報告があっても良かったのではないか。個々の地域の特殊性をこえた学際的な共通の議論の基盤を築くうえでも、思想構造の分析というアプローチも有効ではないかと思われる。
例えば、イスラーム主義と世俗主義の間の様々な対立・相違点を露わにするという点では、豊富な議論がなされた。しかし、イスラーム主義者だけでなく、キリスト教徒やユダヤ教徒、世俗主義的ムスリムなどイスラーム主義や世俗主義を議論する様々な立場・見解の人々が、「イスラーム」や「宗教」、「世俗社会」、「国民」、「国家」、「文化」等々の概念を用いて語る際、そこには何らかの暗黙裡に自明のものとして看過されてきた、議論の共通の土台のようなものが存在すると仮定することはできないだろうか。そのようなものとして、ここでは「近代性」を挙げてみたい。
世俗主義が近代化の必然的帰結として長らく議論されてきたことは周知のことであるが、イスラーム主義もまた、各報告に見られるとおり、単に時代に逆行する反動主義つまり前近代的である、として片付けることのできない現象である。また一方で、今度は逆に時代を先取りするものとして、澤江氏の報告におけるトルコのイスラーム主義者の事例に見られるような「西洋近代の呪縛を超克する方法としてのイスラーム」といった言説も、近代的政治言語システムとイスラーム主義のそれとの比較を待たずして分析者側が安易に取り入れるには、留保が必要かと思われる。
例えば近年、冷戦後多発する民族紛争(それらにムスリムが多く関わっていることは、言を待たない)を背景に、西洋近代の所産である国民国家の功罪に関する議論が活発であるが、彼らイスラーム主義者は自らの所属する国家における世俗主義に対抗する(もしくはそれと折り合う)うえで、現在の国民国家世界システムとでもいうべき現象を、「イスラーム的」な国家観や国民観により相対化させ、そのことでパラダイム・シフトの可能性を示唆しているといえるのだろうか。また、「我々ムスリムの政治理論は○○である」と彼らが唱えるとき、その「我々ムスリム」アイデンティティは、近代的合理主義に基づく二値論理的発想法から、絶対的に自己と異なる存在としての他者を措定することで立ち上げられたものとは違った形態なのだろうか(最近の例として、ビン・ラーディンが米国を「十字軍」と名指して「ジハード」を唱道する論理と、ブッシュの議会演説での二項対立を駆使したレトリックとの親和性)。さらに言えば、このような他者の措定・排除の論理に基づく集団観(特に国民)が現在のマイノリティ問題を各地で生み出しているとすれば、ある世俗主義国家の内部におけるイスラーム主義者のアイデンティティ・ポリティクスは、そうした問題を回避しうるものであるだろうか。
さらに、より重要なことは、イスラーム主義や世俗主義を分析する私たちの側が、これら近代的知のシステムを相対化する構えが求められているのだということである。近代性とイスラームを対立的・相互排除的なものとして捉えずに、個々の事例におけるイスラーム主義の言説傾向がどのような問題点や限界をもち、またどのような可能性をもつのかを分析するための枠組みの構築が、今後の課題の一つとなるだろう。
|