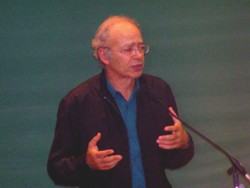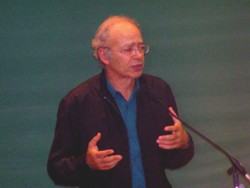| 日時 | 2006年6月15日(木)17:00〜 |
| 場所 | 東京大学法文2号館 1番大教室 |
| 発表者 |
ピーター・シンガー教授(プリンストン大学 生命倫理学)
|
| 司会 |
一ノ瀬正樹教授*(東京大学 哲学)
|
*事業推進担当者
|  |
6月15日(木)午後5時より東京大学文学部一番大教室にて、生命倫理研究および動物解放論で著名なピーター・シンガー教授の講演研究会がCOE「死生学の構築」主催、哲学会共催で開催された。シンガー教授はオーストラリア出身でオックスフォード大学他に学び、プリンストン大学で生命倫理学の教授を務める、ベジタリアニズムの実践等で人々の実生活に直接影響を与える稀有な哲学者である。
今回の講演会「生死の意思決定に関して倫理学を変えること」(Changing Ethics in Life and Death Decision Making)は、脳死、重い障害を負った新生児の扱い、安楽死・医師による自殺幇助等、主に生命倫理に関わるものであった。議論では、氏のもう一つの主題、動物解放論との連携性も感じられた。
まず、「回復不能な昏睡」あるいは脳死は「ひとの死」という定義をあげ、これを、自然科学的根拠に基づく死の定義の変更ではなく倫理的変更だとする。その上で氏は、伝統的な死の定義を維持しつつも「生命の神聖性」という規範を変えて、脳死の人からの臓器移植を認める、という別の倫理的変更もあるはずと論じた。氏の議論は功利主義の立場を極限まで首尾一貫することで結果的に「ひとを殺すこと」を一部容認するという一見過激な倫理的主張に至る。
氏のいう倫理の変更は人権思想とどういう連関にあるのか、人を殺してはならないという「生命の神聖性」が人権思想の核心だとすると、シンガー氏の主張は人権思想の廃棄に結びつくのではないか。この質問に氏は、理論と実践を注意深く分けて考察すべきという点、人権概念に限った主張ではないという点等に言及して答えた。人間と動物を差別する「種差別」を糾弾する氏の議論は、「意識」ある存在とそれ以外を差別する「意識差別」にならないか、との質問には、原理的問題とは別に、実践的感覚に基づく重要性が強調された。平日ながら立ち見も出る盛況ぶりに、「死生学」プロジェクトにとって極めて有意義な催しであったことが確信された。