ご挨拶
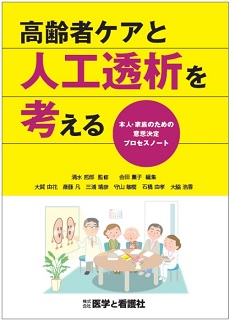 日本社会の超高齢化に伴い、透析療法を受ける患者さんも高齢化しています。患者さんは年齢にかかわらずご自身に合った適切な医療を受けていただくことが大切ですが、高齢の方の治療法の選択は、ご本人やご家族にとって、また、医療ケアスタッフにとっても、難しい場面が多々あります。
日本社会の超高齢化に伴い、透析療法を受ける患者さんも高齢化しています。患者さんは年齢にかかわらずご自身に合った適切な医療を受けていただくことが大切ですが、高齢の方の治療法の選択は、ご本人やご家族にとって、また、医療ケアスタッフにとっても、難しい場面が多々あります。
それは、高齢者の場合は、加齢に伴う生理的な変化によって、病気の医学的な意味や症状の表れ方、治療に対する反応などが若年者とは異なることが少なくないからです。また、複数の慢性疾患を有する方も少なくないため、数多くの薬剤を服用することによる問題を抱えておられる場合もあります。
さらに、これまでの長い人生の道のりのなかで、何を重視して人生を送ってこられたか、今後どのように生きていきたいかについて、その軸となる価値観や死生観がお一人おひとり異なっています。そのため、治療法の選択にはより慎重さが求められます。
透析療法の選択に関して日本透析医学会は2014年に、「維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」を発表し、透析療法の導入・継続・見合わせの方針決定に関しては、医療ケアチームと患者・家族がよく話し合い、ご本人の意思を大切に合意形成することを推奨しました。
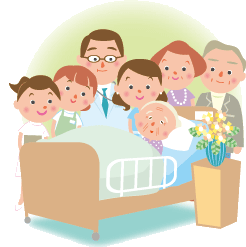 このようななか、私たち「腎臓病と高齢者ケア研究プロジェクト」は、慢性腎臓病の高齢者の本人らしさを尊重し、それぞれの人生における「幸せ」や「満足度」を重視して、これからの治療法の選択肢を選んでいくこと支援したいと考え、『高齢者ケアと人工透析を考える ― 本人・家族の意思決定プロセスノート』を、先行書である高齢者ケアと人工栄養を考える ― 本人・家族の意思決定プロセスノート』を参考に作成し、2016年6月に医学と看護社より刊行いたしました。
このようななか、私たち「腎臓病と高齢者ケア研究プロジェクト」は、慢性腎臓病の高齢者の本人らしさを尊重し、それぞれの人生における「幸せ」や「満足度」を重視して、これからの治療法の選択肢を選んでいくこと支援したいと考え、『高齢者ケアと人工透析を考える ― 本人・家族の意思決定プロセスノート』を、先行書である高齢者ケアと人工栄養を考える ― 本人・家族の意思決定プロセスノート』を参考に作成し、2016年6月に医学と看護社より刊行いたしました。
>> [書籍案内]
このノートは、どのような治療法の選択に至るか、その意思決定のプロセスを、ご本人とご家族が、医療ケアスタッフの助言を得ながら一歩一歩たどることを応援できたらという思いで作られています。
この意思決定プロセスノートの使用によって、ご本人にとって最善で、ご家族も納得できる治療の意思決定に至るお手伝いができれば幸いです。
2015年5月
腎臓病と高齢者ケア研究プロジェクト
- 著者
- 大賀由花 (山陽学園大学 看護学部)
- 斎藤 凡 (東京大学医学部附属病院 看護部)
- 三浦靖彦 (東京慈恵会医科大学附属柏病院 総合診療部診療部長)
- 守山敏樹 (大阪大学保健センター 教授)
- 石橋由孝 (日本赤十字社医療センター 腎臓内科部長)
- 大脇浩香 (岡山済生会総合病院 透析看護認定看護師)
- 会田薫子 (東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター上廣講座 特任准教授)
- 清水哲郎 (東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター上廣講座 特任教授)
『高齢者ケアと透析療法を考える ― 本人・家族のための意思決定プロセスノート』
目 次
- はじめに (p2)
- 腎臓の機能が低下したと言われたら・・・ (p4)
- 第1章 透析療法が必要と言われたとき考えたいこと (p6)
- ステップ1 どなたのことですか? (p8)
- ステップ2 ご本人の生き方、価値観、お人柄、生活状況について (p10)
- ステップ3 身体の状態と透析療法の医学的見込みと評価 (p14)
- ステップ4 何を目指しますか? (p18)
- ステップ5 透析療法を行うかどうか話し合いましょう (p22)
- ・選んだ後のケアの進め方 (p28)
- ・意思決定プロセスのまとめ(フローチャート) (p30)
- 第2章 腎臓の機能を保護するための生活と治療 (p31)
- 第3章 腎不全の治療選択について理解しましょう (p34)
- ① 血液透析療法(HD)(p36)
- ② 腹膜透析療法(PD)(p38)
- ③ 腎移植 (41)
- ④ 透析療法を行わない=自然にゆだねる (p42)
- 第4章 慢性腎臓病の方の人生の最終段階のケア (p44)
- ① 慢性腎臓病の終末期にみられる症状とケア (p45)
- ② 透析療法を終了するという選択肢 (p49)
- ③ 在宅での看取り (p50)
- ④ グリーフ・ケア (p51)
- 意思決定プロセスノート記入例 (p53)
ご連絡先: 臨床倫理プロジェクト
〒113-0033
東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文社会系研究科 死生学・応用倫理センター 上廣講座
e-mail :dalsjp[at]l.u-tokyo.ac.jp *[at]を@に入れ替えてお送りください。