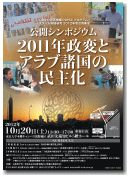| トップページ|研究会活動 | ||
公開シンポジウム「2011年政変とアラブ諸国の民主化」/ NIHUプログラム・イスラーム地域研究2012年度合同集会 立花優(北海道大学大学院博士後期課程) |
||
|
||
|
| 13:00 開場 13:30
|
 報告
報告
|
事例報告1では、鈴木恵美・早稲田大学イスラーム地域研究機構主任研究員から、上記(1)選挙とイスラーム政党について、エジプトにおける政変後の変化を中心とした報告が行われた。まず、エジプトにおけるイスラーム政党について、ムスリム同胞団を母体とする自由公正党と、サラフィー主義団体を母体とするヌール党や建設発展党などの「サラフィー主義政党」が存在しており、政変後に実施された選挙では、自由公正党が予想通り躍進し、サラフィー主義政党が予想外の健闘を見せた一方、政変の立役者であったリベラルを中心とする「革命青年潮流」は政党結成に失敗し、周辺化したことが指摘された。この背景には、イスラーム政党が貧困層に限定されない幅広い階層に支持基盤を持っており、組織的な有権者の動員が容易であることが指摘できるという。鈴木氏はエジプトにおけるイスラーム政党の現状について、経済政策やポスト配分、イスラーム法の位置付けなどで同胞団系の自由公正党とサラフィー主義政党との間に齟齬があること、一方でリベラルの間にある同胞団への不信感から、都市部を中心に二極化傾向が存在していること、同胞団系の大統領と軍部・治安機関との間に今後(水面下での)緊張が予想されることを指摘した。 「アラブの春」においては、イスラーム政党との関連で「トルコ・モデル」という言葉が頻出する。ここから、トルコ政治の専門家である澤江史子・東北大学准教授が鈴木報告に対しコメントした。澤江氏によれば、「トルコ・モデル」という言葉はソ連崩壊時、イラク戦争時、今回と3回登場しているが、過去2回と今回とでは、特に現地発の言及が出てきた点で異なるという。そして、中東アラブ諸国の世論で言われるモデルと現地イスラーム政党が言及するモデルとの違い、現地の大衆・イスラーム政党が言う「トルコ・モデル」とトルコでの実状との違いが論点として挙げられるとし、トルコ的イスラーム政党である公正と発展党について整理したうえで、エジプトにおいては、複数存在するイスラーム政党がどのような票(穏健的な層/急進的な層)を競うのかが注目されるとした。 事例報告2では,石黒大岳・九州大学大学院助教から、上記(2)の憲法改正に関連して、王制諸国の政治改革についてGCC諸国の事例報告が行われた。まず、GCC諸国が「アラブの春」をどうとらえたかについて、一連の流れが確認され、初期においては民衆側を支持していたが、GCC域内へ波及するに及び、利益分配で乗り切ろうとしたものの収拾がつかず、一定の政治改革が不可避となったことが指摘された。そのうえで、政治改革の中身について、制度変更を伴う対応(オマーン)、部分的な対応(サウジアラビア、UAE、カタール)、現状維持(バハレーン、クウェート)の3つに分けて説明がなされた。石黒氏によれば、オマーンを除いて対応の幅はわずかであったが、体制維持の方針は堅持しつつ参政権拡大・一定の立法権強化の方向性は示されたという。また、一連の動きへの対応として出てきた.GCC統合の強化については、経済統合から政治統合・域内共同安全保障への転換が模索されているが、サウジ主導への警戒もあるという。最後に、GCC諸国における政治改革の範囲については「体制側の決断次第」であるが、政治的変化は着実に起こっており、さらなる改革は不可避であるとの見解が示された。 石黒報告に対しては、GCC諸国と同じく王制諸国であるモロッコとの比較の観点から、中川恵・羽衣国際大学教授からコメントがなされた。中川氏は、GCC諸国とモロッコで、アラブの春に対する国民の対応に違いが出た背景として、(1)さまざまな民主化改革へのこれまでの取り組み、(2)王権の制限についての体制側の対応、の2点があると指摘する。(1)については、前国王末期までの政治経済不安の後、政治的妥協を含む様々な改革が90年代から進展し、「体制側の決断」が行われたという。また(2)については、「アラブの春」を受けたモロッコでのデモの中で、議会に対する王権縮小を含む憲法改正案が包括的改革として国王の主導で提出、成立した。このように、モロッコにおいては、改革は国王主導であり、国民からの改革要求によるものではないことが特徴であるが、その方向性としては王権を制限する方向であり、GCC諸国とは異なっていると指摘した。 最後の総合ディスカッションでは、報告全体を総括する形で、1979年に革命を経験したイランを専門とする坂梨祥・日本エネルギー経済研究所主任研究員からコメントが寄せられた。「アラブの春」において、イランは政治変動の「イラン・モデル」として言及されることはなかった。坂梨氏はイランでの革命との違いとして、イランでは(1)革命後に「法学者の統治」論に基づく政治体制が形成されたこと、(2)当時は体制かイスラームかという二者択一であり、イスラーム政党の多様性が低かったこと、(3)対外関係が、限定的自由化の定着・発展を阻むような方向で働いたこと、を指摘した。 質疑応答では,「アラブの春」において、イスラーム政治思想の点から見て注目すべき動き(ポスト・イスラーム主義など)があるのか、といった大きな質問から、イスラーム政党の経済政策や、旧与党の影響力復活の可能性、GCC諸国におけるデモ参加者の要求といった具体的な内容まで多岐にわたる質問が寄せられたことが、司会の飯塚正人・東京外国語大学教授から紹介された。 筆者はアゼルバイジャンを中心として旧ソ連地域の現代政治を研究しているが、「アラブの春」はアゼルバイジャンにおいても類似の抗議行動を誘発するなど、大きな影響を与えている。また、ソ連崩壊に伴う体制移行との比較も可能であろう。その点で、体制の行方に少なからず影響を与えるであろう旧エリート層の動向についてより詳しく知りたいと感じた。 |