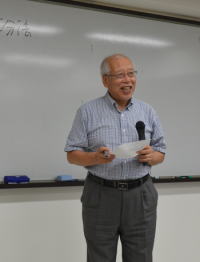| トップページ|研究会活動 | |||||
| 「板垣雄三先生公開インタビュー」第2回:モダニティをめぐって――世界史の書き換え報告 阿久津正幸(イスラーム地域研究東京大学拠点・特任研究員) |
|||||
|
| NIHUプログラム・イスラーム地域研究東京大学拠点 「中東イスラーム研究の先達者たち」プロジェクト
|
 趣旨・事前配付資料
趣旨・事前配付資料
| 昨年度、「中東イスラーム研究の先達者たちNo.2」として、イスラーム地域研究東京大学拠点より『板垣雄三先生インタビューVol.1』が出版されました。第1集に引き続き,中東・地域研究に留まらず広く歴史学研究をリードし続ける、先生の貴重な体験を語っていただきます。特に今回は、研究者がいま問われていることについて、先生自らの体験を通じて、広く次の世代に問いかけていただく予定です。公開インタビューへ多数のご参加をいただいて、今後の第2集の編集に弾みをつけたいと思います。 |
 事前配布資料
事前配布資料
 報告
報告
近代を主題とした著作は意図的に書いてこなかった.しかし西暦7世紀,つまりイスラーム時代以降を近代とみなす考え方は,これまでずっと主張してきた……中心としての西欧近代,その傍流のなかの一つとしてのイスラームがあり,前者に対して後者がどう抵抗し対抗するか,といった枠組みを問題視することから出発している……現状の社会科学を根底から突き崩さねばならないだろう……. (ユダヤ教徒ではなく)ユダヤ人の問題から,西欧史の深層とパレスチナ問題を考えてきた……現状における「ヨーロッパの中心性」は,作為的な仕掛けによるもの……それに基づいたヨーロッパ近代という概念に与することはできない……自ら完結できない,他に依存して初めて成立できるヨーロッパ史……現実を無視して自らをスタンダードとしてみなしていく「盗み」の論理……こうした見解を支えてしまっている,われわれ研究者たちが属する知識人社会のなかのゆがみ……. たとえば中国史研究者は,中華イデオロギーと戦わなければならない.中国史のなかのムスリムを研究する場合,それに配慮をした形で,ムスリムを「回儒」と呼んできたが,むしろ逆に,イスラームによって中国やその文化がどのような影響を受けてきたのかに目を向けなければならない……. ヨーロッパ中心主義に挑むために,現在のアラブ中東地域に広がった革命の波を,「アラブの春」として一括せず,アラビア語のムワーティンmuwatin(住民,市民,国民という原義)というルビをつけた市民革命と定義する……この動きは,チュニジアから突発的に広がったものではなく,先行するパレスチナ地域における抵抗運動から,連続的に把握しなければならない……この観点によると2011年は,新しい世界史的枠組みにとっての重要な転換点であり,超近代(ハイパー・モダニティ)の到来が予見される……. 中国,インド,イスラーム……あらゆる文明は普遍性をもち,かつそれを支える自前の近代性をもつ.こうした状況から,今後当事者であるムスリムがどう対処をしていくのか……そもそも人類の歴史が永続するという前提こそが誤りではないか……. 過去,アラビア語世界を通じて,人類史の遺産ともいうべき科学知識が継承され,翻訳によってヨーロッパに再生されたという形式面については,日本では思いのほか認識されている.そのため今後必要なことは,先進科学を輸入した当時のヨーロッパ・キリスト教は,おそらく知的好奇心に満ちてアラビア語書籍を熱狂的に探求したこと,そうした啓発がたとえばヨハンネス・ドゥンス・スコトゥスなど著名な知識人にどのような影響を与えたのか,ヨーロッパ側の自前の論理と同時にイスラーム世界からの影響がどう結びついているのか,踏み込んで研究していくべきではないだろうか……多様性と統一性について,示唆的な見解をもつと評価されているアントニオ・ネグリの論なども,彼の論旨とは別な次元で,つまり7世紀近代という欧米中心主義を脱した観点からの説明がそもそも可能なのである……. 午前から開始したインタビューだったが,夕方になっても終わりが見えない.それは,われわれ研究者に課された課題が計り知れないというだけではない.その重い課題を,長い体験と研究生活を通じて,われわれに伝えようとしてくれた板垣先生の姿勢ゆえだろう. さて,いったいどうやってこのインタビューを文字化しようか.大きな大きな,本当に大きな宿題を背負ってしまったようだ. |