|
| トップページ|ニュース |
| 2009年度のニュース一覧 |
|
|
|
|
|
 2010年3月 2010年3月
|
|
 2010年1月 2010年1月
北海道中央ユーラシア研究会は、北海道大学スラブ研究センターにおいて、科学研究費基盤B「近代化とグローバル化の文脈における比較帝国史」共催で下記の要領で第84回例会を開催いたします。
- 題目:「イチャン・カラ博物館蔵 3894 文書の研究: 帝政末期ロシア=ヒヴァ・ハン国間関係の一断面」
- 報告者:塩谷哲史(筑波大学大学院人文社会科学研究科準研究員)
- 討論者1:守川知子(北海道大学文学研究科准教授)
- 討論者2:秋山徹 (北海道大学大学院文学研究科博士課程)
- 日時:2010年2月27日(土) 15:00―
- 場所:スラブ研究センター棟4階小会議室401
ご多忙とは存じますが、どうかふるってご参加くださいますようご案内申し上げます。なお,事前にレジュメをご希望の方は、連絡係までご一報ください。
併せてご案内申し上げます。当研究会ホームページでは各例会後に報告書を掲載しております。この他、会員の調査地滞在記も公開しておりますので、ぜひご覧ください。
研究会ホームページ:http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/casia/index.html
北海道中央ユーラシア研究会事務局 須田将
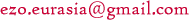
北海道中央ユーラシア研究会は、北海道大学スラブ研究センターにおいて、下記の要領で第83回例会を開催いたします。
ご多忙とは存じますが、どうかふるってご参加くださいますようご案内申し上げます。
なお,事前にレジュメをご希望の方は、連絡係までご一報ください。
研究会ホームページ:http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/casia/index.html
北海道中央ユーラシア研究会事務局 須田将
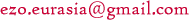
シンポジウム「シーア派社会と聖地・聖廟――歴史学の視点から」を、北海道大学にて下記のとおり開催いたします。遠方ではありますが、ご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
「シーア派社会と聖地・聖廟――歴史学の視点から」
【日時】 2010年1月30日(土) 10:00〜18:00
【場所】 北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟(W棟)309室
【プログラム】
10:00〜10:15
10:30〜11:30
- 基調講演:山岸 智子(明治大学)「シーア派の社会と宗教実践<概要>」
13:00〜13:50
- 守川知子(北海道大学)「ペルシア語旅行記にみるイマーム廟とイラン社会」
13:50〜14:40
- 木村暁(日本学術振興会特別研究員)「マンギト朝期ブハラにおけるシーア派コミュニティーの顕在化」
14:50〜15:40
- 杉山隆一(慶應義塾大学大学院)「18世紀におけるイマーム・レザー廟」
15:40〜16:30
- 近藤信彰(東京外国語大学)「シャー・アブドル=アズィーム廟の歴史とワクフ」
16:40〜17:00
17:00〜18:00
主催:北海道大学大学院文学研究科
共催:NIHUプログラム・イスラーム地域研究・東大拠点「中東社会史班」
*参加は無料です。また終了後には懇親会を予定しています。
問い合わせ先:守川知子 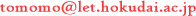 |
|
|
 2009年12月 2009年12月
2010年の1月23日から24日にかけて、国際ワークショップ「イスラームと帝国:思想、教育、移動性の複雑な連結」を下記の通り開催いたします。
参加をご希望の場合は、準備の関係もありますので、本研究集会の事務を担当しております大阪大学の渡辺までお知らせください。その際に、懇親会の出欠もお知らせいただければと存じます。
- 連絡先アドレス:dai5han■world-lang.osaka-u.ac.jp
(*迷惑メール防止のため@を■で表示しています)
本ワークショップの趣旨・プログラムにつきましては、下記のURLをご参照ください。
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/rp/group_04/activities/index.html#20100123
遠方ではありますが、ご参加いただけますようよろしくお願い申し上げます。
長縄宣博(北海道大学スラブ研究センター)
新学術領域研究第5班・第4班合同中規模国際集会
「イスラームと帝国:思想、教育、移動性の複雑な連結」
- 日時:2010年1月23日(土)、24日(日)
- 場所:千里ライフサイエンスセンター701号室
- 主催:新学術領域研究「ユーラシア地域大国の比較研究」
- 共催:大阪大学世界言語研究センター、北海道大学スラブ研究センター
【プログラム】
1月23日(土)
14:00-14:10 開会の辞
14:10-16:00 セッション1:われらの祖国はどこか
- 司会:古谷大輔(大阪大学)
- 報告者:
- モイヌッディン・アキール(国際イスラーム大学、パキスタン)
「戦争の家」と「イスラームの家」:英領インドにおける概念と対立
- 中田考(同志社大学)
「カリフ制」の概念:世界中に法の支配を広める
- 討論者:山根聡(大阪大学)
16:30-18:20 セッション2:イスラームの家と祖国の間での教育改革
- 司会:松里公孝(北海道大学)
- 報告者:
- 松本ますみ(敬和学園大学)
近代中国のイスラーム復興:ナショナリズム、教育、改革
- ムスタファ・トゥナ(デューク大学、米国)
世俗化としてのマドラサ改革:ロシア帝国からの視点
- 討論者:長縄宣博(北海道大学)
1月24日(日)
10:00-11:50 セッション 3:拡張する帝国とムスリムの移動性の限界
- 司会:守川知子(北海道大学)
- 報告者:
- ジェームズ・マイヤー(モンタナ州立大学、米国)
移動する人々と疑わしい臣民:ロシア・ムスリム、旅、オスマン帝国
- 桜井啓子(早稲田大学)
コムをシーア派世界の中心にする:イラン・イスラーム革命後のイスラーム教育ネットワークの再編
- 討論者:宇山智彦(北海道大学)
11:50-12:00 閉会の辞
北海道中央ユーラシア研究会は、北海道大学スラブ研究センターにおいて、下記の要領で第83回例会を開催いたします。
ご多忙とは存じますが、どうかふるってご参加くださいますようご案内申し上げます。
なお,事前にレジュメをご希望の方は、連絡係までご一報ください。
研究会ホームページ:http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/casia/index.html
北海道中央ユーラシア研究会事務局 須田将
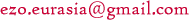
北海道中央ユーラシア研究会は、北海道大学スラブ研究センターにおいて、
ご多忙とは存じますが、どうかふるってご参加くださいますようご案内申し上げます。
なお,事前にレジュメをご希望の方は、連絡係までご一報ください。
研究会ホームページ:http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/casia/index.html
北海道中央ユーラシア研究会事務局 須田将
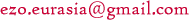 |
|
|
 2009年11月 2009年11月
|
|
 2009年10月 2009年10月
中国ムスリム研究会では、2009年12月13日(日)に中国ムスリム研究会第18回定例会を開催することとなりました。今回は、Jomo
Smithさん(University of California, San Diego)、小嶋祐輔さん(慶應義塾大学)、白井千彰さん(和光保育園)に日頃の研究成果をご報告いただきます。お忙しいとは存じますが、多数のご参加を心待ちにしております。ところで、今回の定例会は学習院大学東洋文化研究所との共催となり、同研究所のご好意により、「旧東亜経済調査局所蔵回教関連資料」を閲覧させていただけることになりました。こちらの貴重な資料につきましては休憩時間の時にご閲覧ください。
なお、準備作業の関係上、参加人数を事前に確認する必要がございます。大変恐縮ではございますが、参加ご希望の方は12月4日(金)までに当事務局のメールアドレスにご連絡ください。また、その際、懇親会への出欠に関しましてもお書き添えいただけましたら幸いに存じます。(中国ムスリム研究会事務局2009年度幹事:澤井充生(首都大学東京・助教)・田中周(早稲田大学大学院博士課程)
- 中国ムスリム研究会事務局
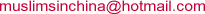
中国ムスリム研究会第18回定例会
プログラム
12:30〜12:40 事務局挨拶
12:40〜13:25 発表1
- 発表者:Jomo Smith(University of California, San Diego, Ph.D. Student)
- テーマ:「Contending for the Faith: Imperialists, Insults, and the Broadening of Hui Identity in Republican China」*通訳:松本ますみ(敬和学園大学)
13:25〜14:10 質疑応答
14:10〜14:40 休憩
- 同館4階の東洋文化研究所会議室において「旧東亜経済調査局所蔵回教関連資料」を展示、閲覧自由
14:40〜15:25 発表2
- 発表者:小嶋祐輔(慶應義塾大学非常勤講師)
- テーマ:「ウルムチの<翻訳者>たちから見るエスニック・バウンダリ」
15:25〜16:10 質疑応答
16:10〜16:20 休憩
16:20〜17:05 発表3
- 発表者:白井千彰(和光保育園)
- テーマ: 「マレーシアのクチンとトレンガヌの鄭和廟を訪れて」
17:05〜17:50 質疑応答
懇親会:定例会終了後、会場近くで懇親会を開く予定です。その他、ご不明な点につきましては、中国ムスリム研究会事務局までお問合わせください。 |
|
|
 2009年8月 2009年8月
北海道中央ユーラシア研究会は、北海道大学スラブ研究センターにおいて、下記の要領で第80回例会を開催します。
ご多忙とは存じますが、どうかふるってご参加くださいますようご案内申し上げます。なお,事前にレジュメをご希望の方は、連絡係までご一報ください。
また、第79回例会の報告書(報告要旨:小田桐奈美著+参加記:井上岳彦著)を当会ホームページに掲載しました。ぜひご一読くださいますよう、お願い申し上げます。
北海道中央ユーラシア研究会事務局 須田将
-
e-mail:
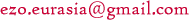
Conference announcement
It is our pleasure to announce you the holding of the International Conference
‘Turko-Mongol Rulers, Cities and City-Life in Iran and the Neighboring
Countries’ at the Institute of Oriental Culture, University of Tokyo on
12th-13th September 2009.
This conference aims to investigate the various types of relationship that
the Turko-Mongol rulers had with cities and city life by bringing together
specialists in various periods and of various disciplines (history, archaeology,
history of art). Contributions will deal primarily with Iran (in its broader
sense) but also Central Asia, Anatolia and the Arab World.
Scholars and students in the field are welcome to attend the conference.
For a presentation of the scientific goals of the conference, a complete
list of abstracts of the papers and the registration form, please visit
the conference site: http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/news/news0909symp.html (For technical reasons, the program, abstracts of the papers, and the registration
form will only be posted at this website on Aug. 21. Please visit the temporary
satellite website of the conference for the time being for downloading
relevant files:
http://homepage3.nifty.com/morikazu/Turko-MongolTemporary.html.
This conference is organized jointly by the Institute of Oriental Culture
(Univ. of Tokyo), the Sonderforschungsbereich ‘Differenz und Integration’(Univ.
Halle & Leipzig), the NIHU Program IAS Center (Univ. of Tokyo), with
the financial support of the Japan Society for the Promotion of Science
(Japan-Germany Research Cooperative Program).
David Durand-Gue'dy (for the organizing committee)
email: david_durandguedy[@]ioc.u-tokyo.ac.jp
I. PROGRAM
September 12
09:30-10:00 Registration
10:00-10:30 Welcome, presentation, keynote address
10:30-12:30: Panel 1: Early Turkish Dynasties (with a 20 mn break after
the first paper)
- Chair: M. Haneda (Tokyo)
- P. Golden (Rutgers): ‘Proto-Urban and Urban Developments among the Pre-Chinggisid
Turkic Peoples’
- M. Inaba (Kyoto): ‘Sedentary Rulers on the Move: Travels of the Early
Ghaznavid Rulers and their Capital’
- Y. Karev (Halle): ‘The Royal Court of the Western Qarakhanids in the Capital
City of Samarqand’
12:30-14:00 Lunch break
14:00-15:10: Panel 2: The Saljuqs
- Chair: K. Shimizu (Kyushu)
- D. Durand-Gue'dy (Tokyo): ‘The Tents of the Saljuqs’
- A. Peacock (Ankara): ‘Courts and Cities in Saljuq Anatolia’
15:10-15:40 Coffee break
15:40-17:25: Panel 3: The Mongols and the Mamlu-ks
- Chair: D. Matsui (Hirosaki)M. Biran (Jerusalem): ‘Rulers and City’s Life
in Mongol Central Asia (1220-1370)’
- T. Masuya (Tokyo): ‘Capitals and Seasonal Palaces: Cities under the Great
Khans and the Ilkhans’
- K. Franz (Halle): ‘The Castle and the Country: Turkish Urban-Centred Rule
from the Ayyu-bids to the Mamlu-ks’
18:30 Reception (Restaurant in Hongo area)
September 13
09:45-10:55: Panel 4: The Timurids and Turkomans
- Chair: H. Mashita (Kobe)
- Ch. Melville (Cambridge): ‘The Itineraries of Shahrukh b. Timur
- (1405-1447)’
- M. Subtelny (Toronto): ‘Between City and Steppe: Gardens as Loci of
- Political Rule under the Timurids’
11:25-12:35: Panel 4 (part 2)
- Chair: Y. Goto (Kwansei Gakuin)
- Cl.-P. Haase (Berlin): ‘Dynastic Mausolea of the Timurids and their Ornaments:
Propaganda and Memorial’
- J. Paul (Halle): ‘A Landscape of Fortresses: Eastern Anatolia in Astara-ba-di-’s
Bazm wa Razm’
12:35-14:00 Lunch break
14:00-15:10: Panel 6: Later Dynasties
- Chair: H. Komatsu (Tokyo)
- N. Kondo (Tokyo): ‘The Last Qizilbash? The Early Qajar Rulers and their
Capital Tehran’
- J. Noda (Tokyo): ‘Turkistan as the Capital of the “Kazakh Khanate” in
the 16-19 Centuries’
15:10-15:40 Coffee break
15:40-16:50: Concluding Panel
- Chair: K. Morimoto (Tokyo)
- General response: M. Hamada (Kyoto)
- General discussion
- Concluding address (D. Durand-Gue'dy)
|
|
|
 2009年7月 2009年7月
北海道中央ユーラシア研究会は、北海道大学スラブ研究センターにおいて、下記の要領で第79回例会を開催します。
-
題目:キルギス(クルグズ)共和国における国家語政策―言語・民族・国民をめぐる言説を中心として―
-
報告者:小田桐奈美(筑波大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程)
-
討論者:野町素己(北海道大学スラブ研究センター准教授)
ご多忙とは存じますが、ふるってご参加くださいますようご案内申し上げます。なお,事前にレジュメをご希望の方は、連絡係までご一報ください。
北海道中央ユーラシア研究会事務局 須田将
|
|
|
 2009年6月 2009年6月
新疆社会科学院の主催による国際学会「歴史上における新疆と中央アジア」のご案内が届いております。会期は本年10月12-14日、場所は新疆ウルムチ市、参加希望者は主催者側にメールかファックスで直接連絡をとればいいようです。詳しくは下記のご案内をご覧ください。(学習院大学・小沼孝博)
*国際会議「歴史上における新疆と中央アジア」の案内(中国語・英語)
I am glad to be able to circulate the first announcement of the International
Conference: Turko-Mongol Rulers, City and City-Life in Iran and the Neighboring
Countries, scheduled to be held at Tobunken on September 12-13, 2009. For
the details of this conference, please visit
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/news/news0909symp.html
The website still does not present the program. The instruction for registration
is also to be posted in due course. Thank you very much for your attention
and interest.
Kazuo MORIMOTO, Ph.D.
Associate Professor of Islamic and Iranian History,
Institute of Oriental Culture, University of Tokyo
*Please visit the website of the sister conference on sayyid/sharifs to
be held on September 22-23, too:
http://133.9.117.42/article/wias/event/g1/20090922-23/announce_en/ .
この度、国問研は、アゼルバイジャン共和国メメディヤロフ外務大臣をお招きしてJIIAフォーラムを以下の要領で開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。ご多忙とは存じますが、ご出席賜りましたら幸いでございます。出席をご希望の方は6月15日(月)までに添付ご案内文書にご記入の上ご返信いただけますと幸いです。また6月15日(月)までに、国問研・道上  まで「御芳名、御所属、御役職、御連絡先(電話・FAX,e-mail)」を日本語と英語の両方でご返信いただいても結構でございます。 まで「御芳名、御所属、御役職、御連絡先(電話・FAX,e-mail)」を日本語と英語の両方でご返信いただいても結構でございます。
- 日時:6月18日(木)15:00-16:30
- 場所:ホテルオークラ別館12階 ケンジントン テラス(東京都港区虎ノ門2-10-4)
- 講演者:エルマル・メメディヤロフ アゼルバイジャン共和国外務大臣(Dr. Elmar
MAMMADYAROV, Foreign Minister of the Republic of Azerbaijan)
- テーマ:「東西文明の交差点・アゼルバイジャン:地域の安全保障と反映における同国の役割
- 司会:野上義二 当研究所理事長
- 言語:英語
詳細、参加申し込みは添付ファイルのとおりとなっております。何かご不明の点がございましたら、遠慮なく、担当の道上までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。(財団法人 日本国際問題研究所・道上真有)
北海道中央ユーラシア研究会は、北海道大学スラブ研究センターにおいて、下記の要領で第78
回例会を開催します。
ご関心のある方々の一人でも多くのご参加をぜひたまわりたく存じます。なお,事前にレジュメを希望する方は連絡係までご一報ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
北海道中央ユーラシア研究会事務局 須田将
この度、平成20年度・大学院教育改革支援プログラムに奈良女子大学の「女性の高度な職業能力を開発する実践的教育」が採択されました。その支援事業の一環として、下記内容のように大学院生による自主企画セミナー「シルクロードのひとびとpart4−みる・きく・まなぶ 沙漠の文化」を開催する運びとなりました。当セミナーは、院生の自研究に役立つだけではなく、当学内外からの研究者や院生の発表のほか、ビジネスや商売上でシルクロードの地域に携わる方々にも毎年ご講演いただき、研究者・一般の方々とともに、理解と親睦を深めようという主旨で行っております。4回目となります今回は、発表とともに当地域の名産である絨毯の歴史とともに実際の絨毯展示、シルクロード民族音楽の実演といった、一般の方にも気軽に参加できる内容のものです。
さらに、講演終了後、参加者の皆様と親睦・交流を深める目的で懇親会を行い、当日は「満足度全国2位」の当大学生協の料理とともに、今回は特別に日本ではあまり食す機会の少ないウイグル料理も何品か用意させていただく予定です。 奈良は間もなく遷都1300年を迎えます。より奈良という都市を活気づけ、シルクロードの終着地である当大学院からも研究や情報を発信し、本大学院生もより広く奈良を呼びかけて行きたい所存でおりますので、何卒足をお運び頂けますようお願い申し上げます。(鷲尾惟子・奈良女子大学大学院)
「シルクロードのひとびとpart4−みる・きく・まなぶ 沙漠の文化」
【内容】
中国西北部に位置する新疆ウイグル自治区はシルクロードの要衝として一般的に認知されている一方で、実際にその地域に居住している人々の生活や文化に関しては、これまで深く掘り下げられていないのが現状です。そこで本セミナーでは生きるひとびとのくらしをテーマとして、多角的な視点から理解することを目的とし、特に今回は暮らしの中に織り込まれる「文化」、中でも当地の暮らしに欠かすことができない絨毯と音楽を通してみていきたいと思います。また、絨毯の展示や民族音楽の実演もとり行います。
【話題提供者】
- 杉山徳太郎(株式会社スガハラ代表取締役)「ホータン絨毯の歴史的プロセスとその変容(仮題)」
- アブドシュクル・アブドラフマン(金沢大学文学部 博士研究員)−ラワープ演奏「ウイグル伝統音楽における音程変化の移行パターン」
- アブドセミ・アブドラフマン (東京芸術大学芸術学部楽理科 助手)「 ウイグルの音楽文化におけるドーラン・ムカームの研究(仮題)」
- 鷲尾 惟子(奈良女子大学大学院社会生活環境学専攻 博士後期課程3年)−ダップ・ピアノ演奏「民間歌曲
『アトシュガバルゴンチェ』に見られる変容」
【日時】 7月11日(土)
- 13:00〜17:00 セミナー発表
- 18:00〜 懇親会 奈良女子大学生協食堂(学生会館1階)
【ところ】
- 奈良女子大学・大集会室(学生会館2階)
- 近鉄奈良駅下車東側出口から北へ徒歩5分
【定員】
- 約40名 セミナー参加無料/懇親会お一人4000円(当日懇親会のみ参加の方は5000円)
【お申し込み方法】
当日の座席準備、資料準備および懇親会参加確認の都合上、あらかじめお葉書、E-MAIL、お電話のいずれかで、下記の連絡先までお申し込み下さい。
※お申し込みの際には、下記の内容をお知らせ下さい。
- ・セミナーと懇親会両方参加 ・セミナーのみ参加 ・懇親会のみ参加
- お名前と参加される人数
- プライバシーは厳守させて頂き、強制はいたしませんが、開催後のお忘れ物や今後の開催通知連絡のために、ご連絡先をお尋ねさせて頂く場合がございます
【お申し込み締め切り】
定員になり次第締め切りますが、若干お席が空いております場合は、当日お申し込み参加も可能です。ご遠慮なくお尋ね下さい。
【お問い合わせ・お申し込み先】
- 古澤文(ふるさわふみ)

- 鷲尾惟子(わしお ゆいこ)
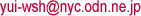
- 住所:〒630-8301 奈良市高畑町1215-5 鷲尾惟子宛て
【後援・協賛】
北海道中央ユーラシア研究会は、北海道大学スラブ研究センターにおいて、下記の要領で第77回例会を開催します。
- 題目:ポスト・ソヴィエト諸国における選挙不正と権威主義体制の命運:カザフスタンとキルギスの比較分析
- 報告者:東島雅昌(早稲田大学政治学研究科博士課程 日本学術振興会特別研究員)
- 討論者:
- 大串敦(北海道大学スラブ研究センター 学振特別研究員)
- 藤森信吉(北海道大学スラブ研究センター COE共同研究員)
ご関心のある方々の一人でも多くのご参加をぜひたまわりたく存じます。なお,事前にレジュメを希望する方は連絡係までご一報ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
北海道中央ユーラシア研究会事務局 須田将
|
|
|
 2009年5月 2009年5月
Workshop on Comparative Colonial History: Focus on India and Central Asia
新学術領域研究「ユーラシア地域大国の比較研究」第4班(比較帝国史)では、下記の要領でワークショップを開催します。
Workshop on Comparative Colonial History: Focus on India and Central Asia
- 日時:2009年6月2日(火)15時〜19時
- 場所:東京大学駒場キャンパス14号館2階208号室
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/access/img/map.pdf
- 報告1:Brian Roger (Tom) Tomlinson (SOAS, University of London)
From the Colonial to the Global: India and the International System in
the 20th Century
- 報告2:Alexander Morrison (University of Liverpool)
Kazakhs Behaving Badly? N. S. Lykoshin and the Aftermath of the Andijan
Uprising
トムリンソン氏はインド経済史・イギリス帝国史の代表的な専門家です。モリソン氏は、話題作Russian
Rule in Samarkand (Oxford, 2008)で英領インドとの比較の視点から露領中央アジアの近代史を論じた、新進気鋭の研究者です。ショートノーティスになってしまいましたが、どうかふるってご参加ください。(北海道大学スラブ研究センター・宇山智彦)
今般、トルクメニスタン外務省より口上書をもって2件の国際学術会議の応募勧奨依頼がございましたので、別添ファイルにて案内書を送付させていただきます。
- 国際学術会議「古代ジェイトゥン:初期農耕の中心地」(9月15-16日)
(国立文化センター「ミラス」、トルクメニスタン文化・テレビ・ラジオ報道省、閣僚会議付属歴史学研究所の共催)
→案内書
- 国際学術会議「叙事詩「ギョログルィ」と東洋文学」(9月23-25日)
(国立文化センター「ミラス」主催、アシガバットとダショグズで実施)
→案内書
ご関心のある方は、直接、組織委員会と連絡を取っていただけますと幸いです。以上、よろしくお願いいたします。(在トルクメニスタン大使館専門調査員・地田徹朗)
下記の要領で、第5回の研究会を開催いたします。本研究会は、中央アジアにおける前近代からソ連期にいたる法制度の変遷をテーマに、イスラーム法、ロシア・ソ連法の研究者が参加して、文字通り学際的で稔りある会になることを願って開催するものです。今回は、科研費による「文書史料による近代中央アジアのイスラーム社会史研究」、及び、イスラーム地域研究東洋文庫拠点の研究プロジェクトの一環として研究会を企画しています。関心をお持ちの方には奮って御参加いただきたく、ご案内申し上げます。(京都外国語大学・堀川徹)
【プログラム】
13:00〜13:10
13:10〜14:40
- イスラーム的土地保有とその影響―エジプト,シリア,レバノン (堀井聡江〔桜美林大学〕)
14:40〜15:00
15:00〜16:30
- 近代中央アジアのイスラーム法廷資料(矢島洋一〔京都外国語大学〕)
16:30〜17:30
【連絡先】
京都外国語大学 国際言語平和研究所 堀川徹
e-mail: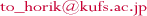
〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6
Tel. 075-322-6055 Fax 075-322-6245
*不明な点がございましたら、上記までお問い合わせ願います。 |
|
|
 2009年4月 2009年4月
2009年3月にとマルテペ大学および筑波大学との共催により、国際会議のINTERNATIONAL CONFERENCE
ON CENTRAL EURASIAN STUDIES: Past, Present and Futureが開催されました。この会議においては、当拠点の研究分担者であるティムール・ダダバエフや、現地協力者であるグルジャナット・クルマンガリエヴァにより、「ソ連時代の記憶プロジェクト」の最新の研究成果が発表されました。
【会議概要】
- 日時:2009年3月17日(9:30-18:00)・18日(9:30-19:00)
- 場所:マルテペ大学マルマ・コングレ・ホテル会議場(トルコ共和国、イスタンブル)
- 共催:マルテペ大学、イスラーム地域研究東京大学拠点、筑波大学
- プログラム(ワードファイル)
会議に関する報告は下記をご参照ください。
2009年6月27日(土)に中国ムスリム研究会第17回定例会を開催することとなりました。今回は、松本和久さん(早稲田大学大学院)、今中崇文さん(総合研究大学院大学)、佐藤航さん(神戸大学大学院)に日頃の研究成果をご報告いただきます。お忙しいとは存じますが、多数のご参加を心待ちにしております。
なお、準備作業の関係上、参加人数を事前に確認する必要がございます。大変恐縮ではございますが、参加ご希望の方は6月6日(土)までに当事務局のメールアドレス 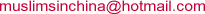 にご連絡ください。また、その際、懇親会への出欠に関しましてもお書き添えいただけましたら幸いに存じます。何卒よろしくお願い致します。 にご連絡ください。また、その際、懇親会への出欠に関しましてもお書き添えいただけましたら幸いに存じます。何卒よろしくお願い致します。
(中国ムスリム研究会事務局2009年度幹事:澤井充生 首都大学東京・助教、田中周 早稲田大学大学院博士課程)
研究発表
- 13:00〜13:15 事務局挨拶
- 13:15〜14:00
- 発表1:松本和久(早稲田大学大学院博士課程)「新疆への漢族進出と生産建設兵団――解放軍主導の辺境開発」(仮題)
- 14:00〜14:45 質疑応答
- 14:45〜15:00 休憩
- 15:00〜15:45
- 発表2:今中崇文(総合研究大学大学院博士課程)「地域と国家の間に立つアホンたち――西安・化覚巷清真大寺の事例から」(仮題)
- 15:45〜16:30 質疑応答
- 16:45〜17:00 休憩
- 17:00〜17:45
- 発表3:佐藤 航(神戸大学大学院修士課程修了)「香港のムスリムと中華回教博愛社」(仮題)
- 17:45〜18:30 質疑応答
懇親会:定例会終了後、会場近くで懇親会を開く予定です。
その他、ご不明な点につきましては、中国ムスリム研究会事務局までお問合わせください。
アフガニスタンを舞台にした映画『子供の情景』が4月18日(土)より公開されています。ご関心のある方は、公式サイトをご覧いただけますようお願い申し上げます。(徳永愛子/ムヴィオラ)
公式サイト:
http://kodomo.cinemacafe.net
以下、映画の紹介です。
戦争が長く続くこの国で、子供たちは何を見てきたのだろう。19歳の少女監督、ハナ・マフマルバフは、テレビのニュースでは流れない、「子供の情景」を映画にしました。
破壊された仏像がいまも瓦礫となって残るバーミヤン。「どうしても学校に行きたい」「どうしても字を読みたい」と願う6歳の少女バクタイはノートを買うお金を得るため、街に出て卵を売ろうとする。四苦八苦の末、何とかバクタイはノートを手に入れるが、学校に行く途中で、少年達に取り囲まれてしまう。そして少年たちは、タリバンを真似た戦争ごっこでバクタイを怖がらせる・・・・・・。
監督は、イラン映画界の新星ハナ・マフマルバフ。ひとりの少女の小さな冒険を通して、戦争が子供に与える影響の重大さを寓話的に描きました。
今般、当国外務省よりトルクメニスタン国立文化センター「ミラス」よりの、「トルクメニスタン−世界の旅行者のまなざし」と題する国際学術会議の案内をいただきました。ちょっとしたレジュメの提出を4月10日までに求められております。ご関心のある方は、直接組織委員会に連絡をとっていただきますようお願い申し上げます。
今後ともこのようなトルクメニスタン史に関連するコンファレンス等の案内をさせていただきます。よろしくお願いいたします。(在トルクメニスタン大使館専門調査員 地田徹朗)
会議案内(PDFファイル) |
|
|
|
|
|
|
| Page top |
|
|
 2010年1月
2010年1月 2009年12月
2009年12月 2009年11月
2009年11月 2009年10月
2009年10月 2009年8月
2009年8月 2009年7月
2009年7月 2009年6月
2009年6月 2009年5月
2009年5月 2009年4月
2009年4月
 国際学術会議「トルクメニスタン−世界の旅行者のまなざし」の案内
国際学術会議「トルクメニスタン−世界の旅行者のまなざし」の案内