| 日時 | 2006年10月14日(土)14:00~17:30 |
| 場所 | 東京大学医学部教育研究棟2階
第1・第2セミナー室 |
| 主催 | DALS(東京大学21世紀COE
「生命の文化・価値をめぐる死生学の構築」) |
| パネリスト | 副田義也教授 (金城学院大学)
大岡頼光助教授 (中央大学)
中筋由紀子助教授 (愛知教育大学) |
| コメンテータ | 佐藤健二教授 (東京大学) |
| 司会 | 武川正吾教授* (東京大学) |
|
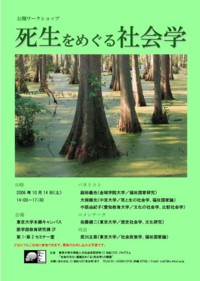 |
*事業推進担当者
去る2006年10月14日(土)午後2時~午後5時半、東京大学医学部教育研究棟2回第1第2セミナー室にて、DALS(東京大学21世紀COE「生命の文化・価値をめぐる死生学の構築」)主催の公開ワークショップ「死生をめぐる社会学」が開催された。プログラムは以下のとおりである。
1 共産主義と大量死――ソヴィエト連邦のばあい 副田義也(金城学院大学教授)
2 支社の追憶から老人介護を考える――スウェーデンを事例として
大岡頼光(中京大学助教授)
3 比較から見た死の文化 中筋由紀子(愛知教育大学助教授)
討論者 佐藤健二(東京大学教授)
司会 武川正吾(東京大学教授)
副田氏は、歴史家ホブズボームにならって「大量死」(mega death)を20世紀の時代の特質の一つと位置づけ、この大量死の実例の一つとして、共産主義の革命と政治によって生まれた大量死の問題を取り上げた。副田氏は、赤色テロル、飢饉による餓死、政治裁判による刑死、強制収容所における虐殺死の状況をつぶさに紹介したあと、これらの大量死を生み出した要因の一つとして、マルクス主義の政治思想が関係しているのではないかとの立場から、自らの考察を述べた。
大岡氏は、スウェーデンの匿名墓地を映像によって紹介することから始まった。匿名墓地では、遺骨灰が森のなかに散布され、墓参した遺族にも遺骨灰がどこに散布されたのか知らされることがない。大岡氏は、匿名墓地の開始と社会援助法の施行が同時期の行われたことに注目し、すべての死者を公共的に祀ろうとする匿名墓地と、スウェーデンの手厚い老人福祉との親和性を指摘する。また、この冥福観は「死者の冥福に対して生者は何もできない」というプロテスタンティズムの教義にまで遡れることを示唆した。
中筋氏は、現代日本における死を、比較社会学の視点から明らかにしようとする。同氏によれば、日本では、死の語りが「わたしの死後、無縁仏となることへの不安や孤独の心情」に満ちている。このような死のありかたは、残された生者よりも死者自身への関心が優位に立っているという意味で近代的である。しかし個人の集団からの独立性が強い現代アメリカの死が「かけがえのない個人の死」と表象されるのに対して、現代日本では「〈我々〉の一員の死」として表象されるのである。
討論者の佐藤氏は、以上の三つの報告を貫く視点として、①日常の死/非常の死、②心/行い、③死後の社会への想像力/他者の死から学ぶ経験といった、死を扱う際のダイコトミーを提起した。
なお、このワークショップの成果は、DALSが中心となって刊行するシリーズ「死生学」の一巻、『死生の社会学』のなかにまとめられる予定である。

