『死生学研究』第8号(2006年秋号)
発刊 : 2006年11月25日 |
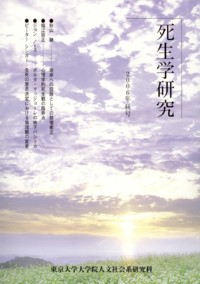 |
秋山聰
彼岸への回路としての祭壇衝立 − ニュルンベルク、聖ロレンツ教会ヨハネ祭壇衝立をめぐって |
堀江宗正
心理学的死生観の臨界点 − キューブラー=ロスをめぐって |
伊藤由希子
『日本霊異記』における信 |
玉村恭
修羅能における生と死 −『清経』の死の意味をめぐって |
佐藤 知乃
曽我祭−江戸歌舞伎の祭式 |
吉原 裕一
死ぬ事と見付けたり−武士道思想における生の構造 |
朝倉 友海
死生の学としての儒学の意義−牟宗三における「生命の学問」 |
宮嶋 俊一
岸本英夫の死生観−宗教学者が死を語ることの意味について |
牛山 美穂
「抵抗」および「戦術」概念についての考察 |
| ******** |
秋山 茂幸
子どもが作る出生の物語−フロイト「ある五歳児の恐怖症分析」(1909)の副旋律 |
大谷 弘
宗教的信念と言語哲学 |
鈴木 健太
インド仏教僧団におけるケアの指針 |
土居 由美
新約文書における「死生観」とキリスト教の「死生観」 |
瀬尾 文子
オーバーアマガウ受難劇の近代化の実態−1811年の台本改作の背景と内容 |
黒岩 三恵
『ビーブル・モラリゼ』とゴシック期フランスの死生観(三) |
福島 勲
ひとりひとりの死の場面で−バタイユの死の概念に見られる個別性 |
福田 桃子
死を乗り越える−ネルヴァルの後期散文作品における唯一性と反復をめぐって |
小寺 智津子
弥生時代の副葬に見られる玉類の呪的使用とその背景 |
| ********* |
| シンポジウム『死とその向こう側』報告
島薗進
はじめに − 身近な死、遠ざかる死、死の文化の多様性
●ワークショップA [進んで死を迎える]
杉木恒彦 死兆、死の欺き、死のヨーガ−初期中世期インドの死の現場の一例
マリーヌ・カラン 半神となるために死ぬこと −カラナ地方におけるブータ崇拝 小峯和明 死の向こう側
−身体・イメージ・パロディ
フランソワ・ラショー ワークショップAへのコメント 討議記録
●公開シンポジウム
フランシスキュス・ヴェレレン 古代道教儀礼における治癒と救済 = 贖罪
ジャン=ピエール・アルベール ヨーロッパにおける殉教と自死 −宗教と政治の間で
塩川徹也 ジャン=ピエール・アルベール氏と フランシスキュス・ヴェレレ氏の発表についてのコメント
古橋信孝 ジャン=ピエール・アルベール氏と フランシスキュス・ヴェレレ氏へのコメント
討議記録
●ワークショップB [非業の死を受け止める]
波平恵美子 非業の死とその受容 −新たな「死の文化」の創出 池澤優 中国古代・中世における“非業の死
”の捉え方の諸類型 −祓い・祭祀・顕彰・救済
ヴァレリー・ロバン=アゼヴェド ペルー南アンデス地方における「悪しき死」 −幽霊譚と中断された喪を
めぐって アンヌ・ブッシィ 除く、識別する、結ぶ −非業の死の処理;自己、他者と暴力の管理の
鏡として 討議記録
●ワークショップC [死者とともに生きる]
池上良正 日本における「死者の身近さ」をめぐって −民俗・民衆宗教研究の視角から
アニェス・フィーヌ キリスト教社会における洗礼親と代子、現世と来世
クローディーヌ・ヴァッサス ディブーク −旧ユダヤ社会における憑依の一形態
末木文美士 ワークショップ「死者とともに生きる」へのコメント 討議記録
●ワークショップD [総合討議] 多田一臣 総括 |
| ******** |
講演研究会
- ジョン・ノース ポルタ・マッジョーレの地下バジリカ
- ピーター・シンガー 生死の意思決定における倫理観の変更
|
| ********* |
| 欧文レジュメ |

