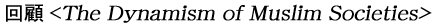
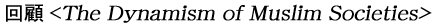
渡部良子(東京大学大学院人文社会学研究科)
|
イスラーム地域研究第6班は、プロジェクト期間を通し、文書史料を用いたイスラーム社会史研究に注目すべき成果を上げてきた。その研究の特徴は、現存文書から単に有用な情報を取り出すだけではなく、むしろ個々の文書が成立した社会的・制度的背景に関心を向け、文書をいかに読み解くかという方法論的な議論を常に怠らなかったということだろう。史書・年代記史料の研究がまだ主流であるイスラーム史研究において、その時代の瞬間の生の現実を伝える文書は、極めて魅力的な史料である。しかし、文書の宝庫であるオスマン朝研究はともかく、稀少な古文書を利用するさいの確実な方法論が、イスラーム史の分野で一般的になっているとは言いがたい。その結果、文書史料偏重ともいうべきオスマン朝と、現存文書の調査もまだ充分に進んでいないイランなど他地域との間に歴史研究の方法論的な乖離が起き、比較史的な議論を困難にしているようにさえ見える。文書を用いた研究が各地域で進展しつつある一方、文書史料を過度に信用する従来の研究方法が批判されつつある現在、イスラーム世界における文書の根本的な性格を問い直し、地域・時代を超えた比較を可能にするイスラーム史独特の文書研究の方法を探ることは、避けることのできない重要な課題であると思われる。 このような問題関心から、イスラーム社会におけるシャリーア法廷の役割を文書発行システムという側面からテーマとしたセッション6は、文書研究の再検討に大きな意義を持つ意欲的な企画であったというべきだろう。シャリーア法廷は、時代・地域を問わず、ムスリムの生活を律してきた重要な機関である。イスラーム史における様々な時代・地域を社会史的な関心から比較する上で、真っ先に取り上げられるべきファクターであろう。しかし、個々の地域におけるシャリーア法廷の実際の機能について、知られていることは少ない。このセッションでなされたのは、各地域・時代に残る法廷文書がどのように、いかなる目的をもって作成されたのかという文書成立の背景を探ることで、シャリーア法廷の社会的役割とその地域・時代による多様性を明らかするという試みであった。これは同時に、法廷文書をその発行システムの中に戻して再検討し、イスラーム社会における法廷文書の役割と影響力を問い直すということでもある。イスラーム世界独特・共通の文書であるシャリーア法廷文書が一体どのような文書であったのかをとらえ直し、法廷文書にどのような分析が可能なのか、法廷文書研究がイスラーム社会史研究にどのような役割を果たしうるのかを考え直すことは、イスラーム文書研究の有効性の根本から問うことでもあるといえる。 報告の中で取り上げられた時代・地域は、14世紀末マムルーク朝時代エルサレム(Donald P. LITTLE氏)、オスマン朝初期〜タンズィマート期シリア(大河原知樹氏)、18世紀オスマン朝下シリア(Brigitte MARINO氏)、16世紀後半オスマン朝イスタンブル(松尾有里子氏)、19世紀前半(近藤信彰氏)である。イスラーム世界の最古の現存文書に属するアラビア語法廷文書、ハラム文書の研究に長年取り組んできたリトル氏、オスマン朝期シリアのアラビア語文書のカタログ化という功績を持つ大河原氏、マリノー氏、オスマン朝文書研究の蓄積を背景に、法廷台帳研究の優れたキャリアを持つ松尾氏、イランのペルシア語ワクフ文書を発掘し、限られた資料をもとに鋭利な分析を発表し続けている近藤氏と、文書研究の最先端に立つ顔ぶれが報告者には揃った。オープニングの提言はオスマン朝研究の林佳世子氏が行い、進行は新文書史料の発掘により近代イランのウラマー社会の研究に努めるChristoph WERNER氏が担当した。14世紀から近代までのアラビア語、ペルシア語、オスマン語圏がほぼカバーされていたことになる。リトル氏のハラム文書とほぼ同時代のペルシア語古文書群、アルダビール文書のベテラン研究者であるMonica Gronke氏が今回のセッションに参加できなかったことは、大きな損失であったと言わざるをえない。 各報告の具体的な内容については同ホームページの石黒報告に詳しいので、繰り返しは避け、筆者の感想を述べさせていただきたい。 現在のところ、イスラーム世界に関しては、多数の法廷文書が残るオスマン朝期以外には文書の数を頼みにした数量分析的な研究は極めて難しい。松尾氏は、法廷台帳の分析に基づき、オスマン朝法行政制度の確立期におけるイスタンブールの主要なシャリーア法廷、Rumeli Sadareti Mahkemesiの特徴的な役割を的確に描き出した。また大河原氏は、オスマン朝期シリアの婚姻契約のシステムをより長いスパンで分析し、また数量的データに基づき20世紀前半のダマスクス住民の結婚の実態を明らかにした。文書研究が特定の時代・地域の個別具体的研究になりがちな中、結婚という個々人の生活と切り離せない法契約について、その歴史的変遷を明らかにしたのが非常に興味深かった。これらの報告で得られた成果は、分析の深さもさることながら、史料の豊かさという基本的な(極めて厳しい)条件から切り離せないものだ。 しかし、限られた史料であっても、その分析方法によって見事なまでの広がりのある研究成果を見せられたのは、爽快な驚きであったというほかない。リトル氏は、ハラム文書群の中から一人のカーディーにより作成された文書を事例として取り上げ、法廷文書作成手引書との比較による文書形式の詳細な分析と、文書中で下されている法判断(ある女性の離婚訴訟に関する)への考察により、法廷文書の形式性と、カーディーの裁定の現実的な柔軟性という二面性を鮮やかに抉りだした。マリノー氏は、18世紀に勢力を振るったシリアの名望家アズム家の資産蓄積が、売買・移転契約やワクフによって、シャリーア法廷を巧みに利用することで行われていたことを文書の分析から指摘した。リトル氏が指摘した形式による権威・厳格さと柔軟な現実性に加え、「トリック」「虚構」という法廷文書の一面を浮かび上がらせた。近藤氏は、カージャール朝時代テヘランの「二重ワクフ」訴訟の経過を追跡することで、法廷が世俗権力から独立した特異な法行政システムと、ひとつの訴訟を遂行する過程で生じる世俗権力とウラマーのネットワークの絡まりあいをいきいきと再現し、19世紀イラン社会におけるシャリーアの独特なあり方を見事に描いてみせた。一点の文書がどのように生成してゆくのかを目の当たりにするような、刺激に満ちた報告だった。 これらの報告は、法廷文書の形式や性質を知悉し、イスラーム法とシャリーア法廷の現実的な機能を批判的にとらえ直した上で、文書が作成された背景に踏み込むことにより広い複雑な社会状況に光を当てることができるという、文書研究の可能性を示している。無論、それには複雑な知識と特殊な鍛錬が必要とされるのだが、従来の文書研究の手法的な問題を踏まえつつ、文書の史料的可能性をこのように引き出してみせたこれらの報告は、文書史料が稀少なため年代記史料などの周縁に置かれてきた地域・時代の研究者にも、大きな希望を与えるにちがいない。 |