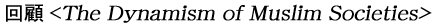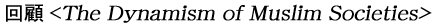| 第4セッションではSufis and Saints Among the People in Muslim Societiesというテーマのもと10人の研究者による発表が行われ、活発な議論がなされた。本題に入る前にまずは発表者とその題目を発表順に挙げておこう。
(1)東長靖(京都大学). "Sufi Saints and Non-Sufi Saints in Early Islamic
History."
(2)Vincent Cornell(University of Arkansas. "People's Saints or the
Saints of People: Urban and Rural Models of 'Popular Sainthood' in the
Western Maghrib."
(3)Boaz Shoshan(Ben-Gurion University). "Popular Sufism Sermons in
Late Mamluk Egypt."
(4)堀川徹(京都外国語大学). "Tariqas and Their Political Roles in Central Asia
in the Sixteenth Century."
(5)今松泰(神戸大学), "'Saints'in Evliya Celebi's Seyhatname."
(6)Mohamed el-Mansour(University of Mohamed V). "Saints and Sultans:
Religious Authority and Temporal Power in Precolonial Morocco."
(7)Nathalie Clayer(CNRS). "Saints and Sufis in Albanian Society."
(8)私市正年(上智大学). "Sufi Orders and Islamic Resurgence in Contemporary
Egypt: Analysis of the Daftar of the Burhami Tariqa."
(9)赤堀雅幸(上智大学). "Partly Saints and Partly Bedouins: The Murabiteen
People Among the Bedouins of the Western Desert of Egypt."
(10)Thierry Zarcone(CNRS). "Bridging the Gap Between Pre-Soviet and
Post-Soviet Sufism in Ferghana Valley (Uzbekistan): The Naqshbandi Order
Between Tradition and Innovation."
各発表をテーマごとに分類するなら、「聖者」を議論の中心に据えてその概念の分析を行ったのが(1)(2)(5)(6)(9)である。それ以外の(4)(7)(8)(10)はスーフィー教団を扱っており、その実態を社会や国家との関係で論じている。このうち(4)堀川以外は全て現代の教団を扱っている。一方(3)Shoshanの主眼はむしろ民衆にあり、それに接近するための史料としてスーフィーたちの説教集(wa`z)の有効性を論じている。
これらの発表を逐一紹介するのは紙数の都合上不可能であるため、本報告記では次の3点に絞って論じるつもりである。第一にまずセッションで特に重要視されていた「聖者」の概念の問題について、(1)東長の発表を紹介しながら考察する。なおこの問題は、これまで一貫して「スーフィズム研究会」(第2班cグループ)で取り上げられてきた問題であり、報告者が最も関心を抱いていたものでもあった。第二にスーフィー教団を扱った発表について(7)Clayerの発表を取り上げて考察する。「聖者」に関する発表がスーフィズムや聖者信仰の研究における分析の枠組みを論じるものであったとすれば、「スーフィー教団」に関する研究はスーフィーや聖者が社会とどのように関わっているのかについてより具体的に論じているものであった。抽象的な概念についての議論と、具体的な事実についての議論の両者をバランスよく見ておく必要があるだろう。そして第三に、まとめもかねてセッション全体に関しての概要と報告者の感想を述べ、またその意義について考察する。
第一の点に関しては、すでに述べたように(1)東長の発表を紹介し、その上で自らの考えを述べてゆきたい。
(1)東長は10-12世紀に書かれたスーフィーや聖者に関する7つの伝記の分析を通して「聖者」および「スーフィー」概念の見直しを行っている。東長によれば、伝記には有名なスーフィーと共に一般にはスーフィーとは見なされていないような人物を扱っているもの(wali-type
biographies)とスーフィーのみを扱っているもの(sufi-type biographies)とがあるという。このうちwali-typeの伝記について、東長はスーフィーとは見なされない人間が伝記で扱われているということへの疑問に対する答えとして次のような推察を行っている。まず研究者がスーフィーとは見なさないような人物であっても伝記作者たちがスーフィーであると考えていた可能性を挙げている。あるいは当時スンナ派がスーフィズムに対して懐疑的であったという思想状況を考慮し、伝記作者たちが、スーフィーではないスンナ派の権威を聖者(wali)として含ませることによって、スーフィズムの正統性を示そうとしていたという可能性も述べている。また聖者(wali)理論に関しては、それがスーフィズムだけでなくシーア派やスーフィーではないスンナ派の思想家によっても発展させられてきた事実にも触れている。そして結論としては以下のように述べている。まず聖者(wali)の存在そのものは、コーランやハディースの権威によって全てのムスリムに受け入れられているものであった。また聖者は必ずしもスーフィズムの枠の中だけで語られるものではなかった。そしてそうしたスーフィーではない聖者(non-Sufi
saints)は、1)イスラーム的基盤を持たない聖者(non-Islamic saints)、2)スーフィーではないが他のイスラーム的権威によって成り立つ聖者(non-Sufi
Islamic saints)、3)一般的にはスーフィーとは見なされないが、思想家によってはスーフィーであると見なすようなイスラーム聖者に分類できるとしている。
聖者にせよスーフィーにせよ、その実態は地域や時代によって大きく異なるものであり、安易な一般化をすることは避けなければならない。だが、東長による分類によって、それまであまりにも漠然と捉えられてきたスーフィーや聖者という現象を分析的に把握する道が開けたと感じる。今後の研究においては、研究者はまず自らが対象とするスーフィーなり聖者なりについての何らかの定義づけを行ってゆく必要に迫られてゆくことになるだろう。そしてその際には、その分類法に対して賛同するにせよ批判的な立場を取るにせよ、東長の示したこのモデルが一つの指針として役立つのではないだろうか。
第二の点に関しては、今回3人の研究者が現代におけるスーフィー教団を扱ったことは高く評価すべきだろう。現代のイスラームを考える際、急進的な行動の目立つイスラーム復興運動へと目が向けられがちであるが、それはともすればイスラームのある種の側面だけを強調した、偏った議論に陥る可能性がある。そして前近代だけでなく近代以降も、民衆に根ざした運動として存在し続けるスーフィー教団はそれとは別の視点を提供する材料として有効なものである。
(7)Clayerは現代のアルバニアにおけるスーフィー教団および聖者の活動を明らかにし、共産主義政権崩壊後のアルバニア社会においてどのような特徴や役割を持っているのかについて論じている。オスマン朝期以来アルバニアには多くの教団ネットワークが張り巡らされていた。1967年に共産主義政権が成立して宗教は禁じられ、教団の活動は停止したが、1990年に政権が崩壊すると、聖者と教団は急速な勢いで復活した。この復活の過程をClayerは3つの段階で説明している。第一段階は民衆による聖者信仰が復活し、地元の廟などが修復された。第二段階ではスーフィー教団が復活し、聖者たちをそのネットワークに組み込んでいった。ただしこの段階までは教団のシャイフや聖者の役割は伝統的なもの(アルバニアにおいては治療者としての役割)に留まっていた。しかし第三段階ではシャイフや聖者はこうした個人の救済の役割だけでなく、より集団的な紐帯、倫理、イデオロギー、さらには国民意識の形成を担うようになったという。またClayerは現在独自の教団を開いているある女性の聖者を例に挙げ、既存のスーフィー・ネットワークとはつながりを持たない新たなタイプの聖者が現れていることも示唆している。
前近代におけるスーフィズムの役割の一つとして、非イスラーム地域への草の根レベルでのイスラームの浸透を促す役割があったことはよく知られているが、Clayerの発表は現在においても依然としてスーフィズムがそうした役割を担っていることを改めて実感させるものである(ただしこの場合はイスラーム化というよりは再イスラーム化と呼んだほうが正確かもしれない)。また最後に触れた新たなタイプの聖者にも注目すべきだろう。Clayerによれば彼女は元々はベクタシー教団のメンバーであったが、現在ではもはやイスラームの聖者という枠組みでは捉えられず、彼女独自の宗教を開いているという。このような聖者の存在は、イスラームの枠に限定されないより広い枠組みからイスラーム地域の聖者を考えるための重要な視点を提供するのではないだろうか。
第三の点に関しては、第4セッションはそのタイトルが示す通り、スーフィー、聖者、民衆という3つの領域を包摂している。各領域はお互いに非常に密接な関連を持ってはいるものの、従来は異なった研究分野によって、それぞれ異なったアプローチや目的を持って研究されてきた。仮に歴史学、人類学、思想研究の3つの分野を挙げるならば、歴史学が主に前近代における民衆や社会集団としてのスーフィー教団を対象としてきたのに対して、人類学は実践としての聖者信仰に焦点を当ててきた。一方思想研究はあくまでもスーフィズムや聖者についての理論的考察の枠内に留まっていた。そして東長がその発表の冒頭で、人類学と思想研究との溝について指摘したように、それぞれがお互いの領域に歩み寄るような試みはあまりなされてこなかったのである。従ってこのような複数の領域にわたるテーマが設定された場合、ともすればその発表は相互の関連付けがなされずにそこでの議論はまとまりを失い、このセッションが共通の議論の場とはなり得ないという危険性があった。
しかし結果を見れば、この危険は回避され、セッションはまとまりを持ち活発な議論の場としての役割を果たすことができた。その理由は次のように考えることができるだろう。まず発表者の多くが共通の学問分野や研究対象を持っていたということである。彼らのほとんどは歴史研究を背景に持っており、またスーフィズムや聖者を専門とする研究者であった。従って議論を行うための共通の基盤がすでにある程度は出来上がっていたと言えるだろう。だがより重要なのは議論の中心となるべきテーマが絶えず示されていたことである。最初の発表者であった東長は「聖者」と「スーフィー」に関する既存の概念に疑問を投げかけることでその後の議論の方向性を示した。そしてCornell、今松、赤堀などによって「聖者」や「スーフィー」の概念が論じられることにより、この問題は引き続きセッションの主要テーマとして留まり続けた。奇しくもこうした発表を行った研究者は、東長は思想研究、今松・Cornell・el-Mansourは歴史学、赤堀は人類学と多領域に渡っていたが、同じ「聖者」「スーフィー」という現象を話題にすることで共通の議論を行うことができたのである。
今回のセッションからは多くの意義が見出されるが、全体として見た時、これは今後ますます増えてゆくであろう学際的な研究の模範となる意義を持っていたと言えるだろう。発表が聖者、教団、民衆とに分かれたのは偶然かもしれないが、それはある意味ではこれまでの研究のあり方を象徴している。そして教団と民衆を扱ったのは全て歴史研究者であった。それにも関わらずセッションがまとまりを持ったのは、ある程度共通の学問基盤(歴史学)と、何よりも複数の領域の研究者が興味を持ち、参加できるような議論の方向性(聖者・スーフィー)が絶えず示されていたことにあるだろう。(文中敬称略)
|