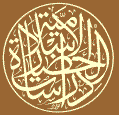


| ニュース一覧 | スケジュール | 活動報告一覧 | ライブラリ | メーリングリスト | サイトマップ |
中央アジアのイスラム復興
小松 久男
『朝日新聞(大阪版)』1999年9月2日、同9日付朝刊より転載
1991年、ソ連の解体によって自立の道を歩み始めた中央アジア諸国は、いま大きな変革の時代を迎えている。それは中央アジアの悠久の歴史においても、特筆すべき転換点として記憶されることになるだろう。このような現代の変容の中で特に注目されることの一つに、イスラムの再生と復興というプロセスがある。
1995年の夏、ウズベキスタンの首都タシュケントのあるマドラサ(イスラムの高等学院)訪ねたとき、私は特別の保管庫に収められている由緒あるコーランの写本を目にした。この大きな羊皮紙に書かれた写本は、伝承によれば、預言者ムハンマド亡き後の3代目のカリフ、ウスマーンが651年、これを読んでいるときに暗殺者の手にかかったとされるコーランであり、写本には彼の血痕が残っているという。この「ウスマーンのコーラン」は、15世紀の初めにオスマン帝国を破ったティムールが、戦利品として持ち帰ったともいわれ、長らくサマルカンドの高名なモスクに保管されていた。しかし、ロシアが中央アジアを征服した直後の1869年、この写本はロシアの総督の手に渡り、ついでペテルブルグの公立図書館に収められた。ところが、1917年ロシア革命の直後、レーニンはこの貴重な写本をムスリム組織に返還する。ロシア国内に居住する多数のムスリムを味方につけるための方策であった。こうして、写本はサマルカンドに帰還した。しかし、ソヴィエト政権が確立し、無神論宣伝と反イスラム政策が実施されると、この写本は再びムスリムのもとから引き離された。それがムスリム組織に返還されたのはペレストロイカの時代である。中央アジア史の転変を自ら経験してきたかのようなこのコーランは、いまイスラム諸国との交流にも重要な役割を果たしているという。
中央アジアのイスラム復興と一口に言っても、それには地域によって明らかな温度差がある。イスラム復興が著しいのは、かつてイスラム文明が深く根をおろしていた南部のオアシス定住民の地域を継承したウズベキスタンとその周辺地域であり、歴史的にイスラム文明の周縁に位置していた遊牧民の地域を継承するカザフスタンなどでは、復興の動きもさほど目立ってはいない。
イスラム復興は、さまざまな形をとって現れている。ソ連時代にうち捨てられていたモスクやマドラサ、マザールなどの再建と再開、巡礼および参詣者の増加、犠牲祭などの祭礼の復活、宗教文献・パンフレットの流布、少年を対象としたコーラン学校の開設、また「祖国愛は信仰の一箇条なり」という近代イスラム世界に広く知られたフレーズの使用など、その例には事欠かない。去年の末、私はウズベク人の知人から結婚式の招待状をもらった。アッラーの御名に始まるその挨拶文には次のようにあった。「父母の祝福を受け、私たちは独立した生活に入ります。アッラーよ、正道に導きたまえ、私たちはイスラムの家庭を築きます。父祖の汚れなき霊よ、守りたまえ、アッラーよいついかなる時も2人を邪視から守りたまへ」と。イスラムは、人々の生活の中へ自然な回帰を果たしているように見える。それは民族文化の復興と軌を一にしているともいえる。
しかし、その一方で、復興するイスラムと政権との間に鋭い緊張関係が生まれていることもまた事実である。イスラムの教義を政治と社会の原則にすえようとする復興主義者とあくまでも世俗主義を貫こうとする政権との間には、深く越えがたい溝がある。
イスラムの政治化にはイデオロギーのほかにも様々な要因が考えられる。それはタジキスタン内戦の悲惨な実例が示すとおり、ソ連時代の負の遺産を含めて、変革期の中央アジア諸国が抱えている政治の民主化、独立後の国民統合、経済の不振、隣接するアフガニスタン紛争の脅威、アラル海の死に象徴される環境の悪化などの難題とその未解決が生み出す人々の不満、これらの問題とも密接に結びついていると思われる。
ウズベキスタンでは今年2月のタシケントでの爆弾テロ事件以来、カリモフ政権と内外のイスラム復興運動組織はさらに対決の度を強めている。さる23日にキルギス南部で日本人技師らを拉致した武装勢力の行動も不明な点は多いが、このような文脈で考えることは可能である。復興したイスラムの政治化は、中央アジアの大国ウズベキスタンの今後にも重要な意味を持っている。*マザール:イスラム世界の各地に見られる聖廟のことで、中央アジアでは一般にマザールという。聖者として敬慕された神秘主義教団(タリーカ)の導師や歴史上の英雄・君主などの墓には、現世利益の祈願に参詣者が訪れるのが常であった。これは現在でも変わらない。マザールは、中央アジアの歴史的な景観を構成する重要な要素の一つであり、神秘主義教団の活動の拠点やムスリム・アイデンティティの再生産の場として機能してきた。ブハラのナクシュバンド廟やサマルカンドのシャーヒ・ジンダ廟は、その代表的な存在である。
中央アジアにおけるイスラム復興の重要な局面の一つに、タリーカ(イスラム神秘主義教団)の再生がある。神との精神的な合一という神秘体験を求めて、優れた導師のもとで修行に励むムスリムが形成したタリーカは、12世紀以降、イスラム世界の各地に広まったが、中央アジアはその中でもタリーカが盛行した地域として知られている。
歴史をとおして中央アジアに移住、定着したトルコ系遊牧民のイスラム化を実践したのは、何よりもこのタリーカであり、かつて精神的な権威に卓越した導師たち(中央アジアでは一般にイシャーンとよばれる)は、君主に指導や助言を与えたのみならず、信徒からの寄進によって莫大な富を形成し、ときに学芸の保護者としてふるまったものであった。
中央アジアからはいくつものタリーカが生れたが、もっとも有名なのはウズベキスタンの古都ブハラを中心に成立したナクシュバンディー教団である。この教団の系譜は後にインド、中国、現代の中東地域やロシア、さらにはバルカンに伝えられ、まさにイスラム世界大に広まったといってもよい。その教義は、スンナ派イスラムの正統に従って公正と秩序を重んじ、信仰と労働の両立を説いたところに特徴がある。
さらに導師への絶対的な服従を原則とするタリーカは、それ自体が規律と秩序を備えた堅固な社会組織であり、外からの攻撃や動乱にさいして共同体の防衛や抵抗の中核を形成することもまれではなかった。ロシア統治期からロシア革命後の内戦期にかけても、タリーカはしばしば武装抵抗運動にかかわってきた。
ロシア統治期の1898年、現在のウズベキスタン東部の都市アンディジャンで起こった反ロシア蜂起は、その代表的な例である。指導者はナクシュバンディー教団に属する高名なイシャーンであり、蜂起は失敗に終わったものの、ロシア軍を直接の標的にしたこの事件は、ロシアの世論にも大きな衝撃を与え、イスラムとりわけタリーカにたいする敵意と警戒を新たにさせた。ソ連時代にタリーカが厳しい弾圧を受けたことは言うまでもない。指導者を失ったタリーカはほとんど解体し、神秘主義の伝統は意味不明の習俗へと退化していった。
しかし、最近の研究は、ペレストロイカ時代の末期から、ウズベキスタンやタジキスタンでは、ソ連時代にかろうじて生き残ったタリーカの系譜をもとに、あるいはトルコやパキスタンのタリーカの感化をえて、しだいに個々のタリーカが再生し始めたことを報告している。その多くがナクシュバンディー教団に属することは興味深い。中には万を数える信奉者をもち、農民や労働者、知識人など多様な人々、さらにはウズベク人やタジク人のみならず、イスラムに改宗したロシア人をも門弟にもつようなイシャーンもいるという。再生したタリーカは、いま新たなイスラム化に寄与しているともいえる。
もう一つ注目されるのは、このようなタリーカの再生がもっとも進展している地域が、先のアンディジャンを含むウズベキスタン東部とキルギス南部、タジキスタン北部とが交わるフェルガナ地方(盆地)だという点である。ここではソ連末期の1989年にフェルガナ事件、90年にはオシュ事件という流血の民族紛争が起こっている。
その背景となった社会経済的な諸問題はなお未解決であり、最近の報告はむしろ問題の深刻化を伝えている。カリモフ政権による「イスラム原理主義者」の摘発がもっとも厳重に行われてきたのも、このフェルガナ地方である。
再生したタリーカは、このような緊張をはらんだ地域でいかなる役割を果たすのだろうか。
中央アジアのイスラム復興、この問題を解明するには地域研究という総合的なアプローチが有効だろう。今年10月内外の研究者が集う「イスラム地域研究」プロジェクトは、国際交流基金などの支援を得て「ロシアと中央アジアにおけるイスラムと政治」をテーマとする国際研究集会を東京で開催する。中央アジアのイスラム復興は、そこでも主要な論点となるはずである。
*この記事は朝日新聞社の承諾を得て転載したものです。筆者及び朝日新聞社に無断で複製、改変、送信するなど、著作権を侵害するいっさいの行為を禁止します。
Copyright(C)1997-2002, Project Management Office of Islamic Area Studies, All rights reserved.