|
|
目次
1)「イスラーム地域研究」へのいざない
研究リーダー 佐藤 次高
2)研究組織について
3)広報と研究成果の公開について
4)国際交流について
5)各班の研究計画
総括班/1班/2班/3班/4班/5班/6班
6)研究分担者名簿
研究リーダー 佐藤 次高(東京大学)
1997年4月から、文部省の新プログラム方式(創成的基礎研究)による地域研究「現代イスラーム世界の動態的研究−イスラーム世界理解のための情報システムの構築と情報の蓄積−」(通称「イスラーム地域研究」)が始まりました。期間は2002年春までの5年間。以下にプロジェクトの目的、内容、実施上の基本方針を説明し、多くの皆様方の積極的な参加を仰ぎたいと思います。
<研究目的>
本プロジェクトは、「イスラーム地域研究」の新地平を切り開くことをめざし、具体的には、以下の三つの目的が追究されます。
(1)イスラーム地域研究の新しい手法の開発
イスラーム世界といえば、日本ではしばしば中東地域に限定して用いられます。しかし文明としてのイスラーム世界は、東は中国、東南アジアから中東や東欧をへて、西はアフリカ西部にまで及んでいます。しかも現代では、ムスリムは欧米諸国や日本にも少なからず居住し、それぞれの社会の重要な構成要素となっています。イスラームがかかわる地域は、すでに世界規模にまで拡大しているとみなければなりません。
このようにムスリムが居住する「地域」に注目してみると、そこには、他者との共生や相互依存の関係と同時に、民族問題、地域紛争、人口爆発、環境破壊など、現代世界が直面する問題が集約的に見出されます。たとえば、ボスニア紛争、アフガニスタン内戦、EUにおける「新しい民族問題」などには、ムスリムの動向が深く関わっています。つまり、イスラーム世界の動向は、21世紀の地球文明を大きく左右するとともに、ムスリムの発するメッセージとその行動は、日本を含む非イスラーム世界に異文明理解の大切さを教示しているといえましょう。私たちは、この点にこそ世界的な規模での「イスラーム地域にかんする総合的研究」の必要性があると考えております。
(2)イスラーム地域研究に適した情報システムの開発
従来のイスラーム研究では、コンピュータ利用は必ずしも十分には行われてきませんでした。これは、関連する文字システムが多様であり、技術系分野との連携も不足していたことによっています。本プロジェクトでは、アラビア語やペルシア語、あるいはウルドゥー語、マレー語などの非ラテン文字によるデータベース化を促進し、地域研究へのコンピュータ技術の応用方法を開発したいと考えています。
(3)若手研究者の育成
近年、日本におけるイスラーム研究の進展ぶりには目覚ましいものがあります。しかし世界的にみれば、研究者の層の薄さと研究蓄積の不足は否めません。21世紀におけるイスラーム世界の重要性にかんがみて、次代の研究を担う若手研究者の積極的な育成をはかり、彼らの国際的研究ネットワークへの参加を支援することが不可欠であると思われます。
<研究内容>
以上のような目的を追究するために、本プロジェクトでは、総括班を東京大学大学院人文社会系研究科におき、そのもとに、以下の6つの研究班をおきます。
- 総括班 代表者:佐藤 次高
研究班1「イスラームの思想と政治」代表者:竹下 政孝
aグループ「現代イスラーム思想」
bグループ「国際関係の中のイスラーム」
cグループ「イスラームの法と国家」
研究班2「イスラームの社会と経済」代表者:村井 吉敬
aグループ「社会開発とイスラーム」
bグループ「現代イスラーム世界と経済」
cグループ「イスラーム研究の動向」
研究班3「イスラームと民族・地域性」代表者:松原 正毅
aグループ「国民国家とムスリム・アイデンティティ」
bグループ「現代のムスリムと文化摩擦」
cグループ「現代イスラーム資料の収集」
研究班4「地理情報システムによるイスラーム地域研究」代表者:岡部 篤行
研究班5「イスラームの歴史と文化」代表者:後藤 明
aグループ「生活の中のイスラーム」
bグループ「歴史の中のイスラーム」
研究班6「イスラーム関係史料の収集」代表者:北村 甫<実施上の基本方針>
前述のように、「イスラーム地域研究」における地域は、中東イスラーム地域に限定することなく、テーマの性格に応じて自在に設定していきたいと思います。地域研究の方法については多様な考えがあってしかるべきですが、少なくとも地域研究が、政治学、経済学、社会学、人類学、歴史学、地理学、宗教学、文学、言語学、国際関係学、都市工学など、それぞれのディシプリンを生かした研究を基礎に、それらの成果を総合するものであることについては異論がないと思われます。
地域研究が現代世界の理解をめざすことは当然ですが、私としては、従来の地域研究よりさらに自由なディシプリン研究がよりよい総合を生み出すのではないかと予想しております。一枚の古文書の解読も、どこかで地域や文明の理解に深く関わっているという意識が大切ではないでしょうか。そして個々のディシプリン研究をどのようにして総合するのか、この試みを実行するための知恵が、6つの研究班、それに所属する13の研究グループ、さらにはプロジェクト全体に求められているのです。
本プロジェクト研究は、国内外のすべての研究者、専門家に開かれています。各拠点の研究班はさしあたり5、6名のメンバー(数年で交代)によって構成されますが、これらのメンバーだけが研究を担うわけではありません。むしろ班メンバーには、研究の立案と実行に当たって、班メンバー以外の研究者、特に若手研究者の参加を広く募ることが求められます。したがって本プロジェクトに興味がある方々には、積極的に研究の企画、実行、成果の公表に加わっていただきたいと思っております。
班員のメンバーシップは特権的でも固定的でもなく、より広い範囲の研究者・専門家の参加が自由に行われること、この点を十分に理解していただけるかどうかが、本プロジェクトの成否に深く関わっていると考えています。e-mail、ファックス、手紙などの手段を通じて、総括班、研究拠点、研究班への活発なアクセスをお願い致します。内外の多数の研究者の協力をえて、イスラーム世界理解のための「実証的な知の体系」を築き上げてゆくこと、これが「イスラーム地域研究」の目的です。
2.研究組織について
総括班
東京大学大学院人文社会系研究科(代表者 佐藤次高)
〒113 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学文学部アネックス
「イスラーム地域研究」総括班事務局
TEL 03-5684-3285(直通) 3812-2111(内線8954)
FAX 03-5684-3279
e-mail: i-office@l.u-tokyo.ac.jp
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/
研究班1
東京大学大学院人文社会系研究科(代表者 竹下政孝)
〒113 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学文学部アネックス
「イスラーム地域研究」総括班事務局
TEL 03-5684-3285(直通) 3812-2111(内線8954)
FAX 03-5684-3279
e-mail: i-office@l.u-tokyo.ac.jp
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/1-han
研究班2
上智大学アジア文化研究所(代表者 村井吉敬)
〒102 東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学アジア文化研究所「イスラーム地域研究」事務局
TEL 03-3238-3162(直通)3238-3697(アジア文化研究所)
FAX 03-3238-3162
e-mail: h-ono@hoffman.cc.sophia.ac.jp
http://pweb.sophia.ac.jp/~h-ono/
研究班3
国立民族学博物館・地域研究企画交流センター(代表者 松原正毅)
〒565 吹田市千里万博記念公園10-1
国立民族学博物館・地域研究企画交流センター
TEL 06-878-8343 FAX 06-878-8353
e-mail:jcasmail@idc.minpaku.ac.jp
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/3-han/
研究班4
東京大学大学院工学系研究科(代表 岡部篤行)
〒113 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻岡部・浅見研究室
TEL 03-3812-2111ex.6226 FAX 03-5800-6965
e-mail: asami@okabe.t.u-tokyo.ac.jp
http://okabe.t.u-tokyo.ac.jp/islam/
研究班5
東京大学東洋文化研究所(代表者 後藤明)
〒113 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学東洋文化研究所
TEL 03-3815-9565(直通)FAX 03-3815-9565
e-mail: 5jimu@ioc.u-tokyo.ac.jp
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/5-han/
研究班6
財団法人東洋文庫(代表者 北村甫)
〒113 東京都文京区本駒込2-28-21
TEL 03-3942-0121 FAX 03-3942-0258
e-mail: IAS6@toyo-bunko.or.jp
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/6-han/
|
3.広報と研究成果の公開について
4.国際交流について
1)日常的な国際交流の方針
2)国際会議について
すでに決まっている本プロジェクト主催の国際会議は以下の通りです。
5. 各班の研究計画
本プロジェクトは、6つの研究班の主体的な活動を軸として進められるが、プロジェクト全体がひとつの統合された総合研究であることが求められている。このため総括班は、各班の研究活動や運営の調整にあたり、以下の活動を行う。
研究班1「イスラームの思想と政治」
(研究拠点:東京大学大学院人文社会系研究科)
イスラーム世界は、キリスト教世界と並んで一つの独立の文明体を形成してきた。近代に至って西洋への従属を強いられてきたが、やがて政治的に独立し、今日に至っている。その間、何度かの戦争があり、地域紛争があり、緊張や危機があり、それが世界の動向と大きく関わってきた。その間様々な形の近代化(西洋化)が試みられてきた。
このようなイスラーム世界の動きの中で、この20年間にはっきりしてきたことは、イスラーム世界が明確に自己を主張してきたことである。それは、イスラームの伝統的価値の再主張と「西洋的近代」への挑戦という形で現われ、様々な摩擦や対立・緊張を生んでいる。このような動向に対して、われわれはどのように対応すべきであろうか。ここに、改めてイスラーム思想研究の重要性がある。
以上の問題関心から、研究班1は「イスラームの思想と政治」を共通のテーマとして、三つのグループを設ける。
a「現代イスラーム思想」 (グループ長 小杉 泰)
b「国際関係の中のイスラーム」(グループ長 五十嵐 武士)
c「イスラームの法と国家」 (グループ長 鈴木 董)まず、aグループ「現代イスラーム思想」では、イスラーム思想全体を視野におきつつ、特に19世紀以降、際立った展開を見せるイスラームの政治、社会思想を動態の中で明らかにする。cグループ「イスラームの法と国家」では、イスラームにおいて政治単位(国家)とそれらの間のルール(法)がどのようにとらえられていたか、を歴史的に明らかにする。
このようなイスラームの国際関係のあり方が非イスラーム世界での国際関係と比較していかに特殊であるのか、また逆にイスラームの国際関係は、国際関係である以上、どのような意味で他の地域のそれと共通性をもちうるのかを吟味するのが、bグループの「国際関係の中のイスラーム」である。
また、97年度はムハンマド・シュクリー・サーレフ(マレーシア、マレーシア科学大学)氏を招聘し、イスラーム政治経済学に関する共同研究を行う。(文責 中村廣治郎)
◇研究班・グループ代表からのメッセージ
班代表 竹下 政孝(東京大学)
このイスラーム地域研究プロジェクトの壮大な計画を見て特に印象に残ることが二つある。その一つはこの計画が5年間の長期に亘るということである。しかもその最後の年度は2001年、つまり21世紀の最初の年である(多くの人は2000年を21世紀の最初の年だと思っているようだが、正確には21世紀は2001年に始まる)。つまり、このプロジェクトは文字通り、20世紀の総括であると同時に、来るべき新世紀への展望となるものにしなければならない。もう一つはコンピューター・ネットワークを最大限に利用しているということである。若い研究者の間ではコンピューターを研究に利用することは常識である。私自身は残念ながらコンピューターを使っていないが、この5年間の間には是非マスターしたいと思っている。それでもまだコンピューターの購入をためらっているのは、コンピューターがテレビや自動車のような成熟した完成品ではなく、まだ進化、発展段階にある商品のように思われるからである。特に8年前にアメリカでパソコンを買って、十分に使いこなすまもなく、そのパソコンが古くて使いものにならなくなってしまうという失敗をしているので、どうしても慎重にならざるをえない。しかし、コンピューターが21世紀にも活躍するであろうことは間違いない。2001年にはミーティングなどもすべて実際に物理的に移動することなく、インターネットのテレビ電話で行うようになっているのであろうか。
しかし欧米や日本で情報革命がますます進行していくのにたいして、中近東がその革命の波から取り残され、格差が拡がっていくように感じるのは私だけであろうか。欧米の情報は日本にいてもリアルタイムで入ってくるのに、中東の情報はあいかわらずコネと口こみが中心である。だからこそ、この新プロによって、中東諸国の研究者を出来るだけ多く日本に招待して、人的ネットワーク作りを行いたいと思う。
研究グループ1-a「現代イスラーム思想」
代表 小杉 泰(国際大学)
「現代イスラーム思想」を対象とする私たちのグループでは、思想を研究するのにふさわしい場を作るために、グループ自体を「しなやかな思索のフォーラム」と位置づけました。みんなで集い、多様な思索の営為をしなやかに交流させるフォーラムを実現させたいと思います。
より具体的には、(1)日本におけるイスラーム思想研究の発展をめざし、(2)おおらかで柔軟な共同研究の場を設け、(3)次世代研究者を励まし、次世代に役立つ成果を生む、というのが目標です。それに向かう中で、活動スタイルとして、標語風な言い方をすると、(a)談論風発・自由闊達(b)開かれた門戸と自由な交流(c)時代と世代の架橋、を実現したいと思います。
研究の目標は、「眺望の広がりと思想の深みへ」というように大きく言ってみたいと思いますが、やや抽象的かもしれません。具体的な目標としては、(1)現代イスラーム思想の広がりをとらえる眺望を確立する(2)現代イスラームの思想家群像を明らかにする(3)現代イスラームの論点と焦点を大胆かつ細心に整理する(4)イスラームの知の伝統(古典)と現代思想を架橋する(5)世界的な視野で現代思想とイスラーム思想を架橋する、の5つを設定いたしました。大変欲張った目標かとも思いますが、歴史的なこの大プロジェクトを始めるに当たって、できるだけ気宇壮大に構えたい気がします。そもそも、大空を駆け巡る思念の翼を持つのが、思想というものの魅力ではないでしょうか。
研究対象は、「思想」という言葉から通常連想するものよりも、広義にとらえて、文学なども含めて考えたいと思います。「現代」はおおよそ20世紀としますが、その前史としての19世紀も入ります。上に触れた「時代と世代の架橋」には、古典とのつながり、比較にも目配りすることが含意されています。さらに、「イスラーム思想」とは「イスラーム・非イスラームを問わず現代ムスリムの思想、および非ムスリムのイスラームに関わる思想」と、広く定義したいと考えています。
もちろん、思想それ自体の研究にも力を入れますが、プロジェクト全体が「動態的研究」ですから、思想と社会の実態や動態との関連も重視していきます。さらに研究班1は「思想と政治」がテーマなので、政治思想や思想と政治の関わりにも十分意を用います。
ユニークな活動をしたいと願っていますが、私たちの通常の研究活動は、本を読んで思索すること、現地に行って調査すること、みなで集まって討論をすることなどですので、あまり変わったことができるわけではありません。共同で行う作業としては研究会が中心となります。この研究会を、「報告」型と「書評」型にわけたうえで、次の5種類のパターンで行いたいと思います。
(1)「論争と争点」研究会(主題別)=略称「論点研究会」
(2)「思想家」研究会(人物別)=略称「思想家研究会」
(3)「思想と地域の動態」研究会(地域/国別)=略称「地域研究会」
(4)「書評」研究会(和書・洋書)=略称「書評研究会」
(5)「原典紹介」研究会(現地語で書かれた思想書や研究書)=略称「原典研究会」以上は、グループの活動の枠組みで、中身ではありません。内容は、皆様と一緒に創っていきたいと願っています。のびやかな活動をしたいと思いますので、積極的にフォーラムにご参加ください。
研究グループ1-b「国際関係の中のイスラーム」
代表 五十嵐 武士(東京大学)
「国際関係の中のイスラーム」は、サミュエル・P・ハンティントンの「文明の衝突」論が発表されて以来、冷戦後の国際問題として注目を浴びているテーマである。本グループではハンティントンの文明論的な視角に注目しつつも、それにとらわれることなく、次の三つの観点からこの問題を検討していくことを目的にしている。
第一は中東地域とそれ以外の地域との関係である。湾岸戦争にみられるように、中東、とりわけペルシア湾岸地域は石油という重要資源の主たる供給地域であり、この資源を生産することによって中東地域は否が応にも他の地域との関わりを深めざるをえなかった。それがいまだに帝国主義的支配を排除しようとするこの地域の対外政策にもつながっており、そうしたこの地域の国際関係の中でイスラームがいかなる役割を果たしているのかが問題になるわけである。
第二は中東地域内部での国際関係である。言うまでもなくこの地域にはイスラエルが存在することによって、国際関係は一種の宗教戦争という性格も有している。現在中東和平が何とかテーブルの上で進められるようになっており、その交渉の中でイスラームがどのような地位を占めているのかが研究上関心の的になる。また産油国と非産油国との経済格差は大きく、イスラーム諸国内部での国際関係の中でイスラームがどのような役割を果たしているかという問題も検討されねばならないところであろう。
第三は国際政治の理論的な関心である。国際政治は国民国家という同質的な単位間の関係を想定して、理論化を試みてきたが、イスラーム諸国間およびそれ以外の諸国との関係ではそもそも同質的な単位間の関係と捉えるのが妥当なのかが問題になる。そこで異質国家間の関係、ないし国際関係の性格および構造が本来異なるものとして捉えたうえで理論化をし直す必要もでている。そのような観点から地域研究と国際政治理論との、学融合的対話も進めていきたいと考えている。
研究グループ1-c「イスラームの法と国家」
代表代理 長沢 栄治(東京大学)
研究班1のcグループ「イスラームの法と国家」では、イスラーム世界における法と国家の特質をめぐる問題点を中心に取り上げることによって、研究班1全体の課題である「イスラームの思想と政治」、すなわち文明としてのイスラームの理念的展開とその社会的政治的な実現形態の双方を統一的に理解することを目的に共同研究を組織したいと考えております。その際には、aグループの思想研究、bグループの国際関係をめぐる研究と有効な結びつきを維持しながら研究を進める必要があります。すなわち、上記にあげた理念と現実的形態の関係をめぐる問題は、直接的な形で思想研究
と結びつきをもっていますし、また現代の国際関係におけるイスラームをめぐる問題は、このcグループが扱うイスラームにおける国家という問題領域と充分重なっているからです。言い換えるなら、このcグループでは、イスラーム史から近現代史にいたる長い時間のなかで、政治単位として国家がどのような形態と機能をもって展開してきたかという問題を、この国家の内外で人々の関係を規定した規範の構造を明らかにすることによって検討することを主要な課題にしているということになります。
ところで、以上に述べてきた研究の趣旨は、本来ならcグループのリーダーである鈴木董教授が執筆される予定でありましたが、現在、在外研究でロンドンに滞在されて多忙のため、同じ職場の事務代理をしている長沢が代筆した次第です。近々、鈴木リーダーの「所信表明」が届くことを祈っておりますが、その際には、ホームページその他の媒体を通じて速やかにお知らせする予定です。
最後に、今後の研究計画の予定を鈴木代表が書き残したメモにしたがって簡単に紹介しておきます。問題発見の年である第1年度の今年は、「イスラーム世界における法の存在形態」をテーマに、イスラーム法の理論と慣行をめぐる問題を扱う予定にしています。続いて、第2年度は「イスラーム世界における政治単位」をテーマに初期イスラームからオスマン帝国にいたる歴史において特徴的な国家の存在形態を制度論的に分析し、第3年度は「イスラーム世界における国家と法」をテーマに、その特質を東アジアや西欧など他の文明圏との比較を通じて明らかにしたいと考えております。以上の成果をふまえて、第4年度では、これらのイスラーム世界の法と国家をめぐる特質が現代の問題にどのように投影しているかという問題を検討し、そして最終年度の第5年度は他のグループとの共同研究によって成果の総合化を図ることを目的にしています。
研究班2「イスラームの社会と経済」
(研究拠点:上智大学アジア文化研究所)
1.問題意識は何か
第二次世界大戦後、発展途上国の経済発展が世界的関心の対象になったが、それは先進国からそれらの地域への資金・技術の支援による開発論や援助論が中心であった。しかし両世界の間での南北問題という格差は是正されず、今や世界的分業体制の確立や途上国の慢性的累積債務などが一般的課題になっている。こうした状況下で、イスラーム地域やムスリム間の経済圏構想や独自な金融のメカニズムは、低開発性の問題を単に量的差異とする認識や西欧流の単線型発展論の限界を明らかにしつつある。
経済開発は市場原理を優先したために、国家と個人の中間にある社会の在り方(運動や組織、共同体)は無視され、人と自然との共生が無視されてきた。人間関係の疎遠化という近代の病理や環境破壊、地域紛争の原因も経済開発と密接に関わっている。ムスリムの間で盛り上がりつつある「イスラーム復興運動」や「女性・人権運動」などはこの問題を鋭く批判している。
2.具体的研究テーマは何か
本班は以上のような問題意識から、社会開発、経済開発、研究動向分析の3つの研究テーマを掲げ、それぞグループ(a、b、c)を組織して研究を推進する。
aグループ(社会開発の研究)では、経済開発がもたらした矛盾や経済開発のために無視ないし軽視されてきた課題、すなわち教育、女性、人権、貧困、福祉、医療、民主主義、市民社会、エスニシティと環境問題、都市化と社会変容、ボランティア論などのテーマが、イスラーム地域との関わりの中で研究される。
bグループ(経済開発の研究)では、量の増加と市場原理を重視した西欧的な経済発展プロセスを見直し、イスラーム地域独自の経済発展の在り方を検証していく。具体的には、発展の担い手、産業構造、労働力の問題、地域統合構想、商業・流通ネットワーク、資源開発と環境問題、ODA、NGOなどの諸問題が研究対象である。
cグループ(研究動向の分析)では、21世紀の「地域」と「国際社会」の在り方にイスラーム文明やムスリム社会が重要な役割を果たすとの認識に立って、イスラームの思想と教義、現代政治や社会制度におけるイスラーム、ポストモダンとイスラームなど多様な観点から、最新のイスラーム研究動向が分析される。海外の研究者や研究機関との密接な連絡をとることもcグループの任務である。3.1997年度の研究活動計画について
aグループは水島司(東京外語大AA研)、bグループは木村喜博(東北大)、cグループは私市正年(上智大)によってそれぞれ指揮されるが、3グループは互いに密接な協力体制のもとで研究活動を推進していく。
研究会は7月から、2か月に一回のペースで行われる。また海外からの研究者招聘も積極的に行い、高発元(中国、雲南大学、中国西南民族史)、ユルケ・アルボアン(トルコ、イスタンブル大学、国際関係論)、ポール・ルフト(イギリス、マンチェスター大学、イラン近代史)の3氏が来日予定である。
これと平行して海外調査も行われ、最新の研究成果が第2班のホームページで随時報告される。 (文責 私市正年)
◇研究グループ代表からのメッセージ
研究グループ2-a「社会開発とイスラーム」
代表 水島 司(東京外国語大学)
21世紀という時代は、世界的な広がりを持つ情報ネットワークに、世界の隅々から情報を発信し、あるいはアクセスすることが出来る時代であると同時に、開発という物理的な変化の波が地球上のあらゆる地点におよび、その中で、人権、貧困、福祉、ジェンダー、医療、エスニシティー、環境などの問題がますます重要になってくる時代であると思われます。開発という世界的現象に対して、個々人は何らかの対応を否応なしにしていくことになりますが、その開発という現象の普遍性のゆえに、他の諸個人と何らかの共同性を見いだし、あるいは創りだし、それを基盤にして運動や組織を創り上げていかざるを得ないことになるでしょう。実際、既にアジア・アフリカの多くの地域で、個人と国家(外部世界)の間のレベルに、社会のあり方を組み替えることを目指す様々な形態の運動や諸組織、共同体が生まれ、あるいは生みだされつつあるようです。
私がとりわけ注目したいのは、特定の空間を共有する人々が、切り離された個と個との関係を組み替え、緊密な関係を築き上げようとするローカルなレベルの動きです。それらの運動自体は、通常、極めて局地的な空間が舞台となっているために、必ずしも共通の展開を示しているわけではなく、またその核には、掘り起こされ、再生され、創造された「固有の」伝統をはじめとする独自の、場合によっては排他的な理念がおかれていることもありえます。私が期待するのは、それらの多様性と複雑さの中に、実は21世紀の人類が共有することの可能な普遍的な共同原理というものが潜んでいるのではないかという点です。
こうした期待から、私は、「社会開発とイスラーム」グループで、アジア・アフリカ世界においてローカルな運動理念やローカルな共同原理によって生みだされ、維持され、あるいは崩壊していった運動体、共同体、即ち個性をもった社会というものを各地域・各時代について掘り起こし、ケーススタディーを重ね、それらを分類・比較するという作業をまず行ってみたいと思います。そして、それらの作業の中で、イスラームが果たしてきた正負両方の役割と意義を解明してみたいと考えています。
研究グループ2-b「現代イスラーム世界と経済」
代表 木村 喜博(東北大学)
社会科学の分野からプロジェクトにコミットする者の一人として、地域研究の原点を再確認する必要を感じております。当り前のことですが、特に次の点を指摘しておきます。
第一は、イスラーム地域研究の目的についてです。これは、現地の人たちから見れば、外国人が自分たちの国・地域なりの社会や文化などを研究するわけですから、当然「どうしてこの研究をするの、これが何の役に立つの」となる訳です。この素朴な問いかけは、この四半世紀の間に益々重みを増してきました。現地では高等教育が普及し、研究者が飛躍的に増加し、研究蓄積が増大しました。自国のことや自分たちの文化は自分たちで研究し、守っていくという体制が実際に出来上がっています。レバノン南部からイギリスへの移住者の家系にあった故A.Hourani教授のように現地と何らかのコミットメントを持つような場合は別として、これに外国人がどう係わっていくのかということになります。もっとも、研究に対する個々人の内発的なリビドーを他人に説明する必要は無いかもしれませんが。
第二は、どのような研究をするか、そして研究の成果がどこにどのように寄与できるのかということです。日本で研究を実施するわけですから、先ず日本にとって、次に研究対象である現地にとって、さらに・・・にとって、それぞれどれ程有益なのかが必ず問われてきます。学問のための学問というような主張は、日本のみならず世界の現在の社会状況からして、なかなか容認されないでしょう。すべての研究が実学であるべきとは言いませんが、社会の同時代の要請と遊離したかたちでの学問の主張は、受け入れがたいものとなるでしょう。
第三に、研究の実施方法が問題となります。上の二点との関連から、必然的に現地研究者との共同研究が浮上してきます。研究の目的や内容が合意できたとして、最後にこのやり方と成果の共有が問題になります。最近、単に日本に招待して発表をお願いするだけの研究会も見受けられます。実質的に対等な共同研究が組織され、その成果が現地にも還元することができるのでなければ、現地研究者にとって日本への訪問は、「出稼ぎ」や観光以上の意味を見いだせないものになってしまうことに注意を払う必要があります。
ともあれ、新たに「イスラーム地域研究」を展開させていくうえで、日本の研究水準を向上させることと研究の目的・内容の座標軸を確認しておくことの必要性を感じております。
研究グループ2-c「イスラーム研究の動向」
代表 私市 正年(上智大学)
プロジェクトへの関わり方:個人的感慨と組織的任務
20世紀から21世紀にまたがる、この大型プロジェクトに関わることになってから、私はイスラーム地域の研究を志すことになった学生時代の状況を時折思い出すことがある。もう4半世紀前になるが、当時のビアフラの難民問題やベトナム戦争の不条理に対して、世界の学生や若者たちが体制や秩序それ自体に抗議の声をあげていた。私がアルジェリアの植民地史研究をテーマに選んだのは、そうした当時の世界的情勢に影響を受けていたことは疑いえない。今から振り返ると、1970年という年は近代性が挫折しイスラームだけでなく、さまざまな宗教の再認識運動が始まる時代の画期であったことがわかる。
本プロジェクトは地域研究の新しい地平を切り拓くことを大きな目的としている。学問研究は高度な知性主義で貫かれなければならないが、しかし地域研究が他者の認識方法と一定の政治的実用性を内在するとすれば(これには反論があろうが)、これに関わる者の研究上の道義性が常に問われなければならない。
こうした認識は、4半世紀前の研究を志す者の多くが共有していたことであった。ところが、その認識は私を取り囲む研究状況からはいつからかどこかにいってしまい、研究の動機にも成果にも、他者性とか道義性という意識はきわめて希薄である。当時と比較して、今日の世界は、紛争や難民、人権や飢餓といった問題がよくなっているとはとうてい思えない。
今、このプロジェクトに関わることになり、感慨をこめて次のようなことをこころがけたい。地域研究が他者を措定することで成り立つ以上は、自らの他者認識を問いつつ、研究が推進されなければならない。高度な知性主義を保ちつつ、成果に対する道義性をも意識しなければならない。そして皆で協力して、221世紀の地域社会や国際関係に「平和的共存・共生」をもたらすような知恵を創出しよう。
研究班3「イスラームと民族・地域性」
(研究拠点:国立民族学博物館・地域研究企画交流センター)
1. 研究目的
今日、世界各地で民族をめぐって様々な問題が生じています。民族問題は、あるひとつの国で起きることもあれば、また国境を超えて生じることもあります。いずれにしても当該地域の構造や性格に原因があることは明らかでしょう。私たちは、人類の平和共存は民族問題の解決なしにはありえない、という前提からこの研究を推進しています。
そこで本研究では、現代イスラーム世界における民族問題を地域性との相関関係という観点から解明することを目的としています。具体的な課題として、次のような問題を設定しました。
- イスラーム諸国の国民統合のあり方に関連して、教育あるいはマスメディアがムスリム・アイデンティティの形成に果たす役割
- ムスリム多数派と宗教的少数派としての非ムスリムの共存と紛争の相互関係
- EU・北アメリカ・中国・ロシア・日本などムスリムが少数民族または移民労働者などのように「マイノリティ」として生活している非イスラーム世界における文化摩擦
- イスラーム世界における女性(ジェンダー)問題の多様性
- 急進化するイスラーム復興運動、民族・地域紛争との相互関係
以上の諸問題を解明・究明するには、イスラーム世界の最新動向を調査・分析することが必要となります。したがって、本研究では、電子メディアなどを用いることによって、イスラーム世界の現地情報を即座に入手するシステムの構築を目標に掲げています。また、当該テーマに関する資料を体系的に収集することも本研究班の課題のひとつです。
2. 研究計画
研究は、以下の3グループに分担して遂行されます。いずれも教育、マスメディア、マイノリティ、女性(ジェンダー)の4つを共通のキーワードとしています。
aグループ:国民国家とムスリム・アイデンティティ(代表:加藤博)
国民統合とマイノリティ・アイデンティティの形成にとって、重要なイデオロギーあるいはイメージの具体的な生産過程を追究します。具体的には、各地域の初等・中等・高等教育機関における教育カリキュラムをデータベース化することを予定しています。bグループ:現代のムスリムと文化摩擦(代表:山内昌之)
生産されたイデオロギーあるいはイメージが特定の政治・経済・社会環境のなかで引き起こす文化摩擦について研究します。まず、各地域においてケーススタディを行い、地域の特質を析出したうえで、それらの比較研究を行います。cグループ:現代イスラームの資料収集(代表:臼杵陽)
aグループとbグループの研究を含む現代イスラーム研究全般にかかわる書籍、地図、新聞、雑誌、パンフレット、マイクロフィルムなどの文献資料、CD-ROMなどの電子情報、ビデオテープ、写真などの映像資料など通常の販売ルートでは入手困難な資料を現地に直接赴いて収集します。収集した資料の全てをデータベース化し、ホームページを利用して、それらの情報提供・公開していきたいと考えています。なお、収集すべき現代イスラーム関連資料についての情報・要望がありましたら、e-mailにて、地域研究企画交流センターにお寄せください。cグループで収集した資料につきましては、新プロ期間中は地域研に場所を設けて、閲覧・利用できるようにする方針です。乞御期待。 (文責 臼杵 陽)
3. 1997度の活動予定
< 研究会>
研究班3班会議・班研究会 平成9年12月13日 於:地域研究企画交流センター
aグループ 研究会3回
bグループ 研究会3回
cグループ 研究会2回<海外からの研究者招聘>
- アーセフ・バヤート(エジプト、カイロ・アメリカ大学、社会学)
「イスラーム社会運動の理論的枠組みに関する研究」- イスケンデル・パラ(トルコ、ミマル・シナン大学、トルコ文学)
「トルコ国民主義生成期に関する研究」- ムハンマド・アフィーフィー(エジプト、カイロ大学、歴史学)
「エジプトにおける非ムスリム・マイノリティに関する研究」- セリム・イルキン(トルコ、イスラーム諸国統計経済社会研究研修センター、トルコ社会経済史)
「トルコ近代経済史に関する研究」- サミー・スムーハ(イスラエル、ハイファ大学、社会学)
「イスラエルにおけるエスニック関係」<海外派遣>
フィリピン、マレーシア、シンガポール(赤嶺淳)中国(王柯)エジプト(加藤博)フィリピン(川島緑)モロッコ、スペイン(山内昌之)に、資料収集等の目的で派遣する。
◇研究グループ代表からのメッセージ
研究グループ3-a「国民国家とムスリム・アイデンティティ」
代表 加藤 博(一橋大学)
われわれのグループに与えられたテーマは、「国民国家とムスリム・アイデンティティ」である。与えられたテーマから想像するに、テーマ設定において、イスラーム世界では「国民国家」の政治的な枠組みと国民個々の帰属意識との間に大きなズレがみられる、との基本的な認識があるようである。国民の帰属意識のなかでも、ムスリム・アイデンティティがことさら取り上げられているのは、イスラーム世界のマジョリティがムスリムだからであろう。しかし、時代と地域によっては、マジョリティとマイノリティは逆転し、ムスリムがマイノリティとなろう。したがって、われわれは与えられたテーマを、狭く国民国家とムスリム・アイデンティティとの関係の問題とは捉えず、広くマジョリティであれ、マイノリティであれ、イスラーム世界における政治単位としての国家とそれを越えて形成される国民の意識形態との関係の諸相を解明することと理解する。
われわれは、こうした問題設定に立ったうえで、研究テーマを、国政のレベルであれ個々の国民のレベルであれ、集団で共有される象徴の総体、つまりイデオロギーの生産過程の解明に絞り込みたい。具体的には、国政のレベルでは国民統合理念が、個々の国民のレベルでは草の根の連帯意識が、いかなるシンボル操作の過程をへて形成されるのかを明らかにしてみたい。その際、キーワードは「教育」「マスメディア」「ネットワーク」の三つである。この三つのキーワードを共有する限りにおいて、具体的な研究テーマ、つまりイシューの選択は個々の研究分担者の問題関心に任せられる。私個人としては、「女性」「映画・観劇を中心とした大衆芸能」「マイノリティ」の三つをとりあえず考えている。この三つのテーマのもとに、海外の研究者との共同研究をも視野に入れた、研究会やワークショップの組織化を持って、研究を開始したい。もちろん、そのなかには、研究分担者間の定期的な交流も含まれる。
研究グループ3-b「現代のムスリムと文化摩擦」
代表 山内 昌之(東京大学)
イラン大統領選挙と「現代のムスリムと文化摩擦」研究
「現代のムスリムと文化摩擦」と題する私たちのグループは、中東を中心としたイスラーム世界と日本、欧米の広い地域を横断するテーマを扱います。イスラーム主義(いわゆるイスラーム原理主義)のように目立った現象だけでなく、国際政治経済とイスラームにかかわる文化接触や摩擦の問題もとりあげます。たとえば、最近のイランの大統領選挙なども、日本や欧米との文化接触と摩擦の文脈で理解することが可能です。
イランがアメリカによる経済制裁の解除を実現するには、高いハードルが両者の間に立ちはだかっています。アメリカは、イラン政府が自らを「大悪魔」と名指しをしており、かつて大使館人質事件を起こしたという単純な理由から反感をもっているわけではありません。むしろ、イランへの態度は、すぐれた現実的な根拠にもよっています。ヨーロッパや中東における<国際テロリズム>の支援と庇護、アラブのシーア派集団を介した中東和平プロセスの妨害工作、核兵器や他の大量破壊兵器の研究開発疑惑、北朝鮮との秘密軍事協力の疑いなどです。こうした側面をラシュディー事件など文化摩擦との関係で議論することも意味があるでしょう。
ハータミーの政局運営のむずかしさを政治文化との関係で議論することも大事な作業になります。貧困低所得者層にたいする社会保障と福祉の充実を掲げるハータミーは、<大きな政府>とケインジアン的発想から抜けきれません。しかし、ハータミーを支持した<リベラル>に近い現実主義層には、欧米との関係改善や自由競争や外資導入を積極的に考える<小さな政府>の信奉者たちもいます。この<リベラル>な現実主義層らは、ナテク・ノーリーら保守宗教者層の政権掌握を抑えるカウンターバランスとしてハータミーを支持したのです。下手をすると、権力基盤の弱いハータミーはどの勢力からも支持を失って孤立する危険性をあながち否定できません。「神の名のもとの横暴」に呻吟して変化願望を託した女性や若者の支持を揺るぎなくするには、内に自由、外に開放という変化を避けて通れないでしょう。これはまさに政治文化の問題です。
国際と国内、二つの側面で文化摩擦が、イスラーム世界では今後も問題になることでしょう。最近大きな話題を集めたイランの例を主にとりあげましたが、アメリカ、ヨーロッパ、中国、日本にもまたがる広域的アプローチを心がけようと思っています。御支援をお願いします。
研究グループ3-c「現代イスラーム資料の収集」
代表 臼杵 陽(地域研究企画交流センター)
「作品」としての地域研究
地域研究とは何か、と問われれば、舌足らずを覚悟のうえで、「地域」設定そのものに賭ける学問的な営為だ、と答えることにしている。つまり、地域研究は個々の研究者の「地域」への思い入れにも基づいており、それぞれの「地域」への全体的構想のうえに成り立つ学問である、と。
私見によれば、これまでは既存のディシプリンと地域研究の関係や如何という設定の仕方が多かったと思われる。したがって、研究分野としての地域研究は研究方法としての個別のディシプリン(経済学、社会学、地理学、人類学、歴史学、生態学など)からおこなわれた場合、どのような学問であるのかといった説明が多かった(という印象を私はもっている)。むろん、地域研究は学際的であるべきだという答えもこの問いが前提となっている。
だからといって私は地域研究におけるディシプリンの重要性を否定するつもりは毛頭ない。それは地図なしに山歩きをするようなものであるからだ。山頂が見えてはいても遭難の危険性からは自由でない。ところが、残念ながらわれわれが呼ぶところの「地域研究」の場合は地図の作成、すなわち方法論そのものが議論されているのが現状である。どの山に登ろうとしているのかも定かではない。個々の研究者によってどこに登ろうとしているのか各人各様だからだ。かりに地域研究の目標を「ある地域を理解すること」と定義したところで、「地域」とは、「理解する」とは、といった最初に挙げた地域研究とディシプリンの問題に戻ってしまうことになる。トートロジーに陥るのだ。
新プログラムでは、略称であれ「イスラーム地域研究」と唱えている以上、「イスラーム地域」という地域設定の根拠は何か、については繰り返し問われなければならない。この地域設定がたんに地理的空間の広がりとして理解されるのであれば、わざわざ「イスラーム地域研究」を唱える必要はないというのが私の考え方である。むしろ、この概念を積極的に提唱するのであれば、その新しさを説明する新たな枠組みが提出されなければならないであろう。なぜ「イスラーム世界」研究あるいは「ムスリム社会」研究ではなく、「イスラーム地域」研究なのか。この問いへの回答がこのプロジェクトが実施される過程で明らかにされなければならないであろう。
私自身はパレスチナあるいはイスラエルと呼ばれる「地域」を研究対象にしている。研究対象とする「地域」によってその課題は自ずから異なるのは当然であるが、私の場合にはパレスチナ・イスラエル地域研究を進めるに当たって既存の国民国家の神話からの呪縛からいかにして逃れるかを自らに課している。新たな地域に向かっての構想は国境という概念を再構築する契機となりうるからだ。
立本成文京大教授は、地域という時空が一体となった全体をいかに構図化するという営為において地域研究者は画家と同じで「地域研究の作品は美術作品とさして離れているわけではない」(立本成文『地域研究の問題と方法−社会文化生態力学の試み』京都大学学術出版会、1996年、7頁)と指摘している。「イスラーム地域研究」の成果もこのプロジェクトに参加している各々が自らの「作品」を通して実現されるしかないというのが目下の私の考え方である。
研究班4「地理情報システムによるイスラーム地域研究」
(研究拠点:東京大学大学院工学系研究科)
工学技術としての地理情報システム(GIS)をイスラーム地域研究に適用する先駆的試みを行い、GISの人文社会科学への応用の有効性を検証し、イスラーム地域研究の新たな空間分析分野を構築する。従来、イスラーム地域における空間的現象の研究では、現地調査と観察、聞き取り調査、紙の地図などが情報源として利用されてきた。しかし、取得は莫大な時間と費用を要し、得られる情報の信頼性も不安定である。そこで本研究班では、GISとリモートセンシングデータ(RS)を基盤とし、現地調査より得られる空間データをそれらと組み合わせてデジタル化することにより、これらの問題点を解決しようと試みる。工学者と人文社会科学者の共同研究によるこの試みは、人文社会科学におけるGISの効果的な応用を実現し、イスラーム地域の空間構成の特性を定量的に明らかにするものと期待できる。
空間スケールに応じて、「大域地域空間分析」グループと「小域地域空間分析」グループの2つの研究グループを設ける。
「大域地域空間分析」グループでは、イスラーム地域における時系列RSデータを利用し、土地被覆パターンの変化を分析する。気候という点で特色を持つ複数地域を対象地域に選定し、これらの地域について、各種解像度のRSデータを取得し、土地被覆データに変換、GISによって処理と分析を行う。分析手法については、新たな空間関係記述手法、時空間統計手法を開発し、土地被覆パターン変化の分析、土地被覆変化をもたらす要因の推定と抽出を行う。本年度は、RSからの土地被覆パターン抽出手法の開発、今後の研究において必要となる基礎データの整備を行う。来年度以降は、土地被覆パターン解析手法の開発とRSデータの取得を並行して実施する。
「小域地域空間分析」グループでは、トルコの諸都市を対象として、GISを用いて伝統的市街地の道路パターンを分析する。対象都市の道路パターンを線形ネットワークとして抽出し、パターンの類似度把握のための指標構築、ネットワークにおける形態的中心地の抽出方法の構築、生活の中心拠点であるジャーミーの立地と中心地との一致度の検討、道路ネットワークの自然発生モデルの構築などを行う。また、トルコの住宅の形態的合理性、民族と住宅様式・住宅地構成の違い、他のイスラーム諸国との住宅・都市の構成の変化の比較分析も行う。本年度は、小域地域分析に耐える空間データをディジタル情報として整備する。来年度以降は、道路ネットワーク分析手法の開発、住宅地空間構成の分析を順次行う。
理工系以外の分野の研究者にも参加を仰ぎつつ、各グループの研究会を開いて研究を進める。本年度は、トルコにおける道路ネットワークの分析を形態学的側面・文化的側面から研究しているアイシェ・セマ・クバト教授(トルコ、イスタンブル工科大学、都市工学)を招聘する予定である。(文責 貞広幸雄・浅見泰司)
◇研究班代表からのメッセージ
代表 岡部 篤行(東京大学)
私たちの研究班は、地理情報システム(Geographic Information Systems = GIS)、地理情報科学(Geographic Information Science = GIS)の研究を専門としている研究班です。このたびの研究では、GISをイスラーム研究の分野に適用する研究を試みます。この研究を通してイスラーム研究者の方々と有意義な研究交流ができればと胸を膨らませています。
しかし、研究交流と言っても、お互いが研究の内容の概略を知り合っていないとできません。おそらく、イスラーム研究を専門とされている方々にとって、GISとは、耳新しい言葉ではないでしょうか。そこで、皆様方の研究に関連しそうなことと絡めて、GIS とは何かをご紹介いたしましょう。
地理情報システム(GIS)とは、「空間データ」をコンピュータで系統的に処理するシステムを言います。
ここで空間データとは、地表、地下、地上の位置や範囲などを明示した自然、社会、経済、文化などのデータを指しています。もちろん、日頃おなじみの地形図などはもとより、イスラーム地域の国別人口データや農業生産額を始め、モニター地点の雨量データ、地下水位データなどは、全て空間データに含まれ、極めて広範なデータです。あらゆる事象は空間で生起する訳ですから、あらゆる事象のデータは空間データの可能性を秘めています。しかし、地球での位置や範囲を明示していなければ空間データとは呼びません。
この空間データをコンピュータで効率的に処理するシステムが地理情報システムですが、その処理は幾つかのサブシステムよりなっています。
第1が、空間データを取得・構築するサブシステムです。この部分は近年の情報技術の発展により、急激な進歩を遂げつつあるあるところです。人工衛星からのリモートセンシングデータの取得、地球測位システム(GPS、自分のいる位置が分かるシステム)を装備した携帯電子地図+ノート=電子野帳による野外調査データの取得などがあります。今回は、電子野帳の実用化を試みますので、野外調査にご利用していただけるかと思います。また紙地図の電子化(大型スキャナー、ディジタイザー)も稼働できると思います。そのデータをCD-ROMに記録する装置も稼働させますので、地図、図形情報を広く研究者に配布することが可能となります。ご利用されたい方はご相談ください。
第2が、空間データを管理するサブシステムです。いわゆるデータベースにあたる部分です。エクセル、アクセスなど文書や数値のデータベース・ソフトウェアは随分普及してきましたが、空間データは位相的な構造(例えばイランの隣にイラクがあるといった空間関係)を管理する必要があり、難しい部分です。今回は、イスラーム世界のある都市(多分トルコの都市)について空間データベースを作ろうと思っています。同じ都市を研究される方は、ご利用ください。
第3が、空間データを分析するサブシステムです。モスクの分布とキリスト教会の分布にどのような関連があるのか、集落の分布と河川の関連はどのような特色があるのか、といった空間的な関連性を分析したり、多くの空間データを同一空間上に射影してそれらを多面的に分析するサブシステムです。今回は、イスラーム世界のかなり広い地域と、ある都市を取り上げて、新たな時空間分析手法の開発を考えています。空間の要素の関係を数量的に明らかにしてみたいとお考えの方は、是非ご相談ください。
第4が、空間データ、空間解析結果の表示・伝達サブシステムです。分析の結果を地図に投影して表示すると、今まで見えなかったことが見えてくる場合が多々あります。さらには3次元表示、4次元表示(アニメーション)をすると、一般の人々にも分かりやすく成果を訴えることができます。今回、イスラーム地域の15年間の地表被覆アニメーションを作ってみようと計画しています。
以上で、GISの香りはご理解いただけたと思いますが、具体的なGISソフトウェア(ARC/INFO)、GISの機器については説明会なり、実習会などを開いて、皆様方にご利用いただけるようにしたいと思っています。
これから5年間、GIS手法をイスラーム地域研究に適用する研究を進めるわけですが、そのためには皆様方よりイスラームに関する様々なことをお教えいただかなければ、私たちの研究は進みません。今後、私たちの素人質問にも是非おつき合いいただくようお願いいたします。
研究班5「イスラームの歴史と文化」
(研究拠点:東京大学東洋文化研究所)
研究班5は、イスラーム世界の歴史と文化を多角的に研究します。研究分担者の多くは歴史研究者と文化人類学研究者です。そこで、班の研究のキャッチフレーズを「歴史学者と人類学者の共同作業」としました。しかし、研究への参加者を、狭い意味での歴史学者や文化人類学者に限定するわけではありません。研究者であれば誰でも、それぞれの領域で歴史なり人間に興味をもつでしょう。そのような人々の積極的な参加を期待しています。
5年間の研究計画の大枠として以下のようにそれぞれの年を位置づけています。
1997年度 問題発見の年、そして研究連絡網構築の年
1998年度 方法論開発の年
1999年度 研究成果の中間発表の年
2000年度 研究の新展開の年
2001年度 研究成果結実の年この大枠のなかで、より具体的な計画をこれから順次作っていきます。
活動スタイルとして、以下の3点を強調しています。
a.開かれた門戸
b.若手の活躍
c.フィールドと文献の統合具体的には、研究会をできるだけオープンな形で開催し、そこに予算の許す限り多くの研究者を招待し、また、自由参加も大歓迎する、という手段を考えています。また、在日のあるいは本プロジェクトによる招請を含め来日した外国人研究者を積極的に招きます。
6月28日(土)に、第1回研究会を開催し、佐藤次高研究代表 そして後藤明班代表の基調報告があり、つづいてaグループ(生活の中のイスラーム)、bグループ(歴史の中のイスラーム)に分かれて研究会がもたれた。両グループともに基調報告を受けて、今後の研究計画について自由討議を行った。内容は、ホームページに掲載されます。
今年度5班では、アフリカのイスラーム運動を研究テーマとするアブドゥル・ラヒーム・アリー・M・イブラーヒーム氏(スーダン、国際アフリカ大学副学長)を招聘し、氏を囲む国際セミナーを企画します。(文責 後藤 明)
◇研究グループ代表からのメッセージ
研究グループ5-a「生活の中のイスラーム」
副代表 赤堀雅幸(上智大学)
研究グループ5-aは「生活の中のイスラーム」を研究のテーマとする。これは、現地調査などを通して、生活の中に実践されるものとしての信仰を、あるいは信仰の発現形としての生活の様々なあり方を考えるということでもあるが、同時に規範的固定的に捉えられることによってイスラームに対する硬直した理解がなされることに抗し、柔軟で動態的な理解の視線をイスラームの現実に向けることでもあろう。
私たちは生活そのものの多様性を十分に考慮するとともに、地域や時代の多様性、さらに研究者の分野とアプローチの多様性を重視し、研究の統合と解体の狭間を常に行き交いすることで何ものかを積み上げることを目指したいと考える。そのために、私たちのグループではいくつかのキーワードを念頭において各自の研究を深め、イスラーム世界の生活の多様性をめぐって、多くのテーマと研究者の出会うところを模索するという手法を取ることとしたい。キーワードとしては移動とネットワーク、地域的脈絡、生活の技法、生活の表象、流行、生活の中のシンボルなどが現在考えられているが、これもまた研究の推移とともに変化していくだろう。活動の成果を発表する形も、研究会を基盤にしつつ、様々な形を模索していきたい。世界各地のムスリムたちを対象とした人類学、社会学、歴史学、美学、文学などが交わったところに何が現れてくるか、楽しみにしていただければ幸いである。
それと同時に、他のグループの研究にも積極的に関わって、グループを横断接合する役割の一端をも当グループが担うことを活動の一環とし、翻って新しいアイデアが常にこのグループの活動を絶えず変貌させ、いたずらな拡散にいたることなく、生活研究への新たな視点を醸成させることを狙いとしたい。多くの研究者、学生の自由で積極的な関与を望む次第である。
研究グループ5-b「歴史の中のイスラーム」
代表 湯川 武(慶応義塾大学)
当グループはイスラーム世界の歴史研究を目的としている。本プロジェクト全体のキーワードは、英語の略称(IslamicArea Studies =IAS)からもわかるように、「イスラーム世界」と「地域研究」の二つである。前者は別にして、後者の「地域研究」と歴史研究はどう関わるのかについて私見を述べてみたい。
そもそも地域研究という語には、現代研究という色彩が強い。実際、多くの地域研究の書物や論文は、特定の地域の政治・経済・社会を扱ったものがほとんどで、地理的環境やそれにつながるエコロジーについての研究がその次に来る。いずれにしても時間的には現代が中心となっており、歴史学の研究は地域研究とは別の枠組みでなされていることが多い。しかし、地域研究はある特定地域を対象として、それをさまざまな角度や視点から総合的に理解しようとするものであり、もともと従来の学問的ディシプリンの枠を超えて学際的な性質を持つものであったはずである。さらにある地域を総合的に見るということは、ある現代の諸相を横断的にみるだけではなく、時系列の上でそれら諸相がどのように変化してきたかということを見ることも重要になってくる。近現代史研究だけでなく、もっと古い時代の歴史研究もつまるところは、何らかの形で現代に繋がっており、また研究者の側から見るならば、現代に生き、研究対象となる地域に何らかの意味で関わりを持っているということ自体地域研究の持つ現代性に繋がってくるはずである。そう考えると、歴史学と地域研究は決して異質なものではなく、むしろ地域研究の中で歴史学の果たす役割の大きさが見えてくるのではないだろうか。
そもそも歴史学というディシプリンにはある種の技術はあるにしても、固有の方法論があるわけではなく、むしろ隣接する諸学問の方法を使いながら研究を進めるのが普通である。言うならば、もともと学際的性格を持つ学問なのである。この点からも歴史学は地域研究に入っていきやすいと言える。
このようなことを前提にして、幅広い地域と時代、そしてさまざまな分野を扱うことになるbグループとしては、当面の共通テーマとして「異文化接触」ということを提案する。ここでは「異文化接触」という語をできるだけ広い意味で使おうとしている。「異文化」の「異」も外国とか外側とかという概念だけでなく、内側に含まれる性格の異なる種々の要素も含むものとして捉える。「文化」という語もいわゆる狭い意味での文化ではなく、人間社会におけるさまざま要素や現象をカヴァーする語として使いたい。また「接触」という概念もその語感からくるものより幅広くかつさまざまな形態を含む現象として考えてみたい。
このように「異文化接触」を定義すると、イスラーム世界で起きた歴史的諸現象をこれまでとは違った目で見ることができ、またより幅広い歴史研究者をまきこんでいけるのではないだろうか。そのような期待を込めて提案する次第である。
研究班6「イスラーム関係史料の収集」
(研究拠点:財団法人東洋文庫)
<ねらい>
イスラーム地域研究の基礎資料の収集と図書館ネットワークの構築
本班は、研究グループ3ーc(近現代資料の収集)と協力し、関係資料の収集と資料情報ネットワークの構築によって、本プロジェクト全体をサポートする役割を担っています。<全体計画>
1.イスラーム地域の政治・経済・文化の基層構造を研究するために必要な各種の現地語資料を、組織的に東洋文庫に収集します。
- 日本において、イスラーム地域に関する現地語資料の収集にもっとも早くから着手し、最大の蔵書量をもち、また資料整理の技術を蓄積しているのは、財団法人東洋文庫です。本プロジェクトでは、東洋文庫に前近代のイスラーム関係資料を集中して収集することによって、ここをイスラーム研究の基礎資料を備えたセンターとすることをめざします。
- 1)アラビア語、ペルシア語、トルコ語、中央アジア関係諸言語の資料について、毎年、計画的な購入を行います。
- 2)東南アジア、南アジア、中央アジア、中国など、従来イスラーム関係史料の収集が手薄であった地域については、現地に資料調査に派遣し、資料の収集を行う。
- 3)対象とする資料は、現地語によるものを中心とし、図書資料のほか、写本・文書資料についても取り組みます。
- 4)収集すべき資料についての情報や要望があれば、お寄せください。
2.図書情報のデータベース化とオンライン・サービスの充実
- イスラーム地域の現地語資料は、アラビア語をはじめ、非ラテン文字を用いることが多い。このため、従来は、図書カードや目録など図書整理の方式が不統一で、相互の利用が困難でした。現在では、パソコンにおいても、アラビア文字など特殊文字の処理が可能となっており、図書情報のデータベース化やインターネットを通じてのオンラインによる検索や利用のシステムを開発することによって、将来は、イスラーム関係の資料を所蔵する研究機関や図書館が連携して、資料の収集と共同利用にあたることをめざします。
- 1)イスラーム地域の現地語資料を所蔵する国内機関を対象に、その所蔵状況、図書整理、利用方法などについて、調査を行い、相互の協力・連携を図る。
- 2)アラビア語、トルコ語、ペルシア語の図書目録のデータベース化、およびそのオンライン化を図る。
- 3)中東諸語の専門司書養成のセミナーの実施。
3.収集資料の公開と利用
- 収集した資料については、その目録をコンピュータを用いて逐次作成したうえ、CD−ROMやインターネットなどの電子メディアを通じて公開し、資料の迅速な公開と利用を図ります。また、手書きの写本や文書資料など特殊な資料については、これを用いた研究会や資料講読会などを開催し、若手研究者の育成を図ります。
- 1)収集した史料は、購入後1年以内に目録をコンピュータを用いて作成し、インターネットなど電子メディアを通じて公開し、東洋文庫において閲覧できるようにします。
- 2)写本や文書資料については、外国人専門研究者を招き、資料講読セミナーを実施します。
<1997年度の計画>
- 1)イスラーム地域現地語資料の所蔵状況調査(97年7-9月)
2)写本資料研究会
3)非ラテン文字資料の目録のデータベース化研究会
4)資料収集のための海外派遣(南アジア地域、中国)。
◇研究班代表からのメッセージ
副代表 永田 雄三(明治大学)
東洋文庫を活動の拠点とする本研究班にとって、班の「仕事」である文献の収集作業は、とりわけ目新しいものではない。これまでは予算の関係で決して十分とはいえなかった「収集」作業を計画的に、体系的に進めるのがまず最初の仕事である。つぎの仕事は収集された史料の情報化であるが、これは東洋文庫ですでに構築されつつあるシステムとジョイントすることになるが、この面では筆者は門外漢である。要は、収集された史料を本プロジェクトに参加される皆様をはじめとして多くの方々に利用していただく便宜を図ることが筆者の役割であると自覚している。今回計画している史料の「収集」は、従来のような刊行図書だけではなく、写本や文書をもターゲットとしているが、これには数々の困難が予想される。それらをどう乗り越えていくかが、本研究班の課題である。たとえば、所蔵権の問題、所蔵する現地の政府や機関との交渉、収集の方法などの問題をいかに解決できるかが、収集作業の質を決定することになろう。筆者個人としては、収集された写本や文書が死蔵されないように、これを閲読・利用するための技術の向上、すなわち写本の解読の訓練、文書学的な知識の教育などのソフト面に関する「研究会」活動を重視したい。
本プロジェクトは、発足したばかりで、まだ今後どう展開するかは、予測がつかないが、各「研究班」の活動が有機的に結びつくことによって、わが国における今後のイスラーム研究にどのような影響をもたらすのか、そして、本プロジェクトの活動を通じてどのくらい若い研究者が育つのか、正直言って、一抹の不安がないでもないが、大いに期待したい。
6.研究分担者名簿
総括班
代表 佐藤 次高(東京大学大学院人文社会系研究科教授、アラブ・イスラーム史)
- 竹下 政孝:研究班1代表
- 村井 吉敬:研究班2代表
- 松原 正毅:研究班3代表
- 岡部 篤行:研究班4代表
- 後藤 明:研究班5代表
- 浅見 泰司:情報システム担当、研究班4
- 私市 正年:広報・出版担当、研究班2
- 小松 久男:総務担当、研究班1
- 長沢 栄治:会計・企画担当、研究班1
- 羽田 正:国際交流担当(東京大学東洋文化研究所助教授、イラン史)
- 林 佳世子:情報システム・広報担当(東京外国語大学外国語学部助教授、オスマン朝史)
- 三浦 徹:広報・出版担当、研究班6
- 湯川 武:国際交流担当、研究班5
研究班1「イスラームの思想と政治」
代表 竹下 政孝(東京大学大学院人文社会系研究科教授、イスラーム思想史)aグループ「現代イスラーム思想」
- 小杉 泰(代表、国際大学大学院国際関係学研究科教授、イスラーム学)
- 小松 久男(東京大学大学院人文社会系研究科教授、中央アジア近現代史)
- 中村 廣治郎(桜美林大学国際学部教授、イスラーム学)
- 八尾師 誠(東京外国語大学外国語学部助教授、 イラン近現代史)
bグループ「国際関係の中のイスラーム」
- 五十嵐 武士(代表、東京大学大学院 法学政治学研究科教授、国際政治)
- 石田 淳(東京都立大学法学部助教授、国際政治)
- 石田 憲(大阪市立大学法学部助教授、国際政治史)
- 高橋 和夫(放送大学助教授、国際政治)
- 立山 良司(防衛大学校社会科学教室教授、中東の国際関係)
- モジュタバ=サドリア(中央大学総合政策学部教授、国際関係論)
cグループ「イスラームの法と国家」
- 鈴木 董(代表、東京大学東洋文化研究所教授、オスマン帝国史)
- 長沢 栄治(東京大学東洋文化研究所助教授、近代エジプト社会経済史)
- 森本 公誠(東大寺教学執事、初期イスラーム史)
- 家島 彦一(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授、イスラーム商業史)
- 柳橋 博之(東北大学大学院国際文化研究科助教授、イスラーム実定法)
研究班2「イスラームの社会と経済」
代表 村井 吉敬(上智大学外国語学部教授、東南アジア社会経済論)aグループ「社会開発とイスラーム」
- 水島 司(代表、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授、南アジア社会経済史)
- 栗田 禎子(千葉大学文学部助教授、中東・北アフリカ近現代史)
- 松本 光太郎(東京経済大学コミュニケーション学部助教授、現代中国研究)
- 水野 広祐(京都大学東南アジア研究センター助教授、インドネシア経済論)
- 宮治 一雄(恵泉女学園大学人文学部教授、マグレブ地域研究)
bグループ「現代イスラーム世界と経済」
- 木村 喜博(代表、東北大学大学院国際文化研究科教授、中東・中央アジアの地域研究)
- 坂本 勉(慶應義塾大学文学部教授、中東イスラーム経済史)
- 清水 学(宇都宮大学国際学部教授、西アジア経済論)
- 原 洋之介(東京大学東洋文化研究所教授、東南アジア経済論)
cグループ「イスラーム研究の動向」
- 私市 正年(代表、上智大学アジア文化研究所教授、マグ レブ・アラブ地域研究)
- 黒木 英充(東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所助教授、シリア・レバノン近現代史)
- 小林 寧子(愛知学泉大学助教授、インドネシア近現代史)
- 小牧 昌平(上智大学アジア文化研究所助教授、イラン近代史)
- 東長 靖(東洋大学文学部助教授、イスラーム思想)
- 間 寧(アジア経済研究所総合研究部研究員、比較政治学)
研究班3「イスラームと民族・地域性」
代表者 松原 正毅(民博・地域研究企画交流センター教授 センター長、社会人類学)aグループ「国民国家とムスリム・アイデンティティ」
- 加藤 博(代表、一橋大学経済学部教授、中東社会経済史)
- 新井 政美(東京外国語大学外国語学部助教授、トルコ近代史)
- 梶田 孝道(一橋大学社会学部教授、国際社会学)
- 川島 緑(上智大学外国語学部助教授、フィリピン研究)
- 新免 康(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助教授、中央アジア史)
- 濱下 武志(東京大学東洋文化研究所教授、中国経済史)
bグループ「現代のムスリムと文化摩擦」
- 山内 昌之(代表、東京大学大学院総合文化研究科教授、国際関係史)
- 王 柯(神戸大学国際文化学部助教授、中国近現代史)
- 大塚 和夫(東京都立大学人文学部助教授、中東民族誌学)
- 内藤 正典(一橋大学大学院社会学研究科教授、現代 トルコの政治と社会)
- 能登路 雅子(東京大学大学院総合文化研究科教授、アメリカ地域文化研究)
cグループ「現代イスラーム資料の収集」
- 臼杵 陽(代表、民博・地域研究企画交流センター助教授、中東現代史)
- 赤嶺 淳(民博・ 地域研究企画交流センター学振特別研究員、フィリピン学)
- 阿部 健一(民博・地域研究企画交流センター助手、東南アジア地域研究)
- 飯塚 正人(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助手、イスラーム学)
- 帯谷 知可(民博・地域研究企画交流センター助手、中央アジア近現代史)
- 黒田 卓(東北大学大学院国際文化研究科助教授、イラン近代史)
- 弘末 雅士(天理大学国際文化学部助教授、 インドネシア宗教社会史)
研究班4「地理情報システムによるイスラーム地域研究」
代表 岡部 篤行(東京大学大学院工学系研究科教授、空間情報科学)
- 浅見 泰司(東京大学工学系研究科助教授、都市工学)
- 桜井 由躬雄(東京大学大学院人文社会系研究科教授、東南アジア歴史地域学)
- 貞広 幸雄(東京大学先端科学技術研究センター講師、地理情報システム)
- 柴崎 亮介(東京大学生産技術研究所助教授、GIS・リモートセンシング)
- 陣内 秀信(法政大学工学部教授、イタリア建築史)
研究班5「イスラームの歴史と文化」
代表 後藤 明(東京大学東洋文化研究所教授、初期イスラーム世界史)aグループ「生活の中のイスラーム」
- 片倉 もとこ(代表、中央大学総合政策学部教授、社会地理学)
- 赤堀 雅幸 (上智大学アジア文化研究所専任講師、文化人類学)
- 大稔 哲也(九州大学文学部助教授、中東社会史)
- 鷹木 恵子(桜美林大学国際学部助教授、文化人類学)
- ヤマンラール水野美奈子(東亜大学大学院総合学術研究科教授、トルコ・イスラーム美術史)
- 和崎 春 (日本女子大学人間社会学部教授、アフリカ地域研究)
bグループ「歴史の中のイスラーム」
- 湯川 武(代表、慶応義塾大学商学部教授、アラブ史)
- 岸本 美緒(東京大学大学院人文社会系研究科教授、中国明清史)
- 杉田 英明(東京大学大学院総合文化研究科助教授、比較文学比較文化)
- 高山 博(東京大学文学部助教授、西洋中世史)
- 中里 成章(東京大学東洋文化研究所教授、南アジア近代史)
- 間野 英二(京都大学大学院文学研究科教授、中央アジア史)
研究班6「イスラーム関係史料の収集」
代表 北村 甫(財団法人東洋文庫理事長、チベット言語学)
- 梅村 坦(中央大学総合政策学部教授、内陸アジア史)
- 小名 康之(青山学院大学文学部史学科教授、インド・ムガル史)
- 清水 宏祐(九州大学文学部教授、イラン史・トルコ民族史)
- 志茂 碩敏(財団法人東洋文庫研究員、モンゴル帝国史)
- 永田 雄三(明治大学文学部教授、オスマン帝国史)
- 三浦 徹(お茶の水女子大学文教育学部助教授、アラブ・イスラーム社会史)
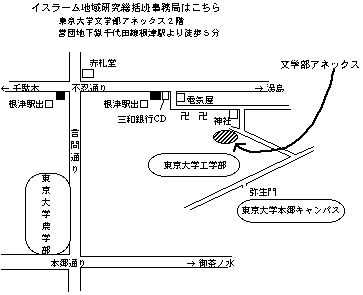 |
『イスラーム地域研究ニューズレター第1号』 |