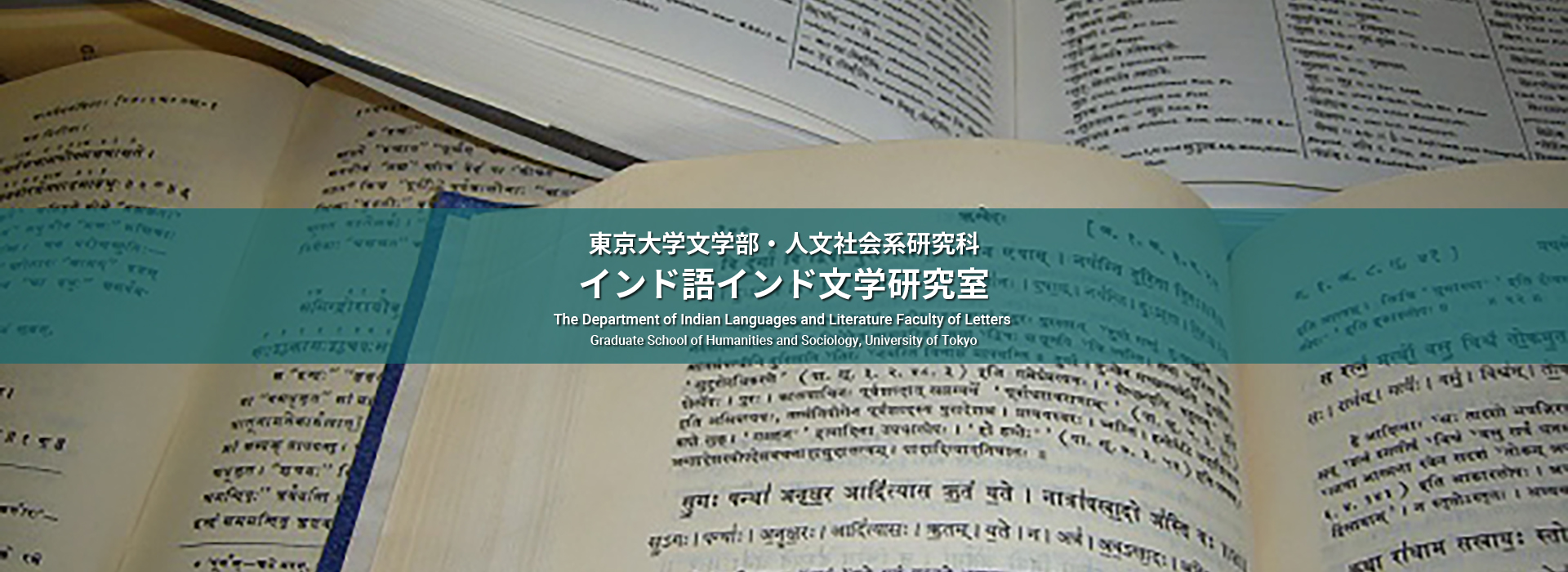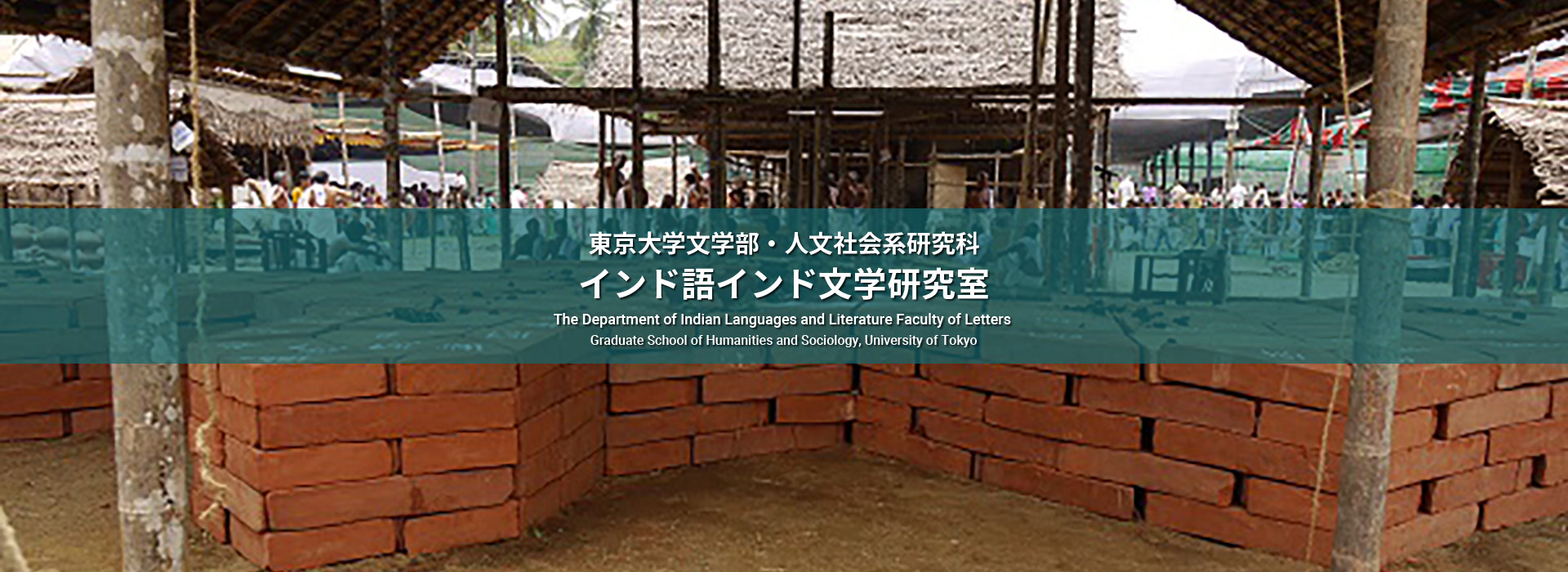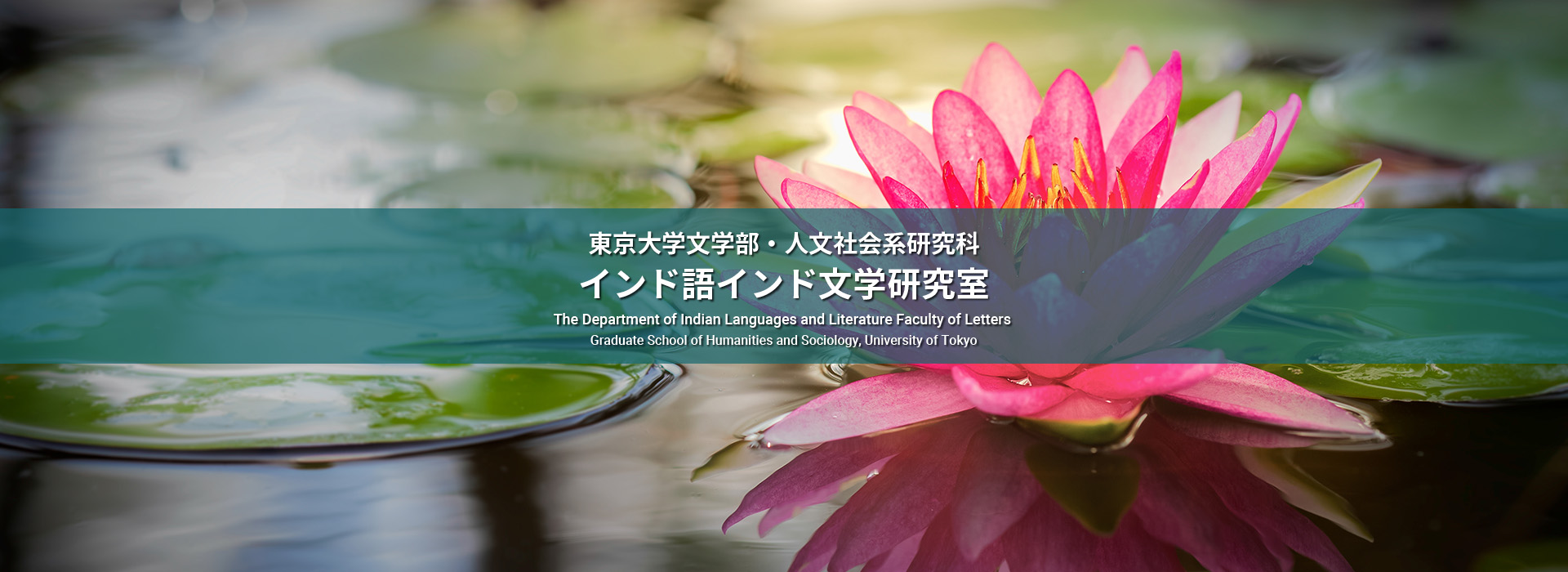教員
| 梶原 三恵子 教授 |
| 専門分野 |
| サンスクリット文献学を専門とする。 古代インドにおいて約一千年にわたって成立したヴェーダ文献を主資料として、各種の古代インド家庭儀礼の構造と発展を研究することによって、インド文明史の源流の一端を明らかにすることをめざしている。家庭儀礼の範疇に属する諸儀礼は、資料がヴェーダ新層からポスト・ヴェーダ時代の文献に集中しているが、これらを詳細に解析記述する作業を積み重ねるとともに、ヴェーダ初期および中期の文献に散見される断片的資料をも掘り起こすことによって、古代インドにおける諸家庭儀礼の原型とその発達・変遷をたどる。一方で、現代インドで行われている家庭儀礼の実態に注意を払い、古代ヴェーダ家庭儀礼との連続性および非連続性についても考察する。当面の研究課題はヴェーダ期の入門と学習に関連する諸儀礼である。入門・学習儀礼はヴェーダ文献の伝承と深く関わるものであり、これらを研究することで、ヴェーダの生成と伝承というインド学の大きなテーマに新たな光をあてることをもめざす。 |
| 主要研究業績 |
| “The `grhya’ Formulas in Paippalada-Samhita 20.” ZINBUN: Annals of the Institute for Research in Humanities, Kyoto University, No. 42, pp. 39-62, 2011.”On the Grhyasutra of the Vadhula School.” Journal of Indological Studies, Nos. 20/21, pp. 25-42, 2009.”The Upanayana and Marriage in the Atharvaveda.” The Vedas. Texts, Language & Ritual (ed. A.Griffiths and J.E.M.Houben), Groningen, pp. 417-431, 2004.「ヴェーダ入門儀礼の二つの相-通過儀礼と学習儀礼-」 『佛教学セミナー』78, pp. 1-20, 2003.『古代インドの入門儀礼』 法蔵館, 2021 |
| リンク |
| 梶原研究室HP/ researchmap |
| 友成 有紀 助教 |
| 専門分野 |
| 主な研究対象は,サンスクリットのインド土着の古典文法体系であるパーニニ文法学と,文学・哲学といった様々な学問分野におけるその受容である。およそ2500年ほど前パーニニによって編纂された文典『アシュターディヤーイー』は,サンスクリット文法をきわめて特殊な記号法を駆使して定式化したものであるが,これに対するカーティヤーヤナによる補修,パタンジャリによる注釈を経て(この三人は「三聖人」と呼ばれる),実に現代に至るまで権威とみなされている。しかし,このように古い文法的性格を伴ったサンスクリットといえども,他の自然言語と同様,様々なイレギュラーの発生は避け得ないものであり,言語活動と文法との間には,常に逸脱事例が生ぜずにはいられなかった。結果として,『アシュターディヤーイー』に対する補遺・補修は後代にまでわたって続けられることとなったが,オリジナルの文典を損なうことを良しとしないパーニニ文法学者たちによる文法解釈はしばしば大変難渋なものとなっていった。こういった理論の変遷をたどることで,現代まで続くサンスクリットという言語の文化的特性と,文典の意義を探ることが研究テーマである。 |
| 主要研究業績 |
| Tomonari, Yūki, 2016, “ākr̥tigaṇa: Mother for Grammatical Restrictions,” In: Vyākaraṇa-paripr̥cchā, Ed. by George Cardona, Hideyo Ogawa, pp. 337–369.友成有紀,2018, 「「正語介在説」について」,『東方』33 巻, pp. 97–117. |
| リンク |
| researchmap |