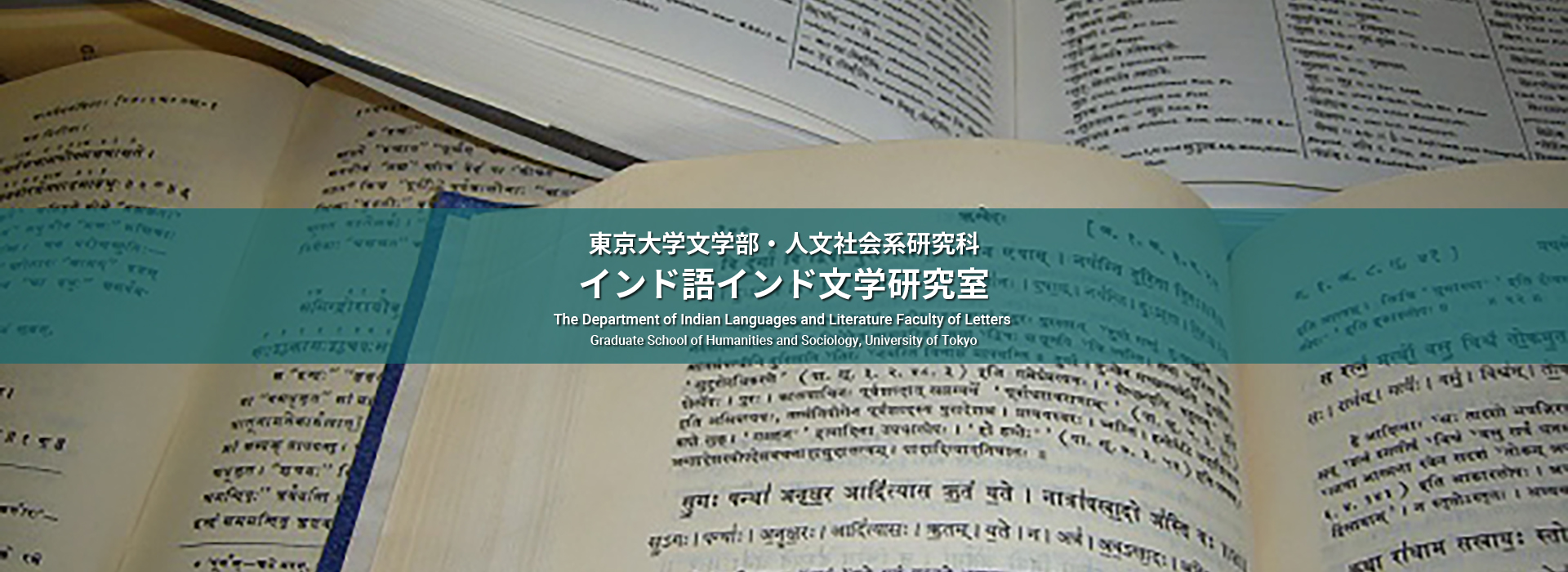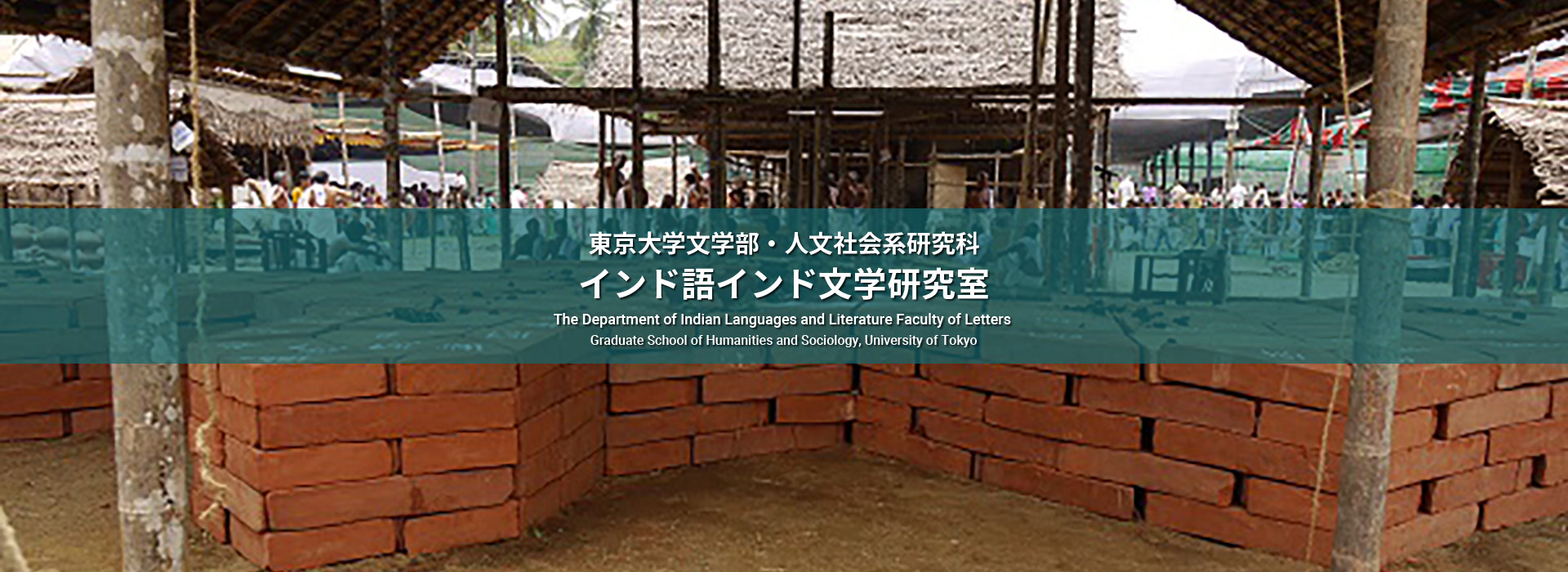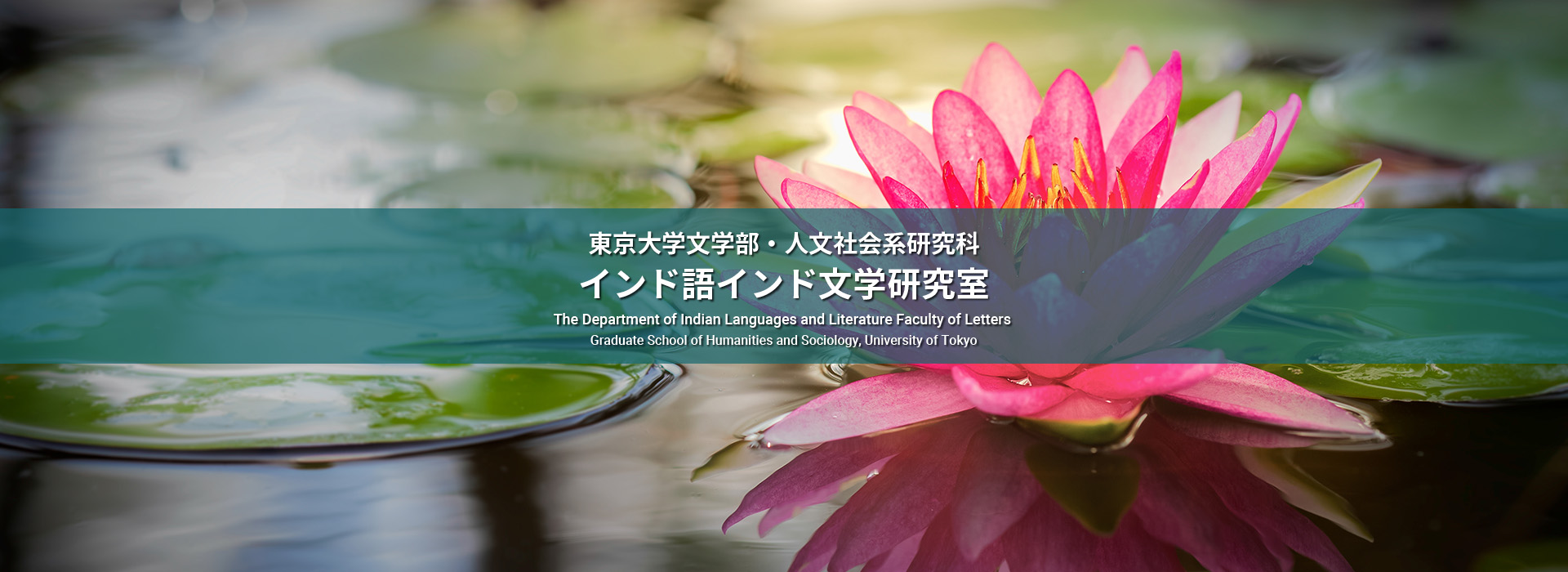研究室の授業
インド文学の対象とする時代も領域も広いですが、専任教員は目下のところ、サンスクリット語学文学担当の梶原と友成の2人です(専門、近年の関心事や研究等については、こちら)。
しかし、これら教員の専門研究が講義・演習にそのまま反映されるわけではなく、狭義の専門分野を越えて、インド古典のさまざまな領域の講義や演習が行われることが少くありません。
この他にも、2~3名を非常勤講師としてお招きし、それぞれの専門領域の講義を担当して頂いています。
必修科目としては、文学史概説・演習・特殊講義のほかに、語学概論が設けられています。
なかでも語学概論は、原典を読みこなすためにもっとも必要な語学力の習得を目指し、力を入れています。演習では、サンスクリット語・タミル語・パーリ語・プラークリット語の原典を講読していますが、特殊講義も実際は演習形式で行われることが少なくありません。
科目一覧(2025年度)
Sセメスター(S1・S2)
| 担当教員 | 授業科目名 | 副題 | 曜時 | |
| 職名 | 氏名 | 内 容 | 備考 | |
| 教授 | 梶原三恵子 | 印度語学印度文学演習Ⅲ | サンスクリット文献講読(Ⅰ) | 月・5 共通 |
| ヴェーダ文献から散文・韻文を選んで、参加者全員による輪読形式で精読する。サンスクリット語講読としては上級演習にあたる。 アクセントを保持しているブラーフマナ文献を中心に、ヴェーダ期の言語・宗教・文化を伝えるサンスクリット散文の読解訓練を行う。サンスクリット語の正確な読解のために、各種辞書・文法書などの使い方を指導する。あわせて、ヴェーダ文献およびヴェーダ宗教思想の基礎知識を解説する。 古いサンスクリット文に慣れておくことは、ヴェーダ文献のみならず、古典サンスクリットによる各種文学・哲学・宗教文献、および中期インド語文献を読む際にも大きく役立つので、専門にかかわらず、積極的に受講してほしい。 | ||||
| 印度語学概論 I | サンスクリット初級文法(Ⅰ) | 火・3 学部 | ||
| 古典サンスクリット語の初級文法を習得し、平易なサンスクリット文を読解する運用力を養成することをめざす。Sセメスターは、文法の前半部(音論、名詞・形容詞の変化)を扱う。 サンスクリット語は古代・中世インドで宗教聖典および各分野の学術書に用いられた古典語である。仏教などを通してアジアの諸地域の文化にも少なからぬ影響を与えた。また、印欧比較言語学分野においては、ギリシア語・ラテン語とならぶ重要な位置を占める。 授業は文法の解説と練習問題による演習を組み合わせて進める。 | ||||
| 印度語学印度文学演習 I | Sanskrit Reader 講読(Ⅰ) | 火・5 学部 | ||
| サンスクリット初級文法を修了した者向けの、中級講読演習である。比較的平易なサンスクリット文の読解練習によって、文法知識の定着をはかり、サンスクリット語の運用力を身につけることをめざす。 Ch. R. Lanman, Sanskrit Reader をテキストとし、『マハーバーラタ』の一部である「ナラ王物語」を主教材として、古典サンスクリットの読解訓練を行う。 | ||||
| サンスクリット語文献研究(Ⅰ) | サンスクリット文献研究(Ⅰ) | 木・2 大学院 | ||
| 担当教員と相談のうえで、各履修者が自分の担当するテキストを決め、それぞれテキストと訳を準備し、順番に講読発表して、授業参加者全員で、原文解釈およびテキストの内容について議論検討するゼミナールである。本授業の主な目的は、(1)多様な時代・ジャンルのサンスクリット文献を講読すること、(2)レジュメを準備しテキストと自らの解釈を説明することで、プレゼンテーションの訓練をおこなうことである。 | ||||
| 教授 助教 | 梶原三恵子 友成有紀 | 印度語学印度文学特殊講義Ⅰ | パーニニ文法学研究(1) | 水・5 共通 |
| パーニニ文法(pāṇinīya-vyākaraṇa)は,ヴェーダ・アンガ(補助学)として始められたとされるインド古典文法の伝統において最も権威的な体系であり,現代インドでもサンスクリット語の伝統文法として様々な学術機関で学習されている。サンスクリット語で著作する者にとって必須の教養であり,文学作品・哲学作品問わず様々な注釈文献は,この文法の知識なくしては正確に解読することができない。 本講義では,標準的な教科書とされるバットージ・ディークシタ著『ヴァイヤーカラナ・スィッダーンタ・カウムディー(以下VSK, 文法学者の定説の月光)』などのサンスクリット語によるパーニニ文法学習書の講読を通じて,パーニニ文法の概略を理解すること,特殊な技術が用いられている文法規則の表現方法に慣れ親しむことを目標とする。 春学期では基礎的な事項の概説・確認の後,VSKのテキストを読み始める予定であるが,必要に応じて予備的にヴァラダラージャ著『ラグ・スィッダーンタ・カウムディー』など他の文法学文献も参照する可能性がある。 | ||||
| 講師 | 髙橋健二 | 印度語学印度文学演習Ⅴ | マーハーラーシュトリー語の研究 | 金・5 共通 |
| マーハーラーシュトリー語はプラークリット諸語のうちの一つで、ハーラ作の『サッタサイー』や『ラーマーヤナ』のジャイナ教版の翻案作品である『パウマ・チャリア』などが知られる。本講義では、中期インド語における言語変化等を確認した上で、マーハーラーシュトリー語の文法の概要を解説し、実際に簡単な説話文学を講読する。 本講義の目的は、マーハーラーシュトリー語の習得を通じて、プラークリット諸語の特徴を理解するとともに、プラークリット語研究の方法を習得することである。 | ||||
Aセメスター(A1・A2)
| 担当教員 | 授業科目名 | 副題 | 曜・時 | |
| 職名 | 氏名 | 内 容 | 備考 | |
| 教授 | 梶原三恵子 | 印度語学印度文学演習Ⅳ | サンスクリット文献講読(Ⅱ) | 月・5 共通 |
| 担当教員と相談のうえで、各履修者が自分の担当するテキストを決め、それぞれテキストと訳を準備し、順番に講読発表して、授業参加者全員で、原文解釈およびテキストの内容について議論検討するゼミナールである。本授業の主な目的は、(1)多様な時代・ジャンルのサンスクリット文献を講読すること、(2)レジュメを準備しテキストと自らの解釈を説明することで、プレゼンテーションの訓練をおこなうことである。 | ||||
| 印度語学概論 Ⅱ | サンスクリット初級文法(Ⅱ) | 火・3 学部 | ||
| 古典サンスクリット語の初級文法を習得し、平易なサンスクリット文を読解する運用力を養成することをめざす。サンスクリット語は古代・中世インドで聖典に用いられ、仏教などを通してアジアの文化にも少なからぬ影響を与えた言語である。また、印欧比較言語学においてはギリシア語・ラテン語とならぶ重要な位置を占める。 サンスクリット初級文法は、S・A両セメスターをあわせて全体像を習得できるように設計している。Sセメスターは文法の前半部を扱い、Aセメスターの本授業では、それを受けて、文法の後半部(主として動詞)を扱う。 | ||||
| 印度語学印度文学演習Ⅱ | Sanskrit Reader 講読(Ⅱ) | 火・5 学部 | ||
| サンスクリット初級文法を修了した後の、中級講読演習である。比較的平易な文章の読解練習によって、文法知識の定着をはかり、サンスクリット語の運用力を身につけることをめざす。 Sセメスターの進度によっては、Aセメスター前半は、ナラ王物語の続きを読む可能性がある。 後半は、ヴェーダ期サンスクリット語のてほどきを行う。主教材に用いる Ch. R. Lanman, Sanskrit Reader の後半は、ヴェーダ期サンスクリット文献のアンソロジーと語彙集である。そのなかから、アクセント記号が付されているヴェーダ期散文をいくつか選んで講読する。 | ||||
| サンスクリット語文献研究(Ⅱ) | サンスクリット文献研究(Ⅱ) | 木・2 大学院 | ||
| 担当教員と相談のうえで、各履修者が自分の担当するテキストを決め、それぞれテキストと訳を準備し、順番に講読発表して、授業参加者全員で、原文解釈およびテキストの内容について議論検討するゼミナールである。本授業の主な目的は、(1)多様な時代・ジャンルのサンスクリット文献を講読すること、(2)レジュメを準備しテキストと自らの解釈を説明することで、プレゼンテーションの訓練をおこなうことである。 | ||||
| 教授 助教 | 梶原三恵子 友成有紀 | 印度語学印度文学特殊講義Ⅱ | パーニニ文法研究(2) | 水・5 共通 |
| パーニニ文法(pāṇinīya-vyākaraṇa)は,ヴェーダ・アンガ(補助学)として始められたとされるインド古典文法の伝統において最も権威的な体系であり,現代インドでもサンスクリット語の伝統文法として様々な学術機関で学習されている。サンスクリット語で著作する者にとって必須の教養であり,文学作品・哲学作品問わず様々な注釈文献は,この文法の知識なくしては正確に解読することができない。 本講義では,標準的な教科書とされるバットージ・ディークシタ著『ヴァイヤーカラナ・スィッダーンタ・カウムディー(以下VSK, 文法学者の定説の月光)』などのサンスクリット語によるパーニニ文法学習書の講読を通じて,パーニニ文法の概略を理解すること,特殊な技術が用いられている文法規則の表現方法に慣れ親しむことを目標とする。 秋学期では春学期に引き続きVSKのテキストを読み始める予定であるが,必要に応じて予備的にヴァラダラージャ著『ラグ・スィッダーンタ・カウムディー』など他の文法学文献も参照する可能性がある。 | ||||
| 講師 | 髙橋健二 | 印度文学史概説Ⅰ | インド古代・中世の文学・文献案内 | 木・2 学部 |
| 本講義では古代から中世におけるインド文学・文献の歴史を辿る。本講義の目標は、古代インド文献の歴史の概要を理解すること、また古代インド文化に通底する古代インドの人々の思考法や感受性を理解することである。なお、開講科目では「文学史」とあるが、本講義では、詩や戯曲といった文学作品だけでなく、祭式文献、法典文献、科学文献や宗教文献など、サンスクリット語をはじめとするインド諸語で書かれた文献群も扱うこととする。 前半の1-8回は、さまざまなインド文献に通底する基層的文化の歴史的展開を追う。古代インドで学術言語、文芸言語として用いられてきたサンスクリット語の最古の文献は、祭式学文献である。講義では、古代インドの祭式文化がどのようなものであり、祭式学的世界観から言語観、社会観、宗教観がどのように発展したのかを探る。後半の9–13回では、サンスクリット美文学の歴史を概説する。講義では、翻訳を通していくつかの文学作品や詩論等を実際に読み、古代インドの豊かな文学世界がどのように発展していったのかを検証する。 | ||||
| 講師 | 髙橋健二 | 印度語学印度文学演習Ⅵ | サンスクリット叙事詩の研究 | 木・3 共通 |
| 本講義では『マハーバーラタ』におけるインドラによるカルナの耳輪・鎧の奪取の場面(第3巻284-294章)を講読する。この部分は、『マハーバーラタ』でも特に人気のある部分で、後世の文学作品等においても多く言及され、また様々な翻案作品が著されてきた。本講義では、底本としてプーナ批判校訂版を用いながら、一つ一つの詩節について、異なる解釈や異読などを韻律論・語形論・統語論・内容等の観点から丁寧に検証しながら読み進める。本講義の目的は、叙事詩の内容に親しむとともに、叙事詩文献の研究方法を習得することである。 | ||||
| 講師 | 横地優子 | 印度語学印度文学特殊講義IV | スカンダプラーナ研究 | 集中 共通 |
| サンスクリット文献の中でも、プラーナというジャンルの作品群は、特定の作者が存在せず集団で制作されている点、ジャンル内の作品間のIntertextualityが非常に高い点、伝承過程での作品の改変がかなり自由に行われていたと思われる点などで、個々の作品研究が難しく、遅れている分野である。この授業では、その中でも比較的初期に作られ、プラーナ文献としては現存最古の写本が残っている『スカンダプラーナ』(5—6世紀成立)を取り上げ、特にシヴァの喉がなぜ黒くなったのかというNilakantha神話を語る第114章を中心として、他の作品とのIntertextualityや伝承過程、制作過程を学ぶ。それによって、インド中世社会におけるヒンドゥー教、特にシヴァ信仰の状況と、その歴史的変遷についてより深い知見を得ることができる。 | ||||