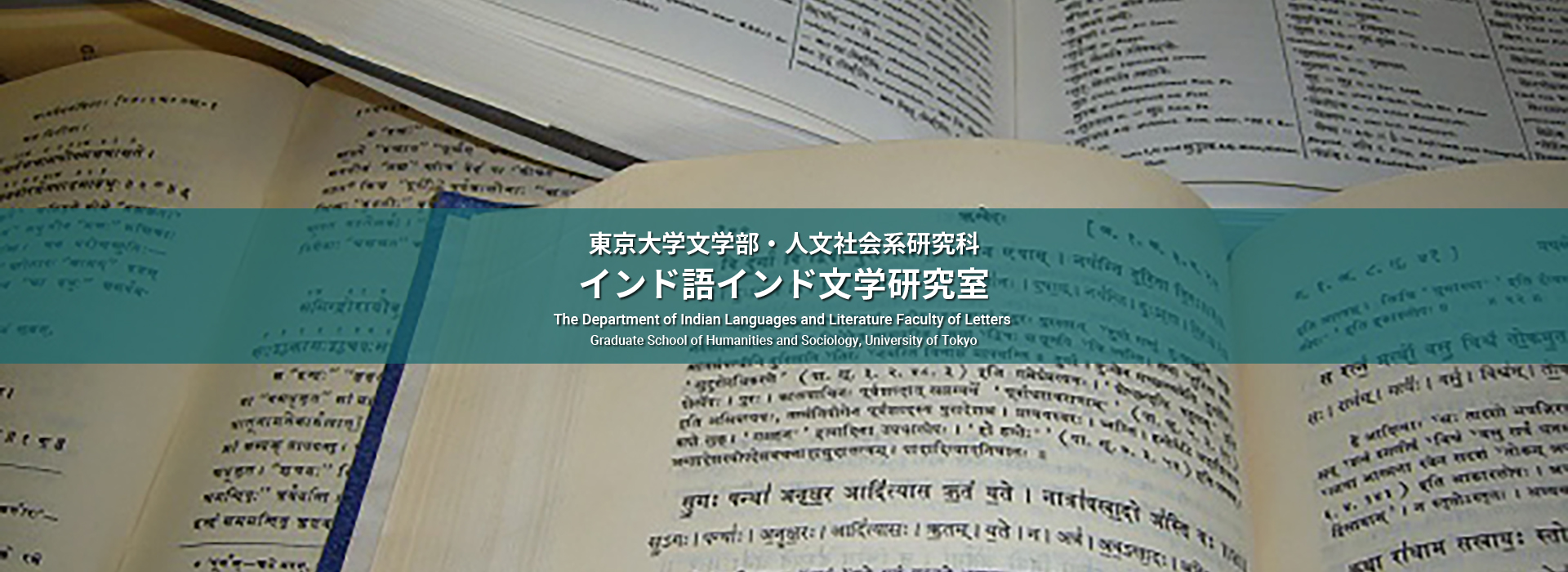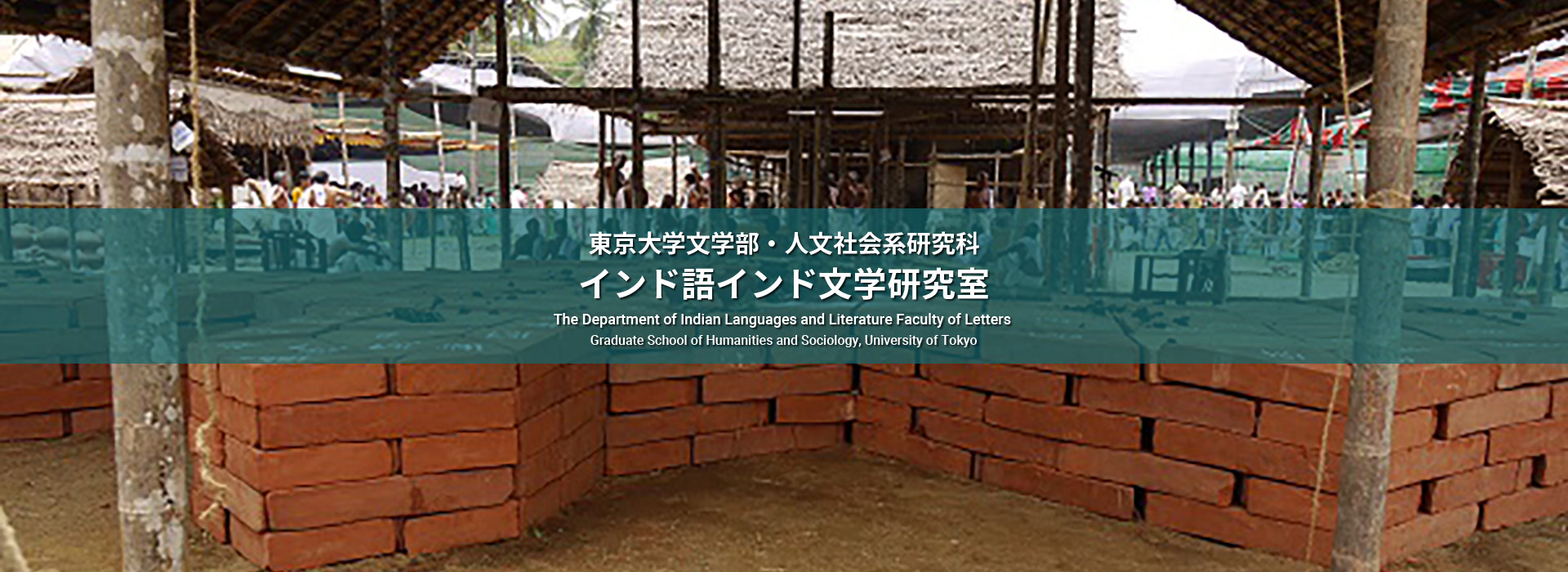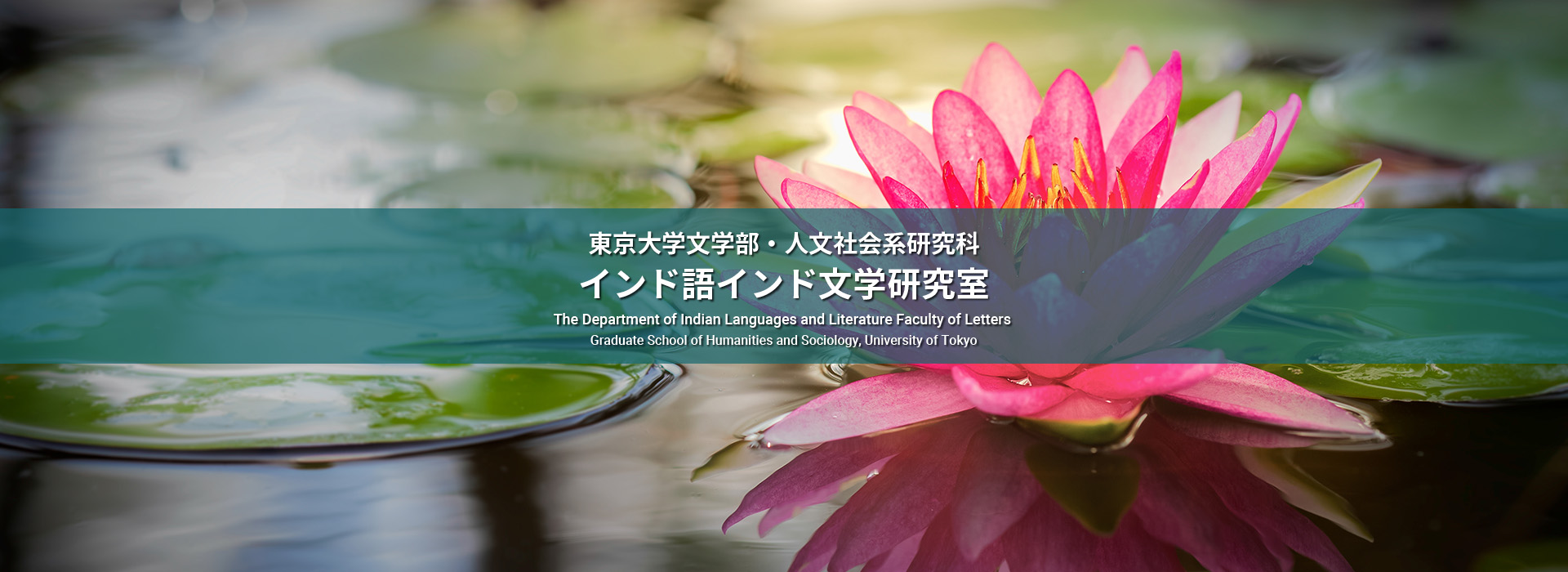タミル文学史の概観
(注意:以下でのタミル語表記は このように なっています。ただし、固有名詞など本来の大文字、たとえば本来の T は &t のように表記されています。)
はじめに
タミル語は、ドラヴィダ語族に属する25以上の言語のひとつである。
同語族のうち、固有の文字文化をもつものに、テルグ語、タミル語、カンナダ語、マラヤーラム語(話者人口の多い順)があるが、タミル文学が紀元前後に始まり、サンスクリット文学の影響をほとんど受けていない独自の古典文学をもつのに対し、他の三語による文学は、いずれもはるか数世紀も経て、サンスクリット文学の翻訳あるいはその影響を色濃く受けた作品から始まっている。
そのためタミル文学はドラヴィダ文化を代表するものとみなされている。
古典文学期(紀元前100~後250年)
現在のタミル・ナードゥ、ケーララの両州にあたる地域は、当時チョーラ、チェーラ、パーンディヤの古代三王朝や幾多の族長によって統治されていた。
文学活動はかなり盛んで、『トルハーッピヤム(&tolkaappiyam, 「古き文典」)』(3章27節、約1600詩節)や二大詞華集—『エットゥトハイ(&eTTuttokai, 「八詞華集」)』と『パットゥパーットゥ(&pattuppaaTTu, 「十の長詩」)』—が残されている。
前者は音韻論、形態論などのほかに詩論も含む広義の文法書である。後者は、宮廷などを中心に活躍していた多くの詩人の作品を、長さや内容などにより分類編纂したもので、古代パーンディヤ王朝の首府マドゥライに存在していたとされる文芸院サンガム(またはシャンガム)にちなんで、サンガム文学とも呼ばれている。
それは470余の詩人による、総計約2380の詩からなるが、各々の詩の行数にはおおきなばらつきがある(3~782行)。内容は、男女の愛を主題にしたアハム(akam, 原義は「内」)と、英雄行為などを主題にしたプラム(puRam, 原義は「外」)とに二大別できるが、このうちアハム文学は量的に古典文学の4分の3以上を占め、後世の文学にも大きな影響を与えた。
古典文学後期(後250~600年)
古代三王朝は衰え、カラブラ(5世紀ごろ)そしてパッラヴァ朝(6世紀)と、北インド文化との関りの深い勢力が台頭する。それにともない、ジャイナ教、仏教、バラモン教もタミル文化に浸透し始め、文学では宗教的・箴言的な作品が現れる。
それらのうち最も有名なのが、1330の二行詩からなる箴言詩集『ティルックラル(&tirukkuRaL, 「聖なるクラル」)』で、アラム(aRam)、ポルル(poruL)、カーマム(またはインパムi_npam)の3章に分かれ(これらは概ね、サンスクリットのダルマ、アルタ、カーマに相当する)、道徳、宗教、国家や社会、家庭や個人生活、それに愛などを説く。
この作品は他の箴言詩集などとともに『パディネンキージュカナック(&pati_neNkiiZkkaNakku, 「十八の小品」)』におさめられている。
これらに続く時期には、叙事詩も現れる。『シラッパディハーラム(&cilappatikaaram, 「踝環(かかん)物語」)』(5世紀ごろ)は、イランゴー(&ilaGkoo または &iLaGkoovaTikaL、チェーラ王子とされる)作のタミル文学史上初の叙事詩で、貞節な女カンナギ(&kaNNaki)の説話を、夫コーヴァラン(&koovara_n)と踊り子マーダヴィ(&maatavi)との愛や夫の不幸な死などをおりまぜて展開させる(全30篇)。
これと対をなす叙事詩『マニメーハライ(&maNimeekalai, 「宝石の帯」)』(6世紀?)は、コーヴァランとマーダヴィとのあいだに生まれた娘マニメーハライの悩みや修行生活を、仏教教理をおりまぜて描く仏教色の濃い作品で、作者はサーッタナール(&caatta_naar)である(全30篇)。
この時期の作品には、劇や音楽の要素が入りこんでくる。
バクティ文学期(600~900年)
この時期はタミルの宗教・社会・文化に、最も大きな変革をもたらした時期である。タミル全土にバクティ(bhakti, 神に対する熱烈な帰依信仰)の気運が盛りあがり、それまで優位にあったジャイナ教、仏教は徐々に排斥され、古典は過去のものと考えられるようになる。
当時、北はパッラヴァ王朝、南はパーンディヤ王朝に統治されていたが、為政者の支持を得てシヴァ教や、ヴィシュヌ教が勢いを増す。ヒンドゥー寺院の建立もさかんとなり、宗教詩人たちはこれらの寺院をわたり歩きつつ、シヴァ神やヴィシュヌ神に対するバクティをタミル語で唄いあげた。彼らの言語は平易で音楽的要素に満ちていたため、民衆にも受けいれられた。
彼らの宗教詩(讃歌)は後にまとめられ、『ティルムライ(&tirumuRai、「聖なる秩序」)』(シヴァ派聖典)、『ディヴヤプラバンダム(&tivviya-p-pirapantam または &divviya-prabandham、「聖なる作品集」)』(ヴィシュヌ派聖典)と総称される。
前者には初期(7~8世紀)の三聖人、サンバンダル(&campantar)、アッパル(&appar、別名 &tirunaavukkaracar)、スンダラル(&cuntarar)の作品をおさめた『デーヴァーラム(&teevaaram、「神への讃歌」)』マーニッカヴァサガル(&maaNikkavacakar)の『ティルヴァーサガム(&tiruvaacakam、「聖なる言葉」)』(9世紀ごろ)、伝説を盛り込みつつシヴァ派の63聖人ナーヤナール(naaya_naar/ naaya_nmaar、6~8世紀ごろ)を描いたセーッキラール(&ceekkiZaar)の『ペリヤプラーナム(&periyapuraaNam、「大古譚」)』(12世紀ごろ)などがある。
後者はヴィシュヌ派聖人アールヴァール(aaZvaar、7~10世紀の12人)の作品をおさめるが、アーンダール(&aaNTaaL、9世紀)の『ティルッパーヴァイ(&tiruppaavai、「乙女の祈願」)』やナンマールヴァール(&na_nmaaZvaar、10世紀)の『ティルヴァーイモジ(&tiruvaaymoZi、「聖なる真理の言葉」)』などが有名である。
中世文学前期(900~1200年)
チョーラ王朝のもとで、歴史上最も栄えた時期である。ヒンドゥー寺院の建立は続き、寺院が人々の生活で大きな位置を占めるようになる。ジャイナ教、仏教は後退し、シヴァ派が圧倒的な勢力をもつようになる。古典文学は文人や注釈家だけのものになり、作品としてはサンスクリット文学の影響の濃いものが多くなる。
ヒンドゥー教の隆盛とともに多量のサンスクリット語彙がタミル語に入り、両者の混じりあったマニプラヴァーラ(maNipravaaLa)という語体が生まれる。マラヤーラム語がタミル語の西域方言から発展し、独自の言語となるのもこのころである。
この時期にはジャイナ教徒ティルッタッカデーヴァル(&tiruttakkateevar、10世紀?)の『ジーヴァハチンターマニ(&ciivakacintaamaNi、「ジーヴァハンの如意珠」)』など、前代にひきつづきジャイナ教徒や仏教徒により幾篇かの叙事詩が書かれたが、最も重要なのは「詩人の皇帝」カンバン(&kampa_n、9/10/12世紀説あり)の『イラーマーヴァダーラム(&iraamaavataaram、「ラーマの降臨」)』(通称『カンバラーマーヤナム(&kamparaamaayaNam)』)である。
これはヴァールミーキの『ラーマーヤナ』の枠組にしたがいつつ、タミルの伝統をふまえ翻案したもので、6篇約10500の4行詩からなるタミル文学中最長の作品である。先述した『ペリヤプラーナム』もこの時期の重要な作品である。
一方、古典文学に対する注釈書や、伝統的文法書も書かれるようになる。12世紀末にジャイナ教徒パヴァナンディ(&pavananti)によって書かれた『ナンヌール(&na_n_nuul、「良き書」)』(461詩節)は、中世を代表する文法書である。
中世文学後期(1200~1750年)
チョーラ王朝の衰亡、ムスリム勢力の侵入、4王国抗争の時代、そしてヴィジャヤナガル朝の確立と続くこの時期は、文学上は衰微期である。
ヴィジャヤナガル王朝(14~16世紀)は熱心にヒンドゥー教を支持したため、各地の僧院(マタ)では学問研究が盛んになり、多くの哲学的作品がマニプラヴァーラム体で書かれた。
メイカンダール(&meykaNTaar、14世紀)は『シヴァニャーナボーダム(&civaJaa_napootam、「シヴァ神智明解」)』などの作品で、シャイヴァ・シッダーンタ派の基盤を固めた。知やヨーガの行を重んじるシッタル(cittar、成就した者)たちが最も活躍したのもこの時期で、宗教史の偉人ターユマーナヴァル(&taayumaa_navar、18世紀)もシッタルの系列につらなる。
サンスクリットのプラーナをもとに、数々のプラーナもタミル語で書かれた。
古典への注釈も文学の一分野として確立するが、代表的な注釈家としてはイランブーラナル(&iLampuuraNar、12世紀)、ナッチナールキニヤル(&nacci_naarkki_niyar、14世紀)、パリメーラリャハル(&parimeelaZakar、14世紀)をあげられよう。
7世紀ごろから発達しはじめた種々の詩作様式プラバンダ(prabandha)は、17世紀ごろまでには96種を数えるようになっていたが、この時期にはアンダーディ(antaati)、ウラー(ulaa)、カランバハム(kalampakam)、コーヴァイ(koovai)、ピッライタミル(piLLaittamiZ)などの分野で多くの作品が著わされた。
タミル地方のムスリムはタミル語を使用していたが、ウマルプラヴァル(&umaRuppulavar、17世紀)はムスリム文学の最高峰である。
15世紀末のポルトガル人の侵入以来、キリスト教も広まり始めたが、宣教師たちは不況のみならず、盛んに文学活動もした。なかでも、イタリア人宣教師ベスキ(J.C.Beschi、1680~1746)は、タミル語の文法書や辞書を作り、タミル語で多くの作品を書いた。
近代文学前期(1750~1900年)
イギリスのインド支配の時期である。前代に続き、ムスリム文学、キリスト教文学は盛んである。西欧の宣教師たちの活躍により、印刷術が広まり識字率も高まる。ジャーナリズムも発達し、それとともに散文が発達する。
これまでにも注釈文献などに散文は見られたが、この時期には口語もとりいれ、やがて19世紀には散文による本格的な文学も現れる。 ラージャム・アイヤル(Rajam Iyer、1872~98)やジャフナのアールムハ・ナーヴァラル(&aaRumuka &naavalar、1822~76)はその代表的作家である。
一方、西欧の文物に刺激されたタミル知識人は、自らの文化を振り返るようになる。こうして19世紀後半には忘れ去られていた古典が堀りおこされ、次々と出版されるようになる。この「古典の再発見」にもっとも大きな功績を残したのがスヴァーミナタ・アイヤル(U.V.Swaminatha Iyer、1855~1942)とダモーダラム・ピッライ(S.V.Damodaram Pillai、1832~1901)である。
宗教文学では、シヴァ派のイラーマリンガ・アディハル(&iraamaliGka &atikaL、1823~74)が大きな足跡を残した。
近現代文学期(1900年以降)
古典以来の文学伝統をふまえ、口語を盛りこんだ詩や散文により近代文学を確立させたのはスブラマンヤ・バーラティ(Subrahmanya Bharati、1882~1921)である。彼は『郭公の歌(&kuyil-paaTTu)』や『クリシュナの歌(&kaNNa_n-paaTTu)』などの傑作をものし、一方ではイギリス支配に対し民族意識を高揚させた。
散文では、読みやすい文体でおもに歴史小説を書き、また雑誌アーナンダヴィハダン(&aa_nantavikaTa_n)などを主宰したカルキ(&kalki、1899~1954)、社会派小説のアヒラン(&akila_n、1922~)、短編小説の領域を確立させたプドゥマイピッタン(&putumaippitta_n、1904~48)などがいる。
古典の再発見はタミル人に誇りをもたせ、政治的、文化的、社会的な要素とあいまって、タミル民族意識を高揚させ、やがて反バラモン運動へと発展し、激しい対立をひきおこしている。
現代文学の背景には、このような複雑な情況に加え、過去の栄光という重圧がある。しかし、50年代末からの「新しい詩」運動に見られるごとく、新たな文学への動きも活発である。
(本稿は、早島鏡正監修『仏教・インド思想辞典』(春秋社、1987年、393~395頁)所収の拙稿に手を加えたものである。)