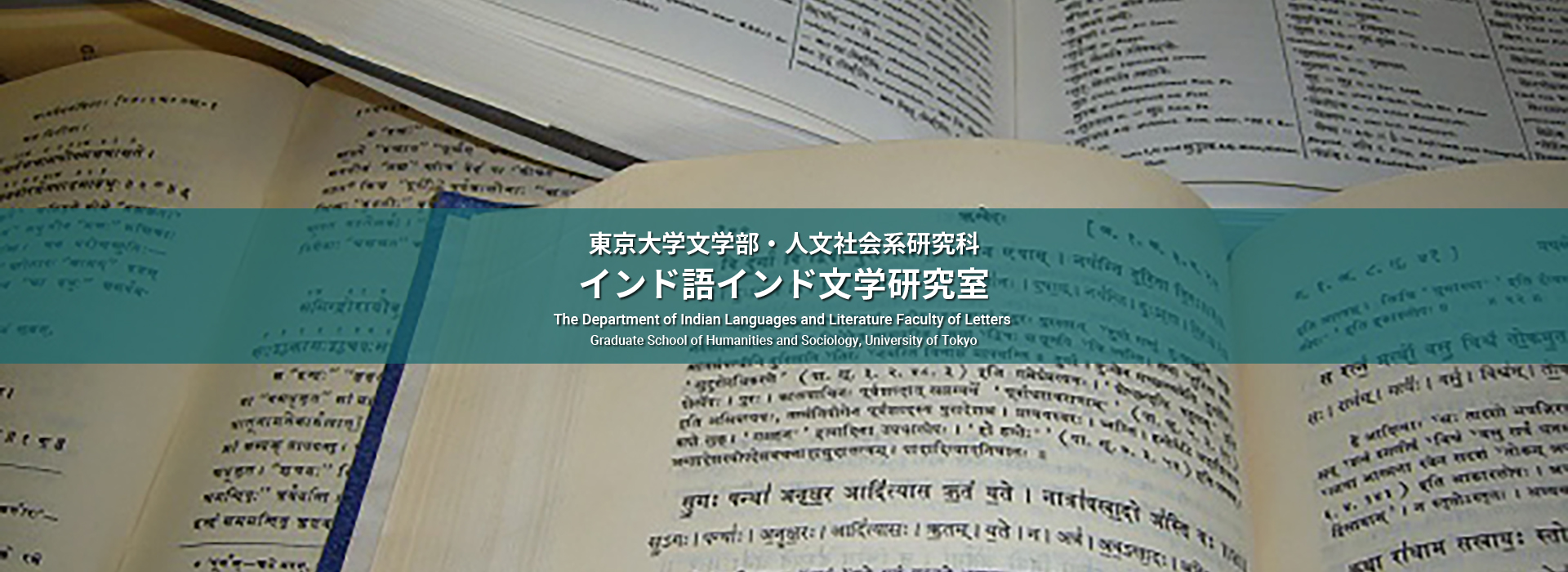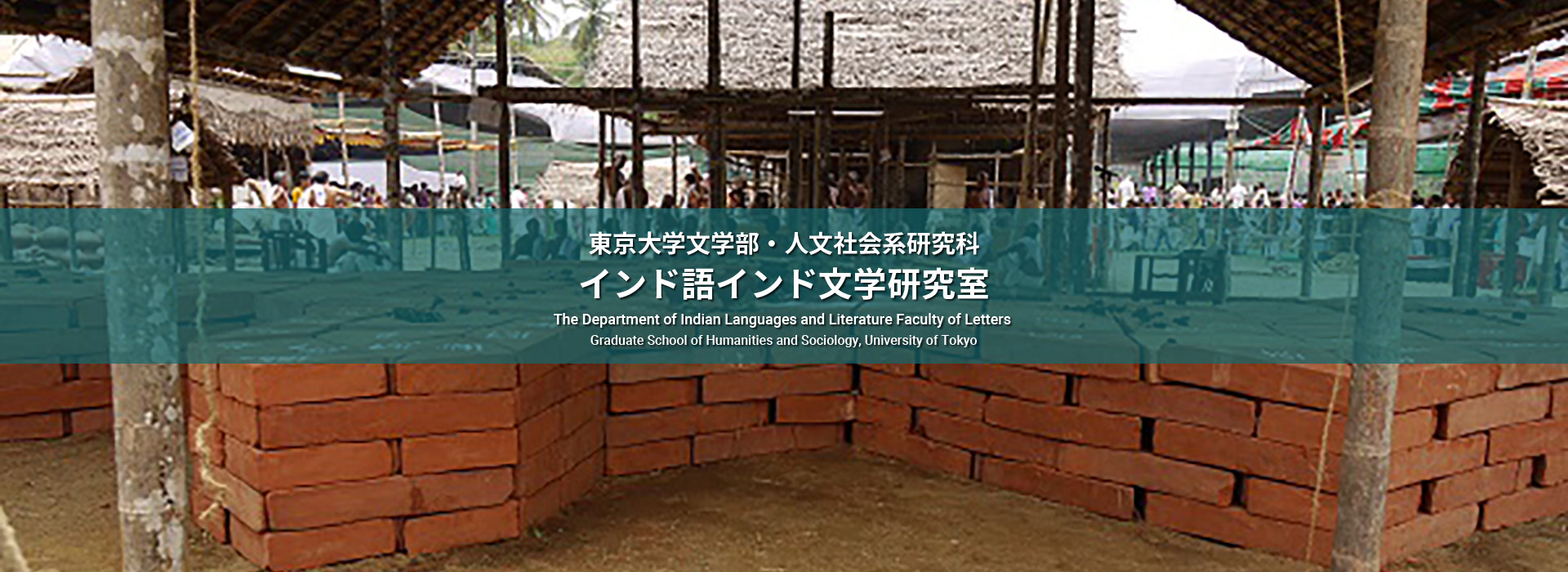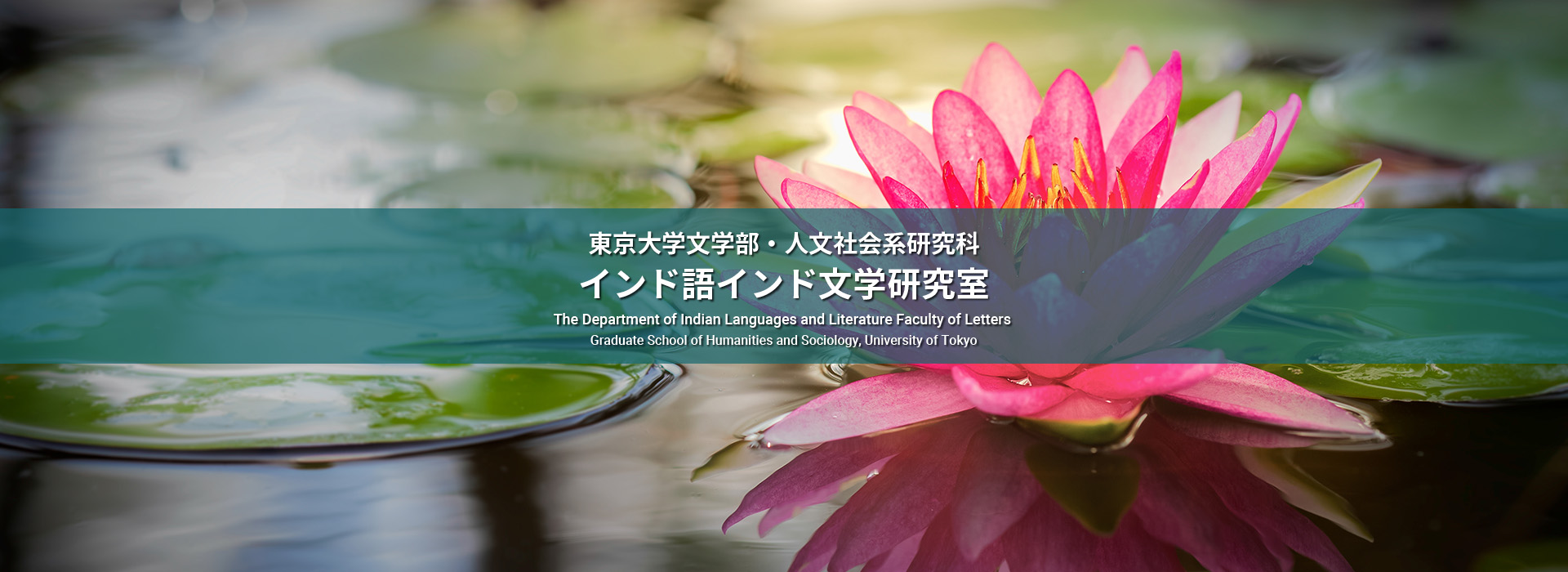研究室概要
ゼロから始めるインド文学
これは、われわれの研究室の標語です。「ゼロ」とはインドで発明された概念ですが、なにもないものを数値化・実体化、つまりゼロという「もの」としたインド人の知恵には驚かされます。
わが国では、現実のインドのみならず、数千年におよぶインドの文化についてもあまり知られていません。
たとえば、環境にたいし議論の高まる昨今、「環境に優しい」とはよく言われることです。
しかし、紀元前5世紀ごろのインドで、仏教とほぼ時期を同じくして成立したジャイナ教では、自殺を理想的な死とします。というのも、人は生きれば生きるほど微生物をふくめた他の生物を殺すことになり、罪が増えるわけですから、おのれが死ぬことが罪を犯さない最高の方法だからです。環境を破壊しているのは間違いなく人間です。ジャイナ教的な発想の断片でもあれば、「環境に優しい」というのは、いささか欺瞞に満ちてはいないでしょうか。
国際化が叫ばれるようになって久しいのですが、上の例からも明らかなように、内実は寂しい限りです。それどころか、たしかに国際化が進んでいる分野もありますが、他方では、目先の国内事情にのみ腐心する傾向もますます強くなっています。東洋・西洋といった区分に大きな意味があるとは思えませんが、かりにその区分を用いるなら、インドはちょうどそのはざまに位置します。これまでの文化志向では見えなかったものが、インド文化を学ぶことによって見えてくると思われます。
研究室名称について
インドには数百の言語がありますが、「インド語」というものは存在しません。それにもかかわらず「インド語インド文学研究室」と名乗っているのは、東京大学文学部の文学系の学科(正式には「言語文化学科」)では、たとえば「フランス語フランス文学研究室」とか「ドイツ語ドイツ文学研究室」というように、対象とする文学名にその言語名を冠することになっているからです。
ちなみに、研究室の英語名は Department of Indian Languages and Literatures(インド諸語諸文学学科)と、言語も文学も複数形になっていて、この方がある意味では正確なのですが、上に書いたように他研究室(学科)と横並びにしています。
なお、われわれの研究室はしばしば「印文」という略称で呼ばれています。
研究室の歴史
インド文学は、質と量のいずれにおいても世界に冠たる文学であり、アジアのみならず西洋にも少なからぬ影響をあたえてきました。そこで、世界の主要大学はインド学(インド文学・哲学を中心とした関連諸学)の講座をもってます。
わが国でもインド文学講座(当初の名称は「梵文学講座」)の歴史は古く、東京大学に開設されたのは明治34(1901)年です。
以来、古典サンスクリット語を中軸とする古期・中期インド・アーリア語をもって著された
文献の研究がなされてきましたが、平成8(1996)年より、タミル語タミル文学の講座も設けられこれにより、専門的なドラヴィダ系語学文学の研究に携ることも可能になり、現在にいたっています。