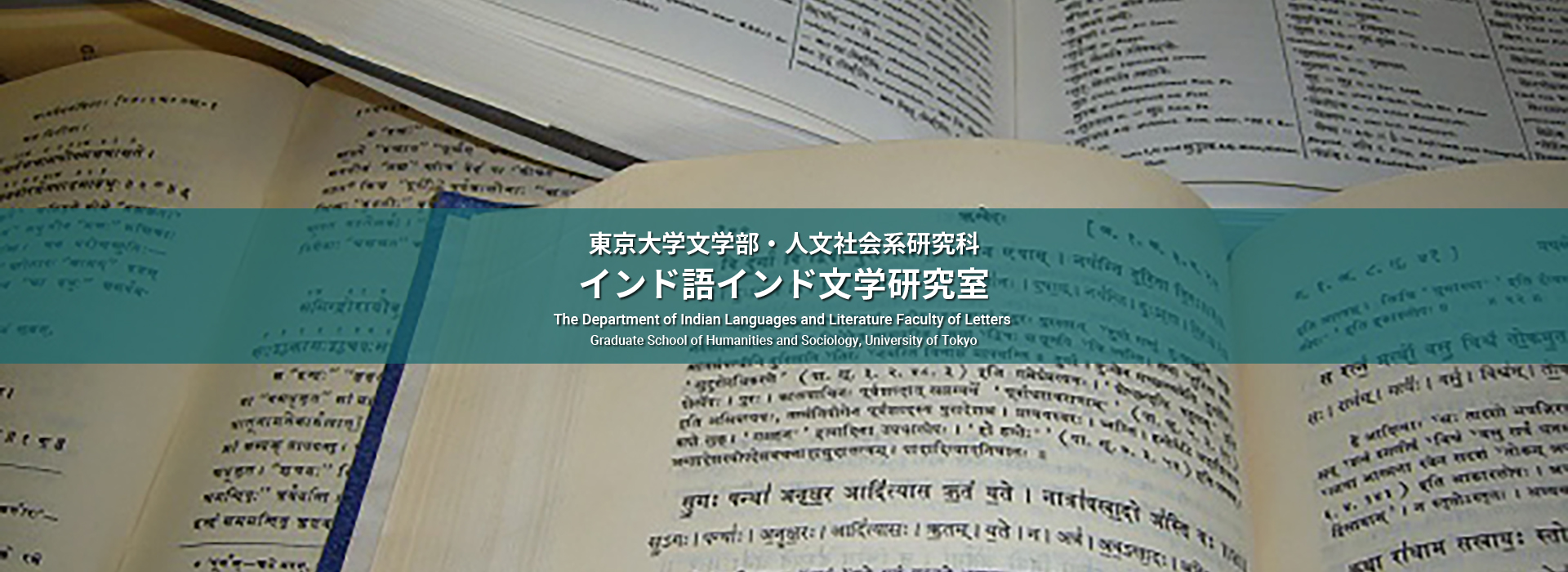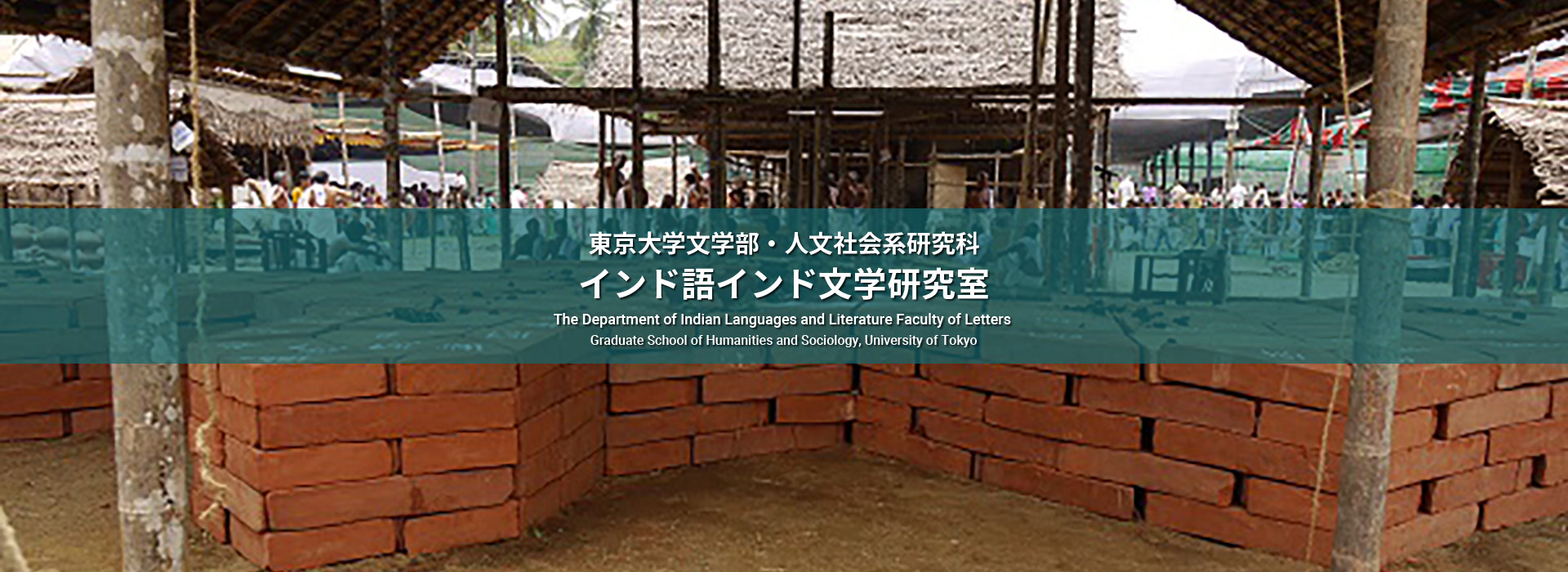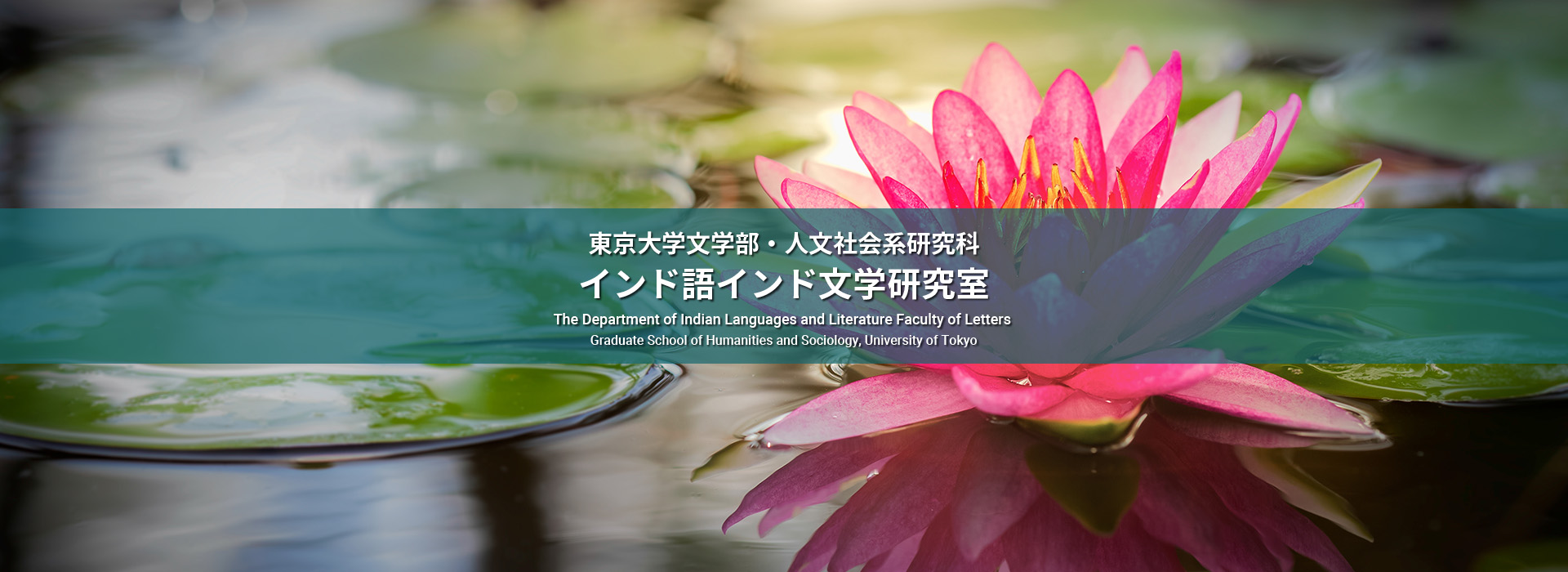タミル語について
タミル語は、インド亜大陸南部を中心に用いられるドラヴィダ語族*に属する言語の一つです。話者人口はインド国内だけで6千万人を超え、国外ではスリランカ、南アフリカ、シンガポール、マレーシアなどに千万人以上います。
ドラヴィダ語族(Dravidian)に属する言語は、今日では少なくとも26が数え上げられています。18世紀末から、主に西欧の宣教師たちによってサンスクリット語などとは系統を異にする言語が見つけられていました。1856年、ドラヴィダ言語学の創始者コールドウエル(R.Caldwell, 1814~91, 英)は、それらの言語のなかで、タミル語が歴史においても内容においても代表的な存在であること、古サンスクリット文献でタミルを話す人々あるいは地域を、draviDaまたはdraaviDaと呼んでいることからDravidianという語を造語し、それら諸言語を呼ぶ語族名としました。
歴史
タミル語の最古の記録は、紀元前3世紀ごろの碑文です(この碑文は、言語はタミル語、文字はブラーフミー文字なので、タミル・ブラーフミー碑文と言います)。以後タミル語は、今日まで2千年以上にわたって用いられてきていますが、文法や語形の変化によって、大雑把に言って後6世紀頃までの古タミル語、7~18世紀頃の中期タミル語、それ以降の近現代タミル語に分けることができます。
文語と口語
音の記録が残っていない近代以前のタミル語については分かりませんが、現代タミル語では、書き言葉(文章語)と話し言葉(口語)とは、これが同じタミル語かと思えるほど違います。
方言
わが国で方言というと「ある地方の言葉という意味で使いますが、かつては「お武家言葉」とか「商人言葉」というようなものがありました。前者を地域方言(regional dialect)、後者を社会方言(social dialect) と言いますが、タミル語にはこれら両方言がそれぞれたくさんあります。
インドで社会方言といえば、まずはカーストによる方言です。例えば、バラモンが使うバラモン方言やキリスト教徒のクリスチャン方言のようなものです。
厄介なのは、バラモン方言を除くと、他の社会方言は地域によって異なるということです。ですから、チェンナイ(マドラス)のクリスチャン方言とマドゥライのクリスチャン方言は異なります。
標準語
では、標準語というものはないのでしょうか。人によってはタミルナードゥ州中部の、ティルチからタンジャヴールあたりのタミル語が標準的なタミル語だと言います。しかし、それはどうやら一番癖がないということのようです。ですからテレビのニュースで、その標準タミル語が用いられているかと言うと、そんなことはなく、テレビ局のあるチェンナイ(マドラス)方言が使われています。タミル人にとっては、「標準語」など、どうでもいいようです。
タミル語文法
では、われわれはどのようなタミル語を学んだらいいのでしょうか。普通、文法書は長い間の経験則から、近現代の散文のタミル語が読めるように配慮されています。
それは、文字に譬えれば、楷書体を学ぶようなものです。楷書体を学んでおけば、各人の手書きの文字(多様な方言やその口語体)も慣れれば読めるようになります。
われわれが学ぼうとするタミル語も同様です。近現代のタミル語散文を読めるようにして、それから口語に進むなり、古典語に進むようにします。