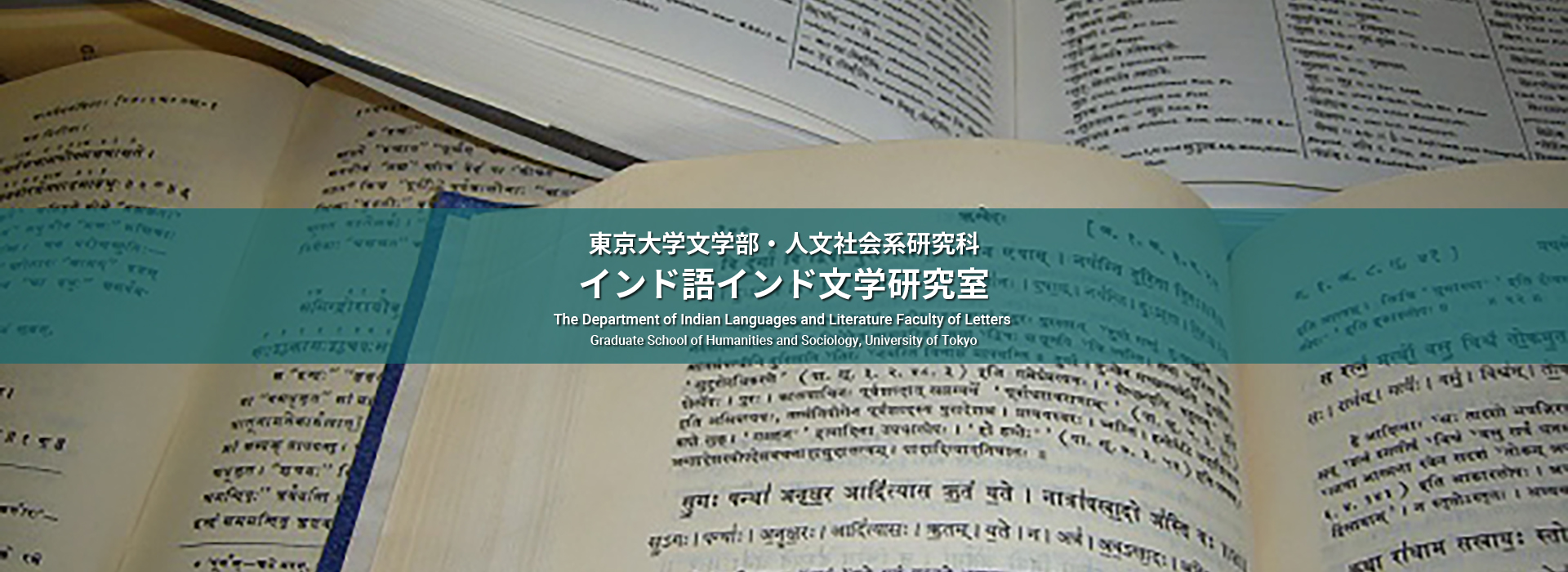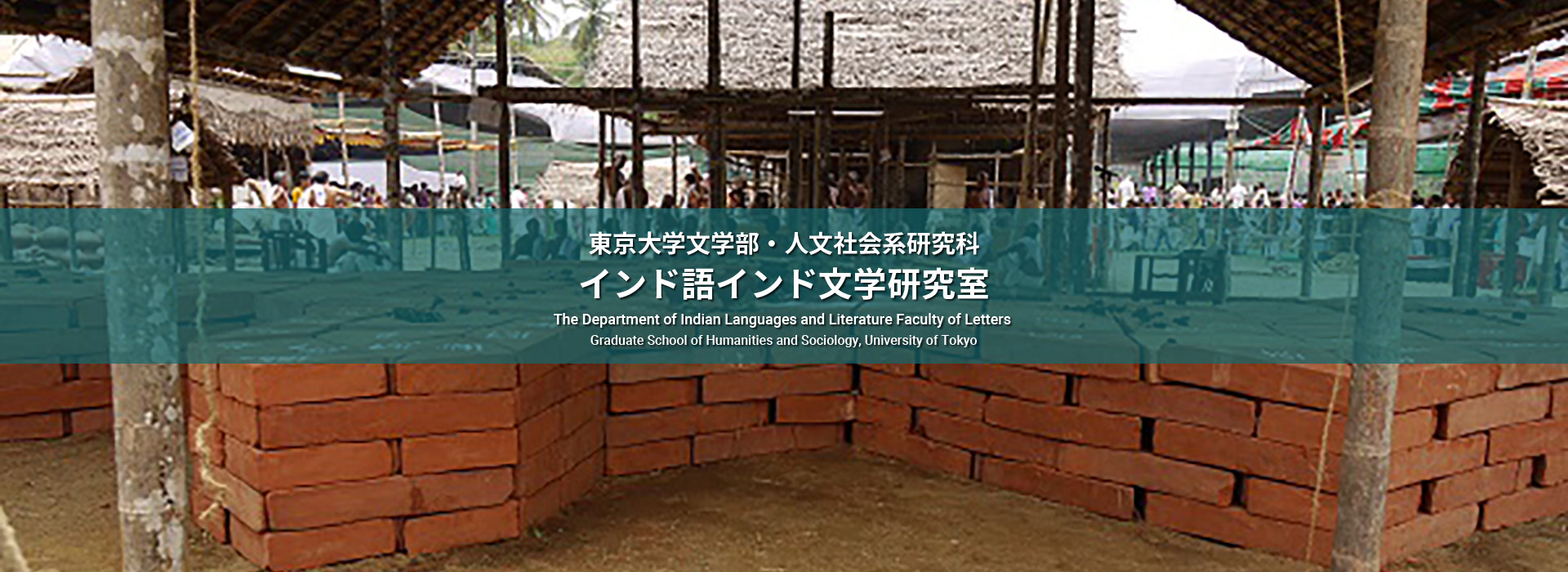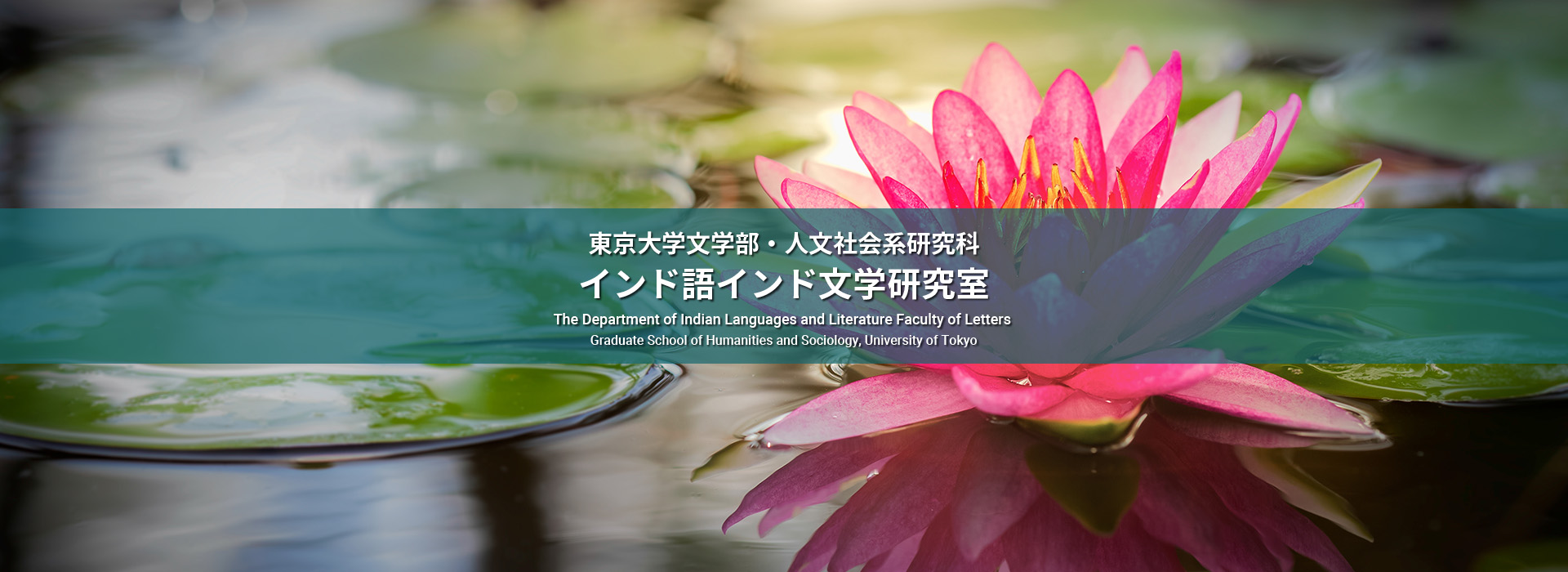サンスクリット語とは
印度では昔から時代ごとに地方ごとに實にさまざまの言語が用ゐられてきました。これら多数の言語はインドアーリヤ語系とドラヴィダ語系に二大別することができますが、この他にもシナチベット語系やオーストロアシア語系の言語も用ゐられてゐます。インドアーリア語系諸言語の中で、最重要なものはなんといってもサンスクリット語でせう。サンスクリット語は、婆羅門教・ヒンドゥー教の聖典の言語として、また高尚学藝一般の文語として、さらに王侯・学者・智識人の共通語として、古代から現代に至るまで弘く用ゐられてきました。パーリ語・マーハーラーシュトリー語・アルダマーガディー語などいはゆる中期インドアーリヤ諸語も、また現代北印度の日常生活で用ゐられてゐるヒンディー語、ベンガーリー語・マラーティー語など近代印度アーリヤ諸語もサンスクリット語を母胎とする言語であると言って大過ないでせう。タミル語などドラヴィダ諸語はサンスクリット語とはまったく系統を異にしてゐますが、やはりサンスクリット語から多大の影響を受けながら發展した言語です。したがって、印度古典文化について少しでも本格的な智識を得ようとすれば、サンスクリット語学習は不可缺となります。また南方佛教やジャイナ教の聖典群は、それぞれ俗語と言はれるパーリ語やマルダマーガディー語で著されてゐますが、本邦の学習者がこれらの聖典語を習得しようとする場合、必ずと言ってよいほど、まづサンスクリット語の修得が求められます。さらに現代印度諸語を学習する場合も、あらかじめサンスクリット語の基礎知識を身につけてをれば、理解が容易になります。
サンスクリット語で著された聖典・文藝作品・学術書はまことに多岐にわたり、その數量も膨大であり、ここでその全容を解説することはできません。今はサンスクリット語を便宜上以下の四種類に分類し、それぞれについて各ページにて略説するのみとします。
ヴェーダ語
紀元年二千年紀にアーリヤ人が西北印度から進出したころ、かれらの奉じてゐた宗教の聖典群を總称してヴェーダと呼びます。このヴェーダの言語が最古のインドアーリヤ語といふことになるでせう。インドアーリヤ語はいはゆるインドヨーロッパ語に一支派をなし、したがって本來は西洋諸語と系統を同じくするものです。したがって、もしサンスクリット語はギリシャ語やラテン語などと基本構造や語彙の上で似かよってゐるこれら西洋古典語の知識があればサンスクリット語学習もかなり容易になるはずです。
ヴェーダとはあくまで總称であり、通常は四種にヴェータを數えますが、各ヴェーダは中核をなすマントラ集成たるサンヒター、マントラと祭祀の散文による解義書たるブラーフマナ、最古の哲学書と言はれることのあるウパニシャッド、諸種の網要書たるカルパスートラなどから成ってゐます。ヴェーダ文獻群とはほとんど一千年以上にわたって順次述作されたものであり、したがって最古のリグヴェーダ讃歌群と網要書たるカルパスートラの間には言語の上ではかなりの差異が認められます。
インドヨーロッパ諸言語の中で、インドアーリア語とイラン語はかなり後れて文化したため、ゾロアスター教の聖典アヴェスタとリグヴェーダ讃歌とは言語の上できはめて類似てゐると言はれてゐます。ヴェーダ語の緻密な研究を志す場合は、アヴェスタ語の学習も必須となることでせう。
古典サンスクリット語
| ヴェーダ語がさまざまの變容を蒙るにつれ、簡素化の傾向を辿っていったものと考えられます。アーリヤ人の分布した北印度にはさまざまな方言が成立していったことも想像に難くありません。紀元前四五世紀頃、文法学者パーニニは西北印度のかれの故郷の教養人士が用ゐてゐた言語を基礎にして、八章から成る名高い文法書を著しました。このパーニニ文典は、その後印度の学者・詩人・宮廷人等がサンスクリット語で著述をするときの規範となりました。このパーニニ文典に遵って著されたとされる典籍の言語を古典サンスクリット語と呼ぶことがあります。もっとも古典サンスクリット典籍のすべてがパーニニ文典の細則に遵って著されてゐるかといえば、若干疑問の餘地があります。それぞれの詩人や学者のパーニニ文典遵守の度合には差があるとみてよいでせう。日本でサンスクリット語を学習する場合は、通常このいはゆる古典サンスクリット語から始めます。しかし最初から難解なパーニニ文典と取り組むわけではありません。 古典サンスクリット語典籍はまことに多岐に亙ってゐますが、主要分野としてはおほむね次のやうなものがあげられます。 | |
| 一、カーヴィヤといはれる美文藝作品 | |
| これには名高い詩人カーリダーサの叙事詩や戲曲が含まれます。ほかに、アシュヴァゴーシャ、ヴィシャーカダッタ、バヴァブーティ、ハルシャ、バッタナーラヤナなど數多の秀れたカーヴィヤ作者の名をあげることができます。 | |
| 二、説話集 | |
| 説話集にはプラークリット語で著されたものもありますが、名高い大説話集カターサリットサーガなどは格調高い古典サンスクリット語で著されてゐます。ほかに有名なサンスクリット語説話集としてパンチャタントラや鸚鵡七十話、ヴィクラマアンカチャリタなどがあります。 | |
| 三、ヒンドゥー系哲学書 | |
| サーンキャ派、ヨーガ派、ヴァイシェーシカ派、ニヤーヤ派、ミーマーンサー派、ヴェーダーンタ派などの重要な哲学派の典籍は ほとんどすべて古典サンスクリット語で著されてゐます。またヒンドゥー教徒のみでなく、佛教徒やジャイナ教徒が哲学書を著すときも、古典サンスクリット語によることが多かったのです。 | |
| 四、法典等 | |
| 古代印度人は、性愛(カーマ)、實利(アルタ)、法(ダルマ)を人生の三大目的と考へましたが、三大分野それぞれの基本典籍として、ヴァーツヤーヤナのカーマスートラ、カウティリヤのアルタシャーストラおよびマヌスムリティなどが知られてゐます。これらの典籍も古典サンスクリット語で著されてゐると言ってよいでせう。ただしマヌ法典の言語には叙事詩サンスクリット的なところがあります。 | |
| 五、個別分野の学術書 | |
| 印度では、文法学・詩論学、天文学、數学、占星術、醫学等さまざまな学術がきはめて高度な発達を遂げましたが、これら諸分野の典籍の多くも古典サンスクリット語で著されてゐます。 |
叙事詩サンスクリット語
名高い二大叙事詩「マハーバーラタ」と「ラーマーヤナ」は古典サンスクリット語に比べやや簡畧な言語で著されてゐます。このため二大叙事詩の言語を特に叙事詩サンスクリット語と言って区別することがあります。ヒンドゥー神話の集成たるプラーナ聖典群も叙事詩サンスクリット語で著されてゐます。いはゆる古典サンスクリット語を修得すれば、叙事詩の読解はさほど困難ではありません。
佛教サンスクリット語
日本人になじみのある法華經、華厳經、般若經、維摩經など佛教経典は俗語的特徴を多く具へた一種獨特のサンスクリット語で著されてゐます。この佛典のサンスクリット語を總称して佛教サンスクリット語と呼びます。法華經などの原典を綿密に読解しようとする場合は、古典サンスクリット語だけでなく、パーリ語やプラークリット語の充分な知識が不可欠となります。
以上サンスクリット語およびサンスクリット語文獻についてごくあらましのみを述べました。印度文化はまことに多様でありますが、その精華をなすものはやはりサンスクリット文化であると言って過言ではないでせう。