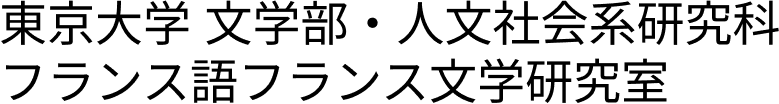東京大学フランス語フランス文学研究室の概要、特徴、専任教員をご紹介しています。
当研究室での研究については、「研究について」のページもあわせてご覧ください。
入試・進学情報をお探しの方は「入学・進学情報」をご覧ください。
研究室の概要
名称
東京大学文学部・人文社会系研究科
フランス語フランス文学研究室
フランス語表記
Université de Tokyo Faculté des Lettres, École doctorale des Sciences Humaines et Sociales
Département de Langue et Littérature Françaises
英語表記
University of Tokyo Faculty of Letters, Graduate School of Humanities and Sociology
Department of French Langage and Literature
研究分野
フランスの文学・思想、フランス語の言語学、フランコフォニー等
住所等
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 文学部3号館3階 電話 03-5841-3842 FAX 03-5841-8966
専任教員
教授 :塩塚秀一郎、王寺賢太 准教授:Raoul DELEMAZURE、鈴木和彦 助教 : 浜永和希
所属学生数
学部:22名 修士課程:10名 博士課程:20名(2025年4月現在)
研究室の特徴
「フランス語フランス文学」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか。スタンダール、バルザック、フローベール、プルーストといった小説家たちの名前でしょうか。ボードレール、ランボー、マラルメといった19世紀の偉大な詩人たちの名前でしょうか。サロート、シモン、デュラスなど現代の作家たちの名前や、『三銃士』、『海底二万マイル』、『星の王子様』など日本の子供たちにも親しまれている作品のタイトルかもしれません。もっと時代を遡って、16世紀のラブレーとモンテーニュの時代から、思想家(デカルト、パスカル)・劇作家(コルネイユ、モリエール、ラシーヌ)を輩出した17世紀を経て、モンテスキュー、ルソー、ディドロらが続々と現れた18世紀までの西欧文化史上の有名人たちを思い浮かべる方もいるでしょう。あるいは、実存主義から構造主義・ポスト構造主義へと連なる20世紀の哲学者・思想家たちのことを考えてもかまいません。
フランス語フランス文学研究室(以下「仏文」)では、こうしたフランス語で書かれたさまざまな作品をとりあげます。つまり、「フランス語フランス文学」が対象とするのは、詩・小説・戯曲・批評といった狭い意味の「文学」のみならず、現在では哲学・歴史・文学・社会科学といったさまざまな学問領域に分かれた「フランス語のテクスト」一般です。実際、ルネッサンス期以来、フランス語の書き手たちは、さまざまな領域で、それぞれの領域の創設や革新に携わってきました。エッセーという形式で自分自身について語ることを始めたモンテーニュや、俗語で哲学書を著した先駆者デカルト、現代的な意味での「世界史」の創始者の一人ヴォルテール、さらには言語学・人類学・精神分析・フェミニズムの領域でソシュール、レヴィ=ストロース、ラカン、ボーヴォワールたちが果たした知的変革など、その例は枚挙にいとまがありません。ひるがえって、シュルレアリスムやヌーヴォーロマンのような集団的な文学運動のかたちこそとらないものの、フランス語圏では現在もなお、詩・小説・戯曲といった諸ジャンルで、またそうした既成のジャンルの枠外で、多様な文学作品がさかんに生み出されています。
仏文ではこれまで、なによりも学生個々人の自発的な関心を尊重し、フランス文学研究・フランス思想研究などの分野で優れた研究者を輩出してきただけでなく、「フランス語のテクスト」に触発されながら、日本の芸術・文化の諸分野で活躍する数多くの作家・芸術家・批評家を生み出してきました。この研究室の良き伝統は現在も引き継がれており、学部生のあいだはまず、特定の作家や作品の研究に視野を限定せず、翻訳を介してでも「フランス語のテクスト」の広がりについて知見を深め、自分自身の関心を発見することが推奨されています。
現在、仏文研究室の専任教員は塩塚秀一郎、王寺賢太、Raoul DELEMAZURE、鈴木和彦の4名がおり、近世・近代・現代の文学・思想を専門的かつ幅広く学び、読み・書き・話すフランス語の実践的な力を身につけるための充実したカリキュラムを準備しています。専任教員だけではカバーすることのできない領域に関しては、多くの非常勤講師を招いてその欠落を補っているのも大きな特徴で、2025年度には、春学期・秋学期あわせて、フランス語言語学、ルネサンス文学、17世紀文学の計3名の非常勤講師の先生方に出講をお願いしています。
学部生・大学院生あわせて現在の在籍者は、50名あまり。現在のコロナ感染症対策のもと、この学生たちが大学の授業の場で、あるいはフランス語の辞書・事典類が揃った研究室で、互いに顔を会わせながら刺激を与え合うといった理想的な状況は望むべくもありませんが、仏文では、大学の方針を遵守しながら、オンライン・ハイブリッドなどさまざまな形態で、学生たちが出会い、議論する場を維持することに最大限配慮しています。
いまやフランス文学の古典的作品が日本人の一般教養であった時代は遠くなったとはいえ、明治以来の日本で、しばしば翻訳を通じて「フランス語のテクスト」の魅力に導かれ、それに触発されて、数多くの日本語の仕事がなされてきたこともまた事実です。その意味では、「フランス語フランス文学」はたんにヨーロッパ西端の遠い異国の文化遺産ではなく、日本語で生活する私たち自身の文化の一部であるとも言えます。
よく知られているように、「東大仏文」からは、小説では太宰治(中退)、大江健三郎、松浦寿輝、詩では天沢退二郎や入澤康夫、文芸評論では小林秀雄、澁澤龍彦、蓮實重彦といった人々が続々と世に出ました。作曲家(三善晃)や音楽批評家(吉田秀和)、映画作家(吉田喜重)や映画批評家(蓮實、松浦)、アニメーション作家(高畑勲)も「東大仏文」の同窓生です。これだけ多種多様な書き手・芸術家が数多く巣立っていった背景には、「フランス語のテクスト」にそなわる領域横断性や方法論上の先鋭性、あるいは同時代の社会に対する批判的関係のみならず、この研究室ならではの自由闊達さがありました。東大仏文はかねてから、アカデミックにも世界水準にある日本の仏文研究の第一線であったのみならず、「フランス語のテクスト」から刺激を受けとって自分自身の領野を切り開き、新たな創造を行う学生たちを応援してきました。その精神を、渡辺一夫はラブレーの一句を借りて言い当てています ——「Fay ce que vouldras 汝の欲するところをなせ」。人文学研究の危機がかまびすしく言われる現在だからこそ、一人でも多くの学生が、この自由闊達な精神を受け継ぎ、けっして己の欲することにおいて譲ることなく、「フランス語のテクスト」の新たな魅力を発見してくれることを願っています。