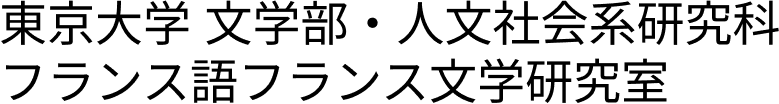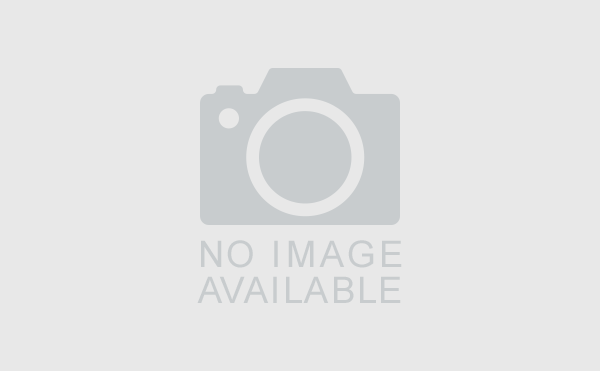49号
- 王の擬制的身体と円卓 : 〈王の歴史〉からの離昇としての聖杯物語
- リュトブフの仮構された「私」によるパリ
- モンテーニュの『エセー』あるいは日常の記録
- 「信じやすい」モンテーニュ…? : 『エセー』における世界地誌的知識
- 悲劇は国王を描くのか : コルネイユ『アッティラ』におけるルイ14世の称賛演説
- アティスの眠り : オペラと「夢」について
- いとも厳密で継続的な検討 : ベールと「迷える良心の権利」
- アポロンの正義 : ラグランジュ・シャンセルによる『オルフェ』
- 「崇高」の概念と「風景の発見」について
- 説得と誓約 : 『エミール』における言語の問題
- ルソーと肖像画の身体・試論
- ディドロ『ラモーの甥』におけるフラヌール的感性 : ディグレッションと都市空間
- サン=レアルからスタンダールにかけての文学=鏡の変容
- スタンダールとモラリストたち
- バルザックを読むカロリーヌ・マルブティ : 『危うい地位』の批評的射程
- 『カディニャン公妃の秘密』の庭
- ネルヴァルのケルト幻想
- 子供・感受性・秩序 : 後期ボードレールの美学と存在論
- 「描きたいという欲望」とともに描き出されているもの
- 纏う詩へ : マラルメとモード雑誌
- 17世紀の著作家はリセでどのように読まれていたのか : 19世紀フランス中等教育におけるexplication成立史と2人の高等師範学校卒業生(シャルル・テュロとオギュスタン・ガジエ)について
- プルーストにおける読書の問題 : 想起と忘却をめぐって
- プルーストにおける〈モラル〉を語るために : マーサ・C・ヌスバウムの考察をめぐって
- フランソワ・モーリヤック『火の河』における「火」と「水」の接合
- 「真理の僕」ルネ・ゲノン : エゾテリスムと著作の公刊について
- 言葉なき世界のエクリチュール : ジョルジュ・ベルナノスの文学
- 根源的倫理学とは何の謂いか : ハイデガー『ヒューマニズム書簡』のー挿話に関するノート
- 至高性から人閣性へ : G. バタイユ著『C神父』におけるレジスタンスの裏切りと赦し
- ジョルジュ・バタイユ『小さきもの』の家族と神学 : 起源についての問い
- ブランショによるサド : 主権と言論の自由
- 「作家」という幻想 : ジッドに憧れたロラン・バルト
- ドゥルーズの賭け : 『差異と反復』を中心に
- 盲人をめぐるファンタスム : エルヴェ・ギベール『盲人たち』を通して
- Girard Desargues, maître de Pascal
- Le sentiment de Pascal
- Rois et tyrans au royaume d’éloquence : du gouvernement des âmes selon Pascal
- Tenter ou chercher Dieu? : Une alternative au cœur des Pensées de Pascal
- La fourberie de Douai (1690-1691) : une analyse théologique
- Le quotidien et la violence : Regards sur le paysage urbain chez quelques écrivains français contemporains
- L’allumette et le pyrogène : le Japon de Pierre Albert-Birot
- Faire le pont entre Europe et Japon : Sur la richesse des archives en langues européennes dans les humanités conservées au Japon
- あとがき