このたび、秋野豊ユーラシア基金では、タジキスタンPKO活動中に死去した秋野氏没後10年を記念し、下記のようなシンポジウムを開催することになりました。ご関心のある皆様の参加をお待ちしています。(防衛研究所・湯浅)
秋野豊氏没後10周年記念シンポジウム「ユーラシアの平和構築を考える――秋野豊の遺したもの」
- 主催:秋野豊ユーラシア基金
- 協賛:早稲田大学政治経済学術院、筑波大学
- 日時:2008年7月18日(金)15時〜17時30分
- 会場:早稲田大学西早稲田キャンパス、小野梓記念館(27号館)、小野記念講堂
- (東京メトロ地下鉄東西線 早稲田駅下車)
【プログラム】
総合司会 瀬谷ルミ子(第2回秋野賞受賞者、日本紛争予防センター事務局長)
開会の辞 伊東 孝之(秋野豊ユーラシア基金理事、早稲田大学教授)
第1部・報告「ユーラシアの紛争と平和――研究と実践を架橋する」
報告者:
- 小山淑子(第1回秋野賞受賞者、国際労働機関[ILO]危機対応・再建計画部)
「国際機関による平和構築――研究、PKO、技術協力からの視野」
- 上杉 勇司(第2回秋野賞受賞者、広島大学大学院准教授)
「アフガニスタンにおける破綻国家再建の試みとPRT」
- 湯浅 剛(第1回秋野賞受賞者、防衛省防衛研究所主任研究官)
「中央アジアで何が変わったのか?」
映像上映(NHKドキュメンタリー国境紀行から)
第2部・パネル・ディスカッション「ユーラシアと日本のこれから――秋野豊の遺したもの」
- 司会:木村汎(北海道大学名誉教授、拓殖大学客員教授)
- パネリスト:河東哲夫(元駐ウズベキスタン大使、早稲田大学客員教授)
- 進藤榮一(筑波大学名誉教授)
- 袴田茂樹(秋野豊ユーラシア基金顧問、青山学院大学教授)
- 村井友秀(防衛大学校教授)
閉会の辞 秋野洋子(秋野豊ユーラシア基金代表)
【問い合わせ先】
秋野豊ユーラシア基金事務局
このたび、学習院大学東洋文化研究所では、第68回学習院大学東洋文化講座を下記の通り開催いたします。ご多忙とは存じますが、ふるってご出席くださいますようご案内申しあげます。(学習院大学東洋文化研究所・小沼孝博)
2008年度学習院大学 東洋文化講座シリーズ<アジアの文字文化>
第68回東洋文化講座(参加自由、無料)
- 日時:2008年6月27日(金)18:00開場、18:15開始
- 会場:学習院大学・西2号館503教室(参加自由/無料)
- 演題:文字文化からみた草原とオアシスの世界
- 講師:松井太氏(弘前大学・准教授)
【お問い合わせ先】
中国ムスリム研究会では、2008年7月19日(土)に第15回定例会を開催することとなりました。今回の定例会では、田中周さん(早稲田大学・院)と矢久保さん(慶應義塾大学・院)に日頃の研究成果をご報告いただきます。お忙しいとはお察しいたしますが、ふるってご参加くださいますよう何卒よろしくお願い致します。
なお、準備作業の関係上、ご参加いただける方々の人数を事前に確認する必要がございます。大変恐縮でございますが、参加ご希望の方は7月10日(木)までに当事務局のメールアドレスにご連絡ください。また、その際に懇親会への出欠に関しましてもお書き添えいただけましたら幸いに存じます。何卒よろしくお願い致します。(澤井充生:首都大学東京都市教養学部都市教養学科)
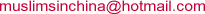
- 研究発表:
- 13:45〜14:30 発表1
- 発表者:田中 周(早稲田大学大学院博士課程)
- テーマ:「中華人民共和国における国家・国民統合と民族政策――1950年代新疆ウイグル自治区成立過程から考える」(仮題)
- 14:30〜15:15 質疑応答
- 15:15〜15:30 休憩
- 15:30〜16:15 発表2
- 発表者:矢久保典良(慶應義塾大学大学院博士課程)
- テーマ:「重慶国民政府期の中国ムスリム団体――『中国回教救国協会会刊』を手がかりに」(仮題)
- 16:15〜17:00 質疑応答
- 懇親会:定例会終了後、会場近くで懇親会を開く予定です。
*その他、ご不明な点につきましては、中国ムスリム研究会事務局までお問合わせください。
昨年12月に、当拠点および筑波大学、ケンブリッジ大学、ストックホルム大学との共催で開催された国際会議
CENTRAL ASIAN STUDIES: History, Politics and Societyに関し、発表者の一人であるアラン・フランク氏による会議の報告が、Central Eurasian Studies Review(Central Eurasian Studies Society発行)のVolume 7, Number1(Spring 2008)に掲載されました。
*Central Eurasian Studies Reviewは下記のURLよりPDF版がダウンロードできます。
第72回例会について詳細が決まりましたのでお知らせ致します。ご関心のある方々のご参加をたまわればありがたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(北海道中央ユーラシア研究会連絡係・井上岳彦)
北海道中央ユーラシア研究会第72回例会
- 日時:2008年6月21日(土)15:00〜
- 会場:北海道大学スラブ研究センター4階小会議室(420室)
- 報告者:小野亮介(慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程)
- 題目:トルキスタンからテュルク全史へ:1930年代初頭におけるゼキ・ヴェリディ・トガンの言説
- コメンテーター:長縄宣博(スラブ研究センター)
この度、下記のとおり、文部科学省「魅力ある大学院教育」イニシアティブ支援プロジェクトの一貫として、一昨年度・昨年度に引き続き、当大学院生の自主企画による「シルクロード・セミナー」を開催致すはこびとなりました。早いもので、今回で3度目となりました。当セミナーは、院生の研究のために役立つだけでなく、学内・学外者からの発表と共に、シルクロード・ウイグルに関して多角的に紹介し、一般の方にも参加して頂きながら、研究上に役立てようという主旨のものです。
今回は、新疆やウイグルに関わる若手女性研究者4名の、斬新で活気ある発表が聞けると、主催者側も楽しみに致しております。みなさまお時間許す限りご参加頂けますよう、お願い申し上げます。(奈良女子大学大学院博士課程・鷲尾惟子)
「シルクロードのひとびとPart3」
−創る・作る・造る−沙漠の民への歴史・生活・文化に対する「生産」の意義とは?
(平成20年度文部科学省「魅力ある大学院教育」イニシアティブ支援プロジェクト大学院生の自主企画による研究セミナー)
【内容】
中国西北部に位置する新疆ウイグル自治区は乾燥地域に属しています。当地域はシルクロードの要衝として一般的に認知され、当地に居住するひとびとは歴史をつくり、農をつくり、そし文化や習慣をつくり、これまでの生活を築き上げてきました。その一方で、現在では中国の経済発展とともに、この地域における社会、文化、環境は大きく変化しつつあります。
本セミナーではこうした社会と自然の変化の中で生きるひとびとのくらしをテーマとして、多角的な視点から理解することを目的とします。今回は、ひとびとのくらしの中でも、「つくる(作る・造る・創る)」という人間的営みをキーワードとして、生産性・創造性に焦点を当て、歴史学・地理学・文化人類学・経済学などの視点から、若手研究者に斬新な話題提供をして頂く予定です。また、現地の文化を映像で紹介するコーナーも設けますので、ふるってご参加下さい。
- 日時: 7/5(土)13:00〜 17:00PM
- 場所:奈良女子大学奈良女子大学 文学部南棟120教室(地域環境学地図室)
- 近鉄奈良駅下車東側出口から北へ徒歩5 分・正門入ってすぐ左側の校舎
- 申し込み:不要、参加無料。どなたでもお気軽にご参加下さい
- お問い合わせ:090-8215-7003 鷲尾(わしお)
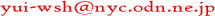
【話題提供】
- 田先千春(九州大学大学院比較社会文化学府国際社会文化専攻)「タリム盆地南縁の棉花・棉布の使用と生産の歴史」
- マイラ・トルスン(東京農工大学大学院連合農学研究科(宇都宮大学配置))
「新疆ウイグル自治区の農業と今後の課題」
- 古澤文(奈良女子大学大学院人間文化研究科社会生活環境学専攻)「タリム盆地の農業について―地理的立地条件とその要因―」
- 熊谷瑞恵 (京都大学アジアアフリカ地域研究研究科・日本学術振興会特別研究員)
「家庭の食事にみる新疆ウイグル族の現在―漢民族料理の受容とその改変―」
筑波大学中央アジア国際連携センターより、ニューズレター『中央アジアの世界』の第2号が発行されました。こちらは、2007年12月に、当拠点と筑波大学、ケンブリッジ大学、ストックホルム大学との共催で開催された国際会議
CENTRAL ASIAN STUDIES: History, Politics and Societyの特集号となっています。
下記のURLより、それぞれ日本語版と英語版のニューズレター(PDFファイル)がダウンロードできます。
(筑波大学大学院人文社会科学研究科 ティムール・ダダバエフ)
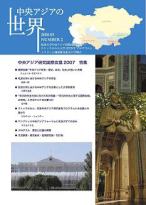 |
|
 |
|
|
|
| 『中央アジアの世界』第2号 |
|
Central Asian World no.2 |
|
 2008年12月
2008年12月 2008年11月
2008年11月 2008年10月
2008年10月 2008年9月
2008年9月 2008年8月
2008年8月 2008年7月
2008年7月 2008年6月
2008年6月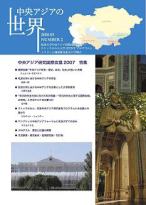

 2008年5月
2008年5月 2008年4月
2008年4月