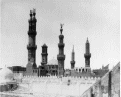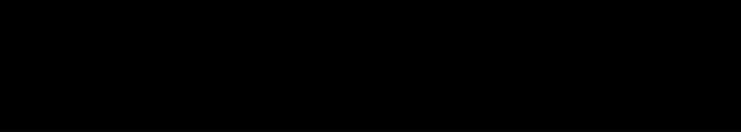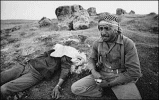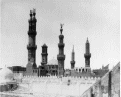



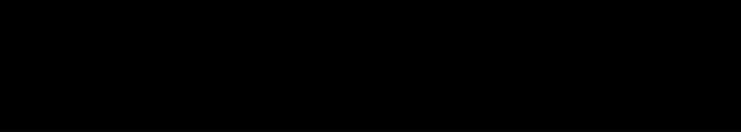

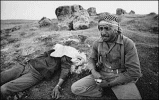


第一回(2007年1月29日) 早稲田大学
サァディー教授は、パレスチナの(アラブ人)人工をイスラエルがどのようにコントロールしてきたという問題を本講演のテーマとして揚げ、イスラエルの政策に影響を与えたオスマン帝国時代、英国委任統治時代に遡り、その変遷を追うという方向性を提示した。第一回にあたる今回は、オスマン帝国治下のパレスチナの社状況が、植民地主義、さらにシオニズムを揚げるユダヤ人入植者の流入を受けて大きく変化し、英国委任統治時代におけるアラブ人とユダヤ人の対立の火種がまかれてゆくまでが語られた。
サァディー教授はパレスチナでの出来事の背景にある、ヨーロッパの人口変動やクリスチャン・シオニズムというバルフォア宣言の関係などを取り上げることによって、当時のパレスチナの情勢を多角的に描き出すことに成功している。
第二回(2007年2月5日)
今回、サァディー氏は英国委任統治時代のパレスチナにおけるユダヤ人組織に焦点を絞り、わずか少数であったユダヤ人コミュニティが、なぜパレスチナの「勝者」となったのかを論じた。サァディー氏はことに、1920年に設立されたユダヤ人ヒスタドルート(労相総同盟)の、ユダヤ人労働者雇用主としての役割に注目し、その結果ユダヤ人の手による産業の繁栄が、のちのイスラエル国家の基盤となったと述べた。
第三回(2007年2月7日)
ユダヤ人組織による産業が発達する一方で、パレスチナにおけるアラブ人はその恩恵から疎外されていた。さらに、不在地主による農地売却が相次いだことによって、アラブ人たちは土地の喪失を痛感するようになる。1920年代から30年代にかけての、この厳しい時代に、パレスチナのアラブ人たちはパレスチナ人としてのアイデンティティを培っていった。
第四回(2007年2月14日)
シオニストによるパレスチナ人社会への監視・管理システムの構造と歴史的変遷を考察した後、とくに宗教・氏族・居住地・職業など多様なカテゴリーによって個々人を分離し、協力者(コレボレーター)を創出するシステムについて具体例を用いて詳細な分析を行った。
第五回 (2007年2月16日)
パレスチナに関する参考文献が紹介された後、分離壁建設計画についての概要説明があり、特に分地壁建設計画の背後にあるシオニズム政治思想の潮流について批判的な考察がなされた。また、分離壁建設がパレスチナ人社会に与える影響についても分析が行われた。
「中東民主化班」 第1回研究会
7〜11回目: 「パレスチナ研究班」第4〜8回研究会
日時: 2007年1月29日(月) 15:00〜17:00
2007年2月5日(月) 16:00〜18:00
2007年2月7日(水) 16:00〜18:00
2007年2月14日(水) 16:00〜18:00
2007年2月16日(金) 16:00〜18:00
場所: 早稲田大学41-31号館2階会議室
講演者・講演題目: アフマド・サァティー(ベングリオン大学教授)
連続講演